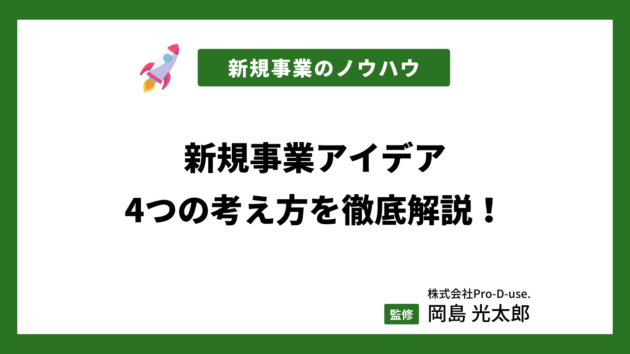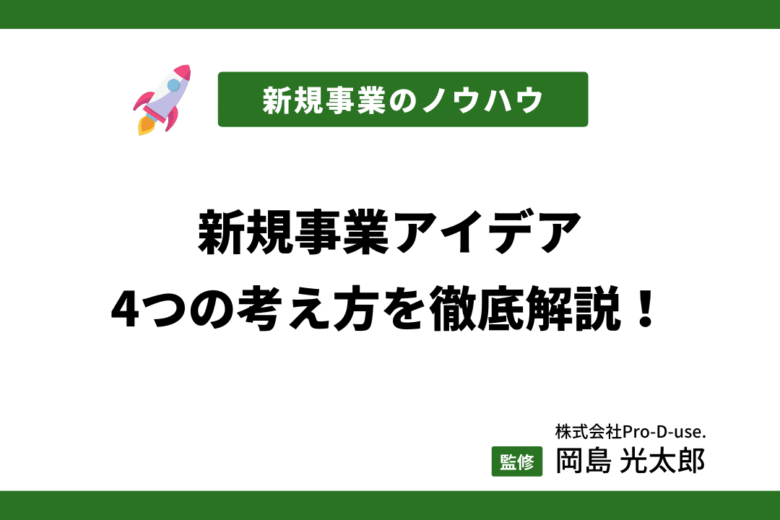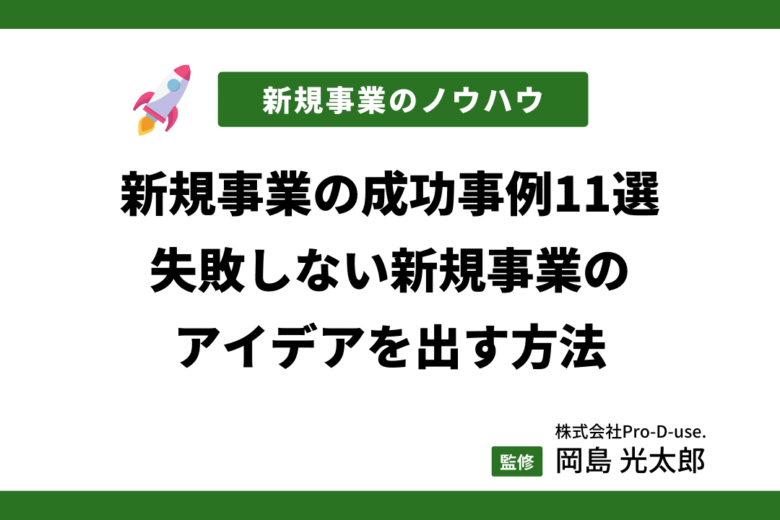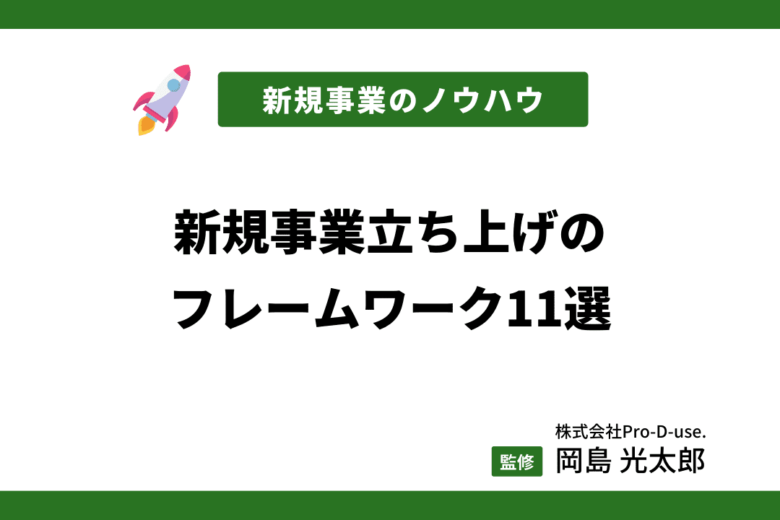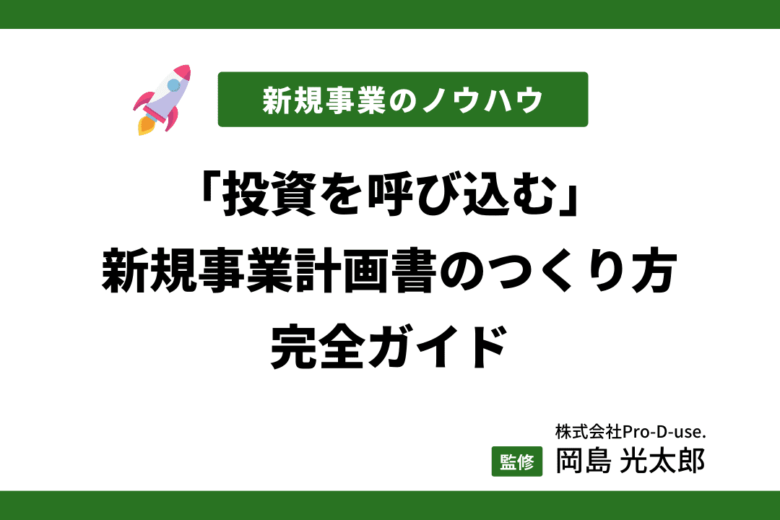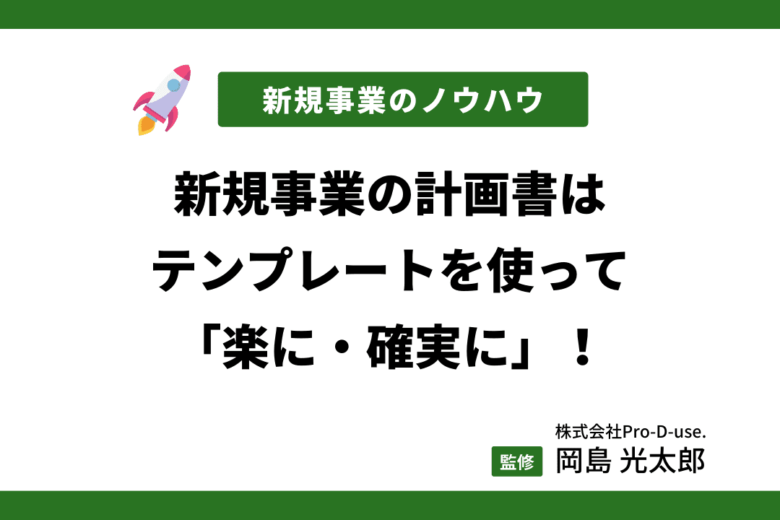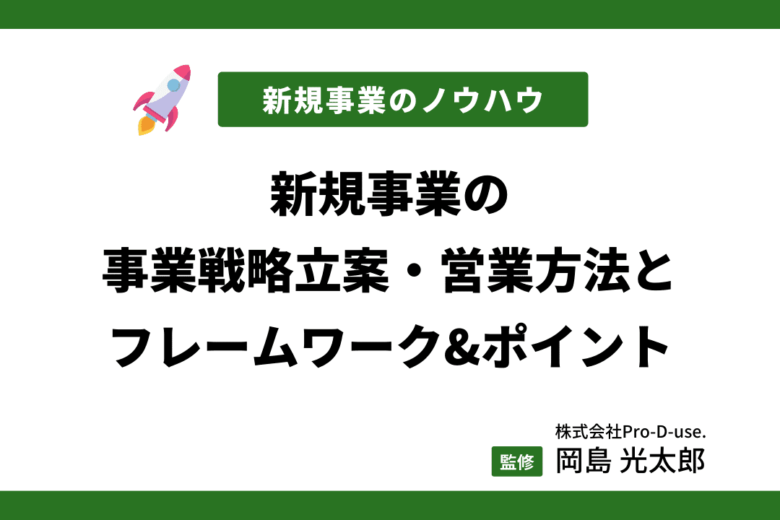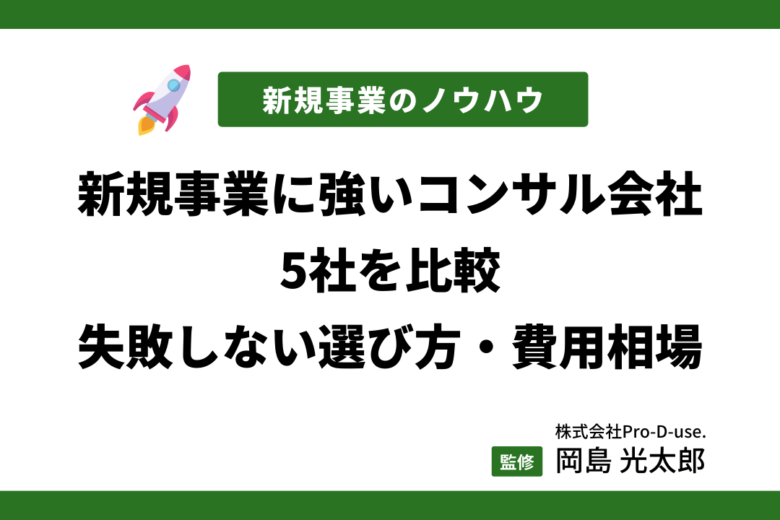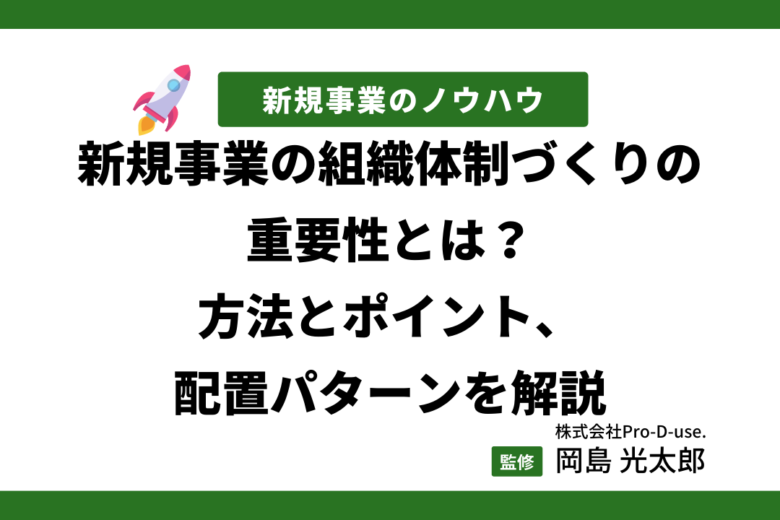新たな事業を作りたいと思っているが、なかなか良いアイディア思い浮かばない。どうすればよいアイディアが思い浮かぶようになるのだろうか?

アイディアは思い浮かんでいるが、新規事業として成功しそうか悩んでいる。どのようなアイディアが成功する確率が高いのだろうか?
経営者であれば、このような悩みは誰しもが考えるのではないでしょうか?
しかし、実際はそう簡単に新規事業のアイディアが生まれるものではないですし、新規事業を始めるには大きなリスクが伴うことも事実としてあります。
一方で、現在、顧客のニーズの移り変わりや多様化のスピードが早くなっているため、既存事業だけでは企業存続が難しくもなってきています。
そこで、本記事では新規事業の立ち上げに成功するためのアイディア創出方と考え方を詳しく解説していきます。
新規事業を成功させるためのアイディアの創出法において、4つの方法があります。
- 現在行っている事業から発想する方法
- 異業種から発想する方法
- 制約条件から発想する方法
- 業種を組み合わせて発想する方法
上記の4つの創出方法の軸となる重要なポイントは、顧客のニーズがあり他社が行っていないことを発想することです。
なぜなら、ただ発想するだけで成功するとは限らず、 顧客に受け入れられるようなアイディアを発想する必要があるからです。
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 新規事業のアイディアの創出法がわかり、成功確率の高いアイディアで新規事業を始めることができ、事業を軌道に乗せやすくなります。
- 多くでてきたアイディアの中を具体的な事業計画に落とし込むことで、思いつきではなく、現実的なアイディアに洗練することができます。
それでは早速、読み進めていきましょう。
▼目次
新規事業の重要性

どんな事業や商品であっても必ず寿命があります。いわゆるライフサイクルと呼ばれるもので、
- 「導入期」
- 「成長期」
- 「成熟期」
の過程を経て、最後の「衰退期」へと移っていきます。
ですから、衰退期に入る前に新規事業で新たな成長曲線を描くことが必要なのです。
従来の事業にしがみき、何もしないでいたのでは売り上げはどんどん先細りしてしまうでしょう。
特に最近は、「消費者ニーズの多様化」や「商品のライフサイクルの短命化」など市場環境が変化するスピードは早まっています。
今までが大丈夫だったからといって、これからも大丈夫だという保証はどこにもありません。
歴史ある企業であっても、途中で新規事業を始めたり、事業の転換を行ったりしているからこそ長年継続しているのです。
企業が安定して収益を上げていくためには、新規事業を起ち上げて変化する消費者ニーズに対応することが必要になってくるでしょう。
新規事業によって、新たな企業価値や商品価値を提供することができれば将来的な安定経営にもつながります。
また、新規事業の効果は経営の安定化だけにとどまりません。
新たな事業に取り組むことで、社内が活性化する効果も期待できます。新しいビジネスにチャレンジすることで社員のモチベーションも向上し、働きがいを感じる社員を増やすことにもつながるでしょう。
新規事業のアイディア創出法

新規事業のアイディア創出法としては、大きく2つのパターンがあります。
1つ目のパターンは、現在行っている事業の技術や資源を活用する方法です。
例えばある写真フィルムのメーカーは、カメラのデジタル化に伴いフィルムの需要が落ち込む中でフィルム製造の技術を利用して化粧品業界に参入しました。
また、大手家電量販店の中には全国に展開している店舗網を利用してリフォーム業界に参入している例も見られます。
このように、従来ある自社のリソースを活用して新規事業を始めることは、
- 事業を起ち上げやすかったり
- リスクが少なかったりする
などのメリットがあります。
自社の資源や強みを分析したうえで新たな事業に活用できないか検討してみましょう。
2つ目のパターンは、既存事業とはまったく関係のない新規事業に取り組む方法です。
アイディアを創出する方法としては、
- 「ある業界で成功したビジネスを別の業界に流用する」
- 「既存の商品やサービスを組み合わせる」
- 「自分が感じている不満や不便さを解決する」
- 「海外で成功しているビジネスをカスタマイズする」
などがあります。
新規事業のアイディアが生まれたら、顧客のニーズや収益性を検討しながら具体的なビジネスプランに落とし込んでみましょう。
そのビジネスプランをしっかり検証することで新規事業の成功へとつながります。
新規事業を考える際のフレームワーク
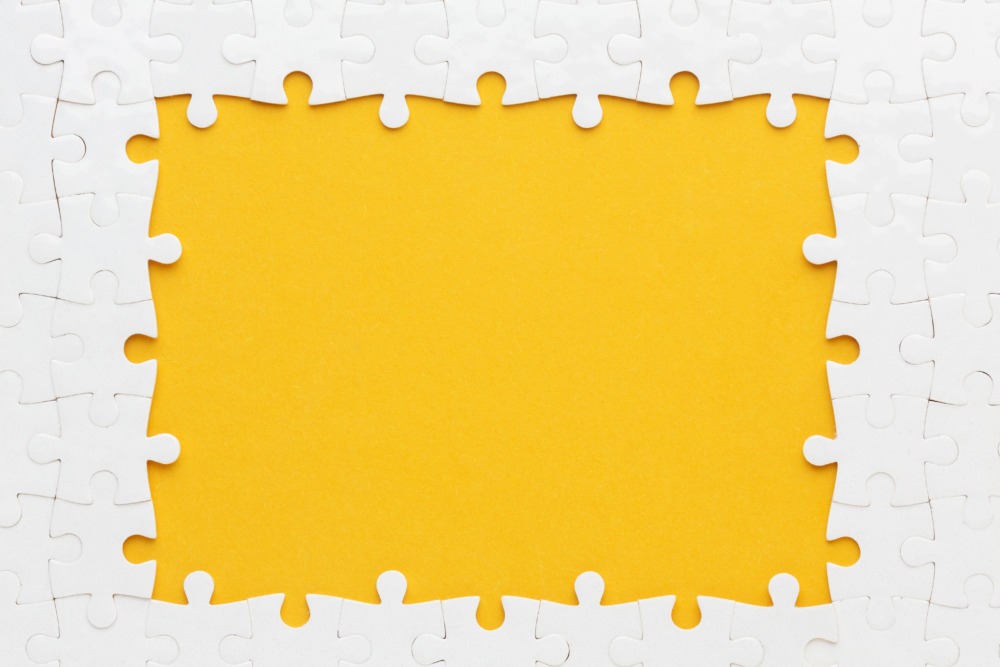
既存事業とは関係のない新規事業のアイディアを出すのは簡単なことではありません。
なかなかアイディアを思いつかないというような場合は、次のフレームワークに沿った考え方をするとアイディアが生まれやすくなります。
1つ目のフレームワークは、「異業種から発想する方法」です。
ある業種や業界での成功事例を、別の業種・業界で活用できないか考えてみましょう。
例えば、「立ち食いそば」をまったく別の料理であるステーキに展開した事例があります。「ステーキを立ち食いで提供する」という発想は今までにないものでした。
それを立ち食いスタイルで、しかも、低価格で提供することで人気を得ています。
2つ目のフレームワークは、「制約条件から発想する方法」です。
これは、「もし○○○がなかったら」とあえて制約を設けることでアイディアを生み出す方法です。
例えば「もし在庫を持たないとしたら」という制約条件からは、メーカー直送やお取り寄せスタイルのビジネスが発想できるでしょう。
「店舗がなかったら」という制約条件からは、ネット販売や移動車販売のビジネスが発想できます。
3つ目のフレームワークは、「業種を組み合わせて発想する方法」です。
例えばネットカフェは、「PCの貸し出し」と「マンガ喫茶」を組み合わせたものといえるでしょう。
新規事業のアイディアは、ただ漫然と考えてもなかなか思い浮かばないものです。
このようなフレームワークを活用して、どんどんアイディアを生み出しましょう。
新規事業のアイディアを実現するためのポイント

新規事業のアイディアが浮かんでもそれをビジネス化するためには、具体的な事業計画が必要になります。アイディアを元に事業計画書を作成してみましょう。
事業計画書の作成を進めていくと、
- 「ターゲットは誰か」
- 「販売方法はどうするか」
- 「必要な資金の額と調達方法」
などクリアすべき課題が次々と見つかります。これを1つ1つ検討していくことで新規事業が実現に近づくのです。
事業計画書に必要な項目としては、まず事業コンセプトが挙げられます。
- 「誰に」
- 「何を」
- 「どのような方法で売るのか」
を簡潔にまとめましょう。
次に参入する市場の状況を分析することが大切です。
- 「市場の規模」
- 「今後どれぐらいの成長が見込めるか」
- 「ターゲットとなる顧客は誰か」
- 「競合関係はどうなっているか」
などを客観的に分析することが重要になります。
市場分析ができたら事業の内容について具体的に詰めていきます。
- ターゲットとなる顧客
- 提供する商品・サービス
- 価格
- 販売チャネル
- 人員体制
などについて詳細に計画することが必要です。
またどんなに優れた商品・サービスであっても、それを知ってもらわなければ売り上げにはつながりません。
素晴らしい商品・サービスであることをターゲットとなる消費者に伝えるためのプロモーション計画も作成します。
そして何より重要なのが資金や収益に関する計画です。
- 「必要な資金はいくらか」
- 「どうやって資金調達をするか」
- 「売り上げはどれぐらい見込めるか」
- 「経費はいくらかかるか」
など現実的な収益シミュレーションが必要になります。しっかりとした事業計画書を作ることが新規事業の成功へとつながるのです。
フランチャイズシステムを利用する方法も
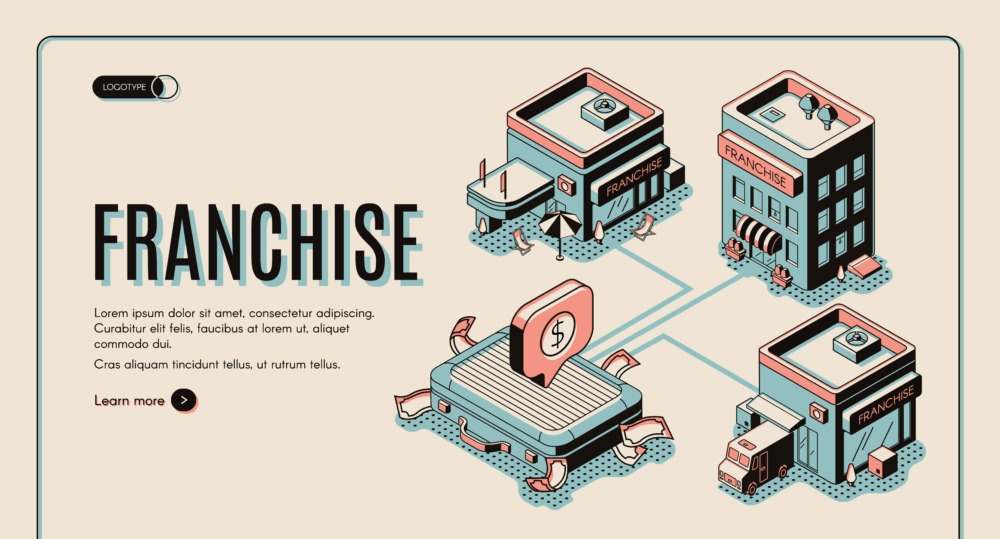
新しい事業を始めるにあたっては、FC(フランチャイズ)システムを利用する方法もあります。
FC(フランチャイズ)を利用すれば、その業種に関するノウハウがなくても本部からの指導があるため未経験でも参入しやすいというメリットがあります。
ブランド力のあるチェーン名を使用してビジネスができるため信頼性が高く、短期間で軌道に載せやすいのも大きなメリットです。
また、本部による宣伝広告や商品開発などの恩恵が受けられるのも大きな魅力でしょう。
逆にFC(フランチャイズ)を利用することのデメリットもあります。
- 決められたロイヤリティを支払う必要がある
- 契約期間内で勝手に辞めることはできない
- 提供する商品やサービスに細かなルールがあり、自社の独自性を打ち出しにくい
もしFC(フランチャイズ)に加盟する場合は、メリット・デメリットをしっかりと検討し、契約内容や収益予測を詳細にチェックしてから契約するようにしましょう。
ちなみに、自分に適したFC(フランチャイズ)を引き当てるには、たくさんの情報を閲覧して、資料を取り寄せるなどの地道な努力が必要です。
「アントレnet」や「フランチャイズの窓口」などのフランチャイズ比較サイトを活用して、効率よく情報収集をするようにしましょう。
「アントレnet
【公式】アントレnet」で自社にあったフランチャイズを探す▼
新規事業のアイディアは天から降ってくるものではありません。
「自社のリソースを別な業種で活用するためには」「あの業界の成功事例を転用できないか」などと常に新規事業のアイディア発想を習慣づけることが大切です。
アンテナの感度を高めて自社の業界だけでなくさまざまな業界の成功事例を観察し、成功につながる新規事業のアイディアを発想しましょう。
アイディアがなかなか浮かばない…そんな時は

ここまで、新規事業の立ち上げ時のアイディア出しのポイントを解説してきましたが、
- 「理論は理解できたけど、自分でできる気がしない…」
- 「考えてみたが、全然思い浮かばない…」
このような悩みも含めて、非常に煩雑で難しい新規事業の企画・立ち上げ、推進や収益化でお困りの際は、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談(無料)ください。
「株式会社Pro-d-use」のサービスを活用すると、新規事業のプロがあなたに代わって新規事業の調査から企画・立ち上げ・推進、収益化までをあなたの会社の現場に入って一緒に進めてくれるので、あなたは「新規事業を進める苦悩や業務から解放」されますよ。
>>> [毎月3社限定] 3回までは無料でご相談をお受付いたします<<<
<参考>
http://leverage-share.com/study/post-1827/
https://biz-shinri.com/new-business-idea-3559
http://www.ocl.co.jp/ocl_column/column05/
http://bizhack.jp/idea/
https://www.fc-hikaku.net/franchises/2080