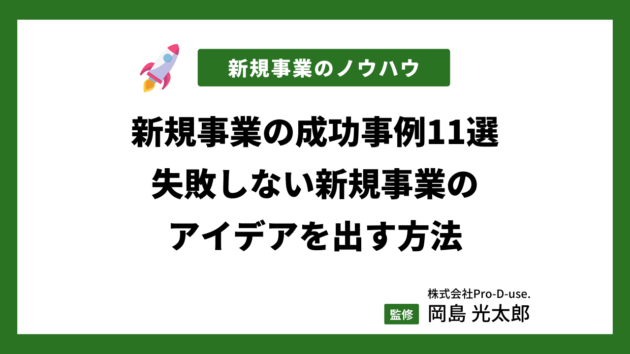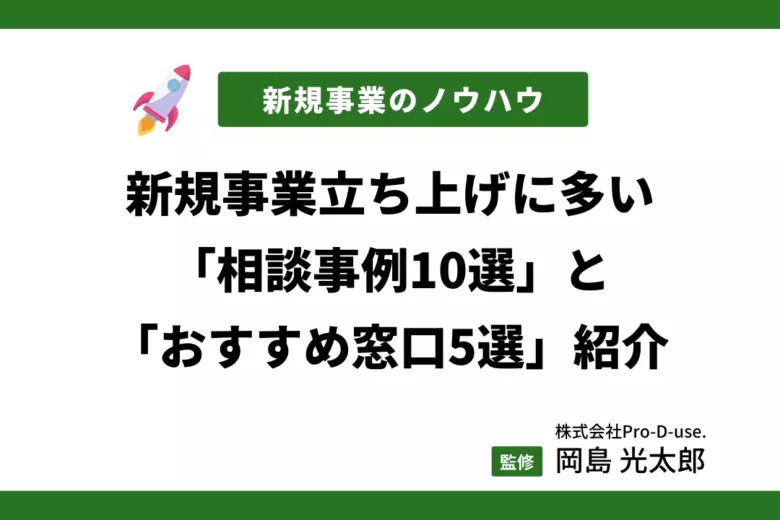新規事業に関わる方であれば、他社の成功事例を参考にして、自社の新規事業を成功に導きたいと思っているのではないでしょうか?
「どうすれば新規事業が成功するのか?成功している他社は、どんな取り組みをしているのか?」
「自社の新規事業がうまくいかない。成功している他社と何が違うのか…?」
新規事業の成功確率を高めるには、先人たちの成功事例や失敗事例を学び、活かすことが有効です。
本日は、中小企業から大手企業までの新規事業事例を集めました。これらの事例を見れば、あなたの会社の新規事業のヒントや参考になる事例が必ずあるはずです。
新規事業には共通の3つのパターンがあり、それを知るだけでも新規事業の成功する確率を増やすことできるはずです。
筆者はこれまで、中小・ベンチャー企業への「新規事業のコンサルティング」を通して、多くの成功も失敗も現場で目の当たりにしてきました。
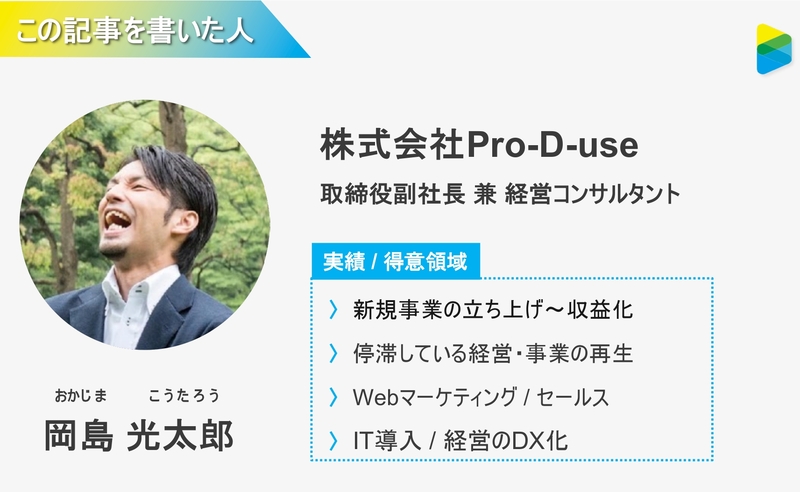
本記事では、数々の事例とあわせて、弊社「(株)Pro-D-Use(プロディーユース)」がコンサルした中小企業の成功事例も紹介するのであわせてご覧ください。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には「参考にすべき事例」があります。
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」の【新規事業の非公開事例】を聞いて、新規事業の参考にしてみませんか?詳しくは下記の新規事業のコンサルサービスページからお問い合わせください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業コンサルサービスはコチラ >>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /
▼目次
【中小企業】新規事業の3つの成功事例|(株)Pro-D-useのお客様事例
まずは、筆者の所属する(株)Pro-D-useがコンサルティングした、中小企業の新規事業の成功事例を紹介します。
各社が抱えていた課題に対して提供した支援や、得られた成果について詳細に解説しますので、ぜひご参照ください。
中小企業の事例1. 株式会社ビー・ファクトリー様

【企業概要】
株式会社ビー・ファクトリー様は、店舗型の音楽レッスンビジネスを提供している企業です。
東京都内に直営店舗が7店舗あり、ボーカルやピアノのレッスン、話し方トレーニングなどを提供しています。
【抱えていた課題】
2020年から始まったコロナ禍で、店舗レッスンが「三密」と呼ばれるビジネスに指定されてしまい、業績が急激に悪化。一時売上が90%ダウンする事態に陥りました。
その中で、既存顧客からオンラインレッスンを希望する声があり、弊社Pro-D-useがプロジェクトを主導し新規事業の立ち上げと収益化につなげました。既存顧客の声を、新規事業のアイデアとして活用した事例です。
【支援内容】
- 市場調査、競合調査
- 事業計画(シミュレーション)作成
- 社内のプロジェクトマネジメント
- 外部パートナーのマネジメント
- サイトやLP、販促関連のディレクション
- ITシステム導入、および改善
- オペレーションの構築、改善
【得られた成果】
- 緊急事態宣言2ヶ月後にオンラインレッスン事業立ち上げ。翌日から問い合わせが発生し収益化に成功。
- 広告を使わず展開していたが、問い合わせのうち10%〜15%がオンラインレッスンに。
- エリアに制限されることなく、顧客層の拡大に成功。
Pro-D-useは、現在でも株式会社ビー・ファクトリー様の経営支援や他の新規事業立ち上げ支援を行っており、過去最高の売上・利益額を達成しています。
事例の詳細については、以下の記事をご参照ください。
中小企業の事例2. コスモス食品株式会社様

【企業概要】
兵庫県に本社を持つコスモス食品株式会社様は、フリーズドライ食品やエアードライ食品、冷凍食品などの製造を手がけている企業です。
大手企業とのOEM製品を中心に製造してきましたが、自社のオリジナルブランド開発という長年の夢がありました。
【抱えていた課題】
オリジナルのフリーズドライ食品ブランドを立ち上げましたが、その後8年にわたって利益が確保できず、赤字の状態が続いていました。
同社はオリジナルブランドの認知向上のための施策として、既存の取引先への案内や全国キャラバンを実施していましたが、どれも成果にはつながりませんでした。
Pro-D-useがこの事業に参画し、営業戦略・戦術の見直しと構築を行いました。施策の実施や従業員様のマネジメントまで並走し、成果へとつなげました。
【支援内容】
- 調査(市場調査、競合調査など足を使って情報集め/売り方・陳列などの把握)
- 実営業(営業代行、営業同行で現場館をつかむ)
- 営業環境の整備(営業資料、営業ツール作成、トークスクリプトの作成)
- ロックオン顧客(5社)の設定と営業、契約
- 新規顧客の販路の開拓
- 営業部長のマネジメント(メンター)
- 営業戦略の策定
- 次年度の営業目標・予算・KPIの設定
- 営業ロードマップの作成
- 営業ツールの作成
- 営業メンバーのマネジメント代行
【得られた成果】
- 全体の売上のうち、オリジナルブランドの売上の割合が2%から20%へ
- オリジナルブランドの売上が5年で7倍になり、数十億円レベルの売上に
コスモス食品株式会社の事例については、以下の記事で詳細をご覧ください。
中小企業の事例1. 老舗システム受託開発会社のC社

【企業概要】
C社様は、中部地方にある設立約20年の、老舗システム受託開発会社です。
【抱えていた課題】
C社様は過去にも新規事業立ち上げを試みていましたが、事業開発スキルが足りず、思いつきで新規事業をスタートしてしまうという課題を抱えていました。その結果、利益が思うように上がらないどころか、売上の見込みすら立てられないという状況に陥っていました。
主な原因は、新規事業立ち上げや事業開発へのスキルがないこと、新規事業への基本姿勢から見直す必要があったという点です。マーケティングのスキルや経験も不足していたため、市場ニーズの把握や効果的なプロモーションができないという点も課題でした。
そこで、Pro-D-useが新規事業立ち上げに並走し、事業開発のための人材育成も同時並行して支援を行いました。
【支援内容】
- 既存事業の棚卸し代行
- 競合調査(覆面調査含む)
- 市場調査
- 新規事業企画の策定
- ビジネスモデルの構築
- 事業計画書、収支シミュレーション作成
- テストマーケティングの企画〜実施
- プロダクト開発のマネジメント
- 従業員様のマネジメント&教育
【得られた成果】
Pro-D-useの支援の結果、作りたいものを開発するプロダクトアウト型ではなく、市場ニーズに合わせたマーケットイン型の新規事業開発が実現しました。独自マニュアルやノウハウが実装され、自社内でも正しい新規事業開発を行えるようになりました。
市場ニーズを調査・把握して事業開発を行ったため、プロダクト開発前に契約(売上)の見込みが発生したのも大きな成果です。
ここまでは、弊社のお客様の新規事業の成功事例をご紹介してきました。
次は、会社規模に関係なく参考になる大手企業の新規事業の成功事例をご紹介します。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には「参考にすべき事例」があります。
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」の【新規事業の非公開事例】を聞いて、新規事業の参考にしてみませんか?詳しくは下記の新規事業のコンサルサービスページからお問い合わせください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業コンサルサービスはコチラ >>>
【大手企業】新規事業の成功事例11選
大手の成功事例1. 富士フイルム

自社の持つリソースや人材を活用して、フィルム業界から化粧品業界への新規事業・事業転換に成功
富士フイルム株式会社はその名前が示すように、もともとは写真フィルムのメーカーであり、日本のリーディングカンパニーでした。
しかしながら、カメラの記録媒体が塩銀フィルムからフラッシュメモリーカードに移行するにつれて、写真フィルムのマーケットの縮小に直面します。この状況を打開するため、自社の持つリソースを活用した業態変換を余儀なくされました。
さまざまな試行錯誤の結果、化粧品を開発し、本業のフィルムとはまったく異なる市場に参入することが決まったのです。無謀な判断のようにも感じられますが、なぜそのようなことが可能になったのでしょうか?
化粧品の材料は、粒子が細かいほど肌への浸透力が向上します。素材の粒子を細かくする技術は、究極的には原子や分子スケールの微小物体を扱うナノテクノロジーにも通じる先端技術ですが、富士フイルム株式会社にはその技術があったのです。
実は写真フィルムと肌の角質はほぼ同じ20マイクロメートルです。つまり写真フィルムの製造技術は化粧品の製造に転用可能なのです。フィルム上に塗布する感光剤の微粒子化の技術では、長年の技術的蓄積がありました。その技術を化粧品に応用して新製品開発を成功させています。
既存の経営資源の価値を技術的な価値の意味として根本的に問い直し、有効活用可能なマーケットに向けて新製品を開発して成功した事例といえます。
大手の成功事例2. ユニ・チャーム

トイレタリーの技術を応用し、ペット用品分野の進出に成功
一般的なユニ・チャーム株式会社の企業イメージは、「日常生活用品のメーカー」といったイメージが多いかもしれません。たしかに、小売店の店頭に並ぶ商品としては、生理用品やおむつなどがあります。
しかしながら、ユニ・チャーム株式会社の業種を専門的に表現すると、不織布・吸収体関連製品の専門メーカーとなります。
不織布(ふしょくふ)というのは、簡単にいえば「織らない布」のこと。通常の布は動物性や植物性の繊維を紡いで、織ったり編んだりすることで平面的な広がりをもたせています。これを織布(しょくふ)と呼びます。それに対し、不織布は繊維同士を融着(熱処理などにより接着する)や機械的・科学的作用で結合・絡み合わせてシートを形成します。
この技術は、さまざまな領域で応用可能な汎用技術です。おむつなどの他には、マスクやガーゼなどの衛生・医療分野、土質改良材として土木・建設分野があります。さらに研磨剤や電気絶縁材などの産業資材分野、フィルタなどの空調資材分野などがあります。
つまり、ユニ・チャーム株式会社は日常生活で目に触れることは少ないけれど、現代社会生活を維持するためのインフラ構築・維持に用いられる素材を扱うメーカーともいえます。
ペット用品に関しては高分子吸収体が封入されたシート(いわゆるペット・シーツ)などの商品化を行っており、主要5大製品(生理用品、生活用品、介護用品、ペット用品、ベビー用品)の一角を担っています。
高分子吸収体とは吸水性と保水性をもつ樹脂のことです。最大で自重の1,000倍(純水の場合)の吸収量があり、それを保持して漏らさないため、おむつなどの吸収剤として用いられています。これを近年需要が増え続けている屋内で飼育するペットの糞尿処理アイテムとして商品化しています。
大手の成功事例3. ヤマト運輸

物流・決済システムを活かして、家電修理サービスに参入
一般に、家電が故障した場合、販売店やメーカーに問い合わせ、センドバック修理であれば、自ら梱包・発送するなどの時間と手間が掛かります。
宅配サービス大手のヤマト運輸株式会社の社是に「サービスが先、利益は後」というものがあります。社会に必要なサービスであれば、利益は後からついてくるのだから、企業としてまずやるべきことはサービスの質の向上が大切という意味です。
ヤマト運輸株式会社には、現場に権限を移譲し、配達員の日々の宅配サービスの現実から問題を発見し、その解決策を提案するという品質改善システムがあります。いわば、日常業務の範囲でそれぞれのメンバーが社内ベンチャー的な思想で動いているともいえます。
その結果として生み出されたのが、「まごころ宅急便」につづく、「クロネコ家電 Dr.修理サービス」などの付加価値のある宅配サービスです。
一般的に家電が故障した場合、販売店やメーカーに問い合わせ、センドバック修理であれば、自ら梱包・発送するなどの時間と手間が掛かってしまうのですが、このサービスは、故障した家電製品について、ヤマト運輸株式会社に連絡すれば、回収・修理・返却をワンストップで行うというものです。
取り扱いはパソコンまたはデジタルカメラに限定されていますが、ヤマト運輸株式会社では「パソコン宅急便」と呼ばれる精密機器を安全に搬送するサービスを運用しており、既存のリソースの活用という面でもリスクの少ない事業といえます。
ヤマト運輸株式会社ならではの、フットワークの良さがよく現れた事業だといえるでしょう。
大手の成功事例4. ヤマダ電機

全国展開の店舗網を活用して、リフォーム業界に参入
家電量販大手の株式会社ヤマダ電機は、2010年代に入ってから、プレハブ住宅メーカーの買収、住宅リフォーム業者との資本提携などにより住宅産業に進出しています。
特に住宅リフォームに特化したサービスに力を入れており、既存の家電量販店網を活用して、販路拡大を目指しています。
では、なぜ家電量販店が住宅業界に参入したのでしょうか。
その理由は急速に発展し続ける社会のICT(Information and Communication Technology 情報通信技術)化があります。
近い将来にIoT(Internet of Things モノのインターネット)が普及すれば、ほぼすべての家電はインターネットに接続されることが予想されています。
IoTとは、簡単にいえば、電気で動く機械をインターネット経由で操作できるようにする技術とその思想のことです。例えば外出先からスマートフォンのアプリを使って自宅にある炊飯器のスイッチを入れたり、冷蔵庫の中身を確認して今夜の夕食の献立を決めたりすることができるのです。
家電のIoT化が進むと、住宅は情報機器化した家電のプラットフォームとなります。
そこで「IoT企業」を標榜する株式会社ヤマダ電機は、家電と住宅が融合する将来性を絶好の投資機会ととらえ、まずは住宅のリフォーム事業に進出したと考えられます。
全国に展開する家電量販店舗の一角にショールームを構え、ユーザー目線での営業活動を展開中です。将来的に拡大が予想される新しいマーケットシェアの獲得に向けて、既存の店舗を利用して機能を拡張するという手法はリスク管理としても理想的な戦略でしょう。
「成功パターンは分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細はコチラ>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /
大手の成功事例5. ホンダ

自動車で培った技術を小型ビジネスジェット機に転用し、圧倒的シェアを獲得
本田技研工業株式会社の「ホンダジェット」は、2015年から発売された小型ビジネスジェット機で、2021年の納入数が37機と同クラスで5年連続で首位を獲得しています。
他社には真似できない独自のエンジン配置などを行った結果、燃費・速度・客室容積・操作性・静粛性などが従来のビジネスジェット機に比べて特に高く、また超軽量ジェット機としては比較的低価格で販売されています。
自社の技術を生かすだけでなく、コロナ過での密を避けられる移動手段の需要など、消費者のニーズを的確にキャッチした成功例です。
また、人気ロックバンドとのタイアップCMを製作し、2018年上半期にYoutube上でもっとも再生された広告になるなど、広告に力を入れたことも成功の要因です。
大手の成功事例6. 三井物産
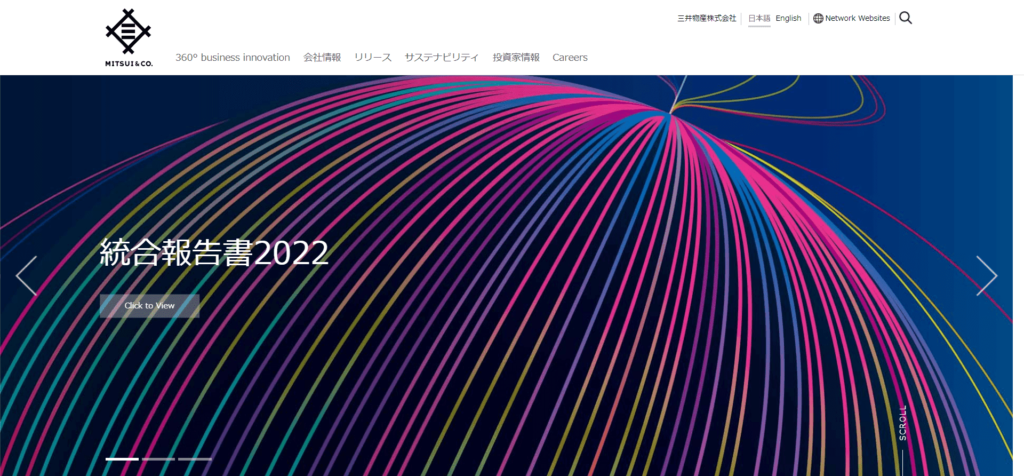
若者向けAIスピーカーを、シニア向けに改良しヒットさせた
三井物産株式会社のボイスタートは、社内ベンチャーの設立例の一つであり、シニア世代に対する音声AIスピーカーを活用した音声サービス・アプリ事業です。
近年、AI・音声認識の技術革新により音声AIスピーカーを活用することで、スマートフォンなどを使うことなく音声のみで音楽鑑賞や調べ物・買い物などができるようになりましたが、それらを活用しているのは若者がほとんどでした。
ボイスタートはシニア世代にも使いやすい音声サービスを提供し、また併せてサービス利用者が地域コミュニティとつながり、心身ともに健康でいられることも支援しています。
社会問題の解決に向けて事業を立ち上げることや、社員が主体的にビジネスを立ち上げることなど、三井物産ならではの戦略です。
大手の成功事例7. 日本郵政×Yper株式会社

高価な宅配ボックスの代替品を開発し、配送業務の人手不足を解決
日本郵政株式会社では、置き配バッグ「OKIPPA」を活用した玄関前などでの置き配を始めました。これにより配送業務の人員不足を軽減したり、コロナへの感染リスクを抑えたりすることが可能です。
置き配はこれまでも宅配ボックスなどを活用する方法がありましたが、高価であまり導入が進んでいませんでした。
しかし、Yper株式会社が運用する折り畳みバッグ方式のOKIPPAは低価格で導入しやすく、また配送大手の8社の配送状況を専用アプリから確認できます。
OKIPPAを活用した新規事業は、配送業務の人手不足を解消できる、理想的な戦略といえるでしょう。
大手の成功事例8. 日立製作所

グループ会社の叡智を結集した、IotTプラットフォーム
株式会社日立製作所のLumadaとは、Iotの進展により社会やビジネスが生み出す膨大なデータを活用することで、経営課題の解決や事業の成長に貢献するサービスです。
大きな時代の変化にあって一社で解決するのが困難な問題も、Lumadaによってさまざまな知恵を結集し、新しい価値やビジネスを見出すことで問題の解決が可能になります。
世界有数の総合電機メーカーであり、さまざまなグループ会社による知恵や技術をもつ株式会社日立製作所にしかできない理想的な戦略です。
多くの大手企業がLumadaのソリューションを活用しており、需要予測や品質管理などに役立てています。
大手の成功事例9. ダイハツ工業

介護事業者向けの送迎サービス、らくぴた送迎
ダイハツ工業株式会社のらくぴた送迎は、送迎の効率的なルートの作成などが可能な、介護事業者向けの通信サービスです。
職員が担当することの多いデイサービスなどの送迎では、道が混雑している時間帯に複数の利用者宅を時間通りに巡回することが難しいことに着目し、開発されました。
専用アプリで巡回するルートを表示してくれるだけでなく、施設とドライバーとの間でキャンセルを簡単に相互連絡できたり、施設や利用者宅への到着を自動で通知できたりするなど、介護事業者向けの送迎サービスという市場で成功するための、細やかな戦略が練られています。
大手の成功事例10. (株)キュア・アップ

禁煙を目指す人をサポートする ascure卒煙プログラム
株式会社キュア・アップは、アプリで治療する未来を創造する、モバイルヘルスプログラムを開発しており、禁煙を目指す人をスマホアプリでサポートする「ascure卒煙プログラム」を企業の健康保険組合向けに提供しています。
禁煙外来での指導経験豊富な指導員が、専用アプリを通じて利用者の状態を把握するため、より個々人の状態や悩みに的確な支援が可能です。
また、オンラインビデオ通話による禁煙指導のため、通うことなく支援を受けることができるので、物理的・心理的にも始めやすい特徴があります。
日中通院できない方でも始められる点や自社の技術を生かせる点など、理想的な戦略です。
大手の成功事例11. ソニー

ソニーのブランドイメージを有効活用し、新規事業の専門家ポジションでマネタイズ
大手総合電機メーカーのソニー株式会社は、新規事業支援プログラム「Sony Startup Acceleration Program(SSAP)」を、社内外に提供しています。
SSAPとは、事業化の進め方が分からない方や企業へ向けた、アイデア創出から事業化までをワンストップで支援するプログラムのことです。
大手企業も多く利用しており、京セラ株式会社や株式会社LIXILなど、7年間で17の事業化に成功しています。
ソニー株式会社のSSAPは、「技術力はあっても事業化のノウハウがない」「BtoBに比べてBtoCのノウハウがない」という企業でも、市場や物流などビジネスの流れを一から学ぶことができ、新規事業成功へ導いてくれます。
「成功パターンは分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細はコチラ>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /
中小企業が新規事業に参入し「成功する3つのパターン」
新規事業への参入には、さまざまなパターンがあります。中でも以下の3つは、代表的な新規事業参入のパターンです。
- パターン1. 「本業に関連した」新規事業参入
- パターン2. 「自社の経営資源を転用した」新規事業参入
- パターン3. 「企業買収による」新規事業参入
パターン1.「本業に関連した」新規事業参入
新規事業を考える際に、1番簡単で効果がすぐに期待できるのは「本業に関連した市場への参入」です。既に事業を行っている市場であれば、事業に関する知識や経験があるため敷居は低いでしょう。
本業に関連した事業には下記2つのパターンがあります。
- 風下の事業
- 風上の事業
例えば製造業を事例として取り上げると、風下とは、「本業に関連する素材分野」、風上とは、「本業と関連する製品分野」のことになります。
パターン2.「自社の経営資源を転用した」新規事業参入
経営資源を転用した参入は、いま自社で持っている経験や設備、ノウハウを応用して新規事業に参入することです。
例えば、ECサイトでの集客ノウハウを持つ会社が、ECサイトの集客コンサル事業を始めたりすることで、市場への参入障壁や競合優位性を持つことができるでしょう。
代表的な競合優位性・参入障壁の事例10個
- ネットワーク効果
- 独自のデータ
- 圧倒的な資本力
- ブランド力
- 知財や特許
- 複数製品のバンドル化
- 排他的な(真似しずらい)流通網や配送網
- コミュニティ
- 人材力 / 人数
- 法的な規制
パターン3.「企業買収による」新規事業参入
先に上げた2つのパターンは、自社で持っているものを転用して新規事業を行います。それに対して企業の買収(M&A)は少し毛色が異なり、既に事業を行っている企業を買収し参入するパターンです。
このパターンのメリットは、参入する市場のノウハウや設備を1からそろえる必要がないため時間を短縮できる点です。(その代わり、企業風土やルールの統一などの手間がかなり掛かります)
「成功パターンは分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細はコチラ>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /
中小企業が新規事業で成功する「4つの共通点」
新規事業が成功する中小企業には、ある一定の共通点があります。本章では、下記の新規事業を成功させる中小企業の4つの共通点を詳しく解説していきます。
1. 人材育成と積極的な採用ができている
2. 仮説検証のスピード感がある
3. ターゲット設定が練られている
4. 顧客志向サービスであること
成功の共通点1. 人材育成と積極的な採用ができている
新規事業が成功するためには、新規事業を担当する従業員と、そのチームに良い環境を用意することが必須事項です。また、新規事業のために新規採用するのであれば、その新たな従業員のチームにおける役割をはっきり明示し、その役割に責任を持たせるよう教育をおこなう必要があります。
また、チーム内でコミュニケーションを円滑にすることは、相互理解が深まり自分の役割が明確になります。良い人材が育つことで良い事業になり、良い事業になることで良い人材が集まるいいサイクルが新規事業の成功の元になりえます。
成功の共通点2. 仮説検証のスピード感がある
新規事業は、とにかくスピードが重要です。完璧な物を世にだそうと思うあまりに、時間がかかってしまい競合他社に先を越されてしまう可能性があるからです。
スピードを大切にするには初めから事業の枝葉までを決めず、最低限の部分だけを決めてスタートを切る方法が有効です。そして、市場の反応を見て、改善を繰り返しながら、素早く修正をしていくことが成功するコツです。
成功の共通点3. ターゲット設定が練られている
どんな事業においても、ターゲットが明確なことは極めて重要です。
ターゲットを決めるときに大切なことは、
- ターゲット市場に強い競合がいないことを見極める
- ペルソナを設定する
ペルソナとは、ターゲットを「年齢」や「性別」といった雑な切り方をするのではなく、「趣味」「家族設定」など人物像をよりリアルに深く設定していくことです。
また、必ずペルソナは定期的に検証・改善・更新をしておきましょう。間違っても、「1度つくって終わり」な状態にしないことが重要です。
成功の共通点4. 顧客志向サービスであること(そのために顧客に向き合う時間を確保する)
サービスを購入してくれる顧客のニーズを掴むため、また改善するには、顧客と向き合う時間を多く確保すること必要です。
そのためには、余計な(事業に直接は関係しない)業務を簡素化、つまり無くしてしまうことが有効です。余計な業務を減らすことで、顧客と向き合う時間を確保でき、早いタイミングで顧客合ったブレイクスルーポイントを見つけることが可能になります。
余計な業務の例としては、経営陣や上司への報告業務が挙げられます。
定例の報告業務は、経営者や上司が思っている以上に「現場の時間とリソースを奪う作業」です。そもそも、経営者や上司も新規事業の立ち上げや収益化に関わっていれば、日々の動きを把握しているため、報告業務などいらないでしょう。ちなみに、新規事業に経営者や上司が真剣に向き合っていないプロジェクトは上手くいきません。(論外です)
新規事業を計画する際には、事前に「なにが重要業務」で、「なにが不要な業務(簡素化)」なのかをすり合わせておくと良いでしょう。
中小企業が新規事業で「失敗する4つの共通点」
失敗の共通点1. 市場調査やニーズ把握が粗雑(そもそも、調査すらしていない)
新規事業が失敗する主な原因は、市場を選び間違える、もしくは顧客ニーズを読み間違えることです。新規事業に参入する前に市場調査もやっていない、きちんと顧客ニーズも把握していないまま新規事業を進めてしまうと、狙って新規事業を当てることは難しいでしょう。(ラッキーパンチもありますが、稀です)
失敗の共通点2. 人材不足
ベンチャーや中小企業の場合、必要最低限のメンバーから新規事業を始めることが多いもの。関連部署からメンバーが招集されることも多く、従業員は元々の担当業務と並行して新規事業をおこなっている、なんてことは現場でよく目にする光景です。
この場合、メンバーは新規事業に上手く時間を充てることができず、
- 革新的なアイデアが生み出されにくくなる
- 新規事業に時間が割けず、新規事業が進まない
こんな事象がかなりの確率で発生します。
経営者や上司の方からすると「既存事業も新規事業も大事なんだから、どっちも頑張れ!」となるのですが、メンバーからすると、難易度が高く、成功するかもわからない新規事業に時間を充てるくらいなら、「慣れている既存事業の自分の担当仕事をこなす方が楽だし、評価につながるし…」というのが本音でしょう。
失敗の共通点3. 仮説検証のスピードが遅い
新規事業の場合、顧客ニーズを把握するスピード、また、サービス化して提供するまでのスピードが重要です。そのため、製品やサービスは完璧な状態で提供するよりも、市場の反応を見ながら小さく改善を加えながら、少しでも早く提供していく(スモールスタート)でおこなっていく方が有効なのです。
失敗の共通点4. 撤退基準が不明確
新規事業は、始めることは簡単でもやめることは意外と難しいものです。
慈善事業を除いて、企業は利益を出さないと倒産してしまいます。新規事業を始めるときは、最初から「ここでやめよう」という明確な基準を設けることが必要です。
「儲かっている間に事業領域の最適化をはかる」という理由で撤退をする積極的撤退の場合は、まだ良いです。難しいのは、赤字や不況などでやむを得ず撤退する「消極的撤退」です。この場合は、今まで投資した資源に見切りを付けなければならないため、判断が難しいといわれてます。
撤退のタイミングに困ったときは、貢献利益を基準にすると良いです。
貢献利益とは、売上高から変動費と直接固定費を差し引いたものです。貢献利益が黒字である場合はその事業から利益が得られているということになります。そのため、営業利益が赤字であっても、貢献利益が黒字の場合は、経営次第で営業利益も黒字にできる可能性があります。逆に、どんなに頑張っても営業利益が黒字になることが難しい場合、事業の撤退を検討する必要があるのでしょう。
その一方で、貢献利益が赤字の場合は、貢献利益を黒字にできそうであるか費用を見直す必要があります。改善出来そうな余地がある場合、撤退せず、再スタートを切るのも良いでしょう。
あわせて読みたい
「事業撤退すべきか?継続すべきか?」判断基準と撤退方法を徹底解説
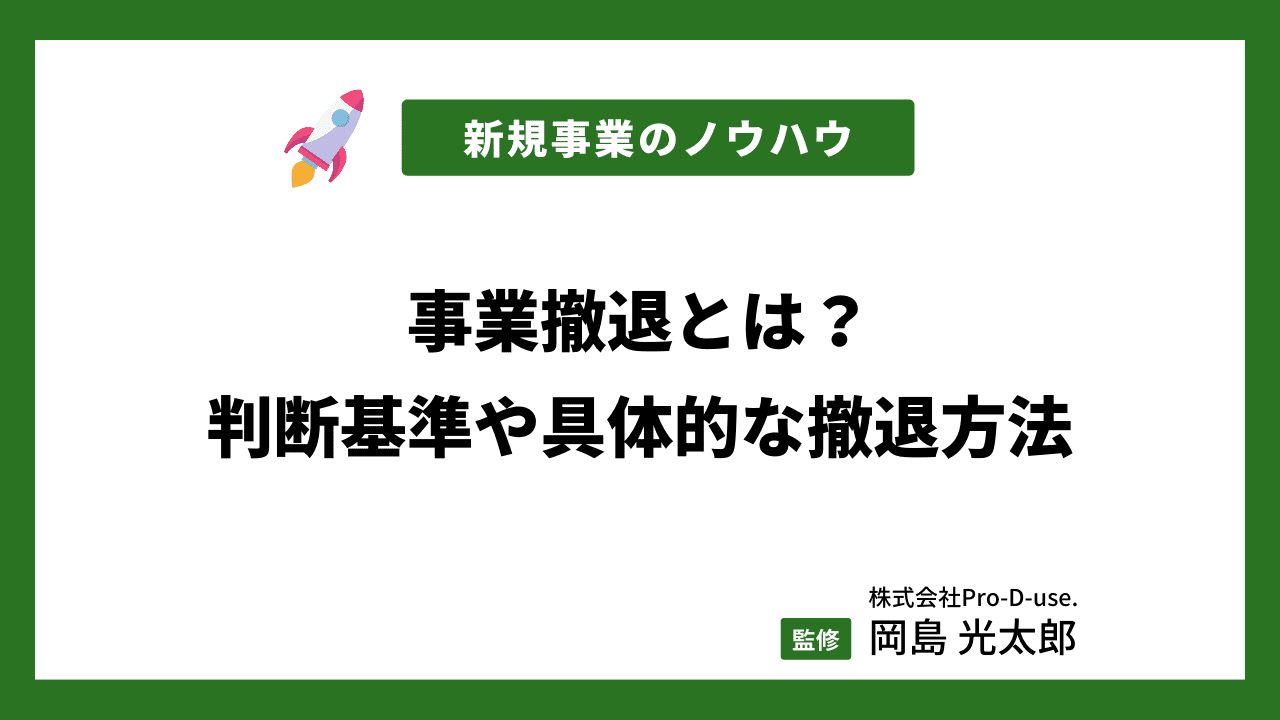
事業撤退とは、「採算が取れない、または、市場で優位性を失った事業を停止すること」です。沈んでいる事業を軌道に乗せるのは簡単ではないため、その事業の損失が会社経営に影響を及ぼすようであれば、その事業は撤退するのが得策です。 事業撤退を視野に入…
中小企業が新規事業の立ち上げを行うべき2つの理由とは?
新規事業には失敗するリスクがある上に、会社の経営資源も投下しなければなりません。それでも安定的な利益の獲得のために、中小企業も新規事業に取り組む必要があります。
なぜ、安定的な利益の獲得のために新規事業に取り組むべきなのでしょうか?その2つ理由を解説していきます。
1. 「市場変化」への対応
現在、人々が時間や場所を問わず情報を受発信することが容易になったため、市場の変化は激しくなっています。市場の変化が激しいということは、「顧客のニーズも日々変化している」と置き換えても問題ないでしょう。
企業は顧客のニーズを適切に把握し、スピーディーにそのニーズに対応した事業を行うことが必要になります。
2. 従業員の育成
新規事業を行うことは、自社の従業員を育てる良い機会になります。
新規事業というのは、もちろん1から事業立ち上げていきます。その過程で、様々な成功や失敗があります。従業員はその成功と失敗を繰り返すことで、ビジネスの本質を学び、書籍などでは得られない経験やスキルを得ることができます。
そのような人材は企業にとって貴重な人材になり、企業を支える大切な人材になりえる可能性が高いのです。
新規事業で成功するアイデアを生み出す方法・事例
成長を続けるため、経営を安定させるためには、新規事業の成功が大切です。しかし、自社に技術や熱意があっても、アイデアがなければ新規事業は成功しません。
そこでこの項目では、新規事業のアイデアを生み出すための方法・事例を5つ紹介します。
- 1. アンチプロブレム
- 2. ブレーンストーミング
- 3. マンダラート
- 4. マインドマップ
- 5. 6W3H
それぞれ詳しく解説します。
あわせて読みたい
社内新規事業の立ち上げにおける5つのプロセス|立ち上げを成功させるポイ…
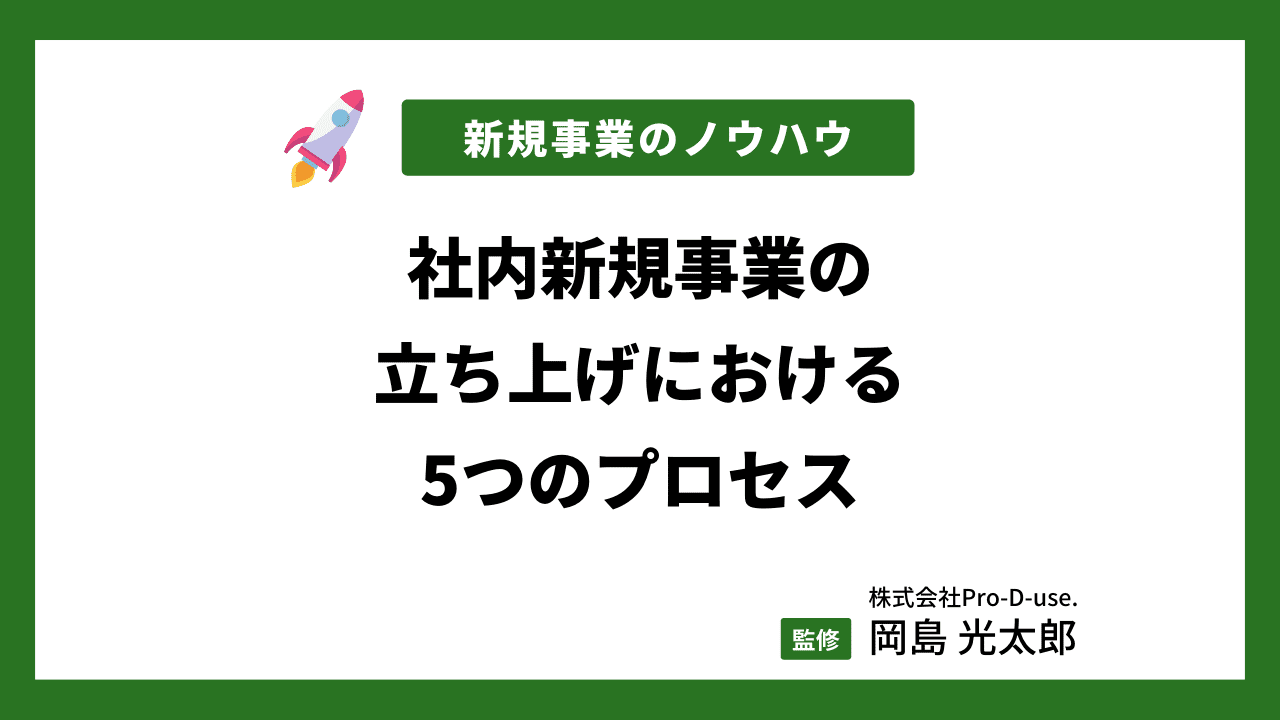
社内の新規事業立ち上げを検討している経営者には、このような悩みがついて回ることでしょう。 社内新規事業を立ち上げるからには、しっかりとした計画を立てて事業を軌道に乗せたいものです。しかし、せっかく新規事業の立ち上げをおこなったにもかかわらず…
アンチプロブレム
アンチプロブレムとは、考えに行き詰ったときに、課題と逆の解決策を考えるアイデア発想法です。逆の考え方をすることにより、アイデアの幅が広がったり、解決方法が見えてきたりします。
活用する際には、課題を解決するためのアイデアではなく、「課題を解決しないためにはどうするか」や「質の悪いプロダクトはどう製作するか」などを考えるとよいでしょう。
正攻法では気づけなかった新しい発想や、斬新なアイデアを出すためには、アンチプロブレムが役に立ちます。
ブレーンストーミング
ブレストとも呼ばれるアイデア創出の方法で、会議形式でアイデアを出し合ったり、紙に書いて張り出したりして発想をブラッシュアップさせます。他の人のアイデアに刺激を受けることで新しいアイデアが生まれやすく、豊かな発想が可能です。
活用する際には、質にこだわらず自由に発言することと、最終的にアイデアを一つにまとめてください。他の人の意見を否定する行為は、その後にアイデアを出しづらくしてしまうため、やらないように気を付けましょう。
ブレーンストーミングは、アイデアが固まっていない初期の頃に行うと、効果的に進められます。
マンダラート
曼荼羅とアートを組み合わせた方法が、マンダラートです。マス目にアイデアを書き込んで整理したり、考えを深めたりできます。
やり方はまず、3×3で区切ったマス目の中心にメインテーマを書き入れ、残る8マスに関連語句を記入します。その後、3×3で区切ったマス目をさらに8つ用意し、それぞれの中心に先ほど書き込んだ8つの語句を記入してください。
再び、残ったマスに関連語句を記入し、さらにそれを繰り返していくと、アイデアを出すために必要な思考をさらに深めることが可能です。
あわせて読みたい
新規事業に必須のマンダラートとは?その効果や作成方法を解説
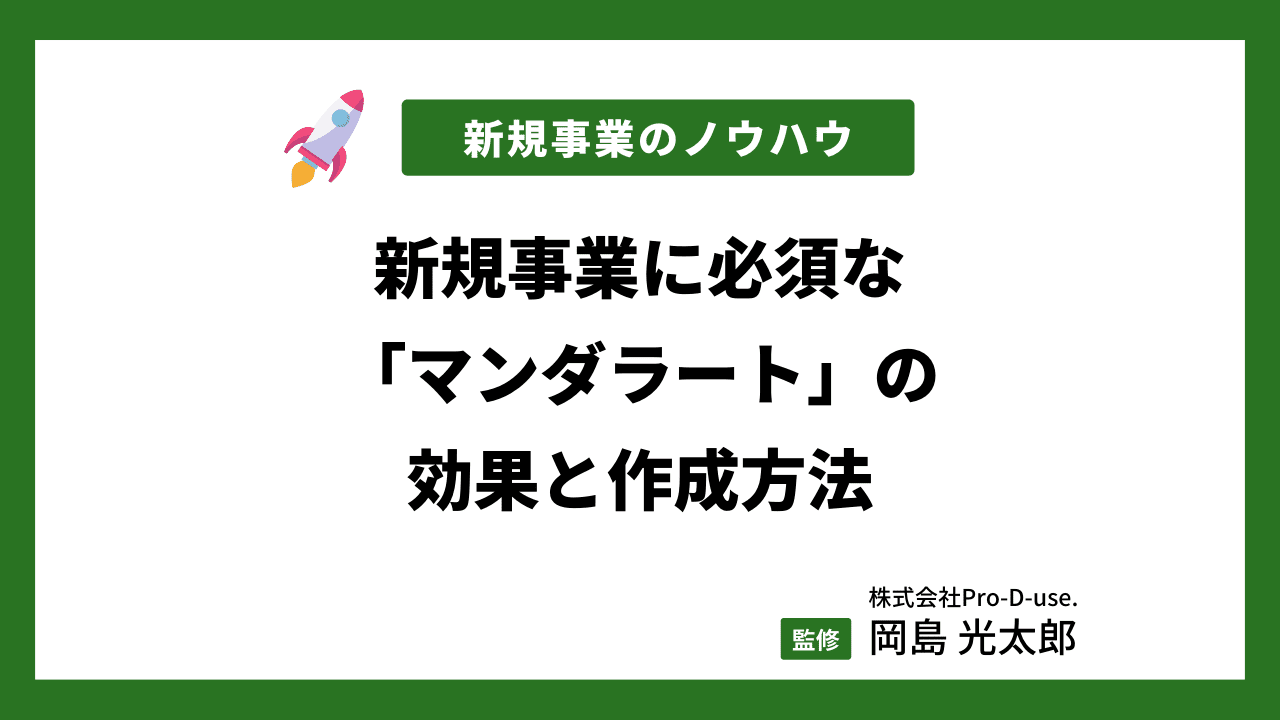
マンダラートは、目標達成やアイデア出し、思考整理などあらゆるシーンで活用できる、思考支援のフレームワークです。特に新規事業では強制的にアイデアを出したい際に活用するとよいでしょう。 この記事では、マンダラートとは何か、新規事業で使う効果や、…
マインドマップ
マインドマップとは、自由な思考・アイデア、情報の流れを、中心にあるメインテーマから放射状に分岐させる形で広げていき、新たな発想を得る方法です。
プロセスを見える化できるので、ブレインストーミングを行う際や、インパクトのあるプレゼン資料作成などの際にも役立ちます。
紙と鉛筆があれば手軽に行えるのがマインドマップの魅力ですが、写真・色どりなどを加えることで、より視覚的に理解を深めることができるため、そちらもおすすめです。
マインドマップ作成ソフト・ツールもあるので、ぜひ使ってみてください。
6W3H
6W3Hとは、文章を書く際に留意すると良い5W1Hに、さらにビジネスパーソンならではの語句を加えた言葉で、以下の9つのことです。
- なぜ:Why
- 何を:What
- 誰が:Who
- 誰と・誰に:with Whom
- いつ:When
- どこで:Where
- どのように:How
- いくら:How much
- どれだけ:How many
「誰に」「いくら」「どれだけ」を定義できるため、マーケティングやプロモーション戦略がより具体的になり、アイデア出しの役に立ちます。
また、仕事を進める上でも6W3Hは基本になるものなので、しっかり設定しておくと「期日に間に合わない」といったケースを防ぐことも可能です。
あわせて読みたい
【6W3Hとは?】フレームワークの使い方や新規事業&ビジネスへの活用法
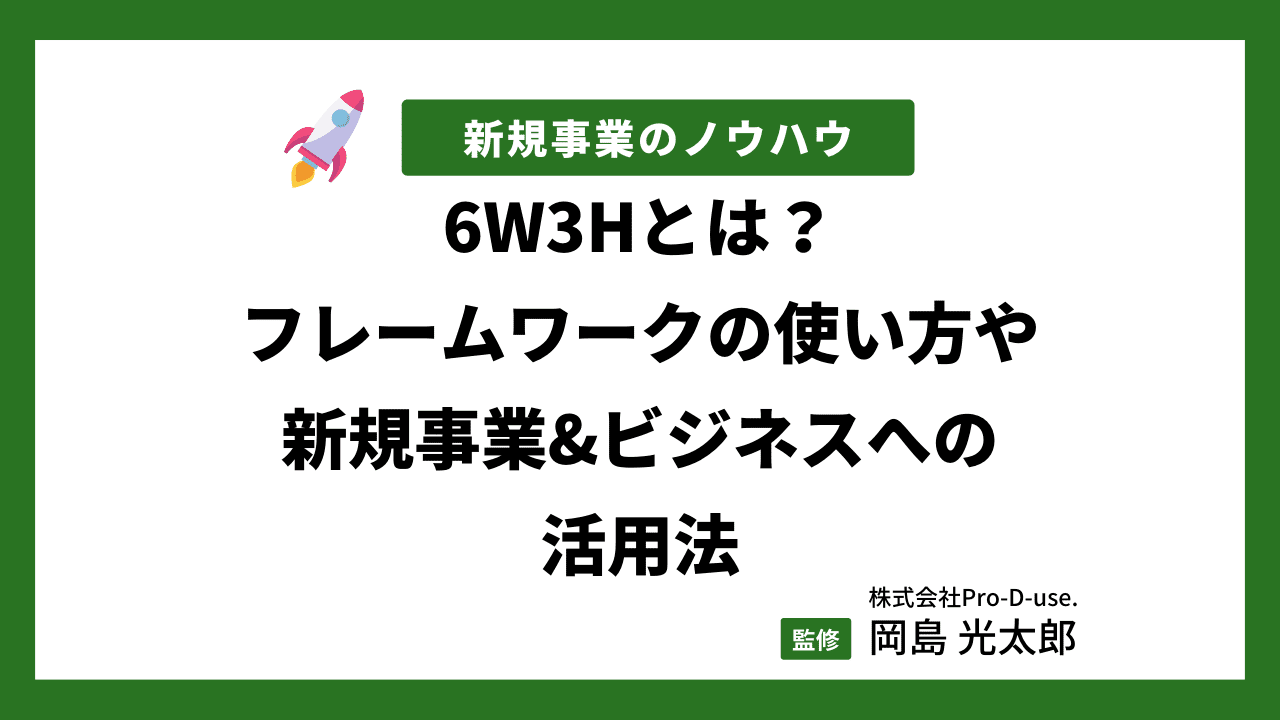
こんなお悩みや疑問を持っている、経営者やビジネスマンは多いのではないでしょうか? 実は、6W3Hはビジネスにおいて強力フレームワークであるにも関わらず、使い方を間違っている率もNo,1なのはあまり知られていません。なぜなら、5W1Hがあまり…
「成功パターンは分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細はコチラ>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /
新規事業の成功のために、まずは自社の技術・資産を見直そう
ここで紹介した新規事業の成功事例は、「既存技術の転用による新規商品開発の例」、または「所有する流通チャネルを活用した多角化経営の一例」でした。
こういった事例は、一見すると何の関係もないような他の業界への進出と見えるため、大きなリスクをはらむ行為のようにも見えます。しかし、既存のリソースの可能性を冷静に分析・把握してみると、意外と他分野への新規事業展開の道筋は見えてくるものなのです。
そこで、これから新規事業を進めていく方は、まずは「自社が保有する経営資源の見直し」から始めることをオススメします。今の経営資源を最大限活用できれば、新たな価値の創造は困難ではありません。自社の技術や資産を見直し、新規事業を成功させましょう!
成果の出ない新規事業にお困りではありませんか? Pro-D-useなら、新規事業の現場に入り込んで、あなたの会社の新規事業がドンドン改善します!
⇒(株)Pro-D-useの新規事業相談(無料)を受けてみる
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には「参考にすべき事例」があります。
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」の【新規事業の非公開事例】を聞いて、新規事業の参考にしてみませんか?詳しくは下記の新規事業のコンサルサービスページからお問い合わせください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業コンサルサービスはコチラ >>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /
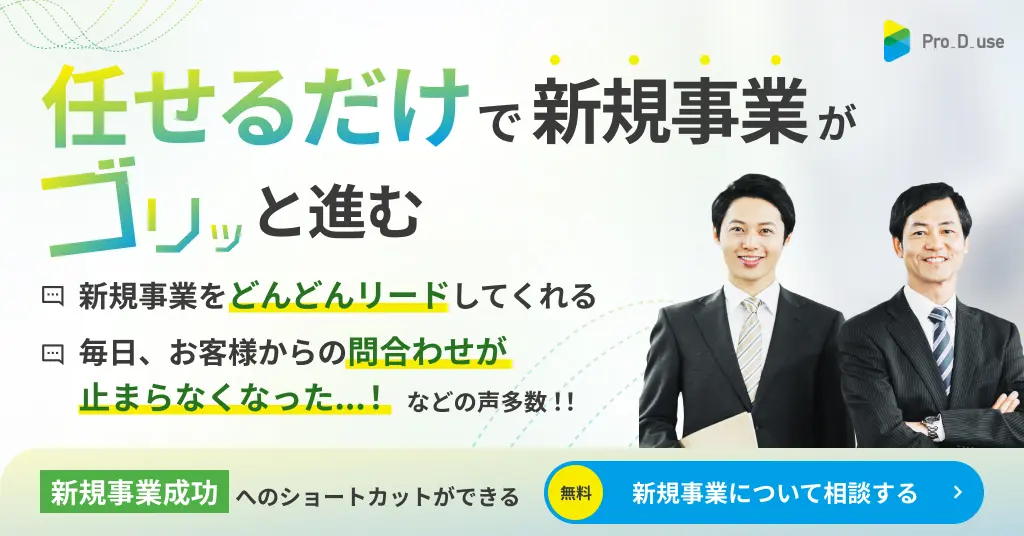
<参考>
http://shop-healthcare.fujifilm.jp/sp/astaliftbrand/technology/
http://www.unicharm.co.jp/ir/3minutes/step3/index.html
http://toyokeizai.net/articles/-/61896?page=3
http://www.nikkei.com/article/DGXLRSP435346_S7A200C1000000/