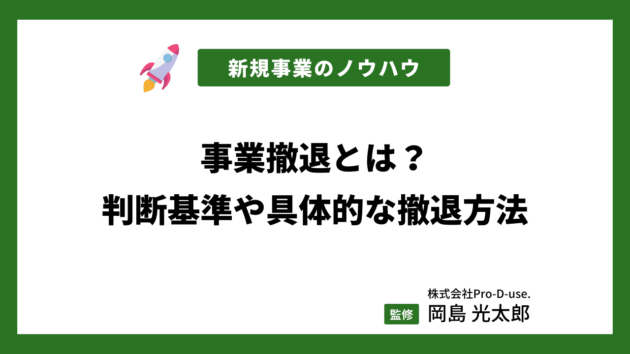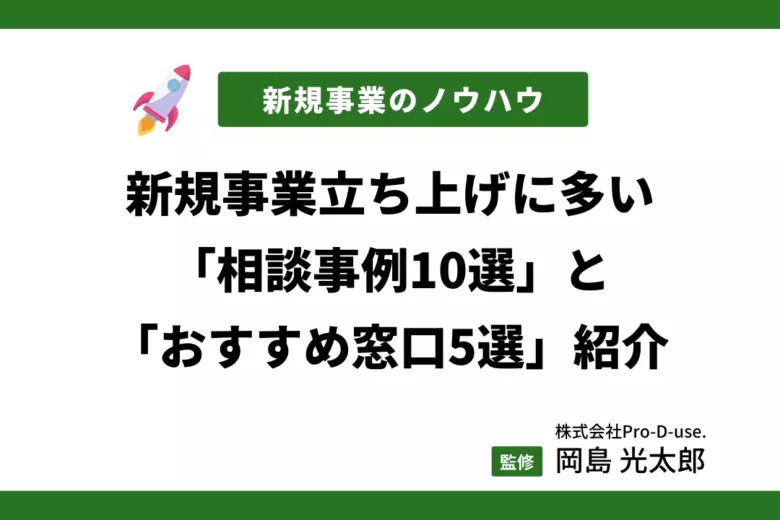事業撤退とは、「採算が取れない、または、市場で優位性を失った事業を停止すること」です。沈んでいる事業を軌道に乗せるのは簡単ではないため、その事業の損失が会社経営に影響を及ぼすようであれば、その事業は撤退するのが得策です。
事業撤退を視野に入れている経営者であれば、こんなことにお悩みではないでしょうか?
「事業継続する方がいいのか、撤退の方がいいのか基準が分からない…。」
「事業撤退したいが、どんな方法があるのか分からない…。」
事業の立ち上げするならば、なるべく順調に、かつ長期的に事業を継続していくよう舵を取るのが経営者の務めです。しかし、状態によっては事業撤退を検討しなければならないこともあります。
もしそうなってしまった場合、
・「事業撤退のタイミングや判断基準がわからない」
・「事業徹底の具体的な方法がわからない」
・「誰に相談すべきか悩んでいる」
このようなお悩みを持つことになります。
事業の撤退タイミングを誤ると、会社存続の危機に直面するおそれがあります。会社や社員を守るためにも、しっかりと理解したうえで検討することが大事です。
したがって、事業の立ち上げを検討するのなら、同時に事業撤退の判断基準も押さえておく必要があります。
筆者は、株式会社Pro-D-useという新規事業・事業再生の経営コンサルティング会社で、これまで多くの会社の事業構築・撤退をご支援してきました。
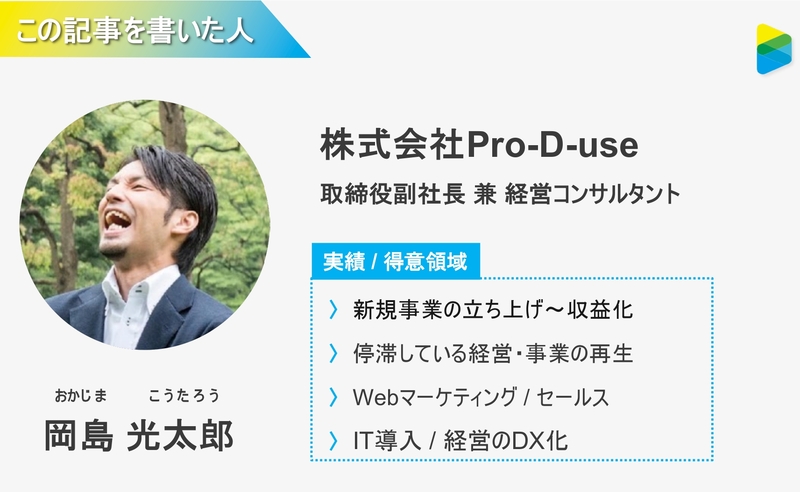
本記事では、そんな筆者の経験をもとに「事業撤退の基礎知識」や「事業撤退の判断基準」、「具体的な撤退方法」など、覚えておくべき情報をまとめました。
本記事で実現できること
- 事業撤退の判断基準がわかり、会社に与える損失を最小限にできる。
- 事業撤退のメリット・デメリットがわかる。
- 正しい事業撤退方法を学び、損失を最小限に、かつスムーズに撤退を実施できる。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。既存事業の事業撤退でお悩みなら、プロのコンサルの意見を聞いてみませんか?
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【既存事業の見直しを無料相談】してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
経営コンサルティングサービスはコチラ >>>
▼目次
【中小企業】弊社 (株)Pro-D-use顧客の事業撤退3つの事例
まずは、筆者の所属する株式会社Pro-D-useのお客様の事業撤退事例を3つご紹介します。
・「建設系会社」J社
・「営業系会社」E社
・「飲食系会社」M社
お客様を守るため、企業を特定できないよう所々をぼかして記載しておりますが、実例を元にしているため生々しい事例となっています。ぜひ、ご参考ください。
中小企業の撤退事例1. 「建設系会社」J社

大手企業や公共事業から大型建設現場を任されるJ社様の事業撤退の事例です。下記の会社概要の通り、中堅企業に該当する法人様です。
◆ 会社概要
会社名 :J株式会社
設立 :1980〜2000年
従業員数:50~100名
事業内容:建設事業
撤退した事業概要は下記の通りです。
◆ 事業撤退の概要
撤退事業 :遮音壁の設計・販売(大型工事向け)
事業シナジー:シナジーを狙っていたが、実際は全くなかった。
事業メンバー:5名
実績 :累計5億円(6~7年)
撤退フェーズ:事業化後
継続年数 :6~7年
撤退理由 :そもそも採算性が低かった。当初期待していたシナジーもなく、本業の建設事業のマンパワーも枯渇していたため、今後の市場性を考えて撤退。
撤退影響 :優秀な人材が2名辞めた。(撤退事業にコミットしていたため)
撤退コスト :施工後の「メンテナンス」「トラブル」対応(対応人件費)
役員の肝入りで「遮音壁の設計・販売」という新規事業を6~7年展開していましたが、そもそも「対象事業で利益が出ているのかどうか?」も管理をしていませんでした(管理会計不足)。
学びのポイントとしては、「販売の見通し・事業シナジーを十分に検討しない状態で参入したこと」また、「利益管理をしていなかった」ことです。
弊社がコンサルティングに入らせていただき、新規事業単体の利益管理をしたところ、人件費を使っている割には利益が極小だったこと、また、事業シナジーもなく、本業のマンパワーも枯渇していたため早々に事業撤退の打診・提案をし、事業撤退となりました。
中小企業の撤退事例2. 「営業系会社」E社

様々な商材を営業代行とアフターフォローで事業を営んでいたE社様の事業撤退の事例です。下記の会社概要の通り、小規模事業者に該当する法人様でした。
◆ 会社概要
会社名 :E株式会社
設立 :1990〜2010年
従業員数:5~10名
事業内容:営業事業
撤退した事業概要は下記の通りです。
◆ 事業撤退の概要
撤退事業 :空気清浄機の代理店販
事業シナジー:なし。想定もしていない。
事業メンバー:4名(新規採用)
実績 :累計450万円(販売は3ヶ月で終了)
撤退フェーズ:テストマーケティング
継続年数 :6ヶ月
撤退理由 :想定より売れなかった
撤退影響 :正社員4名の退職
撤退コスト :なし(在庫もない)
空気清浄機の代理販売を新規事業として起こしましたが、そもそもの参入タイミング、また販売と利益の見通しが甘く、6ヶ月ほどで撤退しました。
学びのポイントとしては、「販売の見通しがない状態で参入したこと」また、「いきなり正社員を新規採用してしまった」ことです。
結果として、事業撤退のタイミングで新規採用した優秀な正社員4名すべてが退職しました。
弊社は新規参入3ヶ月目からコンサルティングに入らせていただき、早々に事業撤退の打診・提案をさせていただきました。
中小企業の撤退事例3. 「飲食系会社」M社

アジア地域に「おにぎり屋(日本食)」を展開するために立ち上がった海外法人M社様の事業撤退の事例です。下記の会社概要の通り、小規模事業者に該当する海外法人様でした。
◆ 会社概要
会社名 :J株式会社(海外法人 / アジア)
設立 :2000〜2020年
従業員数:5~10名
事業内容:飲食業
撤退した事業概要は下記の通りです。
◆ 事業撤退の概要
撤退事業 :低価格帯の回転数の多いおにぎり屋
事業メンバー:8名(海外人材をトップにした組織)
実績 :累計1,100万円(日本円換算)
撤退フェーズ:事業化後
継続年数 :6ヶ月年
撤退理由 :オペレーションの再構築中に、コロナ禍で撤退
撤退影響 :法人休眠状態へ
撤退コスト :店舗の不動産解約費用
日本人のオーナーの「海外の人に日本食の素晴らしさ伝えたい」という想いの元、アジア地域に海外法人を設立して開始した新規法人&新規事業でした。
しかし世界的なコロナ蔓延と、海外人材を法人トップに置き丸投げしてしまったこと、見切り発射での事業展開のため、6ヶ月ほどで撤退しました。
回転数を上げることが売上と利益に直結する業態だったため、テイクアウトを主軸にして店舗運営をするはずが、現地法人のスタッフの判断でイートインスペースを作って運営をしてしまい、回転数・売上・利益ともに想定の50%以下。
「話し合えばわかるはず」と、Web会議のみで現地に日本人スタッフを派遣しなかったため、イートインスタイルが改善することなくコロナ禍に突入し、先が見えないため事業撤退をしました。
学びのポイントとしては、「海外の現地スタッフに任せきり(丸投げ)してしまったこと」また、「途中で現地に日本人を駐在させるという方針転換ができなかったこと」です。
結果として、大きなマイナスを抱えた状態で法人・事業ともに解散となりました。
弊社は新規参入3ヶ月目からコンサルティングに入らせていただき、早々に事業撤退の打診・提案をさせていただきました。
【有名大企業】6つの事例から学ぶ、事業撤退の基準
中小企業の事例のあとは、有名大企業の事業撤退事例を6つご紹介します。みなさんもご存知の大企業であっても、事業撤退せざるを得ないタイミングは訪れます。
本章では、有名大企業の事業撤退の基準を事例を用いながら、具体的に解説します。
本章で紹介する有名会社は以下の6社です。
- 事例1. サイバーエージェント
- 事例2. リクルート
- 事例3. ソフトバンク
- 事例4. メルカリ
- 事例5. DeNA
- 事例6. ユニクロ
大手企業の撤退事例1. サイバーエージェントの新規事業撤退基準

サイバーエージェントは「21世紀を代表する会社を創る」をビジョンに掲げる、メディア・ゲーム・インターネット広告事業を主とする日本のIT企業です。ABEMAやAmeba(国内最大級のブログサービス)、タップル(恋活マッチングアプリ)など多くの方が利用するサービスを提供しています。
同社は営業利益によって事業を3つにランク分けして、2四半期連続で減収減益になった場合は事業責任者の交代や撤退をすることを明らかにしています。
大手企業の撤退事例2. リクルートの新規事業撤退基準

筆者の元勤務先である株式会社リクルートホールディングスは、人材派遣や販売促進、求人広告などさまざまなサービスを手掛ける日本の企業です。
東洋経済が新規事業開発室部長の渋谷昭範氏にインタビューしたところ、同社の撤退判断は想像以上にシビアです。
具体的には、以下の4つの判断基準を順番に確認することで、撤退するかどうかを判断しています。
- 本当にニーズがあるか
- 本当に収益性が見込めるか
- 本当にサービスを使ってもらえるか
- 本当に広く提供できるのか
大手企業の撤退事例3. ソフトバンクの新規事業撤退基準

ソフトバンク株式会社は、携帯電話などの無線通信サービスや国際通信を提供する日本の大手電気通信事業者です。
新R25によれば、ソフトバンクグループの創業者である孫正義さんは「孫正義 リーダーのための意思決定の極意」で「3割以上のリスクは冒さない」「7割以上勝つと見込めるまでは、執拗に理詰めで攻めていく」と発言しているようです。
ソフトバンクは多くの事業を勢いよく進めている印象がありますが、実は用心深く経営を行っていることが伺えます。
大手企業の撤退事例4. メルカリの新規事業撤退基準

株式会社メルカリはフリマアプリの「メルカリ」を運営する日本の企業です。週刊ダイヤモンドのインタビューによれば、撤退基準はメルカリの初期の損益計算書をもとにしているようです。 具体的にはサービスを始めて3ヶ月であれば、いくら広告費を使って、どのくらい成長したかといった数値を基準にしています。
緊張感を持ちながら新規事業を進めるために、事業をプロジェクト制にして可視化しているようです。
大手企業の撤退事例5. DeNAの新規事業撤退基準

株式会社DeNAは スマートフォンゲームの開発やSNS運営、電子商取引サービスといった事業を中心に据えている日本の企業です。
同社は、ある地点までの満足度の伸びやユーザー熱量といったKPIが計画に対して順調かどうかを確認します。ちなみに事業継続の判断は3ヶ月に1回は実施されます。
大手企業の撤退事例6. ファーストリテイリングの新規事業撤退基準

株式会社ファーストリテイリングは、株式会社ジーユーや株式会社ユニクロなどの衣料品会社を複数持つ世界有数のアパレル製造小売業会社です。
Business Journalによれば、同社は1997年にスポーツウェアとシューズの店「スポクロ」を出店しました。しかしユニクロとの違いを見出せなかったため、撤退したのです。本事例を見る限り、同社の事業撤退の基準は「差別化できるかどうか」のようです。
「即座に事業撤退すべき」6つのチェックポイント
事業が好転する見込みがない場合のは、とても簡単に事業撤退の意思決定できるはずです。例えば、下記条件にいくつも当てはまる事業の場合は、即座に撤退を判断できるはずです。
以下は、事業撤退の6つのチェックポイントです。もし、あなたの会社の事業で4つ以上チェックが付く事業があれば、即時撤退をすべきです。
◆ 事業撤退すべきチェックポイント
- 現時点で巨額の赤字を垂れ流している
- 今後も収益化の見込みがない
- 自社の他事業とのシナジーもない
- ビジネスモデル、マネタイズモデルの変更もできない
- 同事業の競合も利益が出せていない(もしくは利益縮小傾向)
- 新規事業に関わっている従業員の士気が低い
しかし、赤字を出しているものの今後持ち直す可能性がゼロとは言い切れない事業の場合、意思決定は極端に難しくなります。例えば下記のような条件が揃っている場合です。
「事業撤退をすべきでない」6つのパターン
- 現在は赤字だが、売上(利益)に改善の兆しがある
- 現在は赤字だが、何かコストを絞れば利益が継続的に出る見立てがある
- 現在は赤字だが、自社の他事業とのシナジーが出ている
- ビジネスモデル、マネタイズモデルの変更すれば可能性がある
- 同じ事業をしている競合は利益が出ており、かつ拡大傾向である
- 新規事業に関わっている従業員の士気が高い
このパターンの場合は、「立て直しを図るのか?」「事業撤退を決断するか?」判断に迷うことでしょう。
ただ、事業撤退の判断を先送りにしていると、赤字や負債が拡大し、大きな痛手を被ってしまうおそれがあります。いざ赤字や負債を出してから「事業撤退するか否か」を考え始めると手遅れになりかねません。
したがって、新規事業を立ち上げるのなら、あらかじめ事業撤退の判断基準を設けておくことが大切です。
事業撤退を判断する5つの判断基準
では、事業撤退の判断基準はどのように決めればよいのでしょうか?ここでは、事業撤退を判断する基準を5つのポイントに分けて解説します。
- KPIを用いて判断する
- 会計上の損益または投資回収率で判断する
- 市場の成長性・シェア率で判断する
- SWOT分析を通して弱点を再度把握したうえで判断する
- 事業が赤字でも貢献利益から判断する
それでは、事業撤退の5つの判断基準をひとつずつ紹介します。
判断基準1. KPIを用いて判断する
企業が特定の目標を達成するために行うさまざまなプロセスや行動に対する評価をKPIで数値化することで、客観的に目標の達成度合いをチェックすることができます。
たとえば、新規事業の立ち上げにあたり、受注数や顧客数をKPIに設定し、「3年以内に70%以上達成できなければ事業撤退」といった基準を設けておけば、大きな損害を出す前に事業撤退か継続かの判断を下すことができます。
例えばサイバーエージェントを例に挙げます。
サイバーエージェントでは、営業利益によって事業を3つにランク分けして、2四半期連続で減収減益になった場合は事業責任者の交代や、撤退することを明言しています。
このようにKPIで事業撤退を判断できると、目に見える指標で判断できるためとてもシンプルですし、とくに競合他社が多い業界においては、「対等か、それ以上に渡り合える存在になり得るかどうか」を見極めるのに役立つでしょう。
判断基準2. 会計上の損益または投資回収率で判断する
KPIを用いた判断基準の場合、赤字や損失を出していても、顧客数や発注数が目標を達成していれば、事業継続という判断になることもあります。
一方、会計上の損益または投資回収率で事業撤退の可否を判断する場合、利益を出すことが最低条件となります。
たとえば、
- 「5年以内に黒字にならなければ事業撤退」
- 「投資額が一定ラインを上回るようなら事業撤退」
といった基準を設けておけば、損失を出す前に、あるいは損失が大きくなる前に撤退することができます。
ただ、どこからどこまでを評価・コストに盛り込むかの判断が難しいという欠点もあります。
新規事業の立ち上げにあたって費やした初期投資を計算に入れるかどうか、他の事業と共通するコストを計上するかどうかなどを当初から決めておかないと、当該事業を正確に評価できなくなるおそれがあるため、要注意です。
判断基準3. 市場の成長性・シェア率で判断する
現時点でかろうじて利益がある、もしくは損失が少ない事業の場合、良い意味でも悪い意味でも会社に大きな影響をもたらす存在ではないため、事業継続か、撤退かで迷うところです。
そんなときは、市場の成長性やシェア率にも目を向けてみましょう。
理想は、市場成長性・シェア率ともに高い事業です。
しかし、今後大きな成長性が見込めなくても、現時点で高いシェア率を誇っている事業であれば、会社にとって貴重な収入源となります。
逆に、市場シェアが低い事業でも、今後の市場成長性が見込める場合は、早期に事業撤退を決めるのは早計です。
市場シェア率が低く、今後の事業成長性も見込めない場合は、事業撤退の積極的な検討が必要です。
市場シェア率と市場成長率は以下の計算式で求められます。過去のデータも参考にしながら、伸び率をチェックしてみましょう。
市場シェア率(%)=自社の市場での売上もしくは販売数/市場の総売上もしくは総販売数
市場成長率(%)=今年度の市場の総売上/前年度の市場の総売上
追加投資を行うと一時的に赤字・損失を出してしまいます。
しかし、将来優秀な収益源となるのなら、大胆な手を打つのもひとつの方法です。
判断基準4. SWOT分析を通して弱点を再度把握したうえで判断する
SWOT分析とは競合や市場のトレンドといった外部環境と、自社のブランド力や商品といった内部環境を見直して状況を把握するフレームワークのことを指します。 SWOT分析は内部環境と外部環境の2つの観点から分析するため、客観的な視点が持てるようになります。

SWOT分析の具体的な手順は以下の通りです。
- 「ファイブフォース分析」と「PEST分析」などを用いながら外部環境(脅威と機会)を分析する
- 「4P分析」「4C分析」を活用しながら内部環境(自社の強みと弱み)を分析する
- 脅威と自社の弱みが重なっていないか確認する
※1 ファイブフォース分析:「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」「競争企業間の敵対関係」「新規参入業者の脅威」「代替品の脅威」の5つの分析して、業界内での競争状況を分析する手法
※2 PEST分析:政治や経済、技術、社会といった4つの観点から外部外部環境を分析するマーケティングフレームワークのこと
※3 4P分析:自社商品やサービスに関係する「Product(商品)」「Price(価格)」「Promotion(販売促進)」「Place(流通)」の4つの戦略領域を分析する手法
※4 4C分析:「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4つを分析するマーケティングフレームワークのこと
SWOT分析で判明した自社の弱みと外部要因の脅威が重なっていれば、事業撤退を視野に入れた方が良いとされています。
あわせて読みたい
【図解・事例付】新規事業のSWOT分析のやり方/活用事例を解説
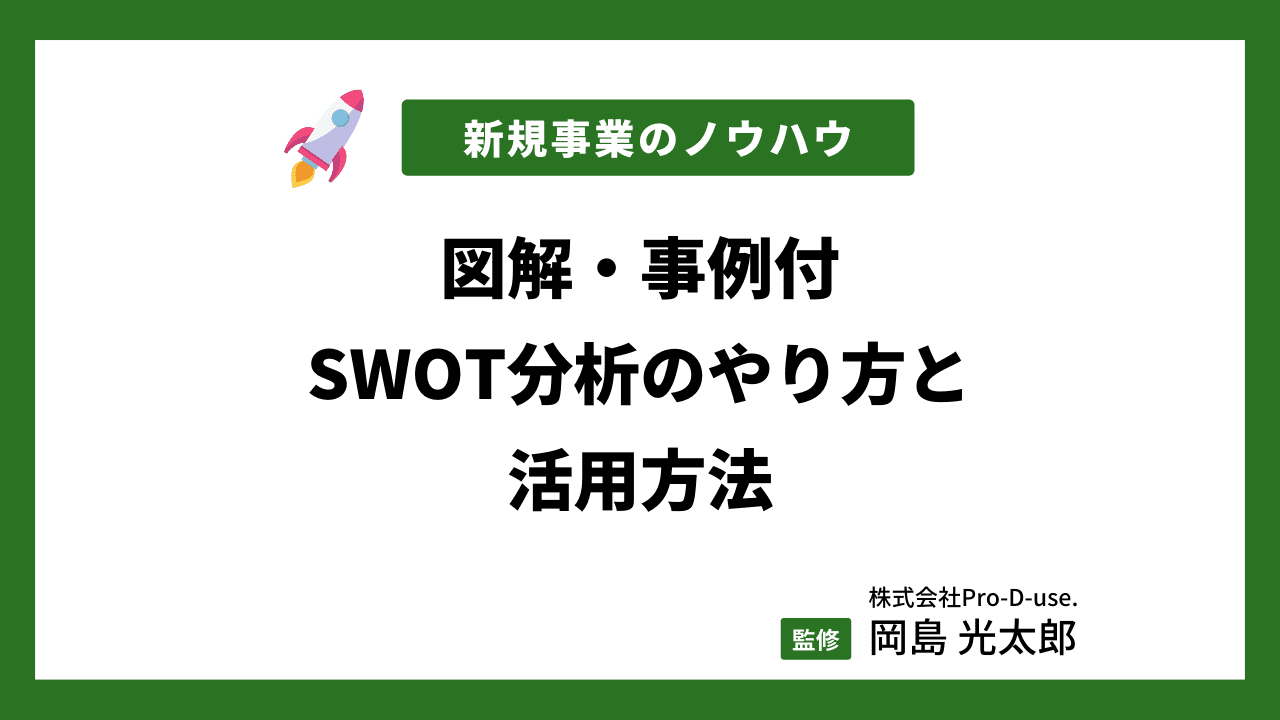
そもそもSWOT分析とはどんな手法なのか、活用したいと思っているが詳しく知らないという方は多いのではないでしょうか? 企業の業績アップや成長のためには、自社の現状をしっかり把握し、冷静に分析する必要があります。その方法としてよく用いられるの…
判断基準5. 事業が赤字でも貢献利益から判断する
貢献利益とは販売する商品やサービスを1つ売った時に儲けられる利益のことです。つまり貢献利益は、その商品やサービスが企業全体の収益にどれだけ貢献しているのかを把握することができる数値なのです。
この貢献利益を算出する際は「貢献利益 = 売上高−変動費−直接固定費」の公式に当てはめて計算します。ちなみにここでいう直接固定費とは、その事業や商品のみに直接関わる固定費のことを指します。具体的には広告費用や販売手数料などが、この直接固定費にあたります。
例えば、ある事業の売上高1,000万円、変動費300万円、直接固定費200万円の場合の貢献利益は、「売上高1,000万円 – 変動費300万円 – 直接固定費200万円 = 500万円」です。
その事業を行うことで、500万円の利益を会社にもたらしていることがわかります。
この貢献利益がプラスの場合は、商品が売れれば売れるほど利益が発生するため、たとえ赤字でも事業を継続すべきと考えられています。これに対して、貢献利益がマイナスである場合は事業を撤退すべきとされています。
あわせて読みたい
赤字の新規事業を黒字化する3つの対策をプロが徹底解説|赤字経営の原因や…
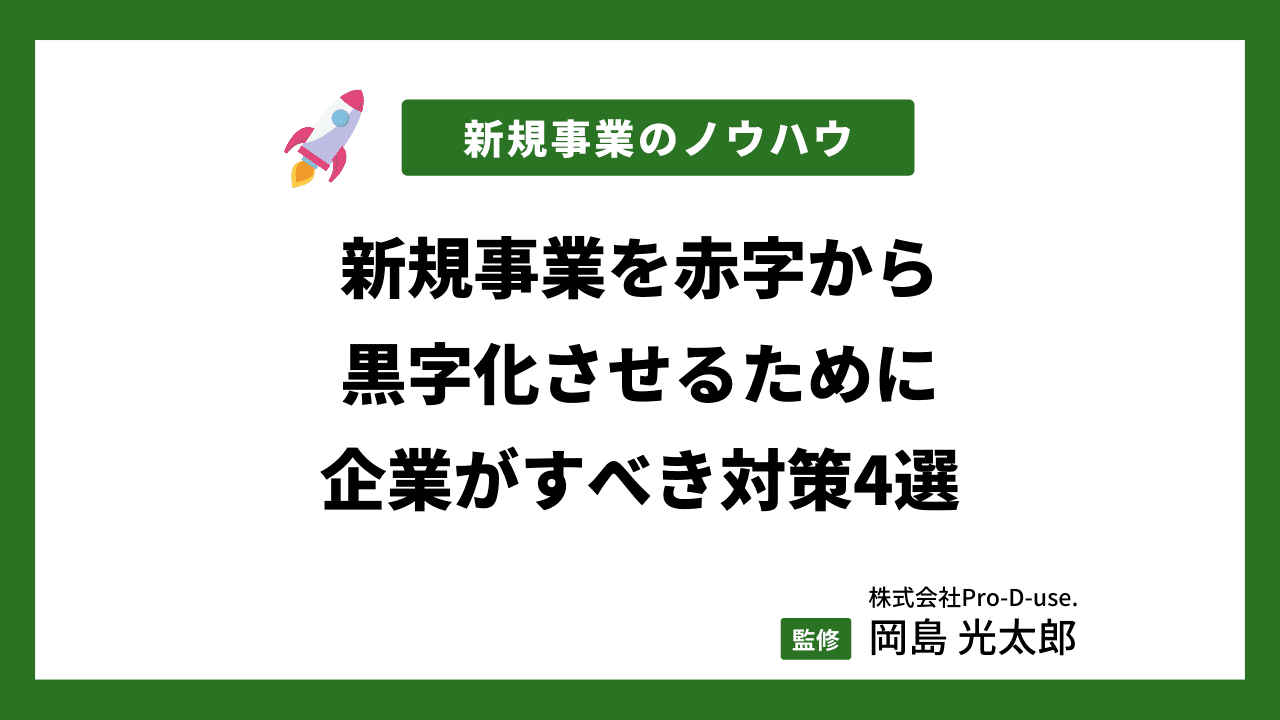
新規事業を始める方、もしくは既に立ち上げたが赤字から黒字への道のりが見えない方は、こんなお悩みをお持ちではありませんか? 「新規事業を始めたが、赤字続き…。どうすれば黒字化できるのだろうか…?」「新規事業が赤字になったらどうすべきなのだろう…
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。既存事業の事業撤退でお悩みなら、プロのコンサルの意見を聞いてみませんか?
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【既存事業の見直しを無料相談】してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
経営コンサルティングサービスはコチラ >>>
事業撤退の2つの方法とスケジュール
事業撤退の手法(方法)は、大きく分けると「事業譲渡」「会社清算」の2つがあります。
それぞれ特徴や手続き方法が異なりますので、状況に応じてどちらの方法を選ぶか慎重に検討しましょう。
方法1. 事業譲渡
事業の一部または全部を他社に譲り渡す方法のことです。
事業の権利や、利用していた資産、場合によっては従業員の雇用契約も引き継いでもらえるため、資産の処分や従業員の処遇決定を行わずに済むぶん、スムーズに事業撤退できるところがメリットです。
一方で、譲り受け企業(買い手)が見つからなかった場合、事業撤退までに時間がかかってしまうというリスクがあります。
また、事業譲渡を行った経営者は、一定期間にわたって周辺エリアで譲渡した事業と同じ事業を立ち上げられないというルールがあります。
仕切り直して再起したいと考えている場合は要注意です。
また、一般的に事業譲渡は以下のスケジュールにしたがって行われます。
◆ 事業譲渡のスケジュール
- 取締役会で承認を得る
- 買い手企業を選定する
- 基本合意書を締結する
- 買い手が売り手に買収監査を実施する
- 事業譲渡契約書の締結で両者の最終的な合意を得る
- 各所に届け出を行う
- 株主に対して事業譲渡を実施する旨を周知する
- 株主総会の特別会議で承認を得る
- 名義変更などの各種手続きを行う
方法2. 会社清算(解散)
会社清算とは、会社を解散し、保有していた資産と負債を清算する方法のことです。
事業撤退=廃業の場合に用いられる方法で、事業に用いていた不動産や設備などはすべて売却して現金化し、負債を返済します。もし資産が残った場合は、株主に分配し、すべての資産・負債を清算することになります。
ただ、事業撤退までには株主総会を開いたり、清算人の登記や財産整理を行ったりと、さまざまな手続きを行わなければなりません。事業規模にもよりますが、相応の手間と時間がかかるため、事業譲渡できなかった場合の最終手段として用いられるケースが多いようです。
会社清算の具体的なスケジュールは以下の通りです。
◆ 事業撤退のスケジュール
- 株主総会で解散の決議を行う
- 解散と清算人選任の登記申請を行う
- 各種機関に解散を届け出る
- 貸借対照表・財産目録を作成する
- 債権者保護手続きを行う
- 解散確定申告書を提出する
- 借入金や買掛金といった会社の債務を支払う
- 清算確定申告を行う
- 清算事務報告の承認を受ける
- 清算結了の登記申請を行う
「自分だけでは、事業撤退の判断ができない」
「事業撤退した後、どう新規事業を進めれば良いか分からない」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの新規事業コンサルの詳細はコチラ>>
事業撤退で発生する代表的な5つのコスト
新規事業の撤退を検討するのは、「これ以上損失を出したくない」という思いがあるからです。
しかし、一度立ち上げた事業を停止するのにもそれなりのコストがかかります。場合によっては、新規事業の立ち上げにかかった初期投資よりもコストがかかることもあります。
そのため、もし事業撤退した場合、どのくらいの出費が予想されるのかをあらかじめ把握しておくことが大切です。
事業撤退で発生する費用は業種によって異なりますが、ここでは店舗閉鎖をともなう事業撤退を例に、主なコストを5つご紹介します。
- 店舗の解体費用
- 賃貸借契約解約違約金
- リース解約違約金
- 原状回復費用
- 固定資産売却損
コスト1. 店舗の解体費用
事業撤退にともない不要になった店舗は、一般的には不動産仲介業者を介して売りに出されます。
しかし、買い手が見つからなかった場合は、店舗や内装を解体する必要があります。
解体費用は建物の規模などによって異なりますが、1坪あたり2~4.5万円くらいが相場とされています。仮に50坪の店舗を解体する場合、100~225万円くらいの費用がかかる計算になります。
コスト2. 賃貸借契約解約違約金
貸店舗を利用していた場合、事業撤退によって賃貸借契約を中途解約することになりますが、契約内容によっては違約金が発生することもあります。
たとえば、5年間にわたって貸店舗を利用することを前提に賃貸借契約を結んだにもかかわらず、3年間で事業撤退することになった場合、残り2年間の残存期間の賃料を賃貸借契約解約金として請求される可能性があります。
ただ、過去に賃貸借解約違約金について争った裁判では、残存期間の賃料を解約違約金として請求できるとする特約は、貸借人の解約の自由を極端に制約することになるとして、違約金は1年分の賃料および共益費相当額を限度とし、残りの部分の請求は無効とする判決が下されています。
そのため、解約違約金の請求額は長くても1年分と想定されますが、仮に30坪の貸店舗を坪単価2万円/月で契約した場合、1ヶ月あたりの賃料は60万円、1年分は720万円にも上ります。
もちろん、契約が切れるタイミングで事業撤退すれば解約違約金は支払わずに済みますが、事業撤退のタイミングを逃すと損失が膨らむ可能性がありますので、契約終了を待って撤退するか、今すぐ撤退するか、よく考えて判断することが大切です。
コスト3. リース解約違約金
店舗が設備投資を行う際、リース契約を利用するパターンも多く見られますが、原則としてリース契約は中途解約が認められていません。
事業撤退を理由に、どうしてもリース契約を中途解約したい場合は、残リース料を一括で支払うか、あるいは残リース額相当の違約金を支払わなければなりません。
貸店舗に比べると、1件あたりのリース金額は少ないものの、多数の設備を導入している場合、多額のリース解約違約金が発生する可能性があるので要注意です。
コスト4.原状回復費用
貸店舗の場合、賃貸契約に基づいて、物件を入居前と同じ状態に戻す「原状回復」を行う義務があります。
原状回復の定義についてはこれまで再三議論されていましたが、国土交通省がまとめたガイドラインにより、原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されることになりました。
つまり、賃借人は自然使用による経年劣化に対して原状回復する義務は負わないということを意味します。
ただし、新規事業の立ち上げ時にさまざまな内装工事を行った場合は、それらの解体費用を負担することになるため、注意が必要です。
コスト5.固定資産売却損
固定資産を売却した際、売却価額によっては売却損が発生する場合があります。これを固定資産売却損といいます。ちなみにここでいう固定資産とは、車両や建物などを指します。固定資産売却損は、固定資産が長期保有を前提として、頻繁に売却されないものと見なされているため、特別損失として計上します。
固定資産売却損の計算方法は以下の通りです。
「固定資産売却損 = 売却収入-固定資産売却時の簿価」
固定資産売却時の簿価には、帳簿価額の他に売却手数料等の経費も含まれます。 定資産を売却する際は、仲介手数料が発生することがありますが、この手数料は別で計上せずに固定資産売却損に含めて処理しても良いとされています。
事業撤退で考えられる3つのリスク
事業撤退は経営上のリスクを軽減するために行う対策です。
一方で、事業撤退によって新たなリスクを生み出すこともあります。
前節で紹介したコストもそうですが、ここでは事業撤退によって起こり得る主なリスクを3つご紹介します。
- 顧客や取引先からの信用低下・ブランド価値の低下
- 従業員からの信頼低下
- 事業撤退の責任を負う必要がある
リスク1. 顧客や取引先からの信用低下・ブランド価値の低下
赤字を出す不採算事業であっても、立ち上げから事業撤退までの間に一定の顧客はつくものです。
事業撤退すると、その事業の商品やサービスを使っていた顧客は少なからず迷惑を被りますので、企業への信用やブランド価値が低下するおそれがあります。
場合によっては、ほかの事業の商品・サービスの不買につながることもあるため、事業撤退する際は、既存の顧客ができるだけ不平・不満を抱かないよう、誠意ある対応を行うことが大切です。
たとえば、商品の最終受注時期や出荷予定時期を余裕を持って伝える、アフターサービス期間を明確化する、といった対応を取っていれば、顧客から大きな反感を買うリスクを最小限に抑えられます。
リスク2. 従業員からの信頼低下
事業撤退にともない、信用が低下するのは顧客だけに留まりません。
従業員にとっても、自分の属する企業が新規事業の立ち上げに失敗したとなると、落胆や失望を禁じ得ません。とくに事業撤退にともなって従業員のリストラなどを行った場合、社内からも反感を買うおそれがあります。
新規事業の立ち上げにともない、新たに人を雇用していた場合、事業撤退後の従業員の受け皿に困るケースは少なくありません。
信頼の低下を防ぎたいのなら、他の事業への配置転換などを検討した方がよいでしょう。
リスク3.事業撤退の責任を負う必要がある
事業撤退をする際は、株主への説明責任や社員へのフォロー責任を負う必要があります。とくに見逃しがちなのが2つ目の社員へのフォロー責任です。事業撤退が決まった際、社員の中には「自分のせいでプロジェクトが上手くいかなかった」と自分を責めてしまう担当者もいます。
経営者はそういった社員に対して「事業撤退を決断したのは誰のせいでもない」といった旨の説明を行い、社員をフォローしなければいけません。丁寧にフォローすれば、社員は次のプロジェクトでも熱意を持って取り組んでくれることでしょう。
「自分だけでは、事業撤退の判断ができない」
「事業撤退した後、どう新規事業を進めれば良いか分からない」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの新規事業コンサルの詳細はコチラ>>
新規事業を立ち上げの際は、事業撤退の基準も設けておこう!
新規事業は必ず上手くいくという保証はなく、想定外の状況によって赤字や負債を出し続けてしまうこともあります。
一定のシェア率や成長性を見込めるのなら、事業継続するのもありです。しかし、今後上がっていく見込みがないと思われる場合、事業撤退を検討しなければなりません。
事業撤退のタイミングを先送りにすると、損失が拡大して会社の経営に大きな影響をもたらすこともあります。新規事業を立ち上げたら、万一に備えて事業撤退の基準を設けておきましょう。
「成果が出ない事業の扱い」や「事業撤退の判断」でお悩みではありませんか? (株)Pro-D-useなら、スピーディな「事業撤退」「事業継続」の判断で、事業がどんどん推進します!
⇒(株)Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。既存事業の事業撤退でお悩みなら、プロのコンサルの意見を聞いてみませんか?
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【既存事業の見直しを無料相談】してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
経営コンサルティングサービスはコチラ >>>
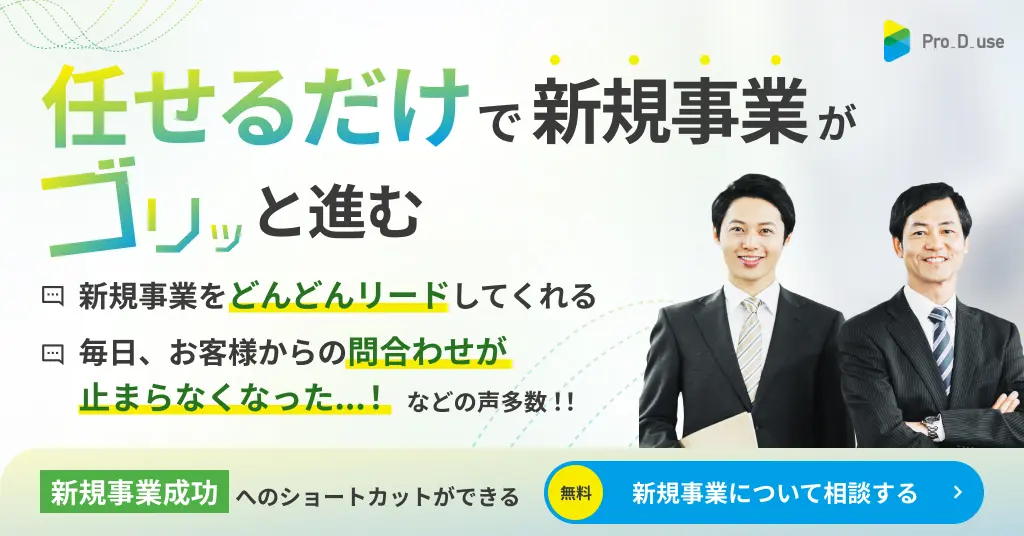
外部参考サイト
公益社団法人 全日本不動産協会:契約期間内の解約と残存期間の賃料の没収
国土交通省:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
債務整理に強い弁護士・司法書士検索なら債務急済