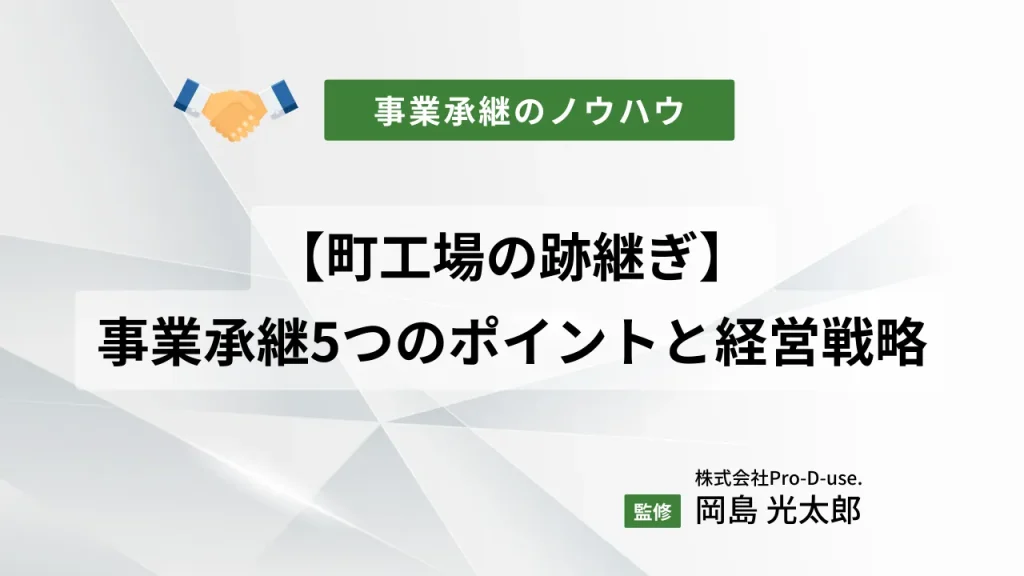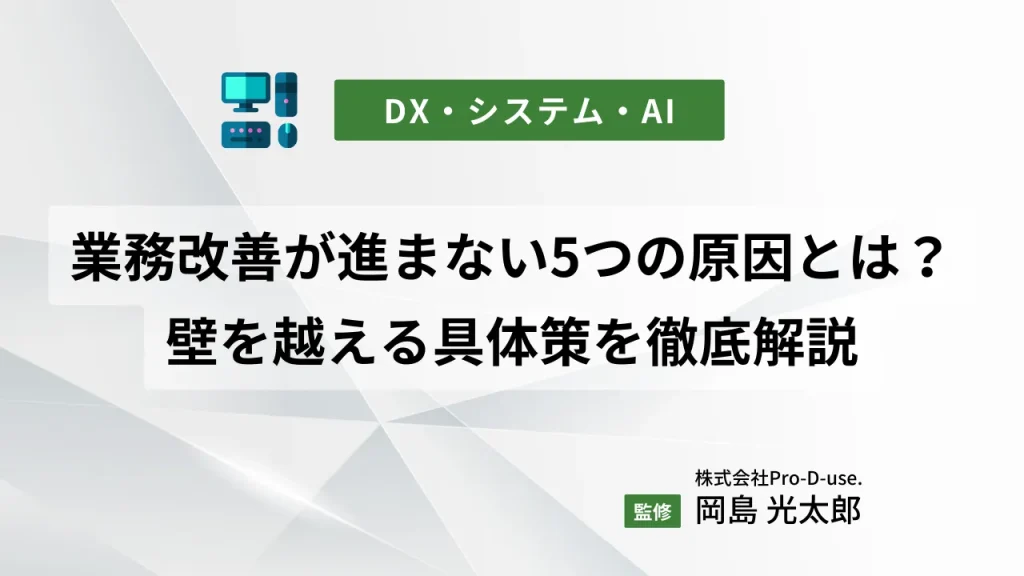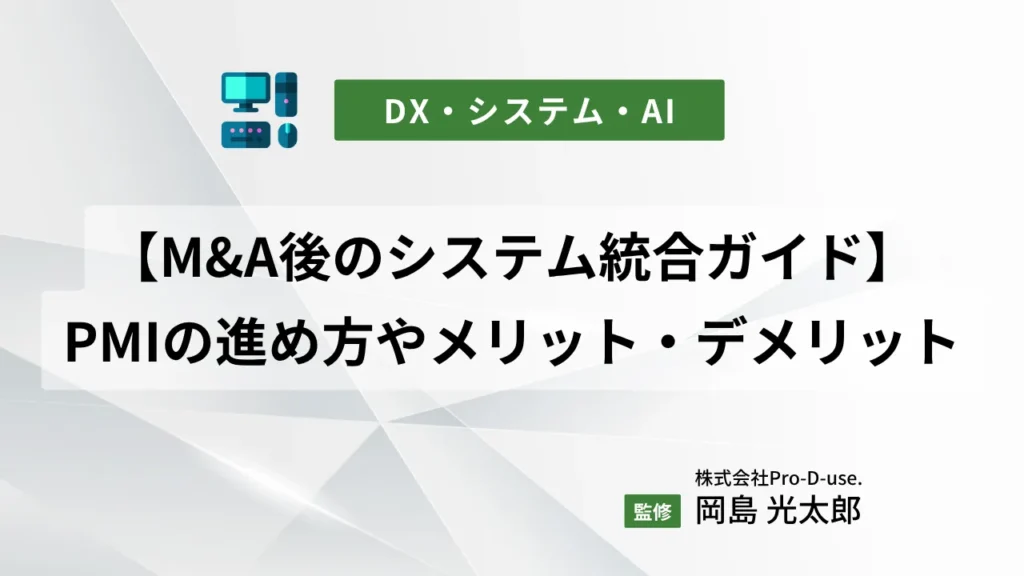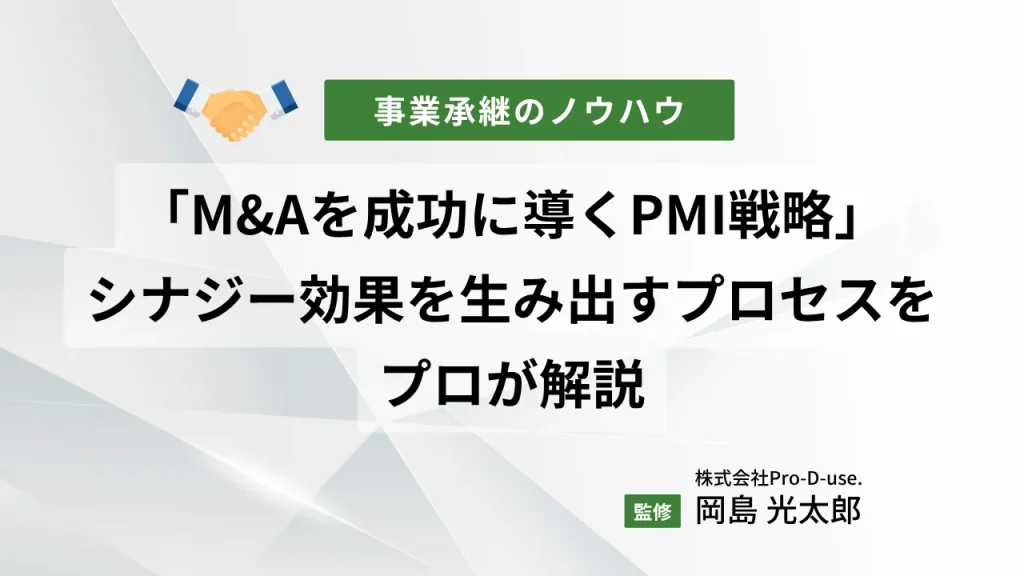プロダクトライフサイクルとは?新規事業の利益最大化を狙う理論を解説
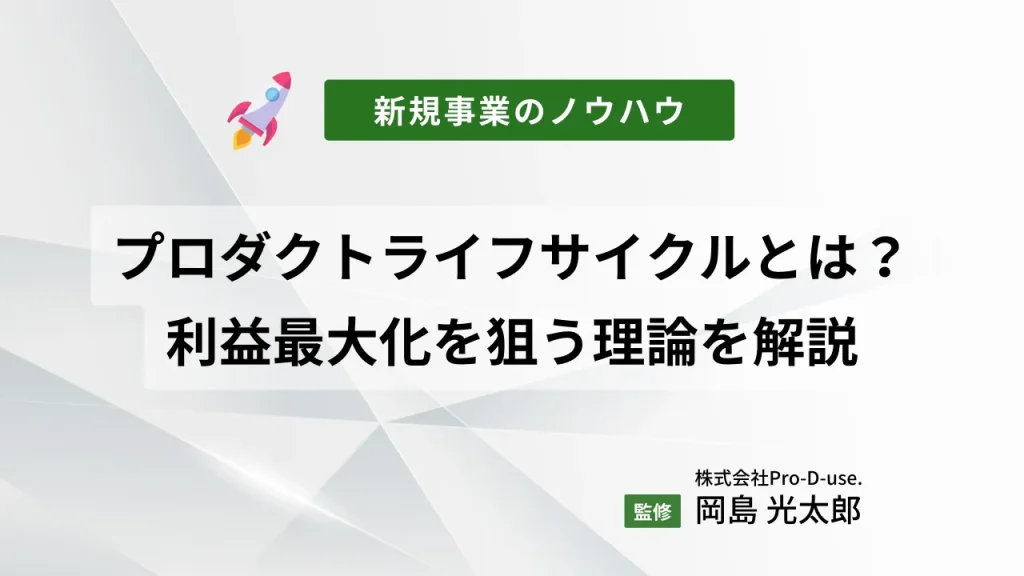
-
- 新規事業
- 経営ノウハウ
- 2023年8月4日
新規事業を進めている方であれば、企画立案や事業計画の策定ためにさまざまなフレームワークを勉強されているはずです。
その中でプロダクトライフサイクルという言葉に出会い、くわしく知りたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

プロダクトライフサイクルとは?

プロダクトライフサイクルは、どのような場面や目的で使うのか分からない。

プロダクトライフサイクルの各段階で、どんな戦略を立てるべきかを知りたい。
実は、プロダクトライフサイクルを理解していないと、適切なマーケティング手法を選べなかったり撤退タイミングを逃したりしてしまいます。
なぜなら、プロダクトライフサイクルの5つのフェーズごとに最適なアプローチ方法があるからです。
私は、新規事業コンサルティング会社のPro-D-useで、数多くの中小・中堅企業、大企業の新規事業支援を行っており、プロダクトライフサイクルに合わせたマーケティングをご提案しています。
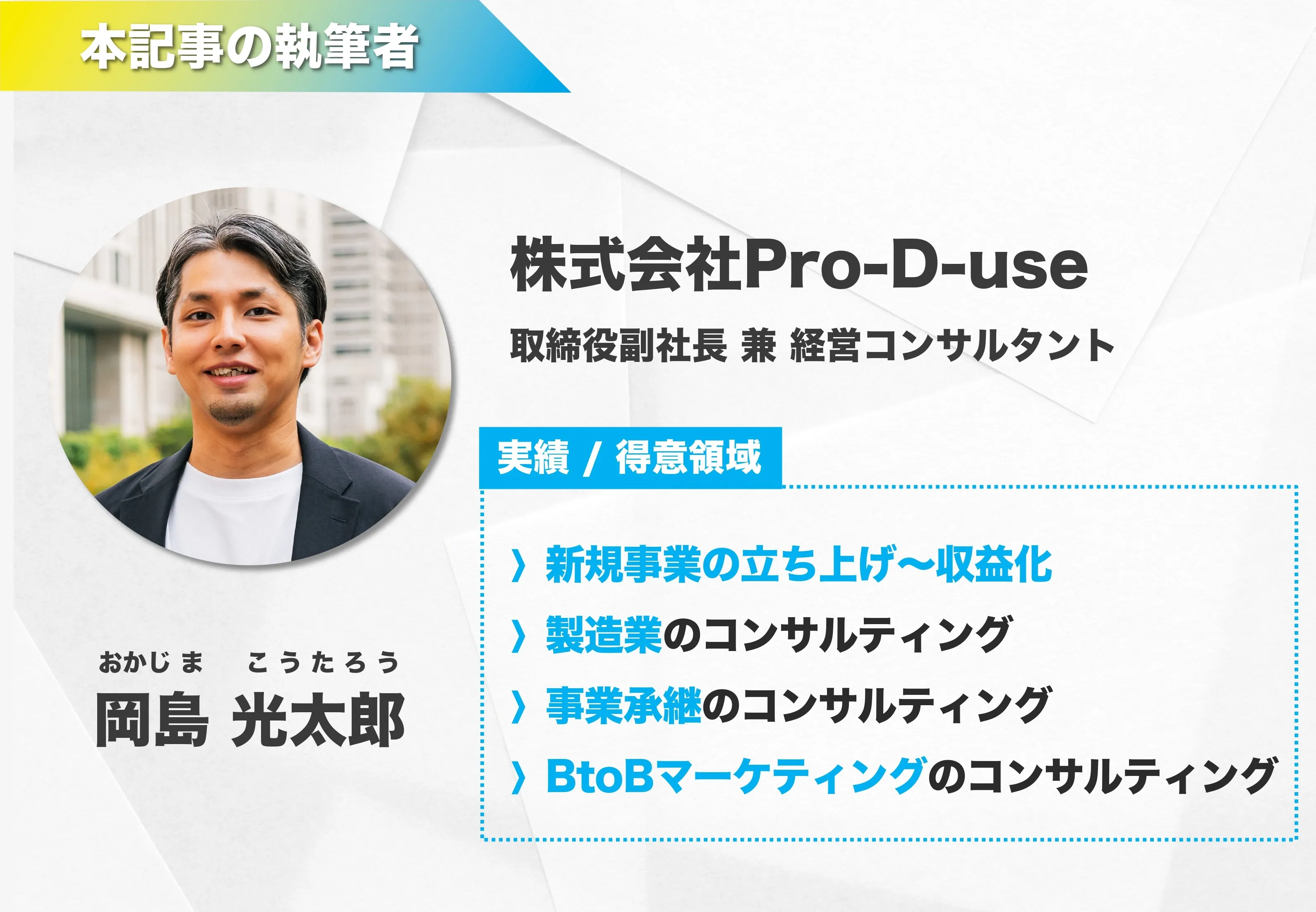
本記事では、プロダクトライフサイクルについての理解を深められるよう、プロダクトライフサイクルを熟知した私がくわしく解説します。
本記事から学べるのは、以下の3点です。
- 利益最大化のために、プロダクトライフサイクルに応じた適切なマーケティング施策の立案と実行が求められる
- プロダクトライフサイクルは、製品やサービスの市場参入後だけでなく、新規事業開発の企画立案時にも活用できる
- プロダクトライフサイクルは4つの要因で変化し、近年短縮化が進んでいる
記事を読み終えた後は、次の2つができるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
- プロダクトライフサイクルについての実践的な理解が深まる
- プロダクトライフサイクルに合わせてマーケティング施策を考えられるようになる
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。
弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業サービスはコチラ >>>
\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /
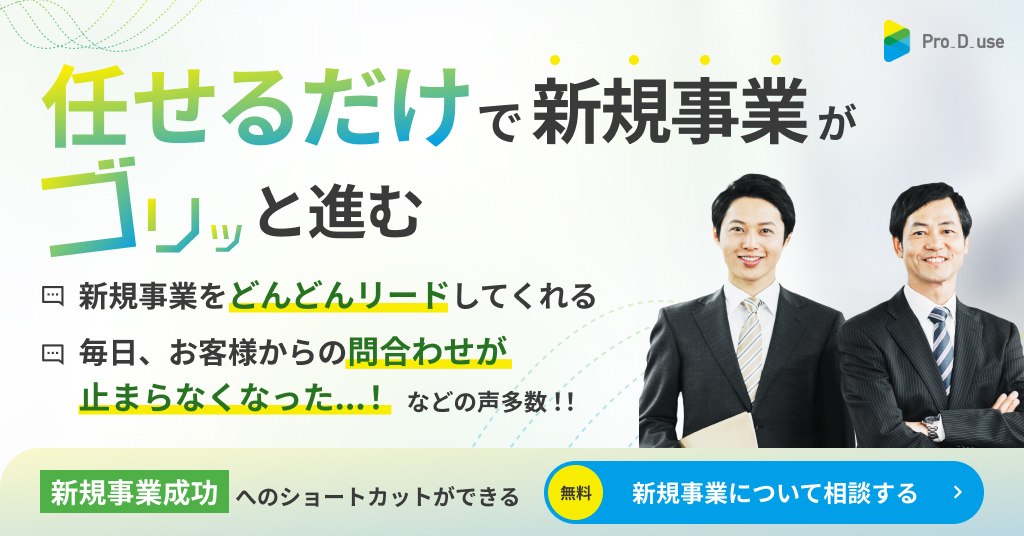
目次
プロダクトライフサイクル(PLC)とは?
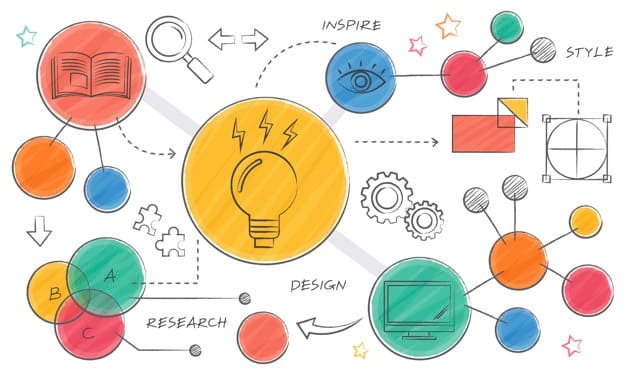
プロダクトライフサイクル(PLC)とは、製品やサービスを市場に送り込んでから撤退するまで、いわば製品やサービスの「一生」を4段階に分けて把握するという理論です。
製品ライフサイクル、あるいはPLCサイクルとも呼ばれています。
プロダクトライフサイクルは、1950年にジョエル・ディーンが発表した理論です。
発表を受けてさまざまな経済学者や社会学者、マーケティング学者が研究を行う中、エベレット・ロジャーズが各段階のユーザーの特徴を明らかにし、あてはめることで現在の形になりました。
なおプロダクトサイクルの他にも、新規事業開発に役立つフレームワークはありますので、下記の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい
新規事業立ち上げで「絶対」使うべき厳選フレームワーク12選
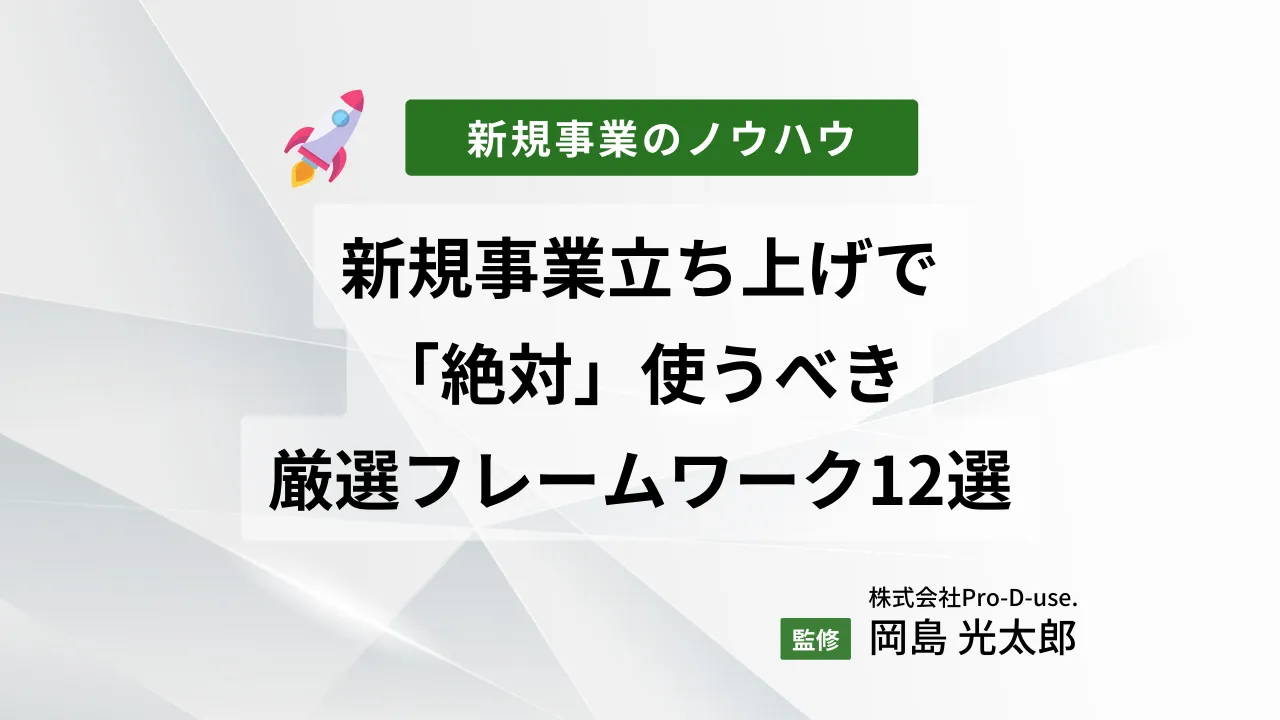
よく「新規事業の立ち上げにフレームワークが必要」と言われますが、それは間違いです。フレームワークを使わなくても、新規事業を成功させている企業は多くありますし、「フレームワークを使えば答えが見つかる」というのは幻想です。 しかし、新事業立ち上…
プロダクトライフサイクル(PLC)が使える場面

プロダクトライフサイクルは、新規事業開発やマーケティング戦略の立案時に活用できます。
自社製品やサービスがプロダクトサイクルのどのフェーズにあるかが分かると、下記の場面で役立ちます。
- 利益最大化のためにどのようなマーケティング施策が適切か判断する
- 現在取り組むべき最重要課題を洗い出す
- 売上と利益が今後どのように推移するか予測する
- 競合他社のフェーズを確認し、追随する
プロダクトサイクルを把握して適切なマーケティング施策を選ぶことで、効率的に利益の最大化を狙うことが可能です。
新規事業開発におけるプロダクトライフサイクル(PLC)
プロダクトライフサイクルは、新規事業開発において、アイデア立案段階で競合他社の製品やサービス理解に役立ちます。
たとえば競合他社がどのフェーズにいるかや市場の状況を把握し、自社製品の作りこみや戦略立案に活かします。
このように製品やサービスを市場に導入する前段階からも、プロダクトライフサイクルの活用が可能です。
あわせて読みたい
【完全版】新規事業の立ち上げのノウハウをプロが徹底解説
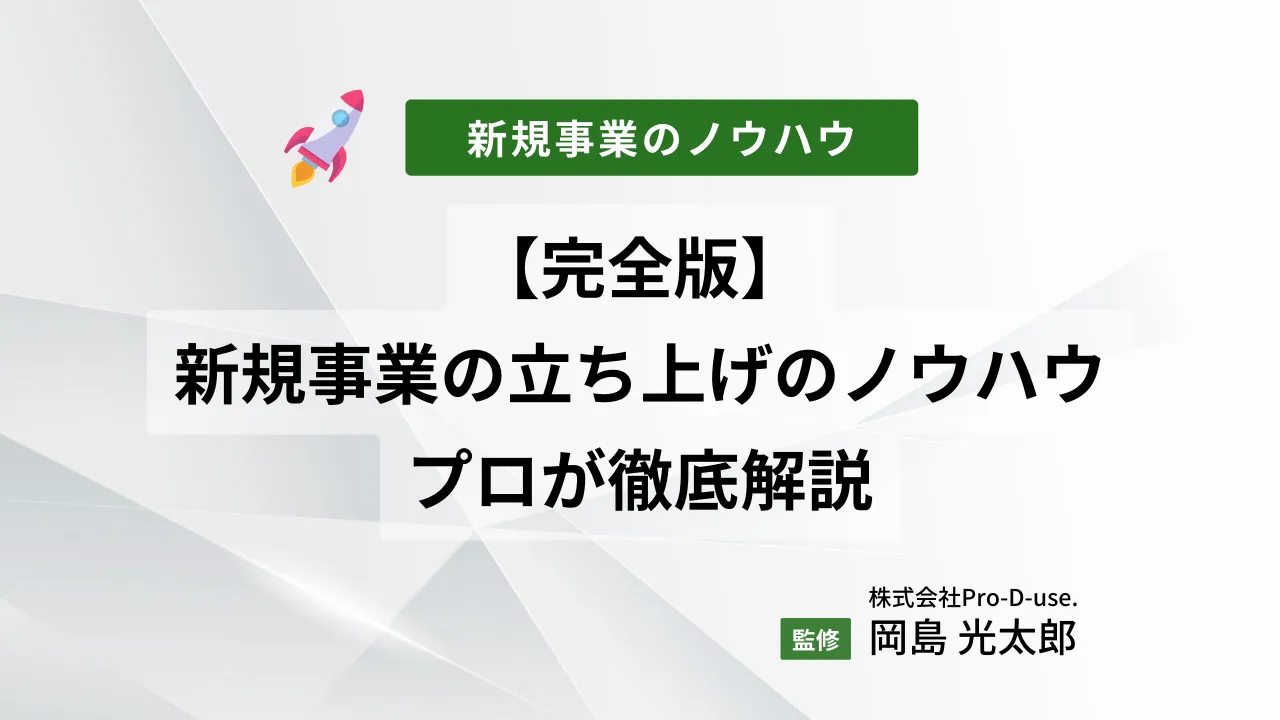
新規事業の立ち上げは、企業が新しい事業を開始する戦略のことです。現在メインにしている事業の業績が悪化しているときに新規事業を立ち上げることもあれば、余剰資源を活用してさらに企業を発展させることや、リスクの分散などを目的に新規事業を立ち上げる…
プロダクトライフサイクル(PLC)の5フェーズ

プロダクトライフサイクルは、一般的に4つのフェーズで語られますが、本記事では「開発期」をふくめた5つのフェーズとして解説します。
| フェーズ | 段階 | 特徴 |
|---|---|---|
| 開発期 | 新製品やサービスをリリースする前の段階 | ・製品やサービスの需要を知るために、市場調査を行う ・テストマーケティングを通してコンセプトや内容を改善する ・試行錯誤が必要なため長引くこともある |
| 導入期 | 新製品やサービスを市場に導入した段階 | ・製品やサービスの需要が小さい ・売上も少なく成長率が高い ・認知度や市場拡大が求められる ・マーケティングに費用がかかるため利益が出にくい |
| 成長期 | 製品やサービスがユーザーに認知されはじめる段階 | ・製品やサービスの認知度、需要が高まる ・製品やサービスの売上と利益が成長する ・市場拡大によって消費者ニーズが多様化する |
| 成熟期 | 製品がユーザーに知れ渡る段階 | ・成長が停滞する ・売上と利益が限界値を迎える ・企業や売上規模によって生き残り戦略が変わる |
| 衰退期 | 市場が縮小する段階 | ・売上と利益が減少する ・既存顧客の維持が求められる ・場合によっては撤退を判断する |
それぞれのフェーズの特徴とあわせて、必要なマーケティング施策と重要課題について解説します。
なおプロダクトサイクルは、製品やサービスの普及率を示すイノベーター理論と組み合わせて活用されることもありますので、モデルユーザーについても触れています。
| イノベーター理論におけるモデルユーザー | 割合(※) | 特徴とプロダクトサイクルにおけるフェーズ |
|---|---|---|
| イノベーター | 2.5% | ・導入期 ・もっとも早い段階で製品やサービスを利用しはじめるユーザー ・好奇心が高く、情報の取得が早い特徴がある ・製品やサービスの価値に重きを置かない |
| アーリーアダプター | 13.5% | ・導入期後半~成長期 ・イノベーターの次の情報の取得が早いが、情報をもとに判断して製品やサービスの利用をはじめる ・利用してみた評価を拡散しようとする性質があるため、市場拡大に大きな影響をもたらす |
| アーリーマジョリティ | 34.0% | ・成長期・前期追随者と呼ばれ、製品やサービスの採用に慎重なユーザー ・製品やサービスの価値の中でも、メリットを重視する ・市場において大きな割合を占めるため、アーリーマジョリティに製品やサービスを採用させることが大きな目標となる |
| レイトマジョリティ | 34.0% | ・成熟期・製品やサービスに対して積極的ではなく、なかなか採用に至らないユーザー ・アーリーマジョリティと同じように大きな割合を占める ・市場全体の動向を気にしており、多数のユーザーが使っていれば使うので、アーリーマジョリティの取り込み具合が重要となる |
| ラガード | 16.0% | ・衰退期 ・製品やサービスが成熟してから採用するユーザーで、話題性や他ユーザーの動向を重視しない ・定番や代名詞レベルまで製品やサービスが成熟すると採用し、信頼度を重視する ・導入期の段階で獲得するのは困難な層 |
開発期

プロダクトライフサイクルの開発期は、新製品やサービスを作りはじめる段階であるため、需要の有無を調べるところからスタートします。
新製品やサービスをリリースできるまでにもっていく開発期では、次の9つのフェーズをクリアする必要があります。
- 3C分析を使ったインプット
- アイデア出し
- ニーズ調査
- 新規事業企画の策定
- テストマーケティングの実施
- 事業計画書の策定・準備
- 予算の確保
- 2度目のテストマーケティング
- 組織体制の構築
テストマーケティングは、ユーザーがはじめて製品やサービスに触れる機会です。
この時ユーザーニーズに合致しているかどうかが、プロダクトライフサイクルにおける導入期で、イノベーターやアーリーマジョリティをどれくらい取り込めるかにつながります。
テストマーケティングでユーザーニーズとのズレが確認できたら、リリース前にコンセプトや内容を調整できるチャンスです。
導入期のマーケティングで成功をつかむためにも、念入りに調整しましょう。
新規事業開発期の9つのフェーズについては、下記の記事でくわしく解説していますので、参考にしてみてください。
あわせて読みたい
失敗しない!新規事業の3つのフェーズをプロのコンサルが解説
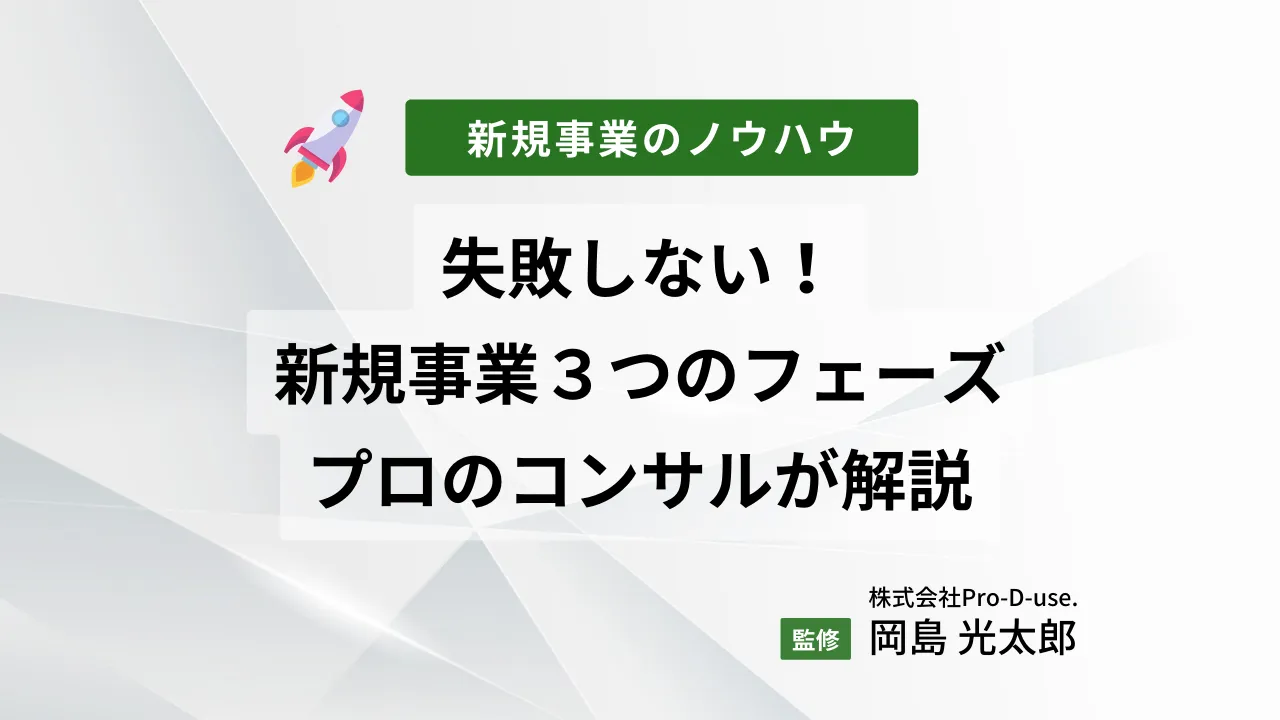
新規事業の担当者の中には、新規事業のフェーズについて下記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか? 「失敗せずに新規事業を立ち上げるには、どのようなフェーズに沿って進めればいいだろう?」「新規事業開発は、各フェーズごとに何を行う…
導入期

プロダクトサイクルの導入期は、新製品やサービスを市場に導入した段階であるため、認知度が低い状態です。
需要と市場が小さい分、非常に伸びしろがあるフェーズでもあります。
導入期では、認知度と市場拡大のためにマーケティング施策を行うことで、将来的な売上・収益の最大化が実現できます。
ただし導入期段階では、少ない収益の中で認知度拡大のマーケティングを展開するため赤字になることがほとんどです。
製品やサービスによっては、早めに黒字化にしなければ事業自体が頓挫する可能性があり、導入期におけるマーケティングは非常に重要な役割を担っています。
導入期は、イノベーター理論におけるイノベーターとアーリーマジョリティの獲得が可能です。
この多段階でアーリーマジョリティを取り込んでいると、より速く需要を拡大できます。
【導入期のマーケティング例】
目的:製品やサービスの認知度、市場拡大
・CMなどのマスメディア広告
・プレスリリース
・オウンドメディアの展開
⇒市場や業界全体に大きめに拡散する
なお、オウンドメディア展開を考えている方には、下記の記事がおすすめです。
参考> 【SEOライティングの基本】基礎知識と執筆の方法を学んで上位表示を目指そう
成長期

プロダクトサイクルの成長期は、認知度と市場が拡大し、売上や利益が成長する段階です。
ただし大きく成長するためには、導入期での認知度・市場の拡大が十分に行われている必要があります。
競合他社が参入しにくいように差別化に力を入れたり、ブランド力を高めて周知したりして、自社の優位性を確立することも大切です。
市場やユーザーにもよりますが、この部分が甘いと追随する競合他社に追い抜かれる可能性があるため、要注意です。
成長期では、アーリーアダプターの評価や口コミを受けてデメリットを改善しつつメリットを拡散し、アーリーマジョリティの取り込みを重視します。
ここでアーリーマジョリティを取り込めたら、市場全体の50%のユーザーを獲得できたことになり、一気に市場拡大が可能です。
【成長期のマーケティングの例】
目的:アーリーマジョリティへの製品・サービスの拡散、優位性の確立
・SNSマーケティング
・動画マーケティング
⇒導入期よりも拡散性の高いマーケティングを適切なユーザー層へ向けて実施する
成熟期

プロダクトサイクルの成熟期では成長率が下がり、売上や収益も限界を迎えるため、成長よりも維持を重視します。
自社の立ち位置によって取るべき戦略が異なりますので、コトラーが提唱したマーケティングの競争戦略を参考にしてみてください。
| 自社の立ち位置 | 取るべき戦略 |
|---|---|
| 市場優位性がある1番手(リーダー) | 競合調査を怠らずトップを維持する |
| 市場優勢のある企業を追う2番手(チャレンジャー) | トップの製品と差別化し、トップを狙う |
| 1番手と2番手を追う3番手(フォロワー) | 製品のコスト優位性でトップを追うか、ニッチャーにシフトして狭い範囲でのトップを狙う |
| ニッチな市場でトップシェアを占める(ニッチャー) | ニッチな市場でのトップシェアを維持するために、専門性を強化する |
この中でもっとも苦しいのがフォロワーの立場です。
トップを取るためには、コスト優位性に振り切るのが早いのですが、それだと収益性は落ちてしまうため長期戦には向きません。
このように成熟期では、自社の立ち位置によって取るべき戦略が異なりますので、立ち位置に合わせたマーケティングを行っていきましょう。
衰退期

衰退期は、ユーザーが離れ市場が縮小していき売上や収益が落ちていくため、新規事業に目を向ける段階です。
ここで重視すべきポイントは、製品やサービスの成長や維持ではなく、撤退のタイミングです。
収益が見込めないなら、早めに撤退し新記事業にシフトしましょう。
ただし製品やサービスのピボットによって、価値転換による需要アップが見込める場合があります。
可能性がある場合はピボットして事業再生も可能ですが、収益の最大化を目的とするなら、事業撤退して新規事業に注力した方がよい場合がほとんどです。
あわせて読みたい
「事業撤退すべきか?継続すべきか?」判断基準と撤退方法を徹底解説
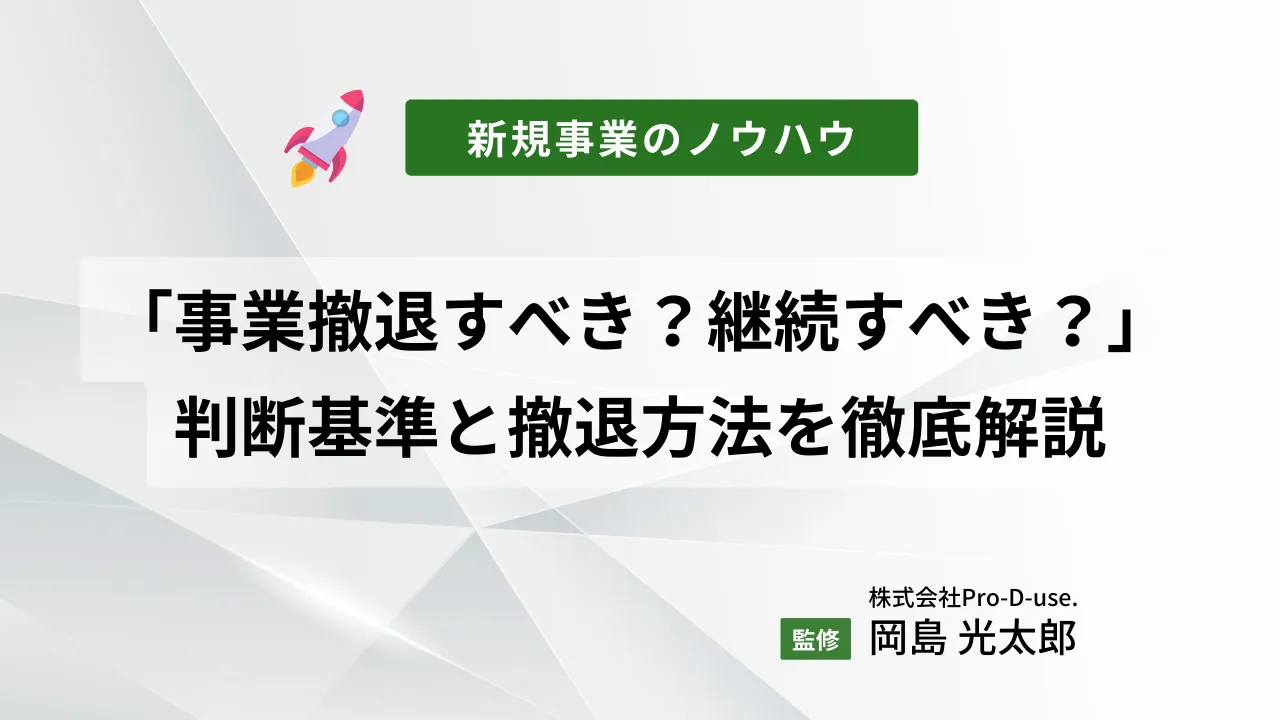
事業撤退とは、「採算が取れない、または、市場で優位性を失った事業を停止すること」です。沈んでいる事業を軌道に乗せるのは簡単ではないため、その事業の損失が会社経営に影響を及ぼすようであれば、その事業は撤退するのが得策です。 事業撤退を視野に入…
プロダクトライフサイクル(PLC)の新規事業への影響要因

プロダクトライフサイクル下記の要因によって、サイクル期間が変化します。
- 顧客のニーズの変化
- 市場の競争状況の変化
- 技術の進歩
- 顧客へのアプローチ手法の変化
経産省の「ものづくり産業が直面する課題と展望」を見ると、「顧客や市場のニーズの変化が速い」と感じている企業が約54%もいることがわかります。
このように昨今、プロダクトサイクルが短縮化されており、市場に製品やサービスが登場してから撤退までのスピード感が昔より速くなっています。
製品やサービスの寿命を伸ばすためには、プロダクトサイクルの環境要因を分析し、柔軟に対応することが必要です。
プロダクトライフサイクルの短縮化に対応する方法の1つに、複数の事業を育てる多角化戦略があります。
多角化戦略については、下記の記事でくわしく紹介していますので参考にしてみてください。
あわせて読みたい
現役コンサルが経営者向けに「4つの多角化戦略」を徹底解説
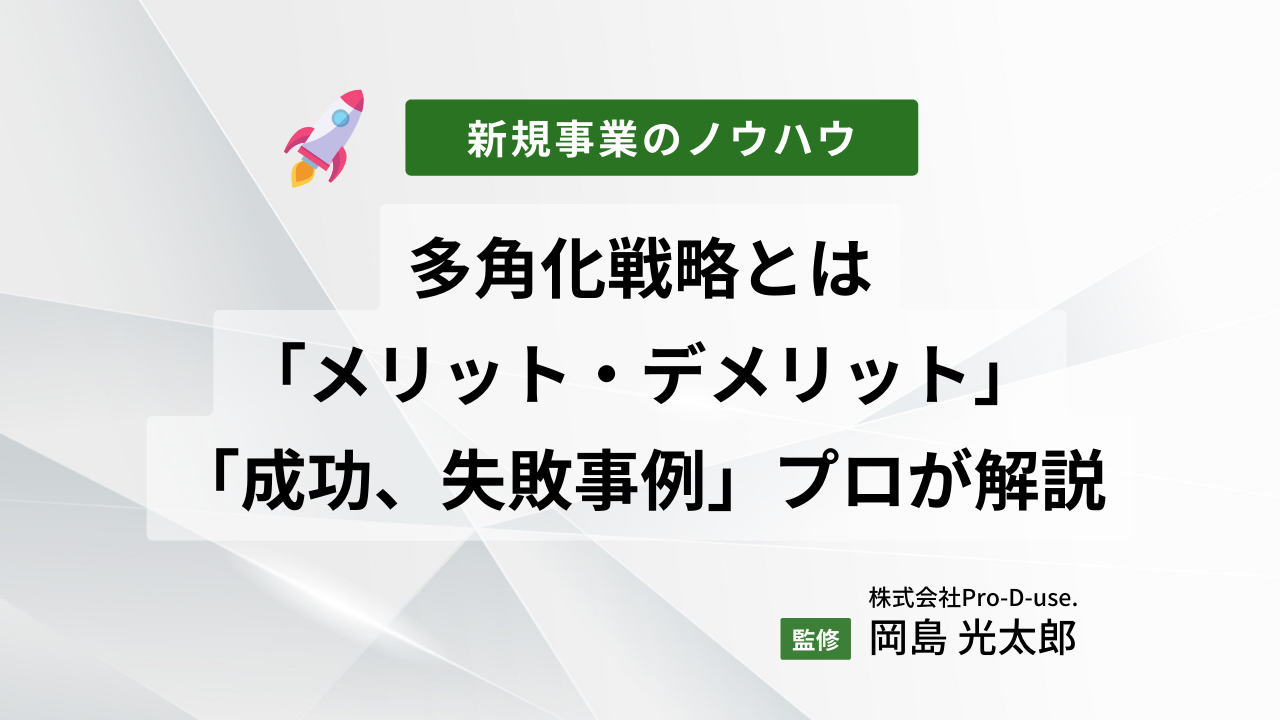
多角化戦略とは、これまでとは異なる市場への参入や、新製品・新サービスの投入により、本業(主力事業)とは別の事業分野に成長機会を求める成長戦略です。 多角化戦略は、ターゲットとする市場を絞り、狭い市場で競争優位性を作る「集中戦略」と対比されま…
顧客のニーズの変化

顧客のニーズの変化スピードが速くなる、あるいは多様化によって、プロダクトライフサイクルも短縮化されます。
新規事業として立案した時のマーケティングリサーチで捉えていたニーズは、市場に製品を導入するタイミングで変わってしまうことがあります。
これによって、新規事業が短いプロダクトライフサイクルの中で衰退してしまうことが増えているのです。
さらに顧客のニーズは多様化し、一人ひとりのニーズに柔軟に対応することが求められます。
こうした変化に対応するためには、顧客の声をいち早くキャッチできる環境整備とPDCAサイクルのスピードアップが大切です。
新規事業における市場・顧客ニーズの調査方法については、下記を参考にしてみてください。
あわせて読みたい
新規事業の成功率がグッと上がる!「ニーズ調査」7つの手法をプロが解説
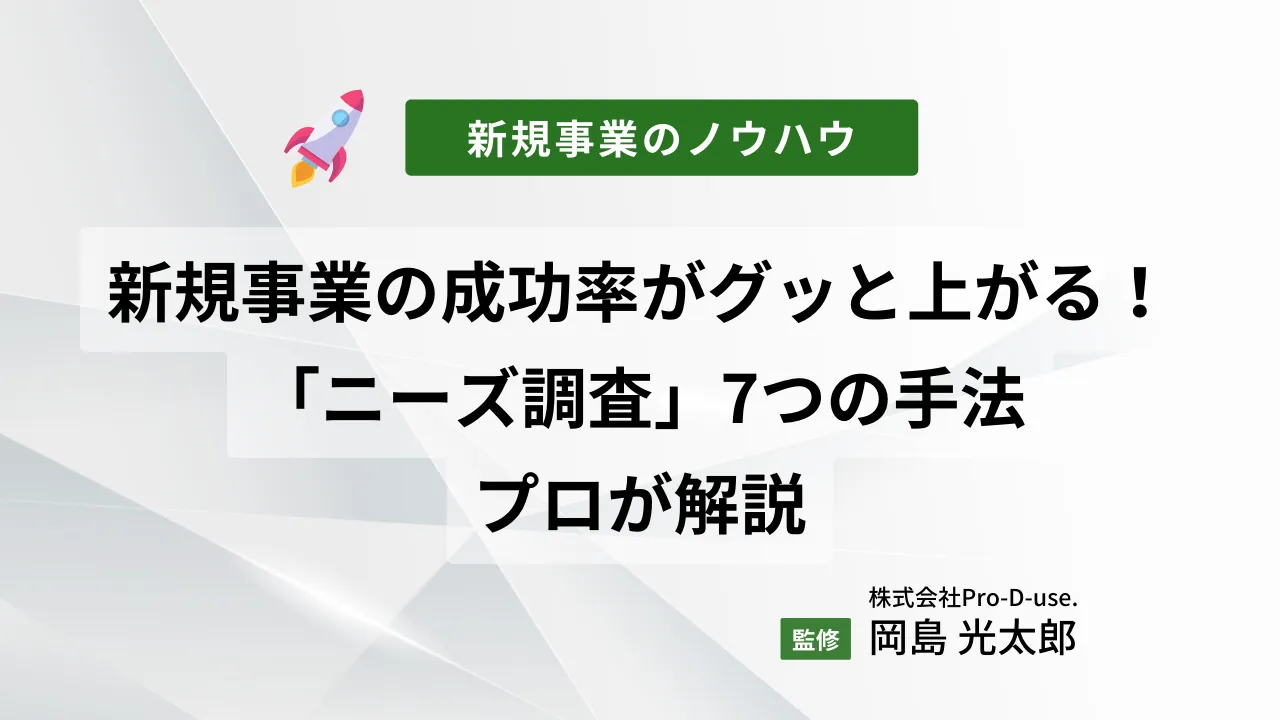
これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか? 「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」…
市場の競争状況の変化

市場における競合他社との競争状況の変化も、プロダクトライフサイクルに大きな影響を与えます。
たとえば、市場が一部の企業の寡占状態になると、新たに参入する競合が減ります。
ライバルが少ない分競争が緩やかになるため、利益を上げやすくなるのです。
一方、影響力の大きい企業が少なく、同レベルの企業が多数集まり過当競争になると、差別化やコスト優位性の獲得といった施策が必要となり、結果的に収益が下がります。
このような市場の競争状況は市場参入前に予測できますので、見通しを持って準備しましょう。
新規事業において参入する業界の特徴を知りたい時は、ファイブフォース分析が有効です。
下記の記事でファイブフォース分析についてくわしく解説していますので、参考にしてみてください。
あわせて読みたい
新規事業のファイブフォース分析とは?その意味や効果を解説
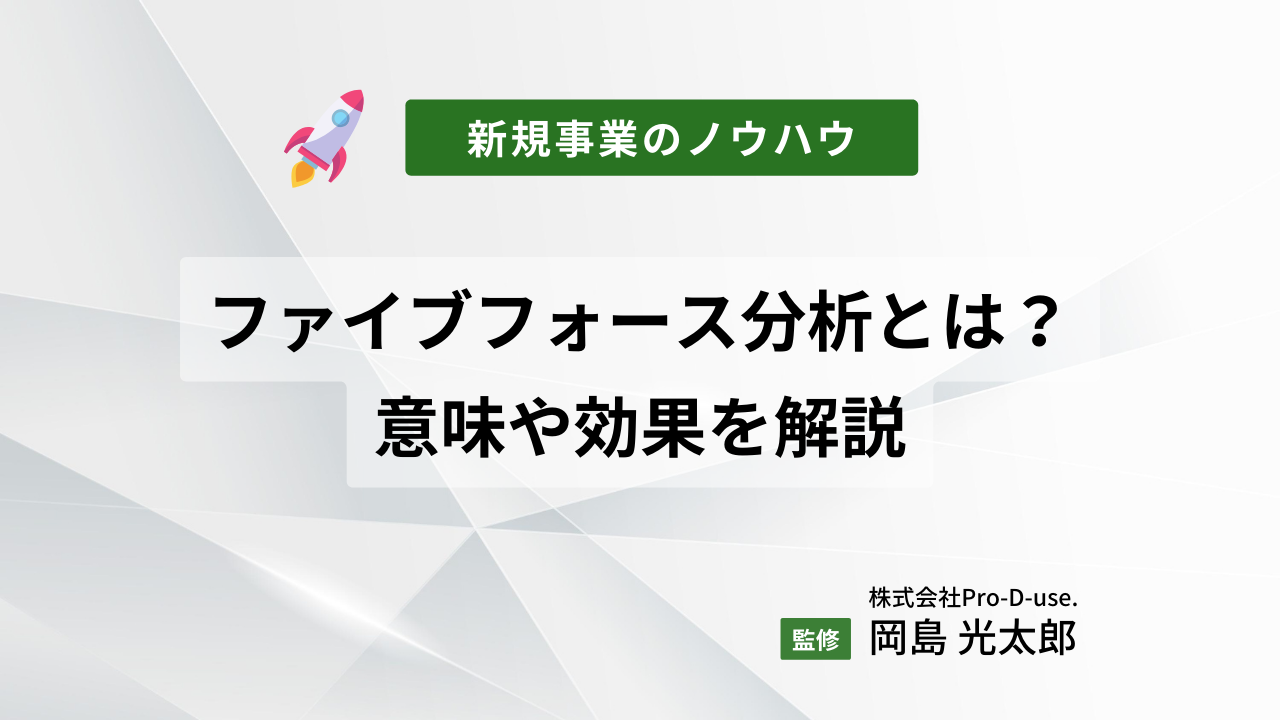
新規事業では、参入する業界選びを間違えると、思うように利益を上げられない可能性も否めません。そんな業界の把握をしたいときに活用したいフレームワークが「ファイブフォース分析」です。 ファイブフォース分析では、外部環境を5つの要素で精査し、商品…
技術の進歩

技術の進歩も著しく、新製品やサービスが技術的に古くなってしまうことも、プロダクトライフサイクルの短縮化の要因です。
たとえば最近は、ChatGPTが話題を集めた瞬間から、さまざまなAI関連プロダクトが爆発的に増え、さらに技術の進歩を加速させています。
ユーザーが製品やサービスを認知してから手を取るまでの間に、大きく変わってしまうのです。
そうなるとユーザーはその時の最新技術が使われている製品やサービスを選ぶため、少し遅れただけでも需要が小さくなります。
変化に対応するだけでなく、予測して先に対応する力が求められるでしょう。
PEST分析を使うと、技術進歩が著しい社会や経済といったマクロ環境をつかみやすくなるので、下記記事をご覧になって試してみてください。
あわせて読みたい
外部環境分析フレームワーク「PEST分析」とは?戦略策定に活かすコツを…
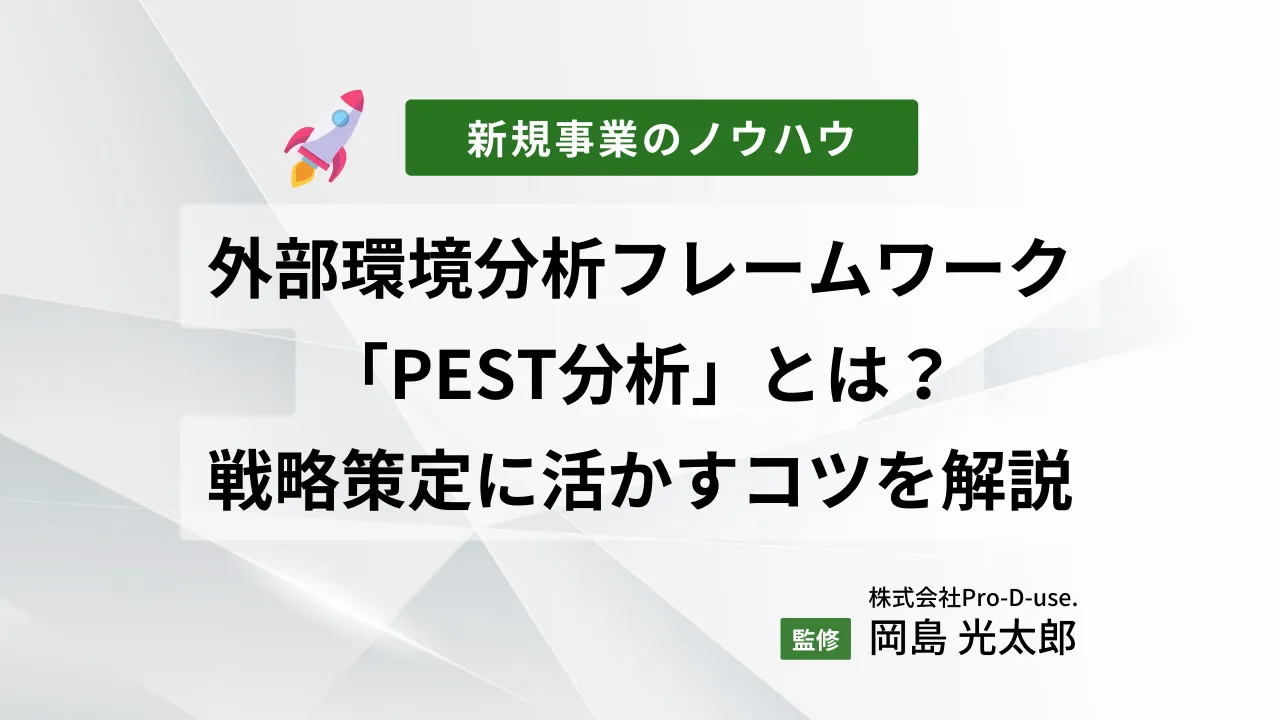
事業戦略や経営方針を策定するには、社会的要因や経済動向をふまえて戦略を考える必要があります。そんな時に役に立つ外部環境分析フレームワークが「PEST分析」です。 実は、外部要因の情報を収集する方法や、整理、分析の方法がわからないという悩みは…
顧客へのアプローチ手法の変化

顧客へのアプローチ手法の変化によっても、プロダクトライフサイクルは変化します。
昔の顧客へのアプローチ手法はマスメディアにおけるCMや広告が主流でしたが、現在はSNSや動画サイトの活用が増えています
これによって拡散性もスピードも上がり、さらには宣伝にかけるコストも縮小され、アプローチ手法が多様になりました。
さらに不特定多数に向けて発信していたスタイルから、特定のユーザー層にピンポイントで情報を届けられるようになったため、アプローチの幅も自由に変化させられます。
アプローチ手法の多様化は、効率的に製品やサービスの情報を拡散できるようになった一方で、最適な手法を選ぶ時に迷いを生みます。
もしユーザーとアプローチ手法がズレると、求めていた効果を得られないこともあるため、さまざまな手法を理解して使い分けることが大切です。
プロダクトライフサイクル(PLC)を理解して適切な新規事業・マーケティングを行おう

プロダクトライフサイクルを理解すると、フェーズに合った適切なマーケティングを行えるようになり、収益の最大化を狙えます。
事業の引き際も見極められるため、余計なコストをかけずに最速で新規事業に移行することも可能です。
ただし最近は顧客ニーズの変化や技術の進歩が著しく、プロダクトライフサイクルが短縮化しており、迅速かつ柔軟な対応が求められます。
新規事業開発経験が少ないと、プロダクトライフサイクルの流れの速さについていけず、適切なアプローチを最適なタイミングで実施するのが難しいでしょう。
そうなると収益の最大化にはつながらず、せっかくの新規事業が中途半端に終わってしまう可能性があります。
新規事業開発の経験があまりない企業では、専門のコンサルタントの導入によって、プロダクトライフサイクルに合ったアプローチができるようになります。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。
弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業サービスはコチラ >>>
\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /
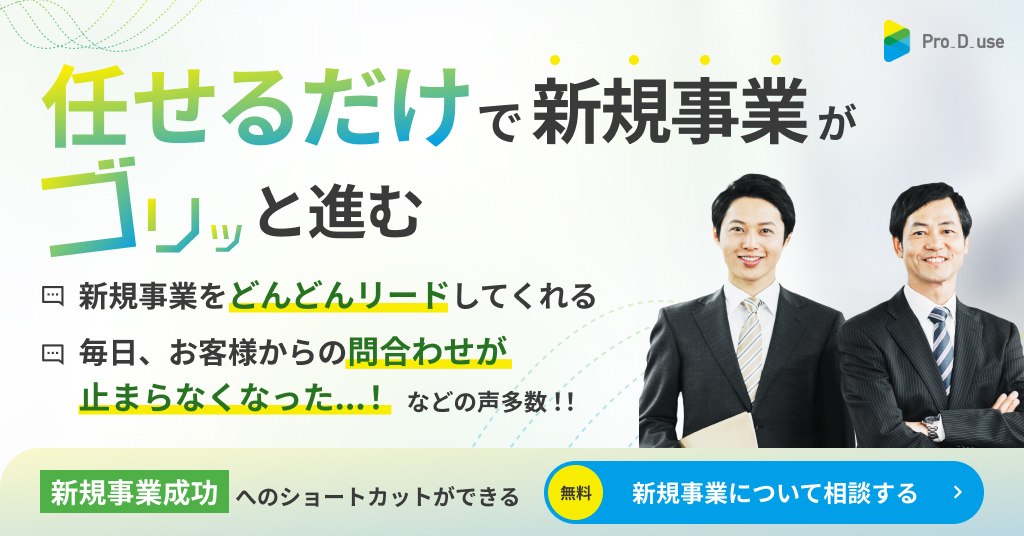
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)