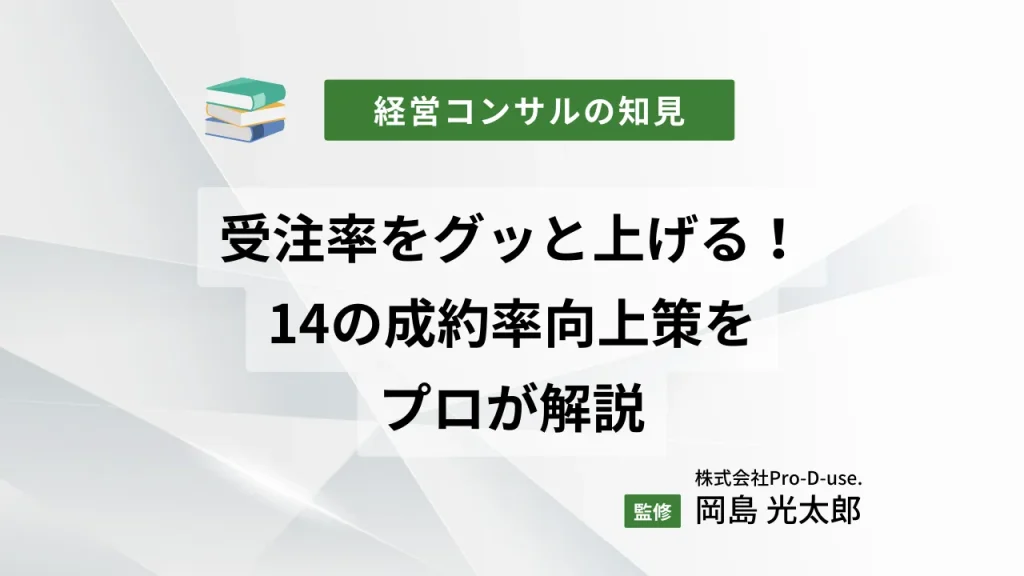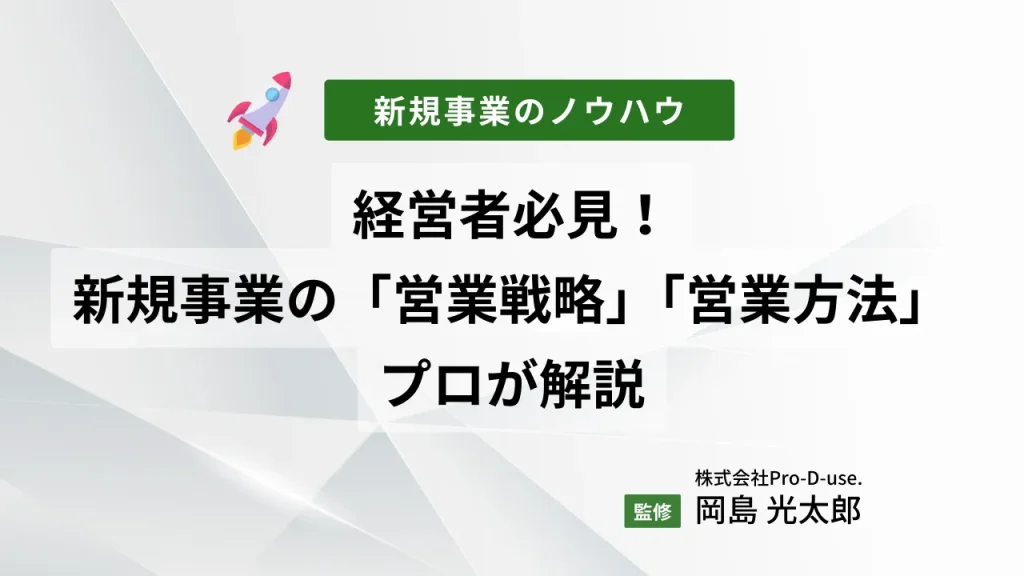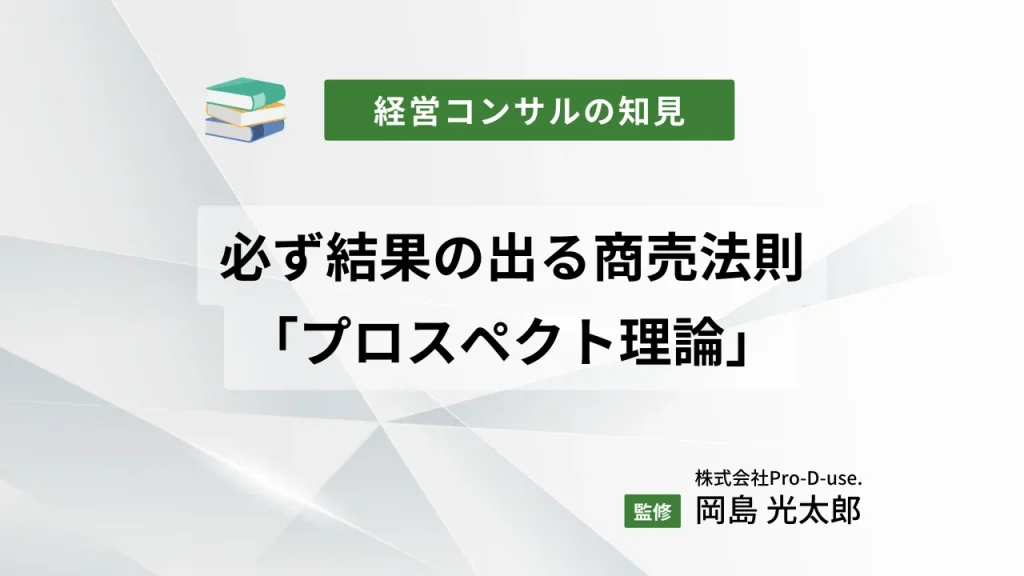中小企業の社長への処方箋「”商品がよければ売れる”危険な思想」
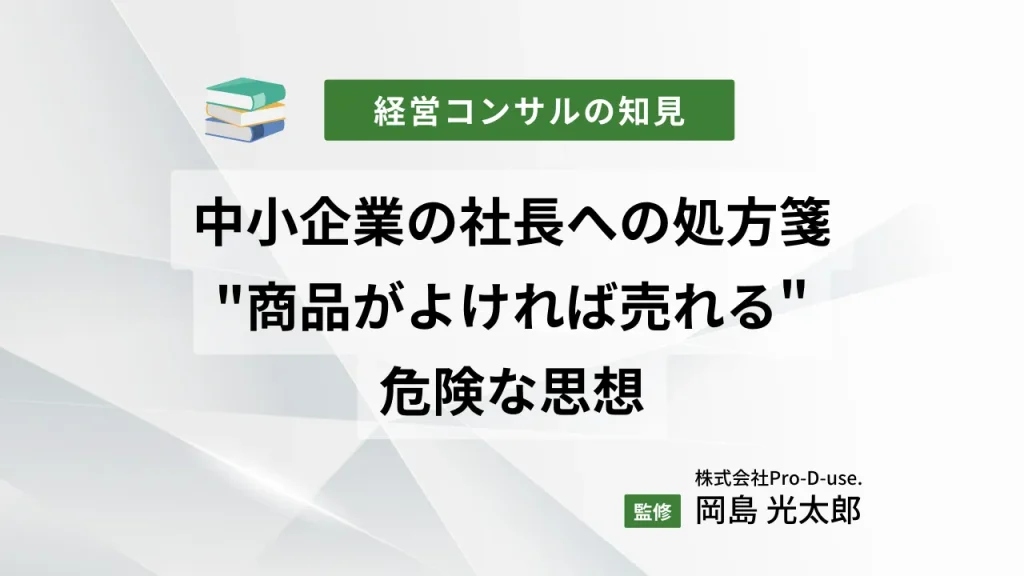
-
- 営業・販売戦略
- 2016年7月12日

うちの商品はいいものなのに売れない、なんで??

売れる商品を作るために、とにかくいいものを作ろう!!
たくさんの経営者の方と多くお話をさせて頂く中で、経営者の方には上記のような『商品がよければ売れる!』という考え方の方が多いという傾向にあります。
実は、その考え方を変えていくことで、事業が成功し続ける可能性が高まります。
そこで、本記事では、いいものと売れるものの違いを明確にしつつ、中小企業に必要なのはマーケットインという考え方について解説していきます。
いいものと売れるものの違いは、いいものとは「作り手」が主語になり、売れるものは「顧客」が主語になります。
なぜなら、いくら作り手がいいものだと思っていても、顧客がいいものと感じない限り購入にはつながらないからです。
今回この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 売れる商品作りができるようになり、売り上げが格段に上がった。
- 売れないものを売り続けるという無駄な時間を費やすことを無くすことができた。
このマーケットインという考え方は、簡単に実現することが可能ですので、ぜひ、参考にしてください。
それでは早速、読み進めていきましょう。
中小企業に必要なのはマーケットインという考え方

この「商品が良ければ売れる」という考え方、事業が上手くいっている時はそこまで問題にならないのですが、逆に事業が上手くいかなくなると一気に危険思想に早変わりをしてしまいますので非常に厄介です。ですから、事業が上手くいっているうちに考え方を少しずつ切り替えることをお勧めいたします。
恐らく、釈迦に説法だとは思いますが、商売は、商品を引き渡す代わりに資金(料金)を頂くという交換取引で成り立っています。つまり、お客様からの共感の対価としてお金を頂くという図式ですね。この取引に着目すれば、「商品がよければ当然売れるだろう」というのは若干、的外れな方程式だと分かるかと想います。
実際に取引を行うのは人であり、必ずしも買い手と売り手の考え方が同じということは滅多にありません。取引には人の価値観が入ってくるので、売り手から見ていい商品であっても買い手から見ていい商品であるとは限りません。
例えば、あなたの会社内でスタッフとコミュニケーションをとる時にも、
『この資料をもっと賑わいのある感じにしておいて』
と指示を出しても、思い描いていたものと全く違う資料が納品されること、ありませんか?これは、『賑わいのある感じ』という考え方が、依頼した側(社長・経営者)と、依頼された側(スタッフ)で違うのですから、当然満足いくものは納品されません。
私たち人間は、同じ日本人同士であっても、長い長い時間や体験を共有していない限り、『賑わいのある感じ』というような感覚が他人と揃うことじたいが稀ですよね。自分が少ない言葉で意思をくみ取ってもらえるのは、家族や、古い友達くらいです。それがお客様というほとんど赤の他人とイメージを共有するわけですから、商売は大変なのです。
野菜だって、北海道の広い土地で育った野菜と、23区内の狭く空気の悪い土地で育った野菜とでは、味も形も大きさも違います。人も育った環境が違えば、言葉の定義一つから変わってくるわけです。ここをキチンと理解していなければいけません。
結局、“買い手がいい”と思ってくれない限りはモノやサービスは売れません。
買い手の生活を想い、買い手の生活をどのように改善できる商品なのかその生活は買い手にとってどれほどワクワクできるものなのか。この点がはっきりわからなければ物は売れないのです。その道一筋●年の職人が『いいモノ』というのであれば、それはいいモノなのでしょう。ですが、そのモノが、買い手がどういう時に使って、どういう効用を得ることができるのか。この点を提案しない限りは、『いいモノであること』は伝わりません。
ですから『いいモノであれば売れる』のではなく、
『買い手が、あるシーンにおいて不満に思っていることを解決できるもの』
『買い手が、普通に過ごしている日常に、その商品があることで日常がより楽しくなるもの』
この二つが、売れるモノであると考えることが出来るのです。つまり、生活のネガティブを消すのか、生活をポジティブにするのか、です。この考え方のこと“マーケットイン”と言います。
簡単にできるマーケットイン思考を実現する方法
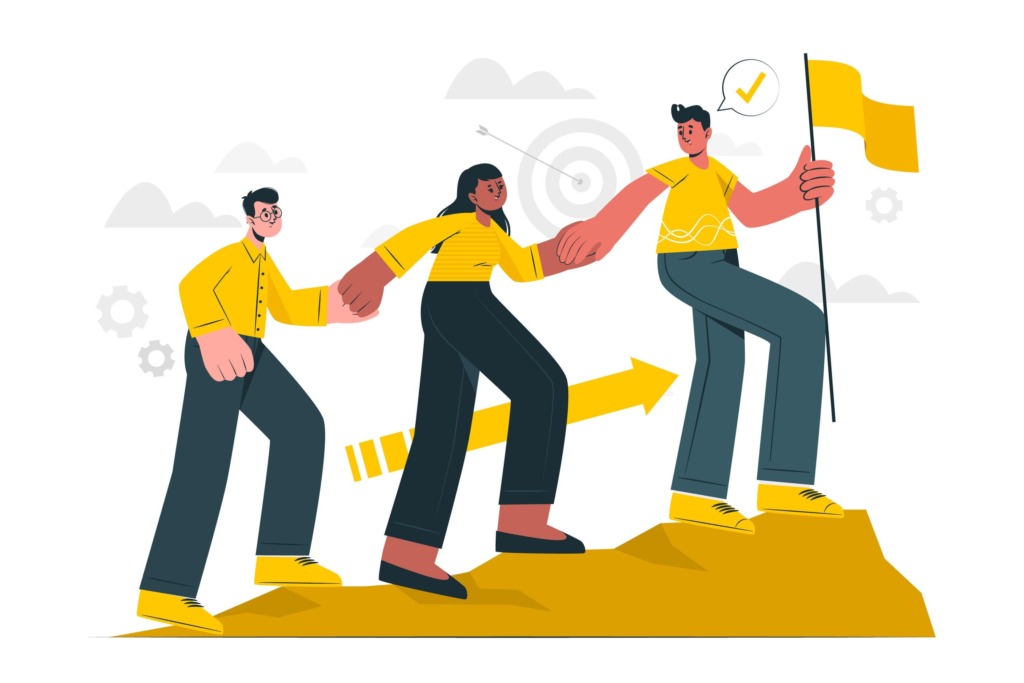
商品ありきで固執して考えてしまう方が“マーケットイン”の思考に切り替えるためにできる1つの簡単な方法があります。それはまず、お客様の声を拾いながら『なぜ私たちの商品・サービスを買ってくれるのか』の答えを導くことです。
実際に、私たちが経営コンサルティングに入る際は、まず直接お客様の声を聴きにいくことが大多数です。例えば、飲食店などのBtoCビジネスの場合であれば、お客様アンケート等で「どんな人が」「なぜ」「どういうタイミングで」「誰と」店やサービス、商品を利用しているのか声を拾っていきます。BtoBビジネスの場合であっても、その会社の営業マンと一緒にお客様先に同行させていただき、「なぜこの商品を利用しているのか」のお客様の声を拾いにいきます。すると、今まで自社内では誰も気付いていなかったニーズや用途に辿りつくものなのです。※これが案外「えっ、そんな風に使ってたんだ!?」という声が拾えるものです。
意外なニーズや用途で言えば、有名な例で言えば炊飯器なんかもそうですね。今では炊飯器は、米を炊く以外にもケーキや焼き芋を作ったりする人もでてきていますね。そんな所に気付けるかどうかでビジネスのかじ取りは大きく変わりますので、まずはお客様の声を拾いながら、『商品ありき』の考え方を変えていってみて下さい。
- 「自社に合ったマーケットインについての話をもっと詳しい話を聞きたい」
- 「自社商品やサービスに関して、マーケットインの視点で一緒に考えて欲しい」
なども含め、非常に煩雑で難しい新規事業の企画・立ち上げ、推進や収益化でお困りの際は、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談(無料)ください。
「株式会社Pro-d-use」のサービスを活用すると、新規事業のプロがあなたに代わって新規事業の調査から企画・立ち上げ・推進、収益化までをあなたの会社の現場に入って一緒に進めてくれるので、あなたは「新規事業を進める苦悩や業務から解放」されますよ。
>>> [毎月3社限定] 3回までは無料でご相談をお受付いたします<<<
コラム著者プロフィール

小笠原 亮太
代表取締役社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
「事業承継」こそ、第二創業の好機。
見えない組織の意志を、次代へ続く高収益体質を築く。
企業経営において、最も難易度が高く、かつ重要な局面は「事業承継」と「組織の意思統一」にあります。どれほど素晴らしい技術や商品があっても、それを扱う「人」の心がバラバラでは、企業は永続できません。
私は株式会社リクルートを経て、飲食店専門コンサルティング会社にて実務を磨きました。そこでは既存のコンサルティングの枠を超えた商品開発を行い、担当した全ての顧客企業を売上増へと導きました。この「結果にコミットする姿勢」と「組織を内側から変えるノウハウ」を基に、現在はPro-D-useの代表として、経営者様が抱える「継承と成長」の課題解決に全力を注いでいます。
■専門性と実績:事業の永続化へのアプローチ
私の最大の強みは、経営者の頭の中にある「ビジョン」や、組織内に漂う「空気感」といった無形のものを有形化(言語化・仕組み化)する力にあります。
▼専門・得意領域
|事業承継の最適化|
単なる株式や資産の引き継ぎではありません。
先代の想いと次代の戦略を融合させ、社員が納得してついていける「事業モデルの承継」を実現します。
製造業や建設業、リース業など、実業を重んじる業界での実績が豊富です。
|組織を動かす仕組み作り|
「笛吹けど踊らず」の組織を変えます。社員一人ひとりのモチベーションを科学し、自発的に利益を生み出す組織構造へと変革させます。
|100%の実績に基づく収益改善|
「担当全顧客の売上UP」を達成した現場力を活かし、机上の空論ではない、現場が実行可能な改善策を並走します。
■仕事の流儀
経営者は孤独です。特に事業承継や組織改革の悩みは、社内には相談できません。
私は外部のコンサルタントでありながら、経営者様と同じ視座・同じ熱量で議論できる「唯一のパートナー」でありたいと考えています。貴社の歴史を尊重し、未来への架け橋となります。
「会社を次の世代へ、より強い形でバトンタッチしたい。」
そうお考えの経営者様。
その想いを、確かな「形」と「成果」に変えるお手伝いをさせてください。