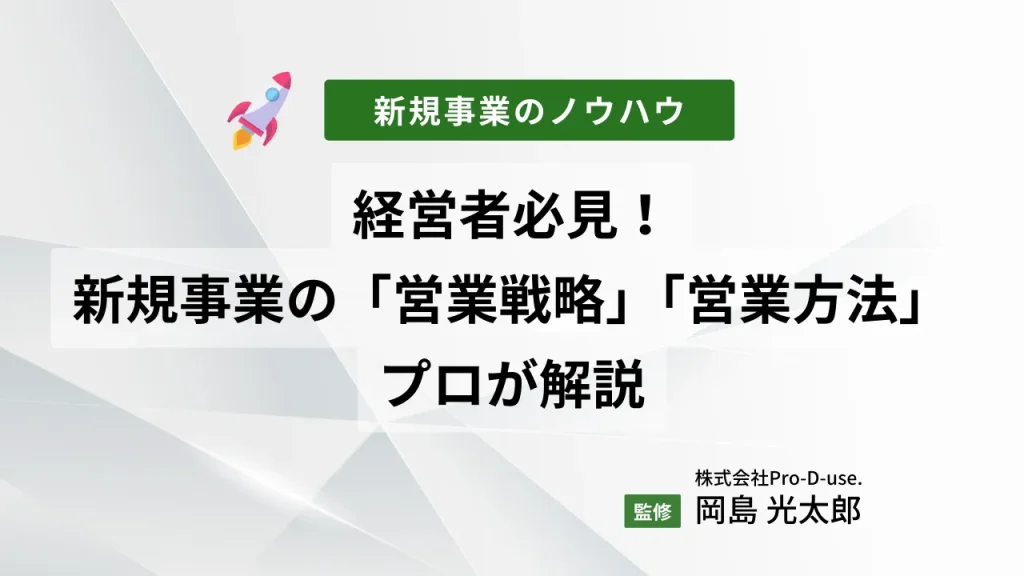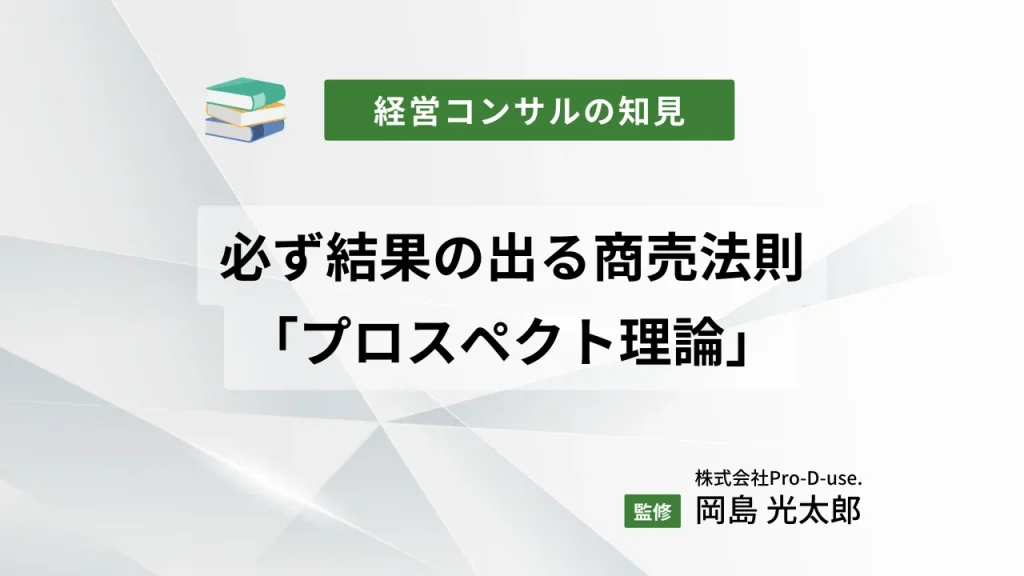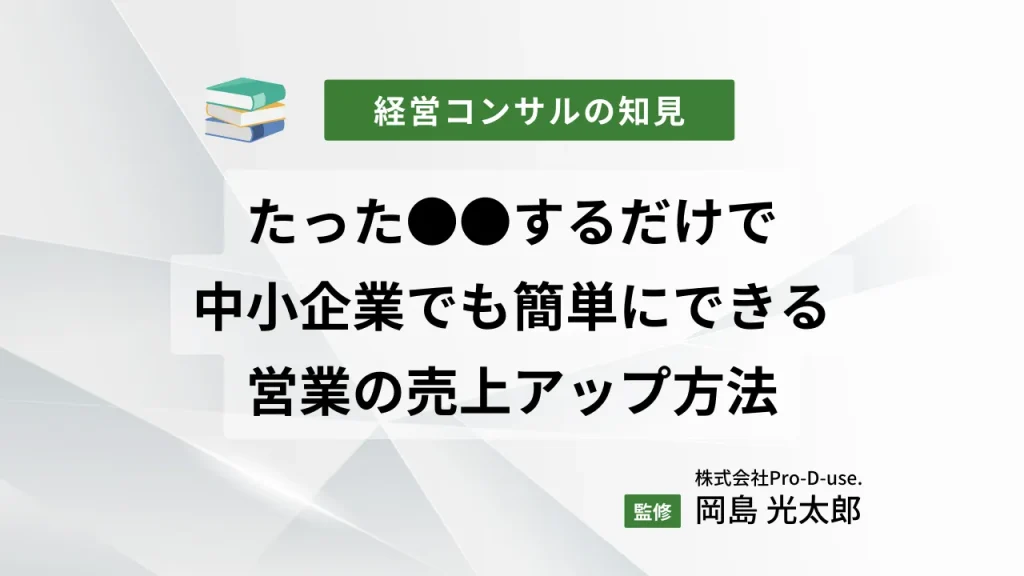受注率をグッと上げる!14の成約率向上策をプロが解説
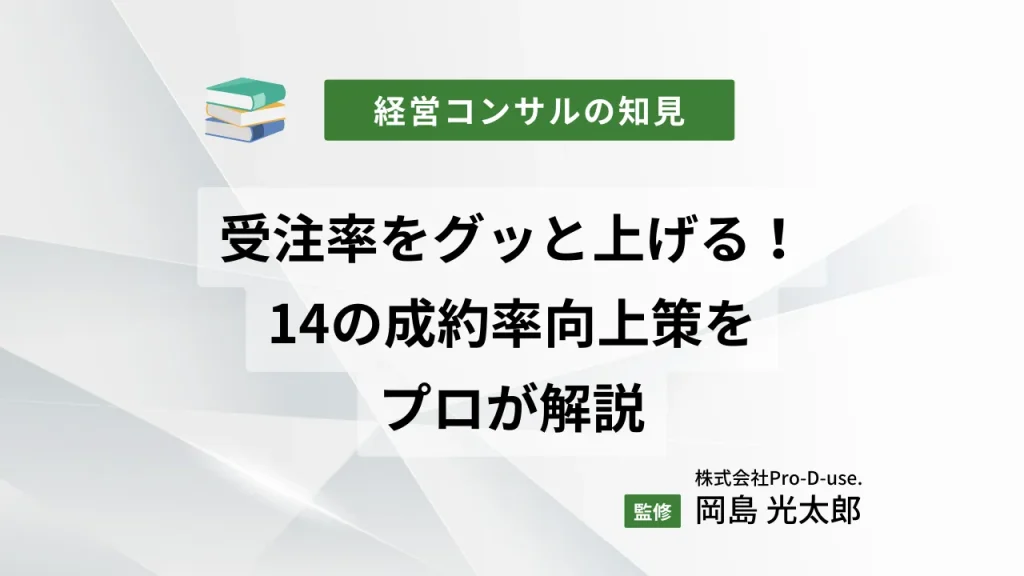
-
- 営業・販売戦略
- 2024年10月17日
契約率・受注率を上げたいと悩む方は、下記のような疑問や不安を抱えていませんか?
「部署全体の受注率が低いが、原因がわからない」
「受注率を何とかしたいが、具体的な方法がわからない」
「すでに対策しているものの、受注率が低調なままで焦っている」
受注率を上げるには、感覚的に改善をしても効果を得ることはできません。受注率を上げるには、受注率が低い原因を明確にし、原因に対して適切にアプローチする必要があります。
また、即時性のある方法ばかりを試すのではなく、中長期的に改善が見込める方法も同時に進めるのが、受注率向上には大切です。
筆者は「株式会社Pro-D-use」という業績アップに強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの中小・中堅企業の業績アップをご支援してきました。
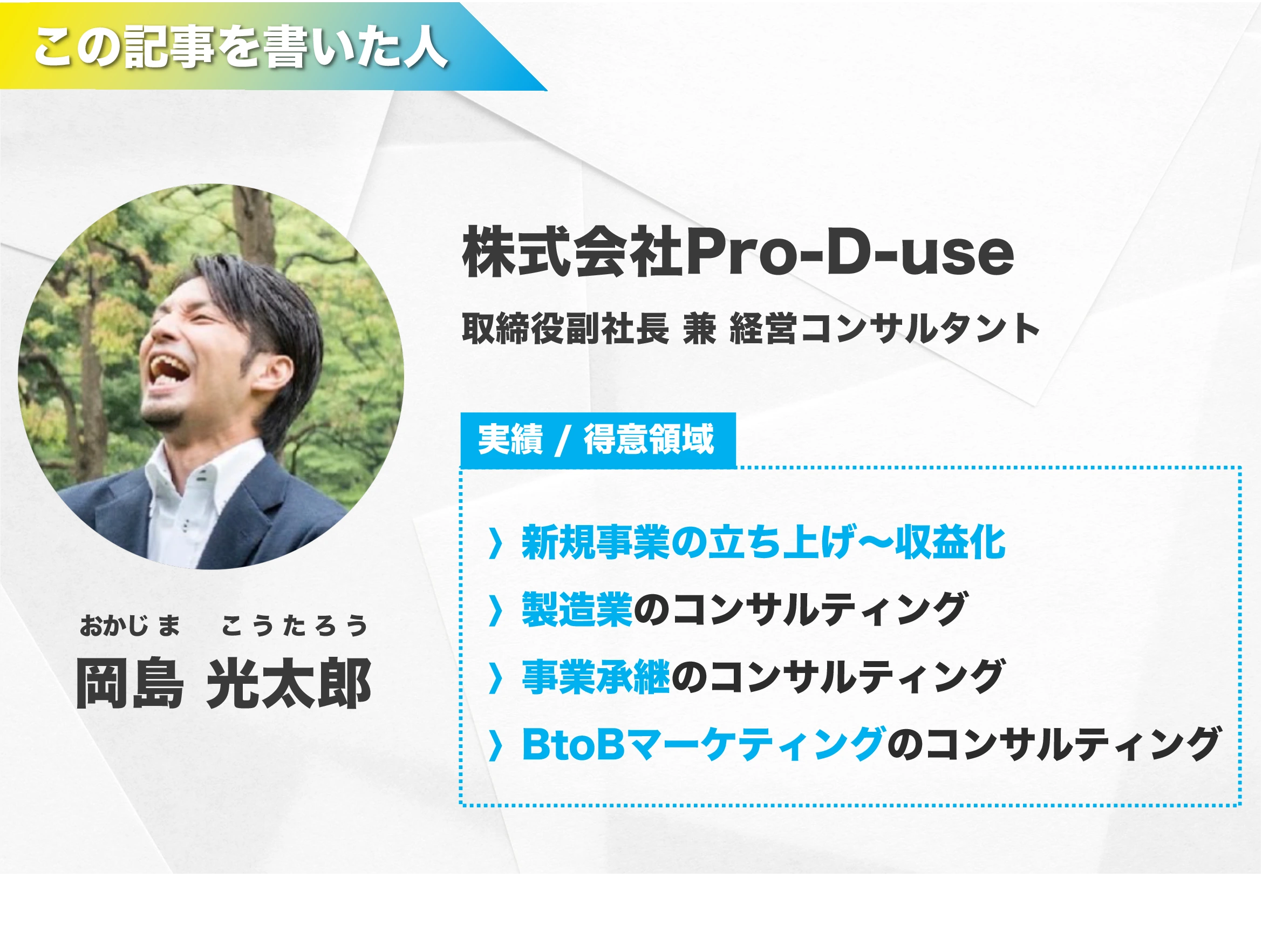
そこで本記事では、営業・販売不振から業績アップの支援を得意とする筆者が、下記の内容を丁寧に解説します。
◆この記事で解説すること
- 受注率の基礎知識
- 受注率が低い原因
- 受注率を上げる方法
「受注率が低い原因がわからない」「受注率をなんとかして上げたい」とお困りの営業担当者または営業マネージャーの方は、ぜひ参考にしてください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>
\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /
受注率の計算方法
受注率とは、商談した件数のうち、実際に契約が成立した件数の割合を示す指標です。また、受注率は以下の計算式で求められます。
◆ 受注率の計算方法
受注率=成約数÷商談数×100
例えば、200件の商談のうち、50件で契約が成立した場合の受注率は、以下のとおりです。
受注率=50÷200×100=25%
業界によって差はあるものの、一般的に営業の受注率は30〜50%が目安とされています。そのため、自社の受注率がこちらの目安より高ければ「受注率が高い」、低ければ「受注率が低い」と判断できます。
受注率が低い6つの原因
受注率はなぜ低くなるのか、考えられる主な原因は次のとおりです。
◆ 受注率が低い6つの原因
- ターゲットがズレている
- 受注の可能性が低い案件に時間を取られている
- BANT条件を確認できていない
- 顧客のニーズや要望を無視して営業している
- 失注した原因を分析できていない
- 業務効率が悪い
原因1. ターゲットがズレている
営業の際、特に考えずに闇雲に営業している場合は、そもそも営業するターゲットがズレている可能性があります。手あたり次第に100件営業するより、見込みが高いターゲットを絞って5件に営業する方が、受注率は圧倒的に高くなります。
事前に適切なターゲットを特定し、顧客リストを絞り込み、少ない営業人数(時間)で営業をすることが1番効果的です。
「ターゲットを決めていなかった」「しっかり考えたことがなかった」という場合は、営業するターゲットについて再度見直す必要があるでしょう。
原因2. 受注の可能性が低い案件に時間を取られている
受注の可能性が低い案件ばかりに営業している場合も、受注率は低くなります。
先ほどのターゲットの話とも重なる点がありますが、案件には成約の見込み(受注確度)が高いものと低いものがあります。しかし、成約の見込みが低い案件ばかりに人数や時間をかけてしまうと、契約が取れないだけでなく、時間も人員も無駄になってしまうのです。
限られた人員、時間で受注率を上げるには、成約の見込みが高い案件をピックアップし、その案件に時間や人員を割けるように案件の選別をする必要があります。
原因3. BANT条件を確認できていない
成約の見込みが高い案件を見分ける基準の一つに、「BANT条件」があります。
BANT条件とは、Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)の4つからなる条件です。これら4つのうち、1つでも条件を満たさない場合は、成約がうまく進まない可能性があります。
たとえば、ある企業へ営業した際、予算・決裁権・導入時期の3つは問題なかったものの、「今は必要ないかな」と必要性の条件を満たさなかったとします。すると、営業している感じでは好感触を得ているものの、最後の最後で「また次の機会に」となってしまうのです。
成約がうまく進まないと受注率にも影響するため、営業のターゲットや受注の可能性が高い案件をピックアップする際は、BANT条件を意識する必要があるでしょう。
原因4. 顧客のニーズや要望を無視して営業している
顧客のニーズや要望を無視しての営業も、受注率が低くなる原因の一つです。
顧客は「悩みや困りごとを解決してくれる取引先を見つけたい」と考えています。それにもかかわらず「自社の製品は最新技術を使用している」「自社のサービスは世界的にも有名」といった、製品やサービスそのものを売り込むような営業では、相手の興味は引けません。
ましてや自社の製品やサービスを押し売りしている場合は、相手との関係性が悪くなることもあるでしょう。
原因5. 失注した原因を分析できていない
失注した原因を分析せず、同じような営業を続けている場合、受注率は上がらないままです。「なぜ成約に至らなかったのか」「失注した案件に共通する点はないか」など、失注後に原因を振り返ることで、解決の糸口が見つかります。
そのため、失注後の分析は受注率を上げるために重要だといえるでしょう。
原因6. 業務効率が悪い
業務効率が悪い場合も、受注率が低くなる可能性があります。見積書や契約書の作成、顧客情報の打ち込みなど、一つひとつの事務作業に時間がかかっていると、本来の営業業務に十分な時間が割けなくなります。
「何年も同じソフトを見直さず使用している」「営業担当によって書類等の形式が異なる」といったような状況の場合は、業務効率を見直す必要があるでしょう。
【個人】受注率を上げる10の方法
個人の受注率を上げるには、以下10の方法が挙げられます。
◆ 個人が受注率を上げる10の方法
- 明確な営業目標を設定する
- 見込み客の情報をデータ化・管理する
- 優先順位をつけてアプローチする
- 丁寧なヒアリングで顧客のニーズを汲み取る
- 顧客のニーズに沿った提案をする
- 心理学のテクニックを取り入れる
- 価格を明確に提示する
- スケジュールを明確に提示する
- 複数プランを用意する
- 断られた後のアクションを決めておく
具体的な方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
個人の方法1. 明確な営業目標を設定する
まずは、明確な営業目標を設定することが重要です。成約数や売上目標はもちろん、成約に至るまでの商談数や見込み客の獲得件数など、具体的に目標を設定しましょう。目標を意識しながら営業することで、「どの部分で成約率が下がっているのか」「苦手な業務はないか」などの課題が見つかりやすくなります。
個人の方法2. 見込み客の情報をデータ化・管理する
見込み客の基本情報を管理している場合は多いですが、アプローチ方法、反応や手ごたえなども合わせて管理することが大切です。これらの情報を残しておくと、失注した際の振り返りや、次のアプローチに役立ちます。他の営業担当と共有することも考えると、情報はデータで管理するのが良いでしょう。
個人の方法3. 優先順位をつけてアプローチする
限られた時間の中で効率的に受注率を上げるには、見込み客に優先順位をつけてアプローチすることも大切です。すべての顧客に対して同じように営業するのではなく、BANT条件が揃っているなど、受注確度の高い顧客から順にアプローチすれば、効率よく受注につなげられるでしょう。
個人の方法4. 丁寧なヒアリングで顧客のニーズを汲み取る
受注率を上げるには、顧客の悩みや課題などを汲み取ることも大切です。相手の困っていることが明確になれば、そのニーズに対して自社の製品やサービスが役立つ点をアピールできます。
個人の方法5. 顧客のニーズに沿った提案をする
顧客のニーズに沿った提案をするためには、自社製品やサービスに対する理解を深める必要があります。製品・サービスの機能や強み、競合他社の情報はもちろん、顧客にどのようなメリットがあるのかまで理解しておくことで、顧客への提案がしやすくなるでしょう。
また、ニーズに沿った提案は、顧客に「自社の悩みを解決しようとしてくれている」といった信頼感を与えられます。顧客との信頼関係が築ければ、よりスムーズに商談が進みやすくなるでしょう。
個人の方法6. 心理学のテクニックを取り入れる
受注率を上げるには、心理学のテクニックを営業に取り入れるのも効果的です。具体的には、以下のようなテクニックが挙げられます。
◆ 受注率向上に寄与する主な心理テクニック
- ミラーリング:相手の言動を模倣する手法
- バックトラッキング:相手の言葉をそのまま返す手法
- ゴールデンサイレンス:意図をもって沈黙する手法
- イエスバット法:相手の意見を一旦受け入れ、その後に自分の意見を話す手法
- テストクロージング:商談から契約に進む前に相手の意思を確認する手法
これらのテクニックを営業に取り入れることで、顧客と信頼関係を築くのに役立ったり、商談がスムーズに進みやすくなったりする効果が期待できます。
個人の方法7. 価格を明確に提示する
顧客が契約するか迷っている場合は、価格を明確に提示するのも効果的です。明確に提示されなかったり、はぐらかされたりするなど、価格の面で不安な点があると顧客が不信感を抱きやすくなります。
その価格になる理由などを伝えたうえで、明確に価格を提示するようにしましょう。
個人の方法8. スケジュールを明確に提示する
価格と合わせて、顧客の返答期限や契約日、契約してからのスケジュールなどを明確に提示するのも大切です。
返答期限や契約日が決まっていない場合や、契約してからのスケジュールが曖昧だと、顧客は契約を先延ばしにする可能性があります。いつまでに判断すべきか、契約してからのスケジュール感が明確であれば、顧客も安心して商談を進めやすくなるでしょう。
個人の方法9. 複数プランを用意する
営業の際は、複数プランを準備したうえで商談を進めるのも大切です。
心理テクニックの「ドアインザフェイス」の効果を利用した手法で、松竹梅の3段階の提案を用意しておくことで、商談をスムーズに進めやすくなります。
具体的には、竹または梅に本来契約したい契約内容を設定し、松(または竹)に断られる可能性がある契約内容を設定します。提案の際は松→竹→梅の順で提案し、何度か顧客に断らせることで、本来の契約内容を承諾してもらいやすくするのです。
顧客情報やニーズなどをしっかりと調べ、顧客に合ったプランを複数用意して営業に臨むと良いでしょう。
個人の方法10. 断られた後のアクションを決めておく
契約できるに越したことはありませんが、実際は全ての商談のうち、何件か断られるケースがほとんどです。しかし、顧客から断られたから終わりではなく、断られたあとでどのようなアプローチをするかが大切になります。
断られる理由の中には「タイミングが合わなかった」「今は必要でない」など、今後の契約につながりそうなものもあります。一度断られた顧客とも良い関係を維持し続けることで、将来契約につながる可能性があるでしょう。
【組織】受注率を上げる4つの方法
受注率を上げるには、個人の能力にゆだねるだけでなく、組織的な改善が必要な場合もあります。必要に応じて以下の方法を取り入れ、組織全体で受注率を高めましょう。
◆ 組織がが受注率を上げる4つの方法
- 受注確度の判断基準を統一する
- 全体の営業力を強化する
- 営業業務を効率化する
- 経営コンサルタントに相談する
それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。
組織の方法1. 受注確度の判断基準を統一する
「受注確度の高い案件に注力した方がいい」といっても、具体的にどんな案件が受注確度が高いといえるのか判断が難しい方もいるでしょう。そこでオススメなのが、受注確度の判断基準を組織全体で統一する方法です。基準が明確に決まっていれば顧客の優先順位をつけやすく、営業担当者が変わっても引継ぎやすくなります。
必要に応じてMA(マーケティングオートメーション)やCPM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)などのITツールを活用し、自社の状況に合わせて受注確度の基準を統一すると良いでしょう。
組織の方法2. 全体の営業力を強化する
全体の営業力を強化することも大切です。定期的な研修やセミナーを開催したり、営業担当同士で意見交換する機会を設けたりして、営業力の底上げをしましょう。
また、トークスクリプトと呼ばれる「営業の型」をつくるのもオススメです。型があれば、新人でもベテランでもある程度同じように商談を進められるようになるため、営業の属人化も防げるでしょう。
組織の方法3. 営業業務を効率化する
受注率を上げるには、営業業務を効率化して、より多くの時間を営業に充てられるようにすることも大切です。
顧客情報の整理や書類の作成といった事務作業をできるだけ削減できれば、受注確度の高い案件に多くの時間を割けるため、結果的に受注率の向上につながるでしょう。手当たり次第に飛び込み営業をするのではなく、ITツールを活用して受注確度の高い案件を絞り込んだり、インサイドセールスを活用したりすることで、業務の効率化が図れます。
組織の方法4. 経営コンサルタントに相談する
「どの方法が自社に適しているかわからない」「今やっているやり方で合っているのか不安」といった悩みをお持ちの方は、経営コンサルタントに相談するのがオススメです。経営コンサルティングを活用することで、専門的な視点で受注率が低い原因や具体的な解決法などを提案・支援してもらえるでしょう。
(株)Pro-D-useは、経営者や営業担当者が抱える悩みに寄り添い、受注率の向上を始めとした営業の経営コンサルティングを行っており、これまでに以下のような課題をコンサルティングしてきました。
◆(株)Pro-D-useに寄せられる営業の課題
- 営業力に差があり、全員で使える営業ツールが揃っていない
- 従業員のモチベーションが低く、適切な営業成果が残せていない
- 思うような営業成果が残せていない
営業支援に関する事例については、以下のページからチェックしてみてください。
「営業・販売不振」コンサル事例 | 株式会社Pro-D-use
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>
\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /
受注率を上げるため、原因を特定して対策を打とう
本記事では、受注率が低い原因や、受注率を上げるための具体的な方法について解説しました。個人・組織における受注率を上げるための具体的な方法は、次のとおりです。
◆個人
- 明確な営業目標を設定する
- 見込み客の情報をデータ化・管理する
- 優先順位をつけてアプローチする
- 丁寧なヒアリングで顧客のニーズを汲み取る
- 顧客のニーズに沿った提案をする
- 心理学のテクニックを取り入れる
- 価格を明確に提示する
- スケジュールを明確に提示する
- 複数プランを用意する
- 断られた後のアクションを決めておく
◆組織
- 受注確度の判断基準を統一する
- 全体の営業力を強化する
- 営業業務を効率化する
- 経営コンサルタントに相談する
Pro-D-useは、現場に入り込み、会社全体を把握しながら事業を一緒に飛躍させる伴走・現場型の経営コンサルティングです。営業戦略の策定からWeb・リアル営業力の強化まで一貫してサポートするため、受注率の向上でお困りの方は、お気軽に無料経営(受注率向上)相談フォームからご相談ください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>
\ 伴走型の経営コンサルを探してるなら!! /
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
2009年:(株)リクルートに新卒で入社。営業・企画の両面で責任者を務める。
※リクルートではMVPやマネジメント賞など、個人・マネージャー賞を多数受賞。
2013年:(株)データX(旧:フロムスクラッチ)の創業期に転職。営業や新卒・中途採用の責任者を務める。
2014年:アソビュー(株)に転職。その後、営業責任者、新規事業責任者を歴任。
2015年:(株)Pro-D-useを創業。取締役副社長(現任)に就任。
【得意領域】
新規事業の立上げ~収益化、成果を上げる営業の仕組み作り、BtoBのWebマーケティングを主軸とした売れる仕組み作り、DXまで見通したIT・SaaS・業務システムの導入や運用、融資を中心とした資金調達~財務のコンサルティングを得意としている。
【担当業種】
「システム受託開発」「Webサービス」「Tech系全般」「製造」「建築」「販売・サービス」「スクール業」など多岐。
【資格・認定】
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)