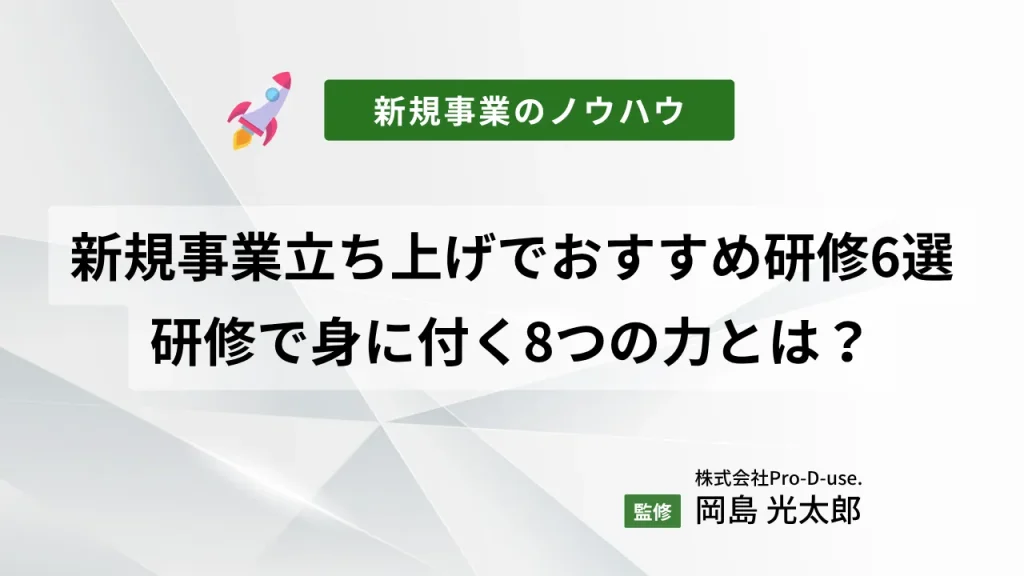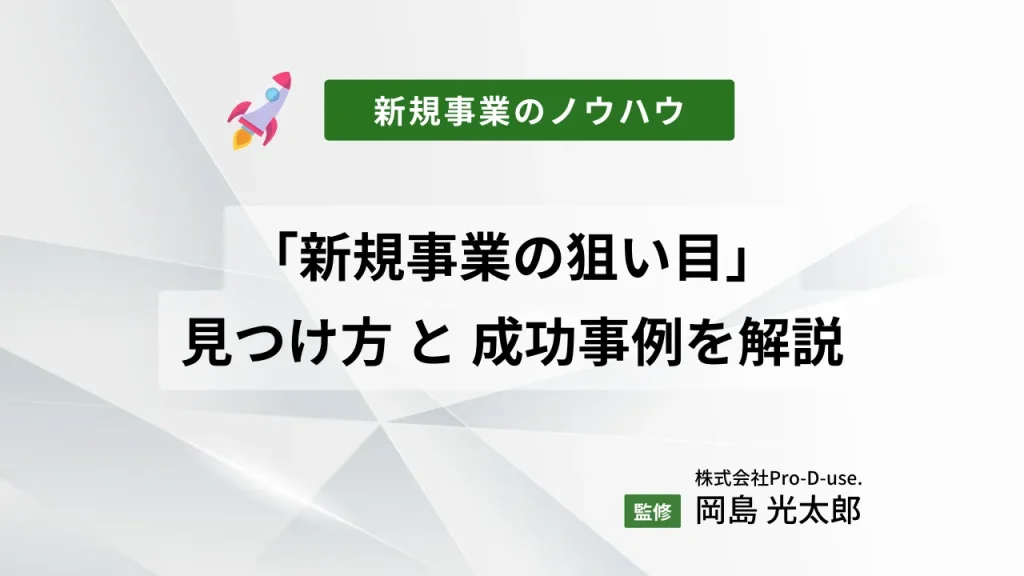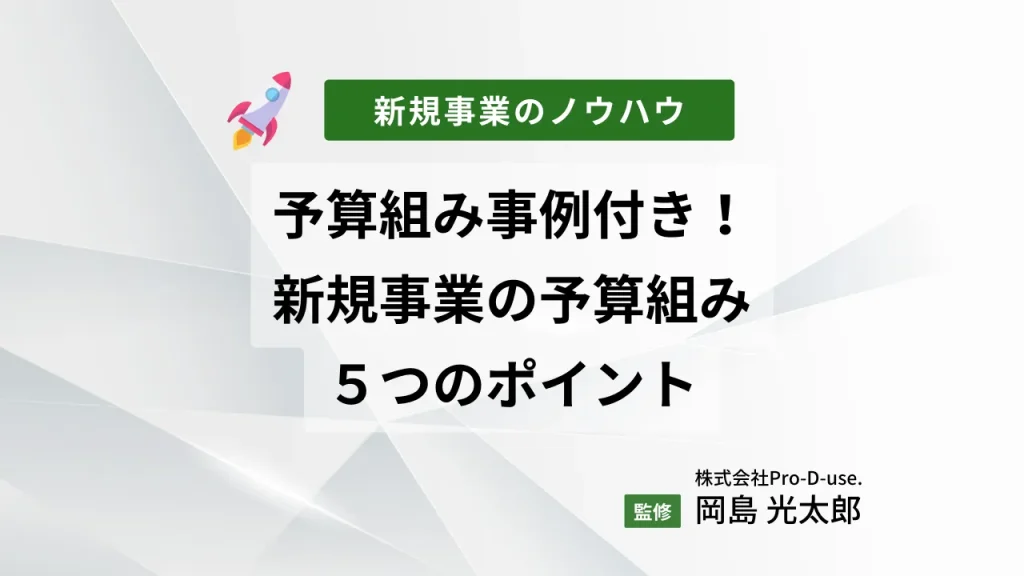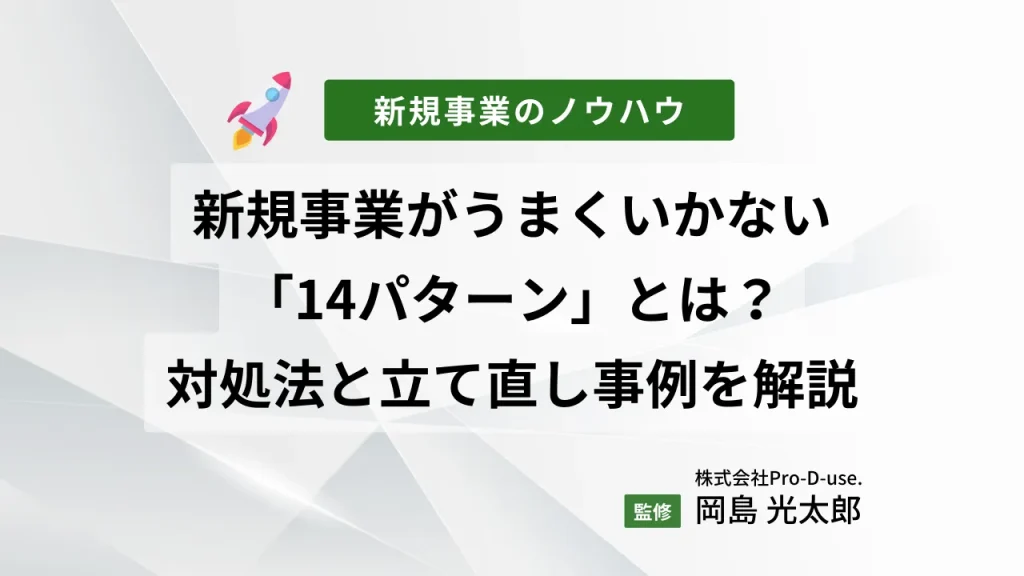ECRSの原則とは?新規事業で欠かせない理由や注意点
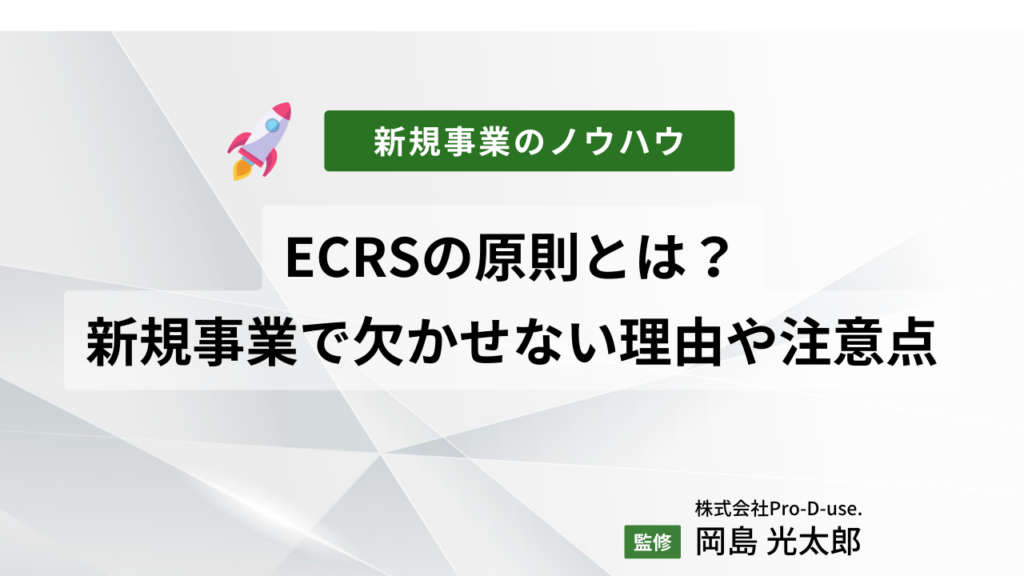
-
- 新規事業
- 2022年11月17日
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。
弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業サービスはコチラ >>>
\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /

業務の効率化を進めて働きやすい環境を作りたい。だが、何から手をつけていいか分からない。

今ある仕事は簡素化したものの、イマイチ効果が上がらない。ECRSの原則には正しい手順があるのだろうか?
ECRSの原則とは、仕事を効率化する上で重要な、4つの要素をまとめたフレームワークです。使い方にもコツがあり、頭文字順どおりに業務を見直すことで、最も高い効果を発揮できます。
今回は、ECRSの原則の基本の手順と、新規事業に活用する効果、注意点を解説します。
この記事を読み終えると、こんなことが実現できます
- 業務効率化の正しい手順が分かるため、余計な方法を使って時間を浪費せずに済みます。
- 手順に従い業務を削減していくため、本当に必要な仕事を見極められます。
ECRSの原則を使って、不要な仕事をどんどん削減していきましょう。
目次
ECRSの原則とは業務を効率化するためのフレームワーク

ECRS(イクルス)の原則とは、業務を効率化するのに必要な4要素をまとめたフレームワークです。提唱者などは不明であるものの、元々は製造現場の業務改善のために利用されていた考え方です。
名称は、下記の頭文字に由来します。
- Eliminate(排除):業務を廃止できないか
- Combine(結合):業務をまとめられないか
- Rearrange(交換):業務の順序や担当者を入れ替えられないか
- Simplify(簡素化):業務を簡単にできないか
「排除」「結合」「交換」「簡素化」の順に効果が高い
ECRSの原則の特徴として、Eliminate(排除)が最も効果が高く、Simplify(簡素化)に行くに従い、効果が薄くなっていきます。
効率化のために業務を見直す際は、文字どおりの順番で確認するのがポイントです。
新規事業におけるECRSの手順

では実際に、新規事業でECRSを活用した業務改善の手順を紹介します。
1.Eliminate:無駄な業務はないか確認しよう

業務改善の前に、まずは、現在の業務を洗い出しましょう。タスクや工程表で管理していないなら、仕事を一つひとつ書き出すと分かりやすいでしょう。
なお、朝礼のように習慣化している業務も見直しの対象です。
業務を見える化したら、その業務の目的は何か、どの目標のために行っているのか考え、曖昧なものは一度廃止し支障がないか確かめます。
無駄を削減すれば、金銭・時間、どちらのコストも削減できるため、業務改善の効果も大きくなります。
【Eliminateの具体例】
- 毎日の朝礼を廃止し、週一回に変更する
- 社内電話を廃止し、緊急時以外はチャットでやり取りする
- 外注できる業務は、社外に依頼する
2.Combine:似たような業務はまとめよう

同じような仕事を別々の部署や担当者で行っているなら、一つに集約し、問題がないか確認しましょう。
また、似たように見えて、実は内容が異なる仕事をまとめていたなら、分けて行った方が効率化できる可能性もあります。
似た仕事を一つにまとめれば、工数自体を減らし、人的コストの削減にもつながります。
【Combineの具体例】
- 請求書はクライアントを担当する社員が作るのではなく、経理部門を設置し作成・発送・問い合わせまで集約する
- コールセンターは全員で対応せず、問い合わせ内容別にチームを分ける
3.Rearrange:業務を組み替えてみよう
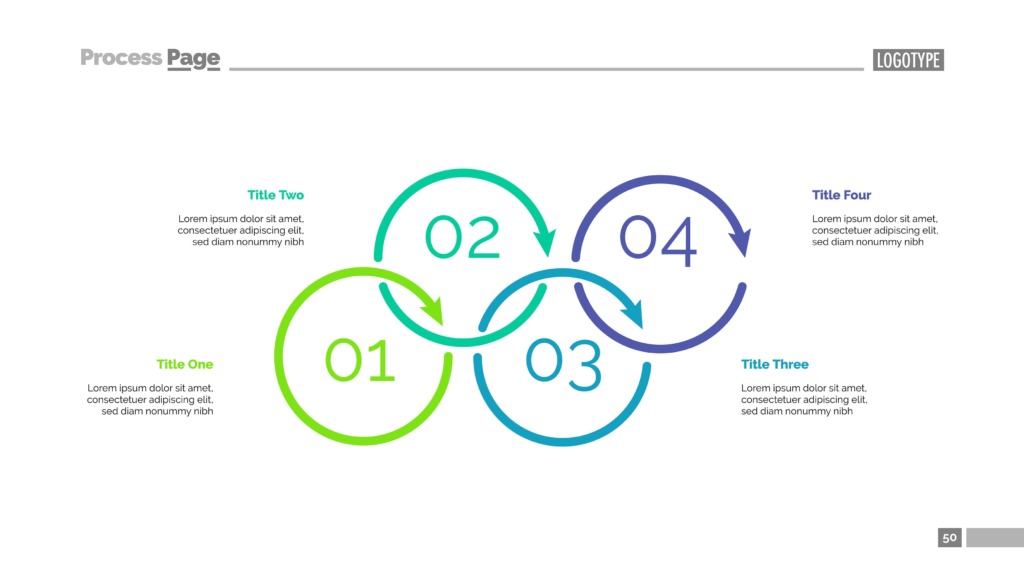
業務の順序・場所・担当者などを入れ替えて、効率化できないか検討してみましょう。
入れ替えでは業務を細かく見ることで効率化できる部分が見つかります。
廃止のように、工数を大幅に削減するのは難しいものの、小さな変更のため、導入しやすい点がメリットです。
【Rearrangeの具体例】
- 報告書など、毎回行う仕事はテンプレートを作成しておく
- 会議場所は本社に限定せず、Webを利用し各事務所から参加する
- 社員の適性に合わせて宜業務を変更する
4.Simplify:シンプルにできるものはないか確認しよう

最後に、簡素化できる業務はないか確認しましょう。
簡素化の中には、人が行う業務をシンプルにするだけでなく、自動化のように適切なシステムの導入も含まれています。単純化すれば、業務の属人化を防ぐのにも役立ちます。
【Simplifyの具体例】
- よく使う文章は辞書ツールに登録する。
- 経費精算は専用のソフトを導入し自動計算にする
- 商品の発送では宅配以外にポスト投函も利用する
ここまでがECRSの原則に関する説明と具体例です。
社員研修サービスを行っているリスキルでも、ECRSの原則の具体例をいくつか掲載しています。→ECRSの原則とは?具体例も多数紹介!業務最適化をもう一歩先へ。
「手順は分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る
新規事業におけるECRSの効果

新規事業も、ある程度仕事の方法が固まってきたらECRSの原則を使い、業務を見直しましょう。不要なコストの削減や、高い生産性の維持に役立ちます。
1.効率よくコストを削減できる
ECRSの原則では、確認すべき手順が決まっているため、効率よくコストを削減できます。
闇雲に業務の効率化を進めようとしても、単純化や入れ替えばかり行い、肝心の削減に着手しないこともあるでしょう。
特に、新規事業のように業務を柔軟に変更できるときにECRSの原則を定期的に使えば、高い効果が期待できます。
2.生産性の向上につながる
無駄をなくし仕事の効率化を徹底するため、最終的には必要な仕事だけが残ります。
やるべきことに注力できれば、生産性が向上するのはもちろん、その分早く帰宅できるため、余暇の充実にもつながります。仕事も生活も充実していれば、より、やる気のある状態で新規事業にも取り組めるでしょう。
3.チーム全体で仕事を進められる
ECRSの原則は、仕事の属人化を防ぐためにも有効な手段です。
仕事が人に偏ることなく、チーム全体で進められれば、万が一担当者に何かあったときも慌てることなく業務を進められます。
チーム化により、家族の育児や介護が必要な社員も取り込みやすくなるでしょう。
新規事業におけるECRSの原則の注意点

新規事業でECRSの原則を導入する際は、何を目的に業務の削減を行うのか、削減して効果を得られるのかに注意しましょう。
1.目標を明確にする
ECRSの原則を使って何を達成したいか明確にしましょう。
「無駄を削減しよう」など、指示が曖昧では、何をどの程度すればよいか分かりません。「週の残業時間を2時間減らす」など、具体的な数値を共有し、そのためにできることがないか確認していきましょう。
2.費用対効果を確認する
新しいシステムの導入のように費用がかかる方法では、現行の方法と比べて本当にコストの削減につながるのか確認しましょう。
例えば、経費精算システムを導入しても、使い勝手が悪ければ、固定費のみかかってしまう結果になります。デモ版を導入するなど、本当に効果を上げられそうか確認してから利用しましょう。
3.効果が出ないときは改める
不要に見える業務が、実は、必要な工程であったというケースも考えられます。
削減や統合をしたものの、むしろ効率の悪化につながるなら方法を改めましょう。
施策を導入した後は、数値で効果を管理するだけでなく、社員の声も聞き、現場から不満が漏れないように配慮するのも大切です。
価値を生み出すために、不要な業務は削減していこう

ECRSの原則は、業務効率化のためのフレームワークで、「排除」「結合」「交換」「簡素化」の順に進めることで、最も効果を発揮します。
また、仕事の属人化を防ぐため、チーム化を進めやすくなる点もメリットです。
削減自体を目的とするのではなく、業務を効率化した先にどのような価値を生み出したいのかを念頭に置いて進めることが大切です。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。
弊社「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで300件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな弊社に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは下記サービス詳細をご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業サービスはコチラ >>>
\「新規事業の悩み」がスッと軽くなる /
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)