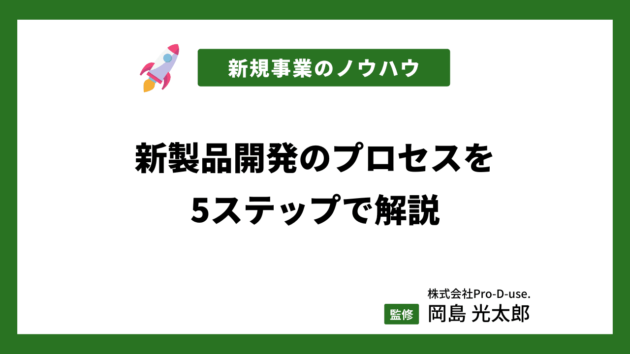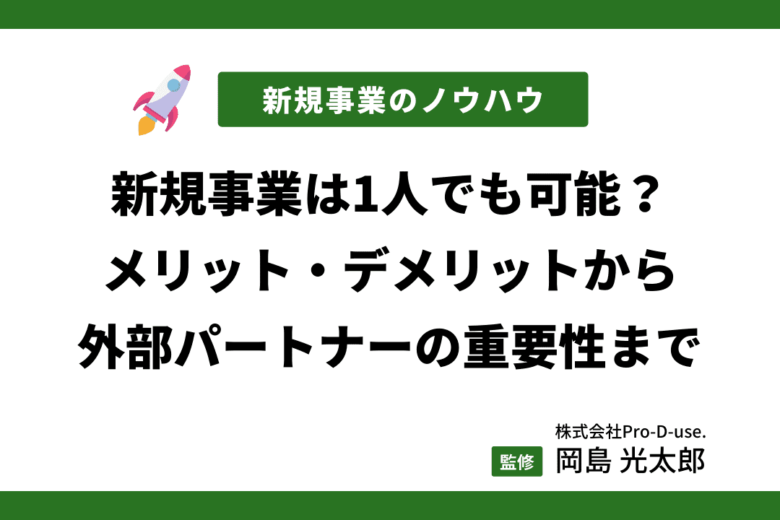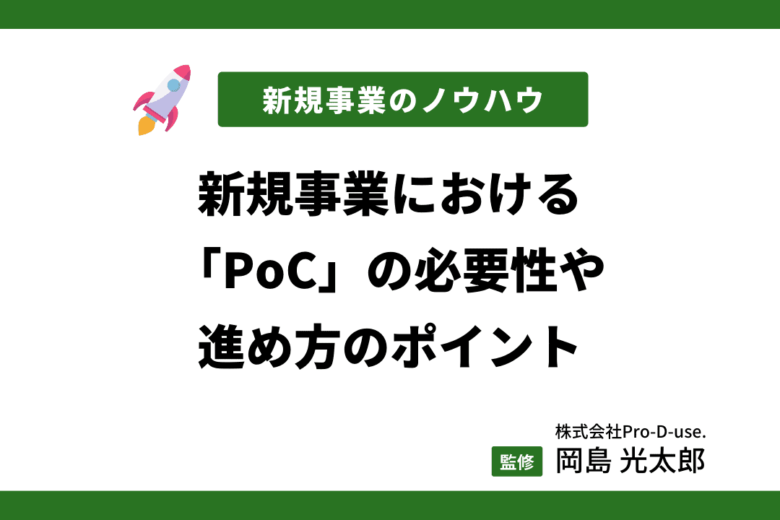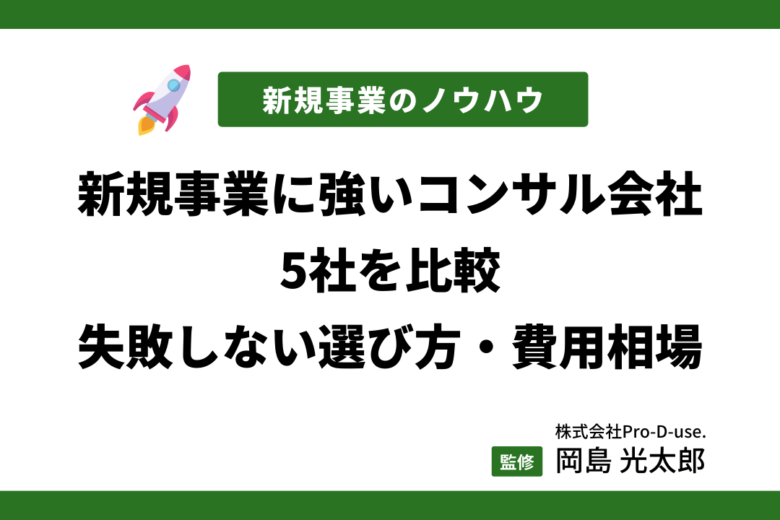新商品開発に携わる方は、下記のような疑問や悩みを持っているのではないでしょうか?
「新製品開発は、どのような流れで考えればいいのだろうか?」
「新製品開発にこれから取り組むが、成功させるために開発プロセスで何に注意すればいいのだろうか?」
「新製品開発の他社の成功事例をみて、成功イメージを沸かせたい」
新たな商品やサービスを作っていくのは企業にとって、収益を上げたり、継続的に事業を続けていくうえで重要なことです。しかし、新商品は「単に新しいだけ」では、顧客の関心を引き付けることができず、失敗する可能性があります。
なぜなら、その新商品が単に世の中になく新しいものだとしても、顧客が求めているかとは別の話だからです。
そこで本記事では、筆者の「新製品開発」プロジェクトの体験を交えて、新商品開発で注意すべきことを解説します。
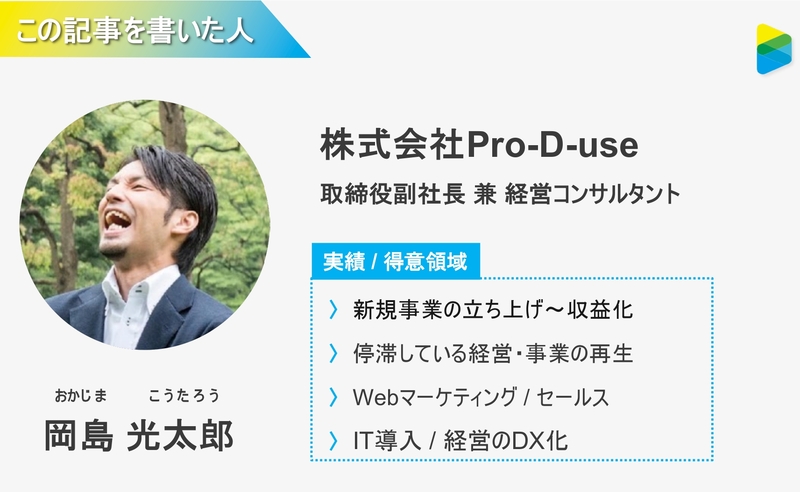
新商品の開発時に、注意しなければならないポイントは以下の2つです。
- 常に顧客の視点で考える
- 事前に開発に必要な資金や期間を定めておく
なぜ上記の2つが重要かというと、企業の目的は利益を得ることあり、その利益は顧客が商品の購入をすることで得られるものだからです。
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 新商品開発のポイントを押さえることで、「新商品を開発し、販売までに至ったが全く売れない、、」という失敗の可能性が格段に低くなります。
- 事前に開発プロセスと注意点を把握できるので、スムーズに売れる商品の開発ができるようになり、収益化するスピードが早くなります。
- 事前に開発に必要な資金や期間を決めておくことで「顧客にとって価値がある商品を開発したのに、資金不足で販売中止にせざるを得なくなった」ということが起こらなくなります。
新製品開発や新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新製品開発にはプロの経験が必要です!
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新製品開発の無料相談】をしてみませんか?詳しくは下記の新製品・新規事業のコンサルサービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新製品・新規事業コンサルサービスはコチラ >>>
▼目次
【中堅・中小企業】新製品開発の2つの成功事例
まずは、筆者および(株)Pro-D-useがコンサルティングした、中小企業の成功事例を紹介します。各社が抱えていた課題に対して提供した支援や、得られた成果について詳細に解説しますので、ぜひご参照ください。
事例1. 株式会社ビー・ファクトリー様

【企業概要】
株式会社ビー・ファクトリー様は、無店舗型の音楽レッスンビジネス(講師派遣サービス)を提供している企業です。
東京都内に直営店舗が7店舗あり、ボーカルやピアノのレッスン、話し方トレーニングなどを提供しています。
【抱えていた課題】
2020年から始まったコロナ禍で、店舗でのレッスンが「三密」と呼ばれるビジネス形態であったため業績が悪化し、一時は売上が90%ダウンするという事態に陥りました。
既存顧客からオンラインレッスンを希望する声があり、弊社Pro-D-useがプロジェクトを主導して新規事業立ち上げにつなげました。既存顧客の声を、新規事業のアイデアとして活用した事例です。
【支援内容】
- 市場調査、競合調査
- 事業計画(シミュレーション)作成
- 社内のプロジェクトマネジメント
- 外部パートナーのマネジメント
- サイトやLP、広告周りなど販促関連のディレクション
- ITシステム導入、および改善
- オペレーションの構築、改善
【得られた成果】
- 緊急事態宣言の2ヶ月後にオンラインレッスン事業立ち上げ。翌日から問い合わせが発生し収益化に成功。
- 無広告状態であったにもかかわらず、問い合わせのうち10%〜15%がオンラインレッスンに関するものに。
- エリアに制限されることなく、顧客層の拡大に成功。
Pro-D-useは、現在でも株式会社ビー・ファクトリー様の経営支援や他の新規事業立ち上げ支援を行っており、過去最高の売上・利益額を達成しています。
事例の詳細については、以下の記事をご参照ください。
事例2. コスモス食品株式会社様

【企業概要】
兵庫県に本社を持つコスモス食品株式会社様は、フリーズドライ食品やエアードライ食品、冷凍食品などの製造を手がけている企業です。
大手企業とのOEM製品を中心に製造してきましたが、自社のオリジナルブランド開発という長年の夢がありました。
【抱えていた課題】
オリジナルのフリーズドライ食品ブランドを立ち上げましたが、その後8年にわたって利益が確保できず、赤字の状態が続いていました。
同社はオリジナルブランドの認知向上のための施策として、既存の取引先への案内や全国キャラバンを実施していましたが、どれも成果にはつながりませんでした。
Pro-D-useがこの事業に参画し、営業戦略・戦術の見直しと構築を行いました。施策の実施や従業員様のマネジメントまで並走し、成果へとつなげました。
【支援内容】
- 調査(市場調査、競合調査など足を使って情報集め/売り方・陳列などの把握)
- 実営業(営業代行、営業同行で現場館をつかむ)
- 営業環境の整備(営業資料、営業ツール作成、トークスクリプトの作成)
- ロックオン顧客(5社)の設定と営業、契約
- 新規顧客の販路の開拓
- 営業部長のマネジメント(メンター)
- 営業戦略の策定
- 次年度の営業目標・予算・KPIの設定
- 営業ロードマップの作成
- 営業ツールの作成
- 営業メンバーのマネジメント代行
【得られた成果】
- 全体の売上のうち、オリジナルブランドの売上の割合が2%から20%へ
- オリジナルブランドの売上が5年で7倍になり、数十億円レベルの売上に
コスモス食品株式会社の事例については、以下の記事で詳細をご覧ください。
新製品開発や新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新製品開発にはプロの経験が必要です!
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新製品開発の無料相談】をしてみませんか?詳しくは下記の新製品・新規事業のコンサルサービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新製品・新規事業コンサルサービスはコチラ >>>
【大手企業】新製品開発の3つの成功事例
以下では具体的に新製品開発の成功事例を3つ紹介します。
- 成功事例1. コカ・コーラ株式会社
- 成功事例2. 味の素株式会社
- 成功事例3. 花王株式会社
成功事例1. コカ・コーラ株式会社
新製品開発の成功事例として、コカ・コーラが代表的です。コカ・コーラは、糖分が気になるユーザーを対象に、ダイエット コカ・コーラを販売しました。
スッキリとした味わいだったため、20〜30代の女性を中心に一定の評価を得ました。
しかしオリジナルのコカ・コーラが好きなユーザーには物足りない商品となっていました。ダイエット コカ・コーラとオリジナルのコカ・コーラを比べると、砂糖が抑えられている分どうしても味を統一できませんでした。
2004年頃からのゼロカロリー飲料ブーム以降、コカ・コーラはオリジナルの味をほとんど変えずにカロリーをゼロにしたコカ・コーラ ゼロを発売しました。
その結果、コカ・コーラ ゼロは、支持され健康志向のユーザーを中心に売り上げを伸ばしていきました。顧客ニーズを的確に捉え、ゼロカロリー飲料市場に満を持して投入した成功の要因でしょう。
成功事例2. 味の素株式会社
次に味の素株式会社の事例です。味の素は、1997年にフライパンに油を引かずパリッとした食感を楽しめる冷凍餃子を発売しました。その結果冷凍餃子は、9年連続で売上金額1位を売上げるヒット製品となりました。
味の素は、調理法の実態調査で多くのユーザーが目分量で水を注いでいたことを発見しました。
水の量は、冷凍餃子の魅力であるパリッとした食感に重要な要素でした。同時に多くのユーザーに、製品の魅力が十分に伝わり切っていませんでした。
調査結果から、味の素は油だけでなく水も使わずにパリッとした食感が作れる冷凍餃子の開発に着手し、油や水分を含ませた羽根の素を餃子底面に着けることで解決しています。
また冷凍餃子をそのまま焼くだけで、羽根までできる見た目の改善もプラスしています。
改良を重ねた結果、冷凍餃子の売上は前年比130%アップの大成功を収めました。味の素は市場調査から製品の課題を洗い出し、問題点を解決した製品を既存市場に投入することで、結果的に新製品開発戦略を成功させました。
成功事例3. 花王株式会社
花王株式会社もアタックZEROで新製品開発に成功している企業です。アタックZEROは、花王の主力製品のアタックを完全リニューアルした新製品として発表されました。
アタックZEROの製品コンセプトは、新開発の洗浄基材で今までの洗剤では落としにくい化学繊維に着いた皮脂などを落としやすいことで、さらに水の使用量が少ないドラム式洗濯機にも最適化させました。
花王の調査の結果、全体の約9%のユーザーしか汚れ落ちに満足していないことがわかったため、より洗浄力のある新開発の洗浄基材を投入しました。長年研究開発を怠らず開発した新製品を、市場に出すことで成功を手に入れました。
それでは、すでに紹介した中小から大手企業の新製品開発事例のように成功するには、何から始めるべきなのか?各プロセス毎に解説してまいります。
新製品開発の5つのプロセス
以下では、新製品開発のプロセスを5つにわけて解説していきます。
- アイデアを出す
- 新製品のコンセプトを打ち出す
- 事業性の検討
- 戦略作成・新製品開発
- 市場参入
プロセス1. アイデアを出す
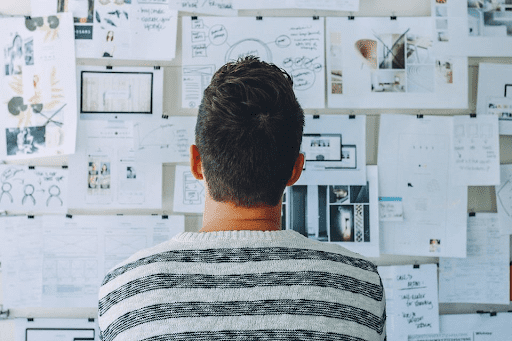
まずは新製品のアイデアを出すことから始めましょう。アイデア出しの段階では、顧客ニーズや価格設定、市場調査などのデータ分析により、製品コンセプトについて検討していきます。
新製品のコンセプト設計においては、ユーザーや既存の製品について以下5つのような分析手法を利用してもよいでしょう。
- アンチプロブレム
- ブレーンストーミング
- マンダラート
- マインドマップ
- 6W3H
それぞれ詳しく解説します。
あわせて読みたい
社内新規事業の立ち上げにおける5つのプロセス|立ち上げを成功させるポイ…
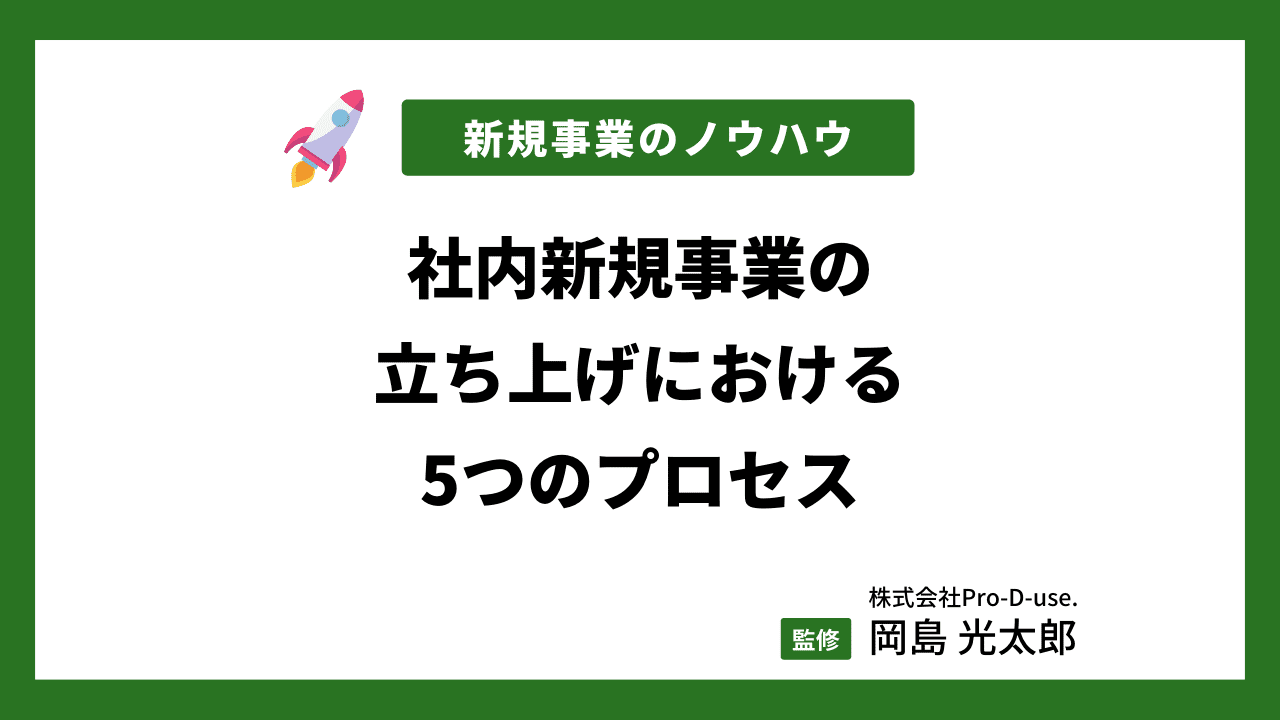
社内の新規事業立ち上げを検討している経営者には、このような悩みがついて回ることでしょう。 社内新規事業を立ち上げるからには、しっかりとした計画を立てて事業を軌道に乗せたいものです。しかし、せっかく新規事業の立ち上げをおこなったにもかかわらず…
分析手法1. アンチプロブレム
アンチプロブレムとは、考えに行き詰ったときに、課題と逆の解決策を考えるアイデア発想法です。逆の考え方をすることにより、アイデアの幅が広がったり、解決方法が見えてきたりします。
活用する際には、課題を解決するためのアイデアではなく、「課題を解決しないためにはどうするか」や「質の悪いプロダクトはどう製作するか」などを考えるとよいでしょう。
正攻法では気づけなかった新しい発想や、斬新なアイデアを出すためには、アンチプロブレムが役に立ちます。
分析手法2. ブレーンストーミング
ブレストとも呼ばれるアイデア創出の方法で、会議形式でアイデアを出し合ったり、紙に書いて張り出したりして発想をブラッシュアップさせます。他の人のアイデアに刺激を受けることで新しいアイデアが生まれやすく、豊かな発想が可能です。
活用する際には、質にこだわらず自由に発言することと、最終的にアイデアを一つにまとめてください。他の人の意見を否定する行為は、その後にアイデアを出しづらくしてしまうため、やらないように気を付けましょう。
ブレーンストーミングは、アイデアが固まっていない初期の頃に行うと、効果的に進められます。
分析手法3. マンダラート
曼荼羅とアートを組み合わせた方法が、マンダラートです。マス目にアイデアを書き込んで整理したり、考えを深めたりできます。
やり方はまず、3×3で区切ったマス目の中心にメインテーマを書き入れ、残る8マスに関連語句を記入します。その後、3×3で区切ったマス目をさらに8つ用意し、それぞれの中心に先ほど書き込んだ8つの語句を記入してください。
再び、残ったマスに関連語句を記入し、さらにそれを繰り返していくと、アイデアを出すために必要な思考をさらに深めることが可能です。
あわせて読みたい
新規事業に必須のマンダラートとは?その効果や作成方法を解説
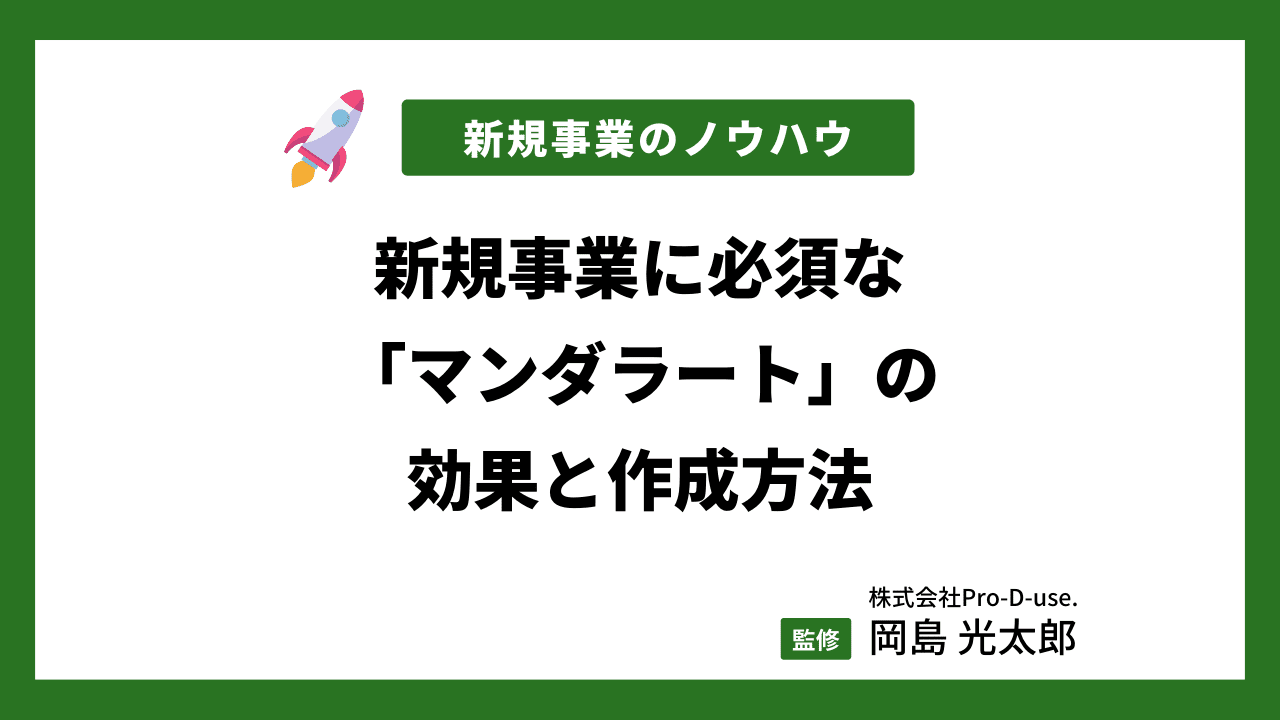
マンダラートは、目標達成やアイデア出し、思考整理などあらゆるシーンで活用できる、思考支援のフレームワークです。特に新規事業では強制的にアイデアを出したい際に活用するとよいでしょう。 この記事では、マンダラートとは何か、新規事業で使う効果や、…
分析手法4. マインドマップ
マインドマップとは、自由な思考・アイデア、情報の流れを、中心にあるメインテーマから放射状に分岐させる形で広げていき、新たな発想を得る方法です。
プロセスを見える化できるので、ブレインストーミングを行う際や、インパクトのあるプレゼン資料作成などの際にも役立ちます。
紙と鉛筆があれば手軽に行えるのがマインドマップの魅力ですが、写真・色どりなどを加えることで、より視覚的に理解を深めることができるため、そちらもおすすめです。
マインドマップ作成ソフト・ツールもあるので、ぜひ使ってみてください。
分析手法5. 6W3H
6W3Hとは、文章を書く際に留意すると良い5W1Hに、さらにビジネスパーソンならではの語句を加えた言葉で、以下の9つのことです。
- なぜ:Why
- 何を:What
- 誰が:Who
- 誰と・誰に:with Whom
- いつ:When
- どこで:Where
- どのように:How
- いくら:How much
- どれだけ:How many
「誰に」「いくら」「どれだけ」を定義できるため、マーケティングやプロモーション戦略がより具体的になり、アイデア出しの役に立ちます。
また、仕事を進める上でも6W3Hは基本になるものなので、しっかり設定しておくと「期日に間に合わない」といったケースを防ぐことも可能です。
あわせて読みたい
【6W3Hとは?】フレームワークの使い方や新規事業&ビジネスへの活用法
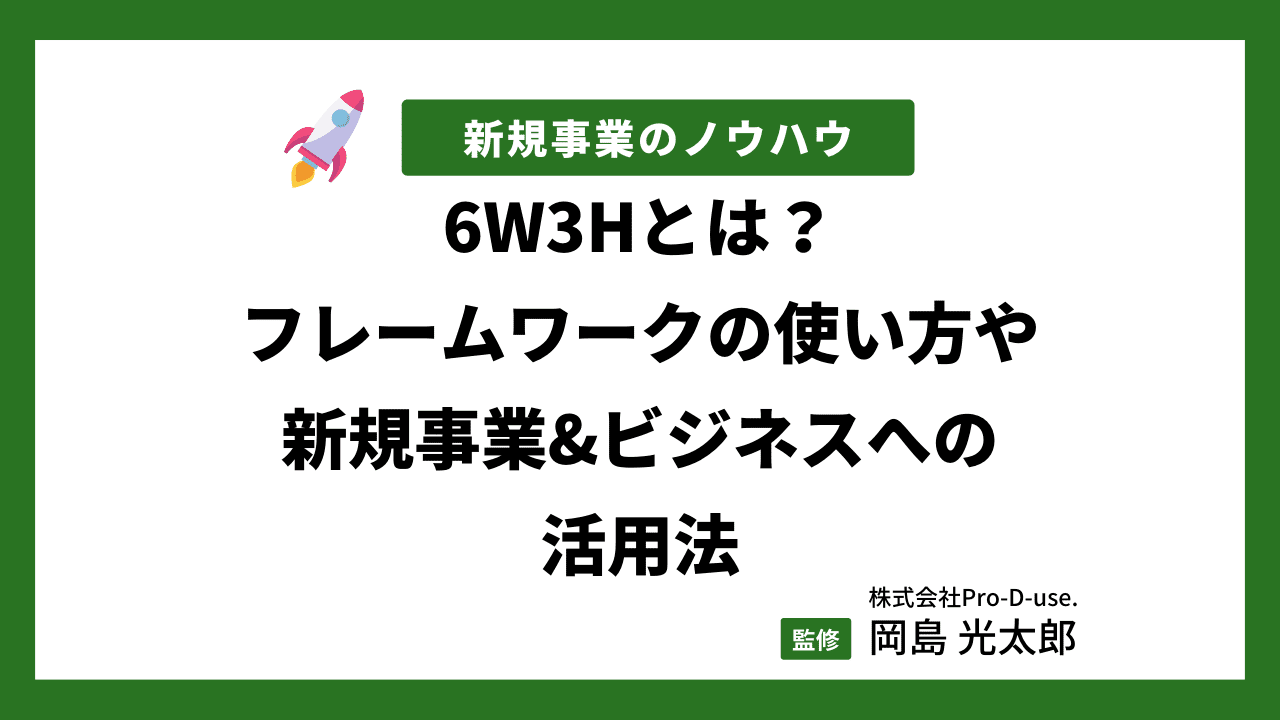
こんなお悩みや疑問を持っている、経営者やビジネスマンは多いのではないでしょうか? 実は、6W3Hはビジネスにおいて強力フレームワークであるにも関わらず、使い方を間違っている率もNo,1なのはあまり知られていません。なぜなら、5W1Hがあまり…
プロセス2. 新製品のコンセプトを打ち出す

製品のコンセプトとは、アイデアを発展させ、消費者が商品を使用する際に、頭に浮かぶ言葉を表現したものです。
そして、製品のコンセプトは、製品開発の核となるため、すべての部門で認識を統一させる必要があります。
また新製品のコンセプトに関しては以下の2つのポイントがあります。
- 顧客が求めているニーズについて的確に把握する
- 他社製品との違いを明確にする
顧客が求めているニーズについて的確に把握する
新商品を開発するためには何よりも「顧客のニーズ」について的確に把握しておく必要があります。顧客が求めていない商品やサービスをいくら提供しても、なかなか収益には結びついていかないものです。
そもそも顧客ニーズとは顧客が抱いている欲求や要求のことを指します。顧客の好みが多様化していると、その全容を把握するのは難しいプロセスでもあります。アンケートやヒアリング、商品説明会などから1つ1つ顧客のニーズを拾い上げていく必要があるでしょう。
膨大な情報の中から、自社が1番勝負をするべき点をきちんと整理していくことが肝心です。「これまでの商品とどう違うのか?」といった部分をハッキリとさせるためには、新商品のコンセプトが鍵を握っています。
「わが社だからこそ、この商品を出す!」と一言で理由をまとめられるくらいまで軸をしっかりと定めるプロセスが大切になるのです。
あわせて読みたい
新規事業の成功率がグッと上がる!「ニーズ調査」7つの手法をプロが解説
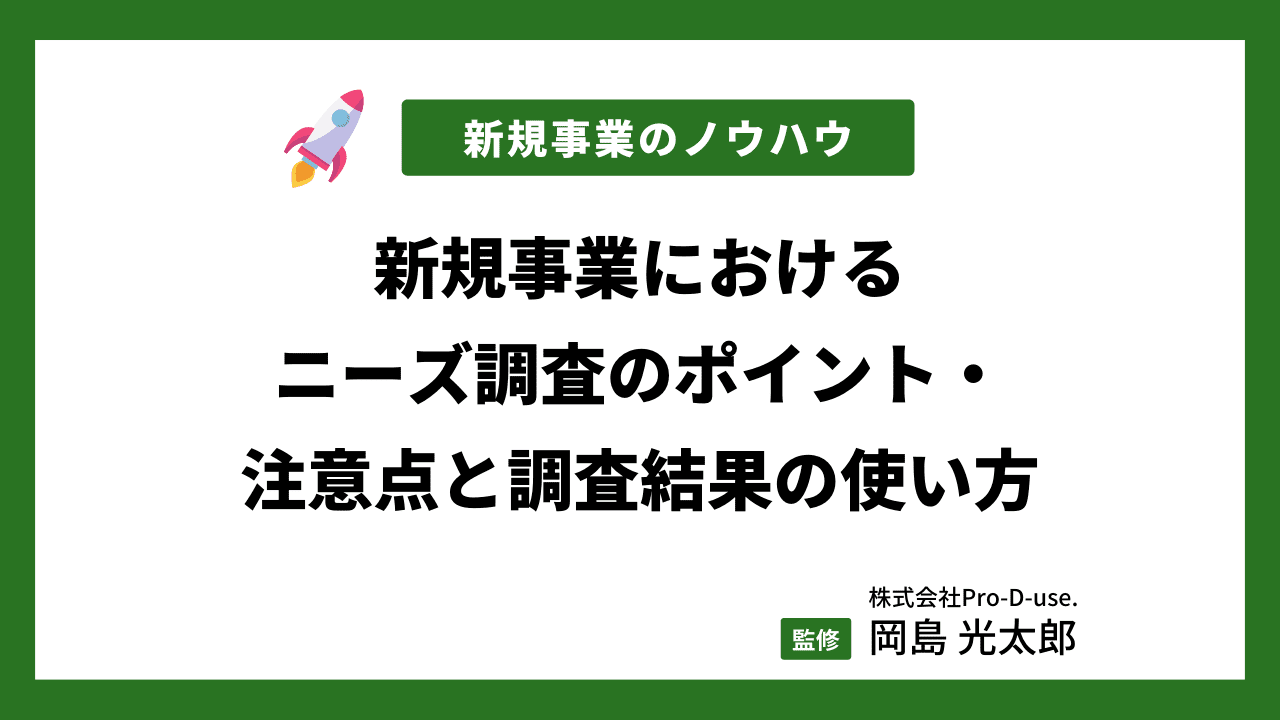
これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか? 「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」…
他社製品との違いを明確にする
顧客のニーズを把握し、その中から自社の強みを見つけていくことが大切ですが、もう1つ重要なことがあります。
それは「他社製品とどこが違うのか?」といった点です。
これまで世の中に出回っていない商品を出すのであれば自社が主導権を握ることも可能でしょう。しかしすでに製品として流通しているものに参入していくには、きちんとした分析が必要となります。
自社の開発陣から見れば「ここが違う!」と強みが答えられたとしても、それが顧客や競合他社にもハッキリと伝わらなくてはなりません。
自社以外の視点から見て、「これまでの商品と大差がない」と思われてしまえば、一気に価格競争の波が押し寄せてきます。また技術的な部分でも目新しさがなければ、すぐに他社から真似をされてしまうリスクもあるでしょう。
新商品は作って終わりではなく、継続的に収益を上げていかなければならないため、開発のプロセスの中には販売戦略や広告戦略もあわせて考えておく必要があります。
プロセス3. 事業性の検討
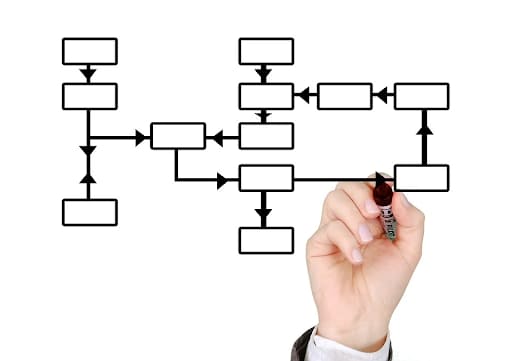
新製品コンセプトを打ち出した後、会社としてその事業を実行していくのか決断する段階です。主に以下のような方法で分析・検討していくとよいでしょう。
- 市場調査
- 事業経済性分析
市場調査
市場調査はマーケティングにおいて欠かせない調査であり、マーケットリサーチとも呼ばれます。
新商品開発にあたり、売れるためには、顧客のニーズを把握して製品を作る必要があります。事前に知っておくべき情報を収集・分析し、製品開発に役立てましょう。
以下のようにさまざまな角度から事業性を検討することになります。
- 市場の将来に見込みはあるのか。
- 自社の強みを活かすにはどうすべきか。
- 販売、流通経路は確保できそうか。
- 競合商品の特徴やシェアはどうなっているか。
事業経済性分析
市場調査からさまざまな状況下で予想される売上高、原価、利益を推定しデータをもとに事業として成り立つのか判断します。
もし想定した戦略目標に届かなければ、製品コンセプトの段階からマーケティング戦略を練り直しましょう。
プロセス4. 戦略作成・新製品開発

新製品のコンセプトが決まり事業性も認められたらマーケティング戦略の骨組みを作っていきましょう。
具体的には以下の3つの手順を踏んでいきます。
- 試作品開発
- テストマーケティング
- 新製品の製品化
手順1. 試作品開発
事業経済性分析で製品化できそうなものを判断してまずは試作品を開発していきます。
完成した試作品は、実用性や顧客の反応を測るために市場調査を行い、問題がなければ製品化されます。
また、製品化される際には、他社との競合を避けるために、開発に関する特許申請を行う必要があります。
手順2. テストマーケティング
地域や対象顧客を限定し小さくテストすることで反応を予測する手法です。
小さくテストすることで、多額の損失を回避できるほか、需要不足による損失回避の効果が期待できます。
しかし、テストマーケティングは、競合に情報を公開することになるため、その後の判断や開発はスピード感を持って進めていく必要があります。
手順3. 新製品の製品化
いよいよ新製品の製品化の段階です。デザインやパッケージを決定して、生産体制を組みます。
しかし、どれだけ長期間製品開発に費やした製品でも、継続的にマーケティングを続けていかなければ後からどんどん競合が参入し、あっという間に飽和した市場に埋もれてしまいます。
引き続き市場の調査、分析して次の製品開発に役立てていきましょう。
プロセス5. 市場参入

製品化し、市場に参入した後はマーケティング戦略についてPDCAを回していきましょう。
また、
- 売上状況
- 認知度
- 市場のニーズ
などの判断基準をもとに、KPI(Key Performance Indicator)を設定しましょう。
これまでの仮説をブラッシュアップさせながら、いかに目標を達成していくかが重要です。
「プロセスは分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use(プロディーユース)」に相談してみませんか?Pro-D-use(プロディーユース)は伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)の新規事業支援サービスの詳細はコチラ>>
新製品開発を成功させるのに大切な4つのこと
以下では、新製品開発を成功させるのに大切なことを4つ紹介します。
- 開発までに必要な期間や資金について把握する
- 商品価格を自社・顧客の双方が納得できるラインに置く
- 新商品を効果的に宣伝する
- 新しい商品を世の中に出す意義をしっかりと定める
1. 開発までに必要な期間や資金について把握する
顧客にとってどんなに価値のある商品であっても、自社の最終的な収益につながらなければ商品開発そのものの目的を見失ってしまいます。
商品だけ先に作って、収益化は後から考えるといった姿勢ではなく、やはり事前に商品開発に必要な資金や期間を定めておく必要があります。
ビジネスである以上、ライバル企業との競争は避けられないところがあるため開発スケジュールについては、きちんと目途を立てておきましょう。
そのうえで「どこまで資金を投入するべきか」を判断することが肝心です。
新商品の販売が開始してから、どれくらいの期間で開発にあてた資金を回収するか見定めておきましょう。
これらのことを的確に決めておかないと、そもそも「販売価格」をどうするかといった肝心な部分が決められないからです。
他社の販売価格を参考にするのはいいものの、「他社がこれくらいの価格だから、ウチはこれくらい」といった何となくの感覚で値決めをしてしまってはいけません。
商品開発にかかった期間や資金、収益化の目途などは販売価格に影響することを忘れないようにしましょう。
2. 商品価格を自社・顧客の双方が納得できるラインに置く
顧客にとっても、自社にとっても商品価格がいくらであるかは関心事の1つです。
自社の利益を無視した値決めをしてしまっては、経営に重大な影響を及ぼすことにもなりかねません。
その一方で、企業側の都合ばかりを優先させて値段を決めてしまっては、顧客を離れさせてしまう要因にもなるでしょう。
自社・顧客の双方が納得できる価格のラインがどこにあるのかを見極めることが重要です。
また、1度決めた販売価格をずっと固定にしてしまうよりも、市場環境にあわせて適切に見直していく姿勢も必要となるでしょう。
商品原価をもとに価格設定を行っていく方法として「コストプラス価格設定方式」があります。
この方式は企業側の視点で決めていくものですが、商品のニーズに対して供給数が少ない場合に有効です。
原価に販売管理費と利益を上乗せしたものが、商品の販売価格となります。一方で顧客側に立った価格の決め方もあります。
「知覚価値価格設定方式」は顧客がいくらなら買いたいと思うかという部分に視点を置いた決め方です。
3. 新商品を効果的に宣伝する
新商品の魅力を顧客に最大限に伝えていくためには広告や宣伝が欠かせません。
広告はテレビCMや新聞、ラジオや雑誌などがあげられます。従来の広告戦略に加えて、インターネットを使った宣伝にも力を入れてみましょう。
またすでにあるメディアだけではなく、「オウンドメディア」と呼ばれる自社所有のコンテンツを活用することも大切です。商品を開発した企業自らが情報を発信することによって、自社のファンを獲得し、最終的には商品の購入にまでつなげていきます。
商品の使い方動画を作成したり、ポイントがすぐにわかる説明書などをPDF化したりといったことがあげられるでしょう。開発スタッフが商品の魅力を伝えるためにビジネスブログを書くこともこの中に含まれます。
どれか1つの媒体に特化して宣伝をするというよりも、商品にあわせて媒体を組み合わせていく方法が有効です。広告や宣伝にかけられる予算枠や人員を踏まえたうえで販売戦略を立ててみましょう。
4. 新しい商品を世の中に出す意義をしっかりと定める
新商品を世に送り出すことは企業にとって、事業主体としての存在感を示す絶好の機会です。
しかし顧客へのアプローチを誤ってしまうと商品が売れないだけでなく、自社のブランドイメージを低下させてしまう要因にもなってしまいます。
「どうしてこの商品が必要なのか」といった核となるテーマを定め、まずは社内で共有することが大切です。
顧客や取引先からの意見も踏まえて、商品を開発する段階から多角的な視点で見ていく必要があります。
顧客が待ち望んでいた商品を売り出せば、収益が得られるだけではなく企業価値を高めることにもつながっていきます。
また新商品の開発や販売を通じて、社内の意識を高めることにもつながるでしょう。
予算や開発期間を踏まえたうえで、魅力ある商品づくりを行っていきましょう。
「プロセスは分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use(プロディーユース)」に相談してみませんか?Pro-D-use(プロディーユース)は伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)の新規事業支援サービスの詳細はコチラ>>
顧客の視点に立って新商品開発を成功させよう!

ここまで、新商品の開発プロセスのポイントを解説してきました。
新製品を開発する際には、事前に開発に必要な資金や期間を定めたうえで、常に顧客の視点で考えることが重要です。
今回ご紹介した成功例を参考にしつつ、しっかりとポイントを押さえて、新商品を成功に導きましょう!
なかなか進まない「新製品開発」でお困りではありませんか? Pro-D-use(プロディーユース)なら、新製品開発がドンドン進みます!
⇒(株)Pro-D-use(プロディーユース)の無料新規事業相談を受けてみる >>
新製品開発や新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新製品開発にはプロの経験が必要です!
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新製品開発の無料相談】をしてみませんか?詳しくは下記の新製品・新規事業のコンサルサービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新製品・新規事業コンサルサービスはコチラ >>>
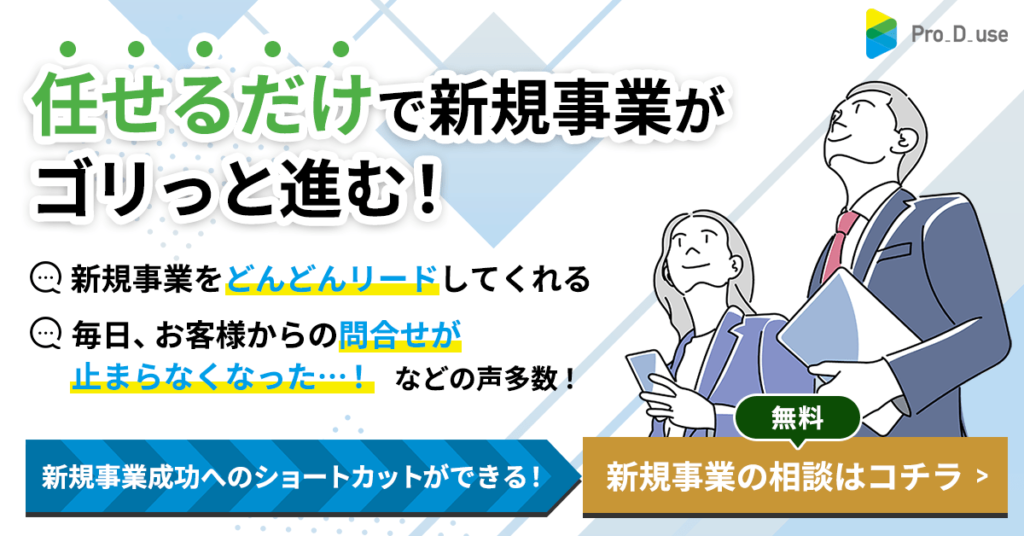
<参考URL>
https://www.happystream.net/product_consulting/develop/
https://web60.co.jp/owned_media.html