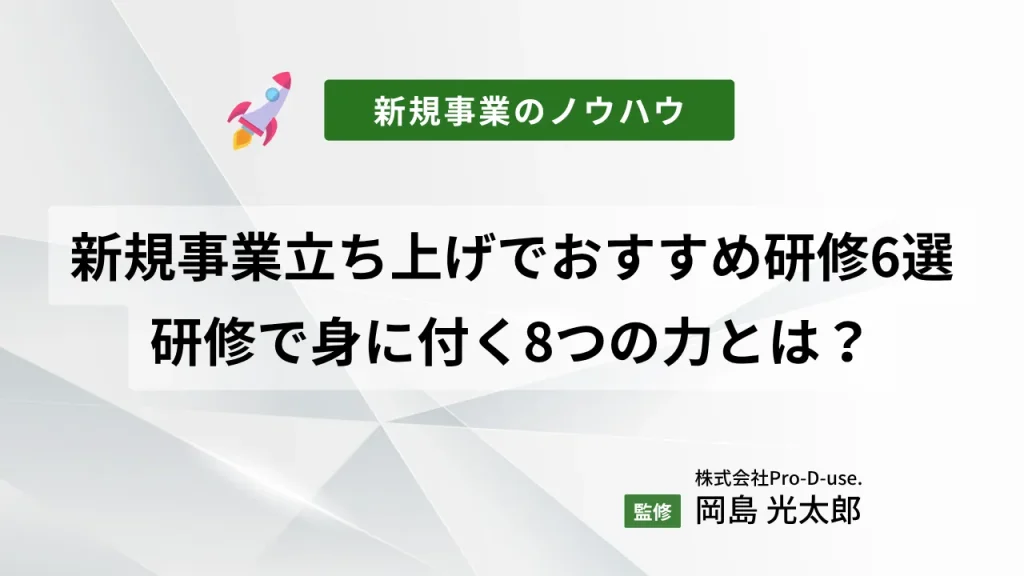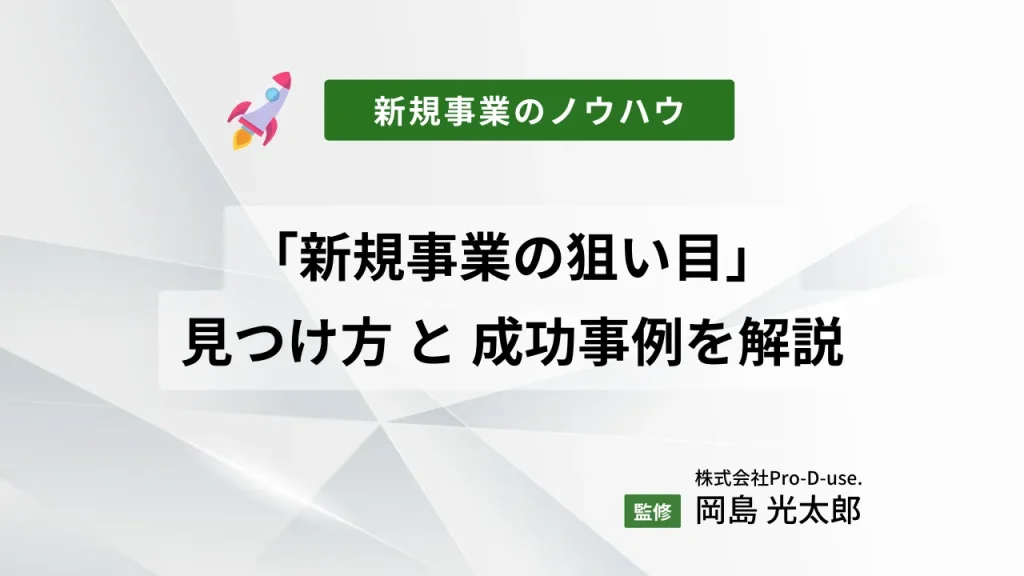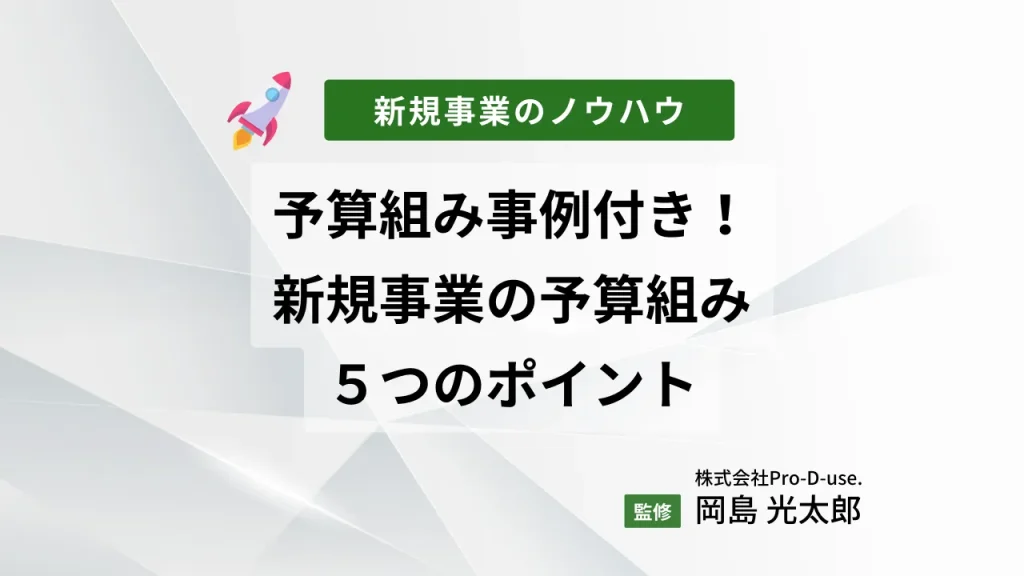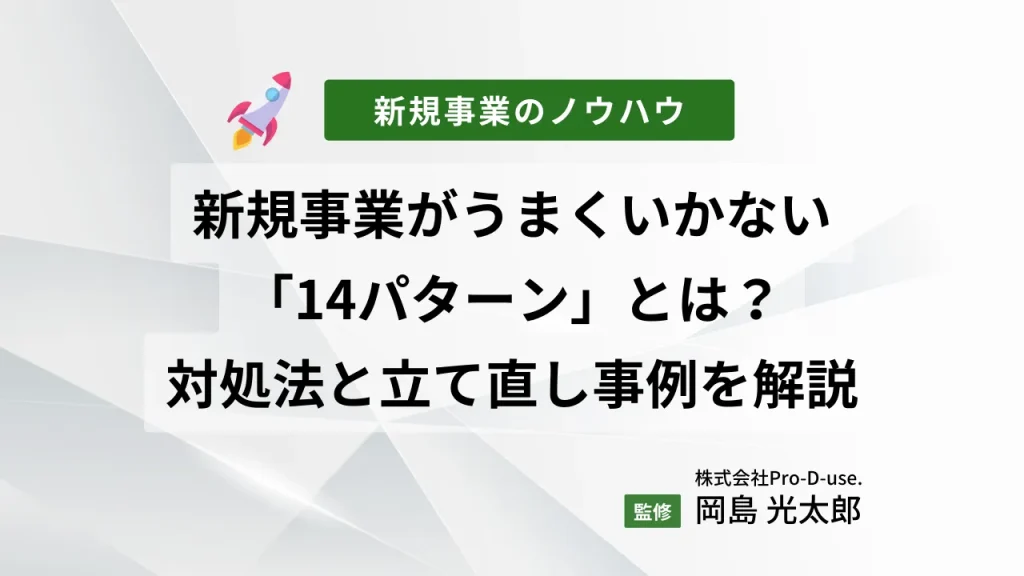化粧品業界の市場規模とその動向とは?
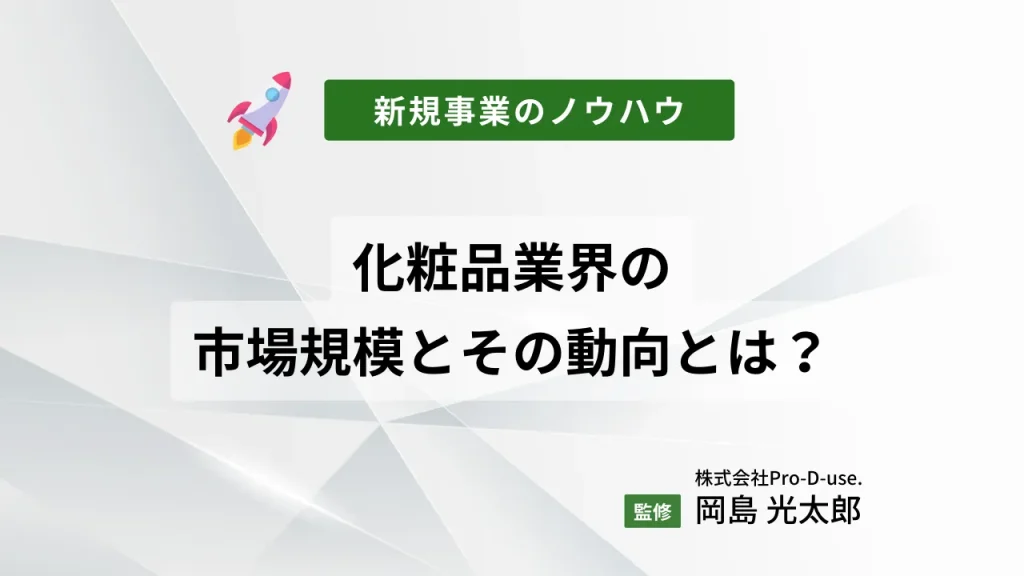
-
- 新規事業
- 2019年2月5日

化粧品業界の市場規模や今後の展開について詳しく知りたい。

化粧品業界に参入したいと考えている。化粧品業界には、新たに参入する余地はあるのか?
化粧品業界に参入を考えている方にとって、このような疑問を持っていう方は多いのではないでしょうか。
化粧品業界は、化粧品業界は国内のみならず世界中に進出をしています。
また、インターネット通販による販売や異業種からの参入も活発なのが特徴です。
そこで、本記事では、化粧品業界について3つのポイントを詳しく解説していきます。
- 化粧品業界の市場規模の推移
- 化粧品業界に関連する流通構造
- 化粧品業界の将来性
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 化粧品業界の現在の全体像から将来までを把握できるため、化粧品業界のリサーチにかける時間が短縮されます。
- 化粧品業界に起きている動きが把握でき、今後のビジネスチャンスの手助けになります。
それでは早速、読み進めていきましょう。
化粧品業界の市場規模の推移

インターネットの普及による消費者の購入スタイツの変化や少子高齢化による国内人口減少の影響で、化粧品業界には業界再編・業務提携の流れが生まれています。
有名な化粧品ブランドを自社に取り込むM&Aや研究開発施設・製造工場の買収を目的とするものまでさまざまです。
2010年以降、化粧品とはまったく関わりのなかったメーカーが相次いで参入しました。本業で培った技術を武器にお互いにしのぎを削っている状態です。
既存の化粧品メーカーと異業種の企業が業務提携をして、お互いに販路を拡大する流れも出てきています。
市場規模の推移については2013年の経済産業省の「工業統計調査」によると、化粧品業界の市場規模は2兆97億円でした。
2015年には2兆1,516億円へと上昇しています。過去のデータでは2008~2012年までは業績は停滞が続いていましたが、2013年を契機に大きな成長を遂げています。
2012年まで横ばいが続いたのは景気の悪化の影響や化粧品の高機能・低価格化が求められたことに伴い企業の業績が低下を続けたためです。
ところが2013年以降は観光客による化粧品需要が高まりました。
訪日外国人によるインバウンド需要は質が良く、価格も安い化粧品に向けられたのです。
さらに2014年10月には化粧品が免税対象として認められました。
これが外国人、特に中国人の購買力を大きく押し上げたのです。
いわゆる「爆買い」の影響もあり国内メーカーの業績は上昇しました。
しかし、インバウンド需要も落ち着きつつあり、長期的な不安要因である少子高齢化などが表面化し、国内市場は先行きが不透明になっています。
さらにSNSなどの普及に伴い、化粧品に対する消費者の目はこれまで以上に厳しくなっていくでしょう。
そこで、大手メーカーなどは海外進出に活路を見出しつつあります。品目別市場動向分析について見ていくと低価格帯のものが5,913億円となっています。
中価格帯では9,648億円、高価格帯では7,116億円でした。
低価格帯の商品では洗顔料・シートパック、ポイントメイクといった分野がインバウンド向けに好調です。
中・高価格帯についても百貨店やドラッグストアを中心として、インバウンド向けの販売が好調で全体の業界全体の業績を押し上げています。
化粧品関連業界の流通構造

化粧品業界の流通構造は大きく分けて4つあります。
1つはメーカーから直接小売り業者に商品を販売するシステムです。
「制度品流通」がこれに当たり、制度品とは店頭での美容部員によるカウンセリング販売を必要とする化粧品のことを指します。
高価格帯のものを販売する時にとられる方法であり、卸売り業者を挟まずにメーカーと百貨店などの小売り業者が直接契約をします。
メーカーから直接派遣された美容部員が消費者に対して販売を行う方式です。
2つ目は卸売り業者を介した流通システムだといえます。
低価格帯の商品の場合は大半がこれに当てはまり、メーカーは卸売り業者を通じて百貨店やドラッグストア・コンビニエンスストアなどに流通させます。
小売り業者は全国に存在するため、卸売り業者を挟むことであらゆる商品を消費者のもとに届けることができるのです。
3つ目は訪問販売であり、メーカーの販売員が個人宅や職場を訪れ販売を行う方法です。
1996年をピークとして売り上げは減少しているものの、数ある訪問販売の中では安定して1位を保っており、化粧品の販売にあってはなくてはならない流通システムとなっています。
そして4つ目は通信販売で、消費者がメーカーに対して電話やインターネットを通じて直接購入する方法です。
メーカーみずからがサイトを立ち上げたり、カタログを配布したりする方法や通販専門会社が各メーカーの商品を販売する方法があります。
産業別の市場動向

メーカーにとっては訪日外国人の増加は業績を押し上げる要因となっています。
アジア諸国から日本を訪れる外国人が増加したのに加えて、2014年10月には化粧品が免税対象消費に加わったことで購買意欲が高まりました。
日本の化粧品は品質が高く外国人客に好評だったことが業績に良い影響を与えたといえます。
メーカーの商品を販売する商社は基本的には安定した経営を行っています。
ただ、少子高齢化に伴って人口が減少しているため、以前よりも商社同士の競争が活発になってきている傾向です。
特約店に関しては地方の商業地域で来店客が減少している店舗は経営が苦しくなっています。
デパートやドラッグストアに客を奪われてしまって、思うように商品が売れない店舗も目立っているのです。
集客やスタッフの教育にどれくらい力を入れられるかが鍵となっているといえるでしょう。
その一方で、インターネットを通じた販売は好調だといえます。
経済産業省が2016年に取りまとめた「電子商取引に関する市場調査」によれば、2016年の化粧品等の市場規模は5,268億円となっており前年比で12.1%と高い伸び率になっています。
これはSNS広告をうまく活用した企業が業績を上げているのが要因だと見られています。
消費者が直接メーカーのウェブサイトから商品を購入する流れも定着しつつあるでしょう。
ただ、インターネットでは商品の特徴や品質・使い勝手について消費者がSNS等を通じて自由に情報交換ができるため、消費者の動きを意識したマーケティングが必要だといえます。
注目される市場動向

円安の影響によって訪日外国人が多くなった時期には、メーカー各社の業績を押し上げました。
ただ、周辺諸国も化粧品の関税を高くするなどして対抗措置をとってきているため、好調な業績にも一服感が出てきています。
しかし、日本の化粧品は品質が良く評価をされており、インターネットを通じての購入も増加してきているので引き続きインバウンド向けの販路は拡大していくでしょう。
その一方で、化粧品業界には異業種からの参入の動きも活発になっています。
フィルム製造会社や食品メーカーなどがこれまで培ってきた技術を活かして、自社独自の化粧品の開発に乗り出してきているのです。
既存の発想にとらわれない商品開発を行うことによって、市場シェアの獲得に動いています。
食品メーカーであれば自社が強みとする健康食品と美容を主眼とする化粧品の2つを販売することで相乗効果を狙い、顧客のニーズに応えようとしているのです。
また化粧品メーカーの中には自社のブランド力を活かして、海外進出を図る企業も出てきています。
単に日本で売れている商品を販売するだけではなく、現地の環境に合った商品開発を行って顧客の獲得に努める動きがあるのです。
メーカーの中には海外での売り上げが全体の約半分を占めている企業もあり、将来を見据えて事業展開を行っています。
また海外でヒットした商品を日本に逆輸入するといった動きも見られ、化粧品業界を取り巻く環境はますます広がっているのです。
市場規模から読む化粧品業界のこれから

国内市場の縮小は長期的に見れば避けられないものでしょう。少子化による人口減少から逃れることはできません。
ただし、中期的な視野で見れば、新しい市場の開拓が進む可能性はあります。男性向けのスキンケア用品は今後も需要が増えていく可能性があります。
また、近年は美容に関心を持つ女性も、年齢層の幅が広がっていきますから、急に市場が小さくなり、立ち行かなくなるということはないでしょう。
ただ、これまでのビジネスモデルが通用しなくなっている点も無視できません。
高額な宣伝広告費を投じることで、高価格商品への需要を喚起する方法は、SNSなどを通じた「口コミ」の影響力に押されつつあります。
そうした現状から将来的な展望を見つめ、海外という新しい市場へと挑戦する企業は少なくありません。
低価格と高品質を兼ね備えた製品が持つ競争力は決して低くはないでしょう。
ただし、そこには海外企業との競争という厳しい一面もあります。
特にこれまで国際的にブランド力を高めてきた企業に負けない認知度を手に入れるには、まだ時間を必要とします。
消費者のニーズを細かく分析し、商品開発に活かしていく姿勢が求められています。
もし、化粧品業界への参入含めて、非常に煩雑で難しい新規事業の企画・立ち上げ、推進や収益化でお困りの際は、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談(無料)ください。
「株式会社Pro-d-use」のサービスを活用すると、新規事業のプロがあなたに代わって新規事業の調査から企画・立ち上げ・推進、収益化までをあなたの会社の現場に入って一緒に進めてくれるので、あなたは「新規事業を進める苦悩や業務から解放」されますよ。
>>>3回までは無料でご相談をお受付いたします<<<
<参考>
http://www.ma-cp.com/gyou_c/15.html
http://bhn.jp/special/32668
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/
http://gyokai-search.com/3-kesyo.htm
http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/161028_16087.pdf
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/2010-07-08-01.html
https://www.cao.go.jp/consumer/history/03/kabusoshiki/tokusho/doc/20150305_shiryou3.pdf
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)