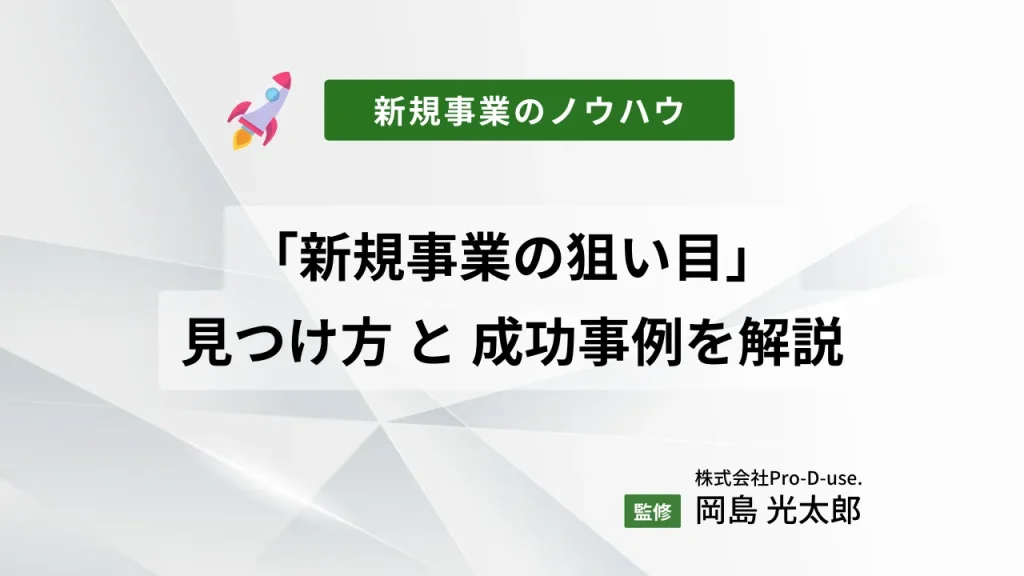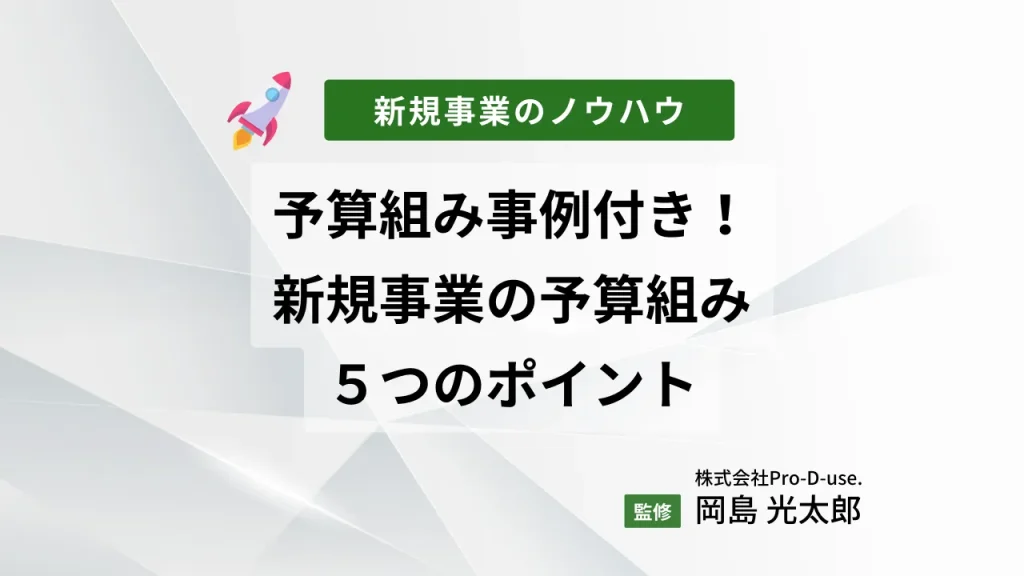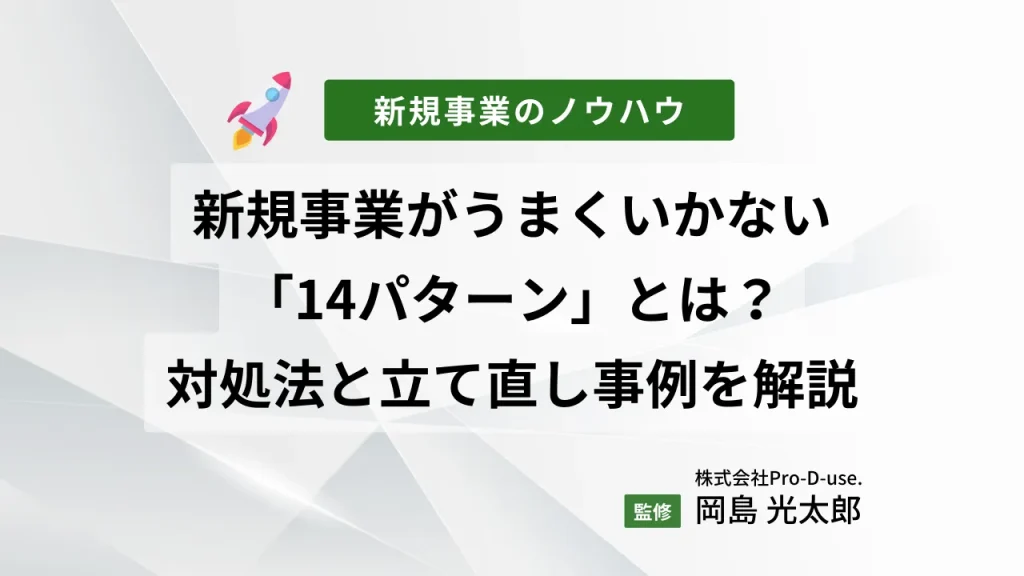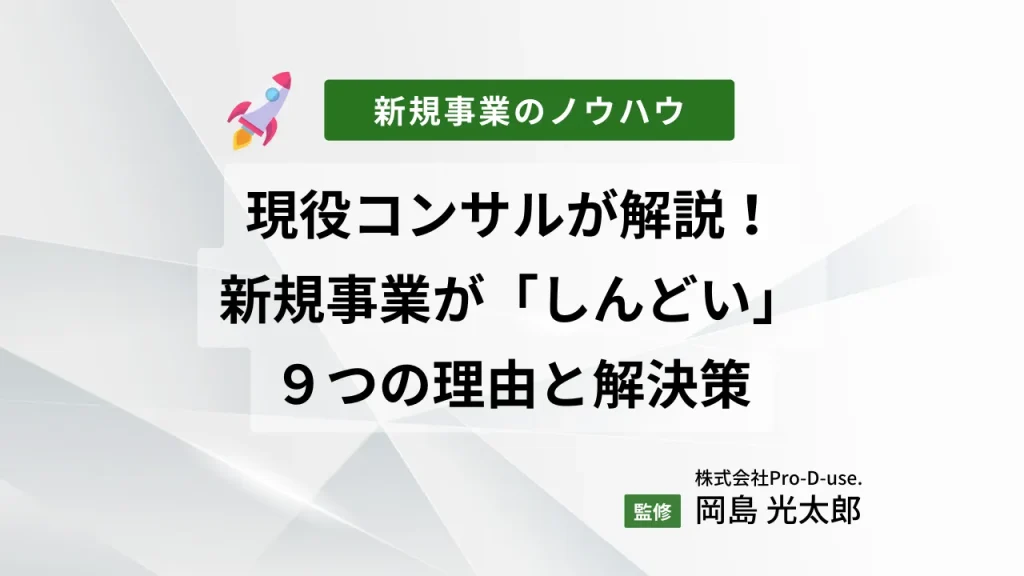旅行業界の市場規模とその動向とは?
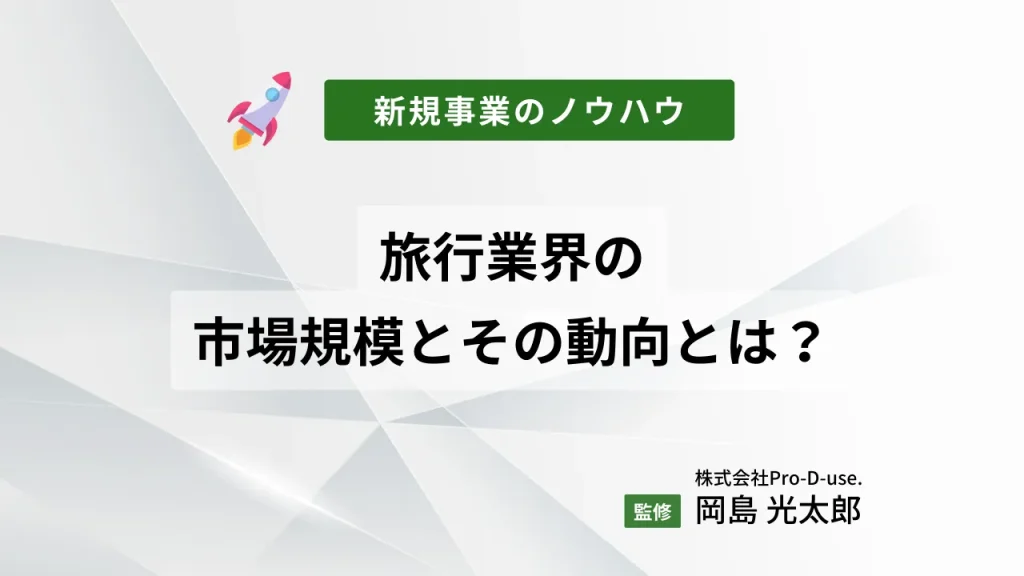
-
- 新規事業
- 2019年3月2日

旅行業界の市場規模や今後の展開を知りたい。

旅行業界に参入しようと考えている。旅行業界には新たに参入する余地はあるのか?
旅行業界に参入を考えている方にとって、このような疑問を持っていう方は多いのではないでしょうか。
旅行業界は、下記の3つの要因によってに近年高く注目されています。
- 格安航空機の登場
- 大手航空会社の燃油サーチャージの撤廃の動き
- インバウンドの増加
本記事では、以下の3つポイントについて詳しく解説していきます。
- 旅行業界の市場規模の推移
- 旅行業界に関連する流通構造
- 旅行業界の将来性
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 旅行業界の現在の全体像から将来までを把握できるため、旅行業界をリサーチする時間が短縮されます。
- 旅行業界に起きている動きが把握でき、今後のビジネスチャンスの手助けになります。
それでは早速、読み進めていきましょう。
旅行産業界の市場規模の推移

旅行業界ではインターネットの普及による顧客ニーズの多様化や原油価格の高騰などの影響から、業界再編・業務提携の流れが加速しています。
特に旅行代理店では顧客が航空会社から直接、航空券を購入する流れが増加しているため、航空会社から得られる利益が減少しています。
そのため、構造的な業績悪化の打開策として経営の体力強化のために合併や業務提携を推し進めているのです。
観光庁の2015年「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」によると旅行業界の市場規模は2015年において25兆5,000億円です。
品目別市場動向分析では2015年の旅行消費額の国内市場が22兆1,000億円となっています。
内訳としては宿泊旅行16兆2,000億円、日帰り旅行4兆6,000億円、海外旅行の国内消費分が1兆3,000億円です。
また訪日外国人市場が3.3兆円となっていることが分かります。
2008年には新型インフルエンザの世界的な流行が起こり世界同時不況の影響から2010年まで大幅な市場規模の縮小が起こりました。
2011年には東日本大震災の影響によって海外旅行・国内旅行ともに落ち込んでしまい倒産する企業が増加しました。
一時は人気の観光地にまったく人がいないといった現象も起きました。2014年以降は訪日外国人旅行客(インバウンド)の増加によって業界には活気が戻っています。
円安などの影響もあり、2016年には訪日外国人数は2,400万人を突破。日本から海外への海外旅行者数1,621万2,100人を超えて逆転しています。
また燃料価格が高騰した時に航空運賃とは別に乗客から徴収する燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)が、大手航空会社で2016年にゼロとなりました。
これによって、邦人の海外旅行の伸びが期待されています。
国土交通省の2015年「宿泊旅行統計調査」よると、国内宿泊者数は5億545万人泊(前年比6.7%増)となっており、初めて5億人泊を超えました。
北陸新幹線の開業や円安の影響による海外旅行を避け、国内旅行に変更する動きが増えたことが要因として考えられています。
都道府県別での内訳は、東京・北海道・大阪の順です。また団塊世代の一斉退職によって、旅行業界がレジャーの受け皿となるかが注目されています。
旅行関連業界の流通構造

旅行会社の構造はツアーなどの商品を企画し、販売をすることで収益を得ます。
国内旅行業務・海外旅行業務に分かれており、訪日外国人向けの業務も行います。
渡航手続きの代行業務・旅行相談業務・旅行関連商品や保険販売といった業務から、現地での添乗員業務や経理業務など、旅行会社が行う業務は多岐にわたります。
大手旅行会社と中小旅行会社の違いは、商品企画、仕入れ、手配、販促などの面での規模です。
旅行者のニーズをくみとり、いかに魅力的な旅行商品を出すかが鍵となっています。
旅行における運輸業は飛行機・鉄道・バスなどの交通機関を利用してもらうことによって収益を得ますが、現地までの交通手段を旅行商品のパッケージとして売り出しています。
これによって交通各社は安定的な乗客の確保ができる点がメリットです。
宿泊施設も旅行会社と連携し、旅行商品の中に宿泊を組み込むことによって自らの集客だけでなく、旅行会社を通じて宿泊客を確保できます。
テーマパークなどの娯楽施設は旅行の企画に盛り込んでもらうことで、団体客などの集客につながります。
大手の旅行会社ほど安定的な旅行者の確保ができるため、ホテルや旅館、交通各社やレジャー施設との価格交渉が行えます。
旅行業は旅行会社だけで完結するものではなく、関連する業界との連携が不可欠だといえるでしょう。
産業別の市場動向

2000年代に入ってからテロ事件や戦争、災害やインフルエンザの流行など旅行業界に影響を与える出来事が多くなっています。
またインターネット直販型による旅行商品の販売など、従来の窓口業務だけではない販売の方法も登場し、旅行業界を取り巻く環境は大きく変わってきているといえるでしょう。
円安や原油高、旅行運賃・宿泊料金の高騰などの影響はあっても、2010年代以降は訪日外国人の増加や団塊世代退職者によって業界は活気を取り戻しています。
また大手旅行会社とインターネット専業旅行会社との競争が激しくなっており、これが業界再編にもつながっています。
インターネットの普及は消費者のライフスタイルにも変化を与えているため、旅行会社だけではなく運輸・宿泊・レジャー施設などの経営にも影響を与えています。
自由度を求める旅行者はインターネットで宿泊施設や利用する旅行会社を選び、自ら旅行の企画を立てる流れも一般的となっています。
格安航空会社の出現によって、旅行者は安価に旅行を楽しむ環境が整い始めているといえるでしょう。
そのため、旅行会社は企画を立てる際にいかに商品の魅力を出していくかが課題となっています。
注目される市場動向
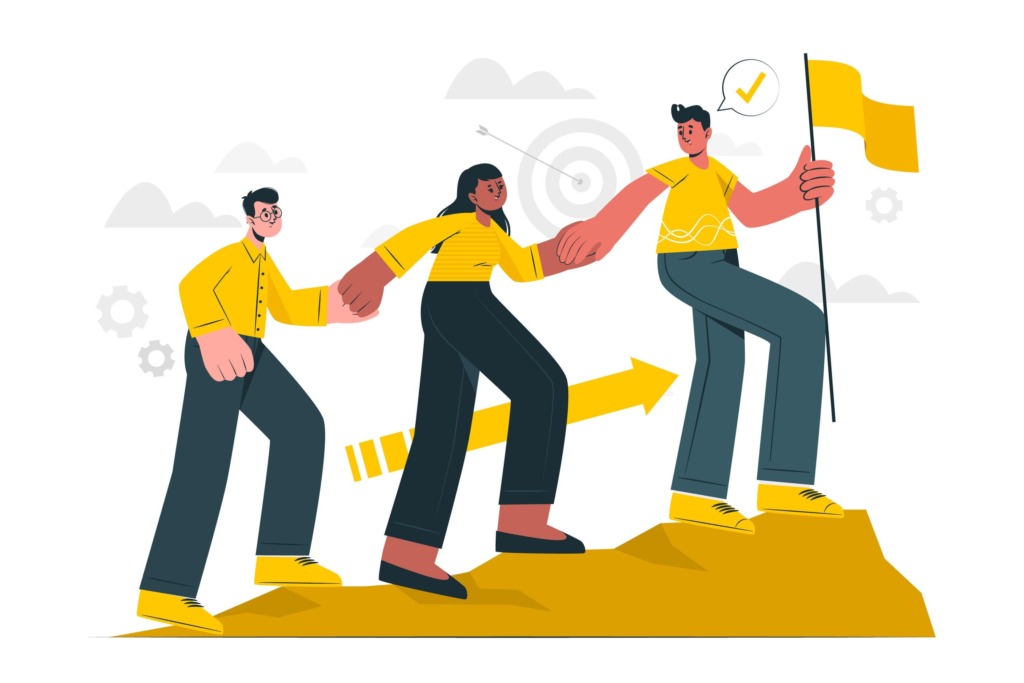
格安航空会社(LCC)の登場によって旅行代金も相対的に低くなっています。
以前は旅行会社が契約をしている航空会社をパッケージ商品に組み込むことができたものの、インターネットの普及によって消費者の間で価格に対する意識が高まっています。
大手航空会社は2016年から「燃油サーチャージ」をなくし、顧客が利用しやすい環境を整えつつあります。
また格安航空の影響によって、鉄道各社は大きな影響を受けたため独自の路線を切り開こうとしています。
寝台列車自体は全国的に姿を消しつつあるものの、団塊世代やシニア世代のニーズに応えるために高級寝台列車を開発し、新たな収益源としての道を模索しています。
円安などの影響もあり、2012年あたりから訪日外国人旅行者も増加しており、インバウンド向けのサービスに特化した旅行会社や宿泊施設なども出てきています。
邦人だけではなく、日本を訪れる外国人旅行者のニーズもくみとっていく努力が業界全体に求められているといえるでしょう。
さらに民泊新法と呼ばれる「住宅宿泊事業法」によって、旅行者に対して個人宅を貸し出す動きも活発化しています。
従来の旅館業法を適用してしまうとほとんどが違法営業となってしまうため、新たな枠組みで法律を定める流れとなっているのです。
そして、家族やカップル向けの国内レジャーとして大型のテーマパークの新設や既存施設の大規模な改修も進んでいます。
旅行業界の将来性

2013年ごろから旅行業界の業績が増加したのは、訪日外国人旅行者が増えたことが要因としてあります。
2014年には日本人海外旅行者数よりも訪日外国人旅行者数のほうが上回る逆転現象が起こりました。
円安などの影響もあり、今後もインバウンドの増加が見込まれるため、外国人旅行者向けのビジネスモデルを整えていくのが業界の課題となっています。
政府は観光立国を経済政策の柱として置いており、2020年までに訪日外国人旅行者数を4,000万人に引き上げることを目指しています。
それに伴って、政府はビザの発給条件を緩和したため東南アジアからの訪日外国人旅行客が多くなりました。
また国内では団塊世代の一斉退職の影響から、ゆとりのある世代の受け皿として業界の存在感が示せるかが課題となっています。
高級寝台列車の投入や世代に合わせた旅行企画の立案、家族でゆったりと過ごせるプランの販売など顧客のニーズに合わせた取り組みが行われているといえるでしょう。
インターネットの普及によって顧客のニーズも多様化しており、既存の旅行会社はインターネット専業会社との差別化も課題となっています。
旅行を通じて、どういった付加価値を顧客に提示していき、ビジネスモデルを立てていくかが問われているのです。
顧客から見て似たような商品なら安い物が好まれてしまい、価格競争にさらされて結果的にサービスの質が低下してしまう恐れもあります。
国内でも高速バスの事故などによって安全性が問題視される出来事が起き、ビジネス優先ではない姿勢も求められています。
業界として収益を上げつつも、時代にあわせて顧客の満足度をどう高めていくかが今後の鍵となっています。
もし、旅行業界への参入も含めて、非常に煩雑で難しい新規事業の企画・立ち上げ、推進や収益化でお困りの際は、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談(無料)ください。
「株式会社Pro-d-use」のサービスを活用すると、新規事業のプロがあなたに代わって新規事業の調査から企画・立ち上げ・推進、収益化までをあなたの会社の現場に入って一緒に進めてくれるので、あなたは「新規事業を進める苦悩や業務から解放」されますよ。
>>>3回までは無料でご相談をお受付いたします<<<
<参考URL>
http://www.ma-cp.com/gyou_c/96.html
https://www.mlit.go.jp/common/001091028.pdf
https://www.jata-net.or.jp/data/stats/2017/pdf/2017_sujryoko.pdf
https://www.jtbcorp.jp/jp/colors/detail/0095/
https://minpaku.yokozeki.net/about-minpaku/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/ukeire.html
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
2009年:(株)リクルートに新卒で入社。営業・企画の両面で責任者を務める。
※リクルートではMVPやマネジメント賞など、個人・マネージャー賞を多数受賞。
2013年:(株)データX(旧:フロムスクラッチ)の創業期に転職。営業や新卒・中途採用の責任者を務める。
2014年:アソビュー(株)に転職。その後、営業責任者、新規事業責任者を歴任。
2015年:(株)Pro-D-useを創業。取締役副社長(現任)に就任。
【得意領域】
新規事業の立上げ~収益化、成果を上げる営業の仕組み作り、BtoBのWebマーケティングを主軸とした売れる仕組み作り、DXまで見通したIT・SaaS・業務システムの導入や運用、融資を中心とした資金調達~財務のコンサルティングを得意としている。
【担当業種】
「システム受託開発」「Webサービス」「Tech系全般」「製造」「建築」「販売・サービス」「スクール業」など多岐。
【資格・認定】
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)