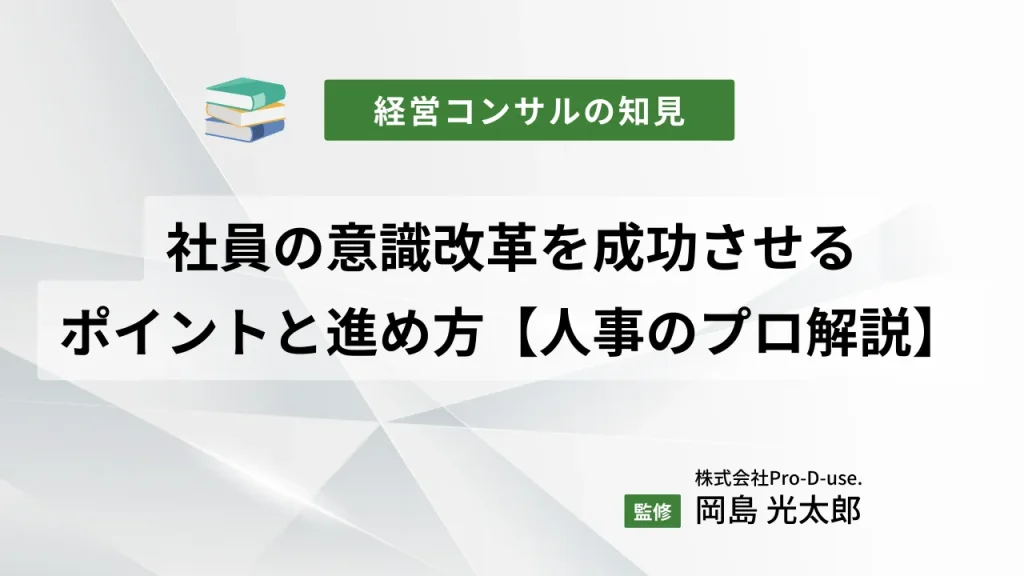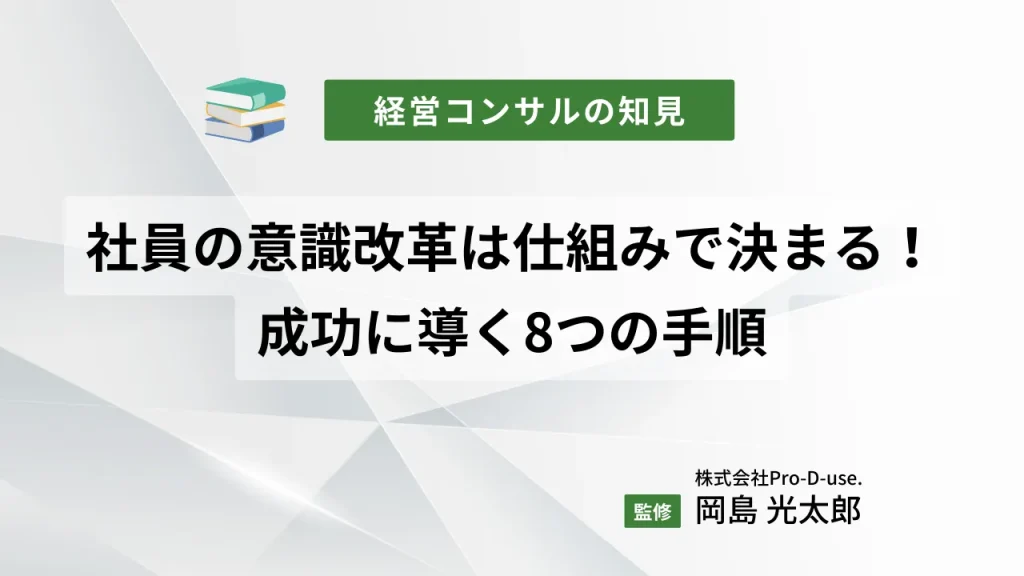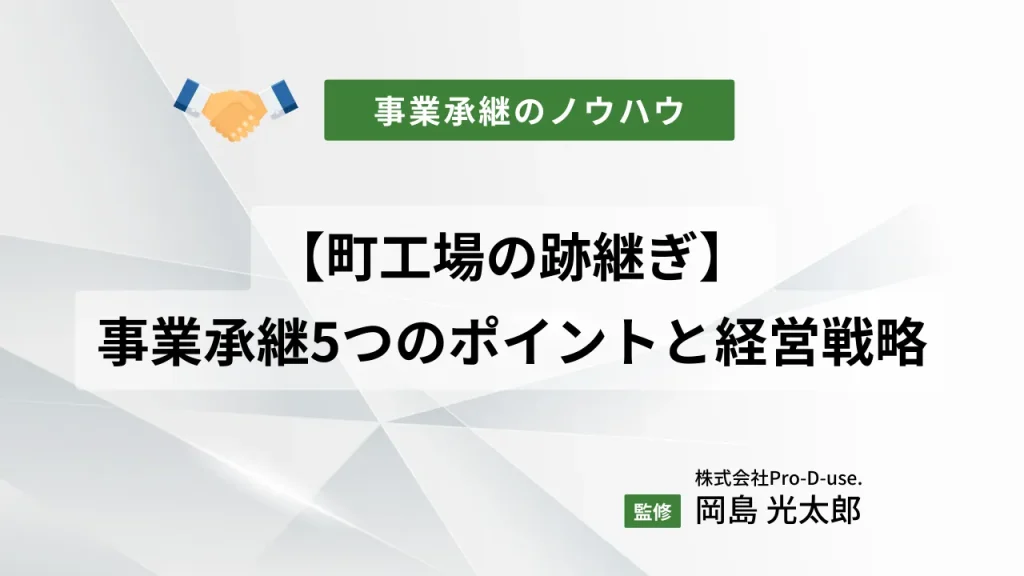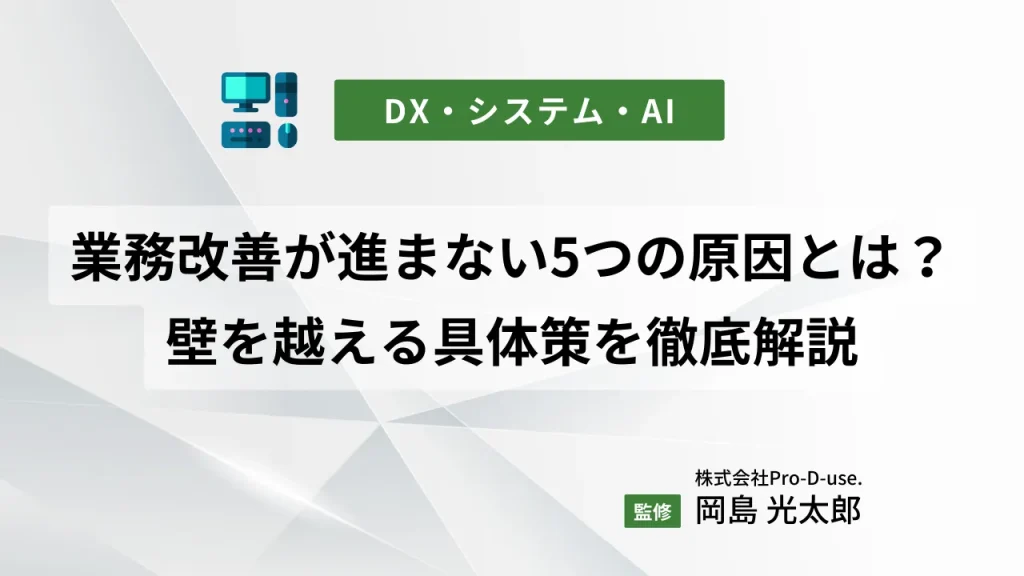\ 事業がグンっと前に進む /
\ サービス内容が知りたい方 /
会社の方針に従わない社員への対応方法とは?注意指導する際のポイントについても徹底解説
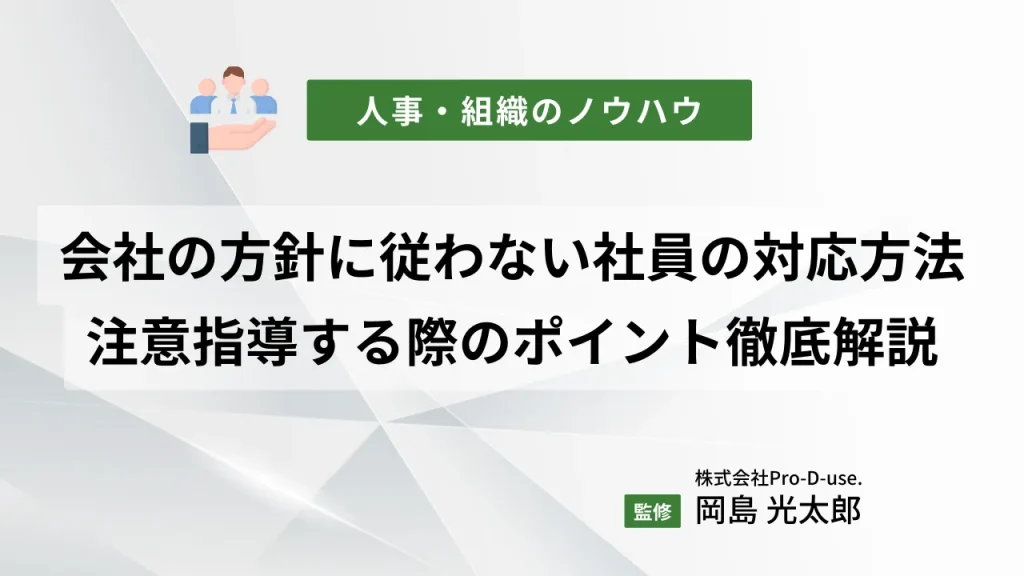
-
- 経営ノウハウ
- 2024年8月2日
会社の方針に従わない社員への対応方法について知りたいと悩んでいませんか?

なぜ会社の方針に従わないんだろう。上手く対応する方法はないのか?

このままだとチームの雰囲気が悪くなる…どうやって解決すればいいのか?

最悪、法的な措置を考えないといけないかもしれない。どういった手続きが必要なんだろう。
会社の方針に従わない社員への対応は、指導や面談を行い、それでも改善されないときには、懲戒処分を検討する必要があります。
一方で、注意指導のやり方については問題になる可能性があるため、注意しなければいけません。
私はこれまで、中小・ベンチャー企業への「組織マネジメントのコンサルティング」を通して、多くの成功も失敗も現場で目の当たりにしてきました。
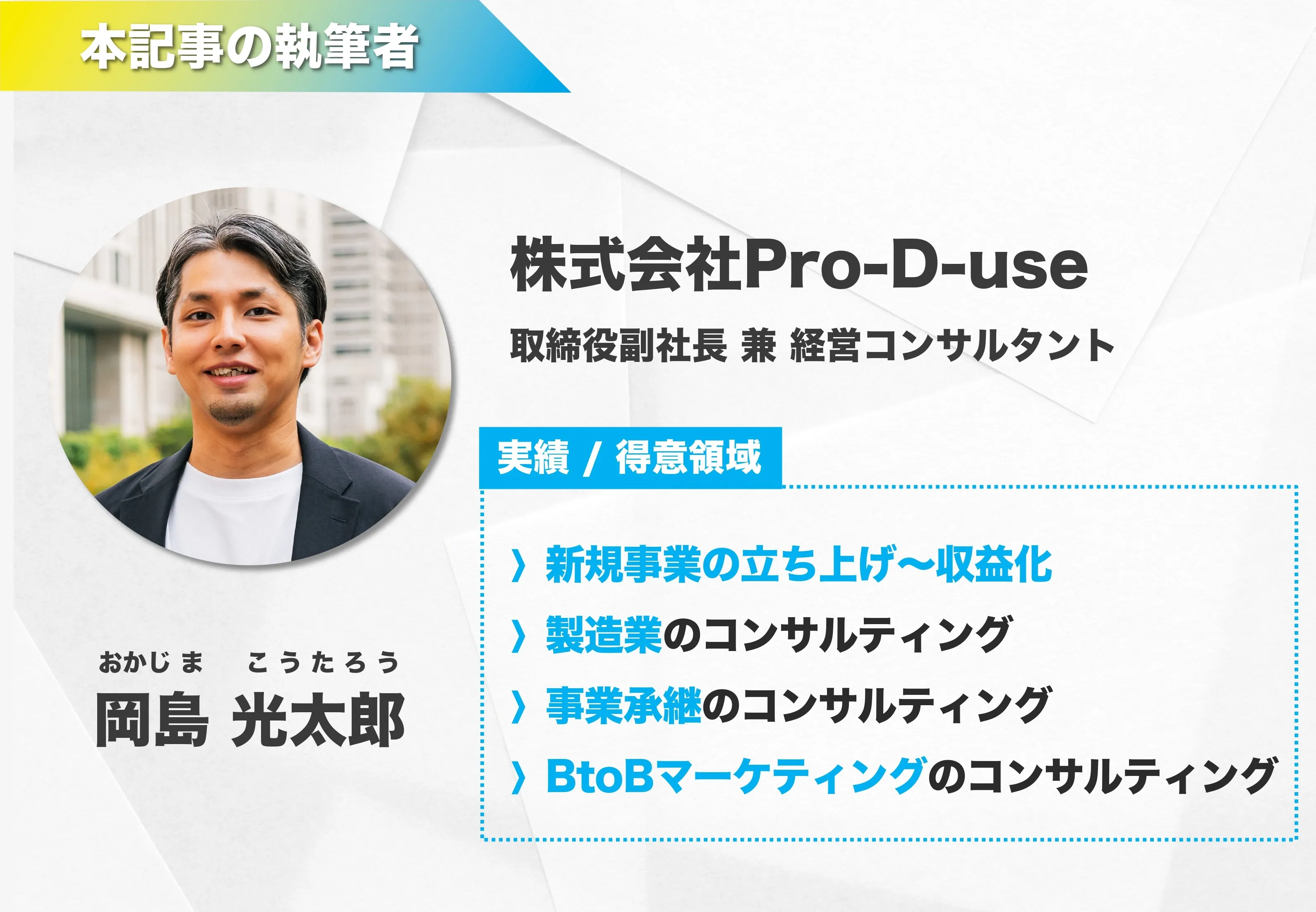
本記事では、「会社の方針に従わない社員の特徴」や「会社の方針に従わない社員を生まないための対策」について言及していきます。
マネージャークラスが抑えるべきポイントは以下。
- 社内教育の見直し
- 注意指導する際の注意点
上記を意識し、「会社の方針に従わない社員に対しての適切な対策」の再考察をかけることをおすすめします。
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- マネジメントを改め、社員のモチベーションを向上させる
- 社内の統率がとれるようになり、一丸となって同じ方向に進んでいける
ぜひこの記事を参考に、会社の方針に従わない社員への対応について理解を深めてみてください。
また以下で「やる気のない社員の特徴」について解説してあります。詳しく知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
あわせて読みたい
やる気のない社員を”グッと引き上げる”5つの対…
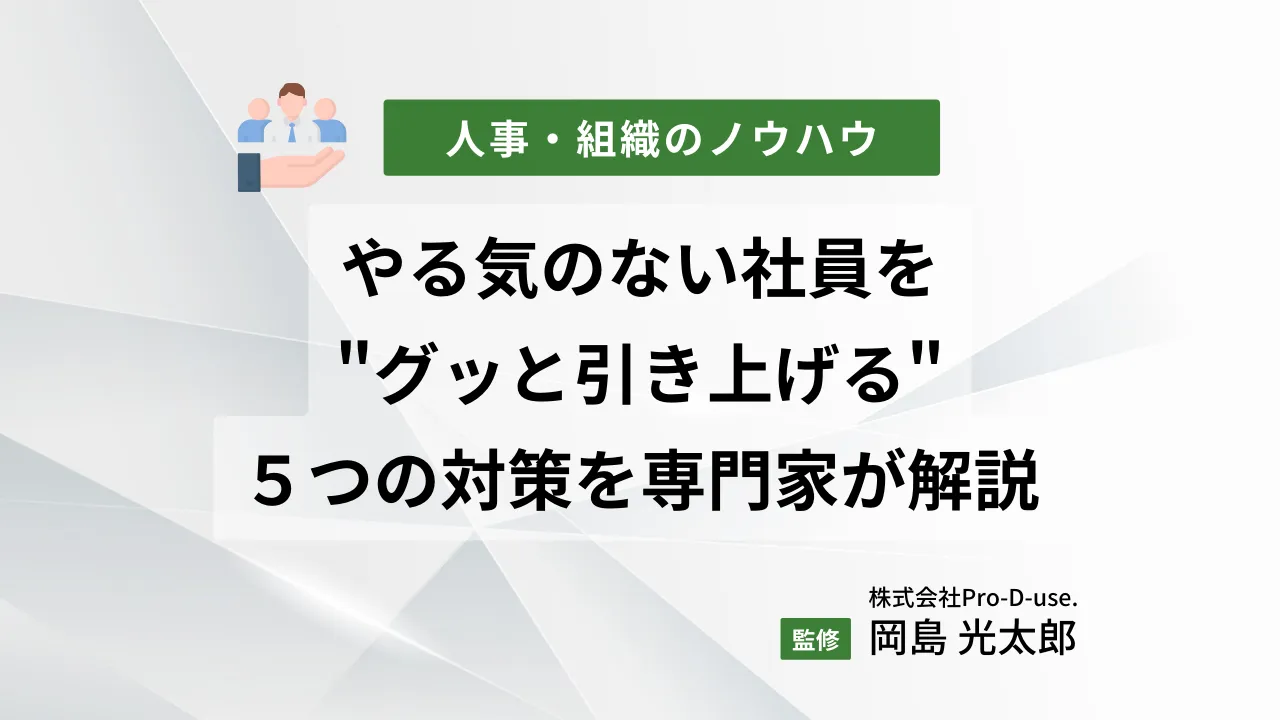
中小企業の経営者の中には、「やる気のない社員のやる気を上げたい…」とお悩みの方は多いはずです。 「あの社員はなぜやる気がないのか?彼のモチベーションを上げるにはどうすればいいか…。」「社員のモチベーションが低いのは会社の問題か?それとも個人…
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
目次
会社の方針に従わない社員への対応方法
会社の方針に従わない社員への対応方法については、主に以下の5つがあります。
- 指導する
- 定期的に面談をする
- 懲戒処分を検討する
- 部署の異動を検討する
- 退職推奨を検討する
それぞれの対応を紹介します。
1.指導する
社員が会社の方針に従わない場合には、すぐに指導することが重要です。
問題がある社員を放置してしまう期間が長くなってしまうと、その分会社への被害が大きくなってしまいます。
また、以下のような対応をしてしまうと、さらに問題行動が拡大してしまう可能性が高いので注意してください。
- 退職してしまうと困ると思ってとりあえず我慢してしまう
- 男性上司が女性の問題社員に対して遠慮したり距離を置き、必要な指導をしない
- 指導することによる反発を避けるために見て見ぬふりをする
- 成績のよい社員の問題行動について見て見ぬふりをする
2.定期的に面談をする
会社の方針に従わない社員に対しては、定期的に面談をするようにしましょう。
面談を行う際には、社員の顔色をうかがってコミュニケーションをとるのではなく、問題箇所がある場合には遠慮せずに指導を行うことも重要です。
3.懲戒処分を検討する
しつこく指導したり、定期的に面談などをしても問題行動が改善されない場合には、懲戒処分を検討することも必要です。
問題がある社員に警告を与えるのはもちろん、周囲の社員に対しても問題行動をしてはいけないという姿勢を明確にすることができます。
具体的に懲戒処分には、以下の種類があります。
- 戒告・譴責・訓告
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇
問題行動をしてしまうレベルに応じて、懲戒処分の種類を選択することが必要です。
懲戒処分の判断基準の目安
懲戒処分の判断基準の目安については、以下のとおりです。
| 懲戒処分の種類 | 判断基準の目安 |
|---|---|
| 戒告・譴責・訓告 | ・無断欠席 ・業務上のミスが頻発に起きている |
| 減給 | ・遅刻や欠勤が繰り返し続いている ・会社に大きな損失を出してしまった |
| 出勤停止 | ・職場内の暴力 ・業務命令の拒否 ・職務の破棄によって会社に損害を与えてしまった |
| 降格 | ・部下に対するセクハラやパワハラなど ・社内の重要なルールや規定に対する違反 |
| 諭旨解雇 | ・14日以上の無断欠席 ・業務上の横領 ・職場内で強制わいせつなどのセクハラをしてしまった |
4.部署の異動を検討する
会社の方針に従わない社員は、部署の異動を検討して、適性を見ることも重要です。
現在の業務で能力を発揮していない可能性もあるので、他の部署に配置転換をして、適性を見る機会を作るようにしましょう。
退職に追い込むのは違法
部署の異動を行う際に、退職を追い込むことを目的とした異動は違法になってしまうので注意が必要です。
基本的に、就業規則によって会社の配置転換命令や転勤命令に従うべきことが定められている場合に、正当な理由なく、これらの理由を拒否することは懲戒の対象となります。
しかし、会社から社員に対して人事異動命令には一定の制限があり、業務上の必要性のない不当な目的による異動命令は違法となってしまう可能性があります。
不当な目的と判断されてしまうと、異動命令が無効になったり、会社が損害賠償を命じられたりするケースもあるので注意が必要です。
5.退職推奨を検討する
懲戒処分を実施しても改善が見られない社員については、退職推奨を検討するようにしましょう。
退職推奨とは、強制的に退職させるのではなく、退職に向けてしっかりと説明を行い、社員の同意を得て退職させる目的があります。
強制的に退職させる「解雇」に比べて、トラブルになりにくい方法です。
注意指導する際のポイント
会社の方針に従わない社員を注意指導するポイントについては、主に以下の3つがあります。
- 注意指導はその都度行う
- 具体的な内容を注意指導する
- 注意指導は記録に残す
それぞれのポイントを解説します。
1.注意指導はその都度行う
会社の方針に従わない社員を注意指導する際には、その都度行うことが重要です。
問題がある行動をしてから時間が空いてしまうと、社員側の問題意識が低くなってしまい、反発してしまうリスクが高くなってしまいます。
また、懲戒処分や解雇を実際に行う際に、不適切な行為として扱われてしまう可能性があるので注意が必要です。
2.具体的な内容を注意指導する
注意指導を行う際には、できるだけ具体的な内容を示す必要があります。
問題がある社員に対して注意指導をする際に、「社会人としてやってはいけない行為なので、きちんとしてください」と注意指導しても、社員側からすればどの行動に問題があるのか分からずに、また同じような問題を繰り返してしまう可能性が高くなります。
どのくらい問題がある行為なのか、どのくらいの影響・損害を出してしまったのかなど具体的に伝えるようにしましょう。
3.注意指導は記録に残す
注意指導を行う際には、議事録やメール、チャットなど記録に残すようにしましょう。
問題がある社員に対して、注意指導を繰り返しても改善が見られない場合に、記録を残しておくと、懲戒処分や解雇などが行いやすくなります。
また、社員側が裁判を起こした場合でも、注意指導の記録が残っていると、会社側が有利になるメリットになります。
会社の方針に従わない社員の特徴
会社の方針に従わない社員の特徴として、以下が挙げられます。
- 自己評価が高い
- 相手の立場を考えない
- 会社に対する評価が低い
それぞれの特徴を紹介します。
1.自己評価が高い
会社の方針に従わない社員の特徴として、「自分は間違っていない」「しっかりと仕事をしている」など自己評価が高い特徴が見られます。
自己評価が高くなってしまうと、上司から注意されたとしても、自分が正しいと思ってしまい、聞き流されてしまうケースが多いです。
そのため、問題がある箇所を繰り返し根気強く指導を行い改善を求めることが重要になります。
2.相手の立場を考えない
相手の立場を考えない社員は、問題を起こす行動をしてしまう傾向が多いです。
自分の判断や考え方には強いこだわりを持っており、自分とは関係がないと判断すれば、ひたすら無関心に行動をしてしまいます。
自分の主張を突き通してしまい、さらに問題がこじれてしまうリスクが高くなってしまいます。
このような社員に対しては、会社の就業規則やルールを明確に示して、終業時間中は守らなければいけないという内容を繰り返し指導することが重要です。
3.会社に対する評価が低い
会社に対する評価が低い社員は、会社の就業規則やルールに納得していないケースが多く、問題を起こしてしまう傾向が見られます。
会社に対して強い不満を抱いているので、故意的に会社の方針に従わない社員も少なくありません。
このような社員に対しては、普段からコミュニケーションをとって不満や要望などを聞いて、少しづつ歩み寄ることが大切です。
会社の方針に従わない社員を生まないための対策
会社の方針に従わない社員を生まないための対策については、主に以下の3つがあります。
- 適切に評価する
- 定期的に業務のローテーションを行う
- コミュニケーションを増やす
それぞれの対策を解説します。
1.適切に評価する
昇給・昇格など適切に評価することで、会社の方針に従わない社員を生まないための対策につながります。
会社の方針に従わない社員は、会社の人事評価に納得していないケースも多く見られるので、適切に評価することは重要といえます。
2.定期的に業務のローテーションを行う
定期的に業務のローテーションを行うことで、幅広い考えや視野を持つことができ、自己中心的な社員を生まないための対策にもつながります。
同じ部署にいることによって、自分にしか分からないという考えを持ってしまうと、自己中心的な要求を通そうとしてしまいます。
このような状態を予防するためにも、定期的に業務のローテーションを行うのをおすすめします。
3.コミュニケーションを増やす
会社の方針に従わない社員を生まないための対策として、普段からコミュニケーションをとっておくことで、不満やストレスなどが溜まってしまうのを防げます。
具体的に社員とコミュニケーションを増やす方法として、以下が挙げられます。
- ランチを一緒に取る
- ビジネスチャットなどのツールを活用する
- 定期的なコミュニケーションの場を設ける
- タスクや進捗状況を報告する
- 月に一回は飲み会を開催する
しかし、コミュニケーションを取る機会を増やしすぎてしまうと、それが負担になってしまい、逆効果になってしまうリスクもあるので注意しましょう。
会社の方針に従わない社員へ対応する際の注意点
会社の方針に従わない社員へ対応する際には、段階的な処分を行う必要があるので注意が必要です。
段階的な処分を行わずに懲戒処分などをしてしまうと、処分が無効になったり、違法にあたると判断されてしまったりするリスクがあります。
まずは、指導や注意を行い、それでも改善が見られないのであれば、降格など段階的に処分を実施していくようにしましょう。
会社の方針に従わない社員には適切に対応しよう!
今回は、会社の方針に従わない社員への対応方法について知りたい方に向けて、会社の方針に従わない社員の特徴や会社の方針に従わない社員を生まないための対策を紹介しました。
会社の方針に従わない社員への対応方法については、主に以下の5つがあります。
- 指導する
- 定期的に面談をする
- 懲戒処分を検討する
- 部署の異動を検討する
- 退職推奨を検討する
今回の記事を参考に、会社の方針に従わない社員に適切に対応できるように参考にしてみてください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)