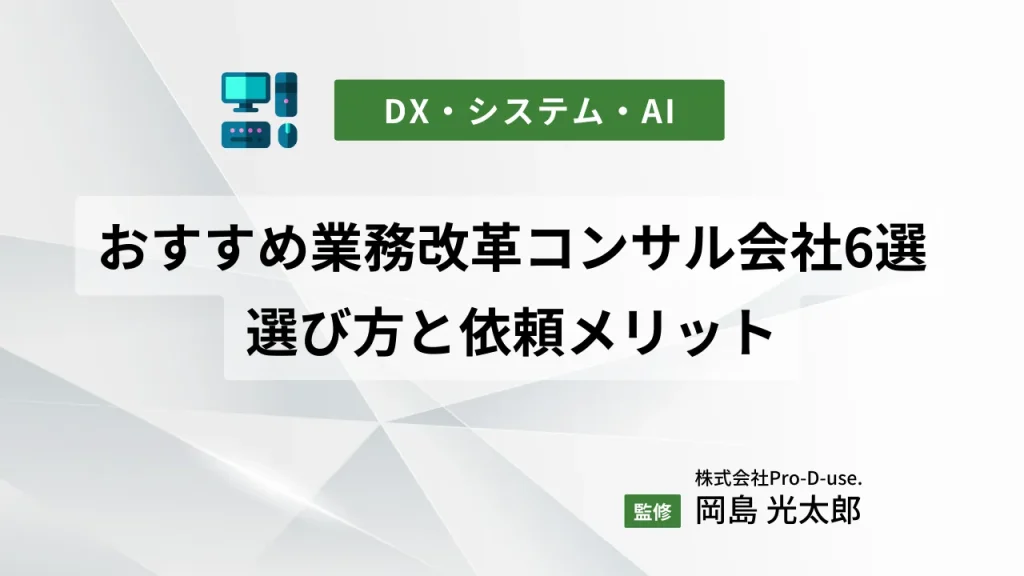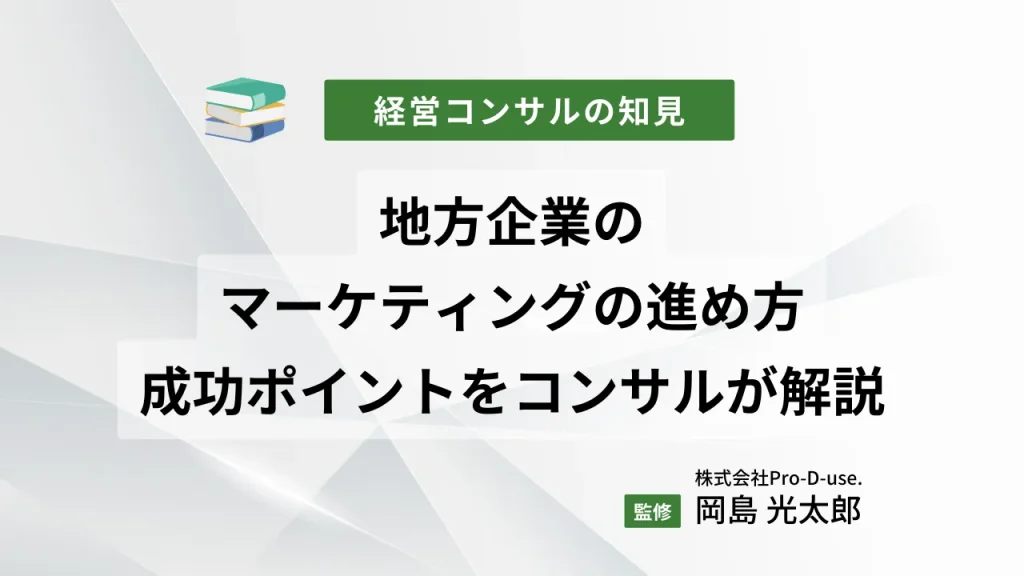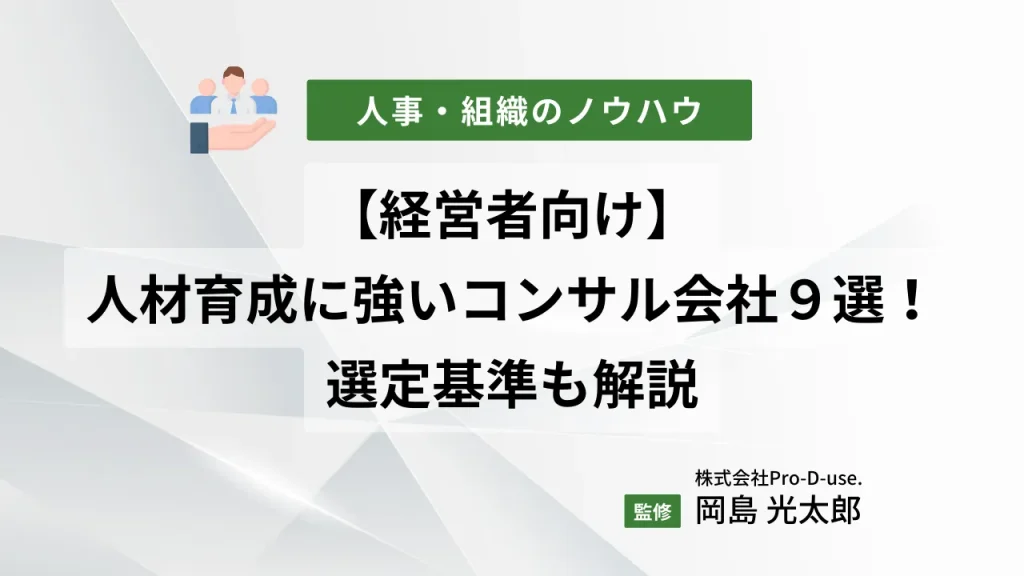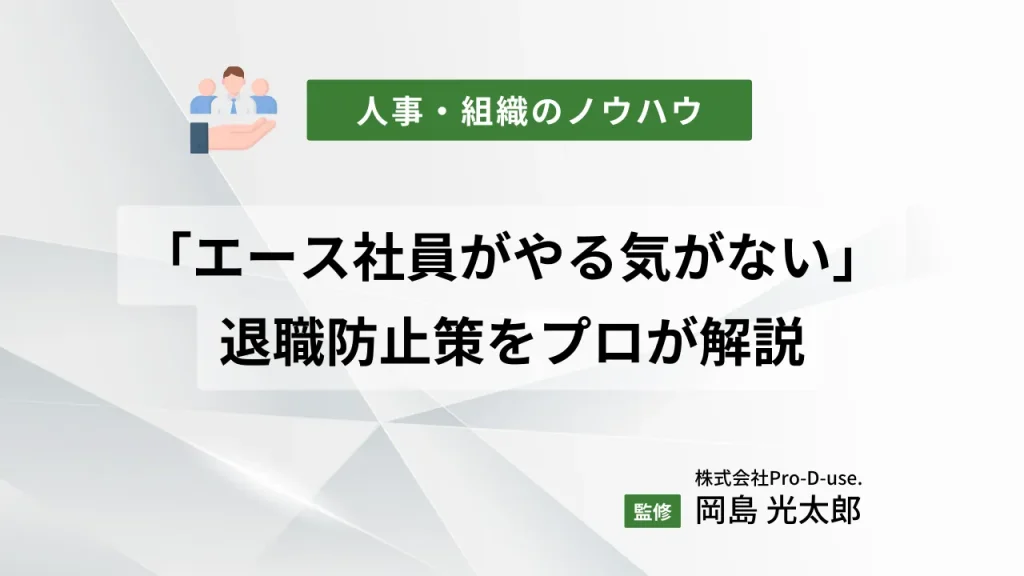優秀な若手ほどなぜ辞める?若手社員が早期離職する本当の理由と退職を防ぐ方法

-
- 経営コンサルティング
- 2024年8月2日
会社の経営者や上層部の方で、「若手社員の早期離職」について悩んでいませんか?

なぜうちの会社の若手はすぐに辞めてしまうの?
上司として、若手社員が辞める前兆を見逃しているかもしれない

新入社員が入社後すぐにやる気を失ってしまう原因は何?
若手が辞める理由は、実は違うものなのかもしれない

優秀な若手社員が辞めていく…何が原因なのかな?
若手社員にとって魅力的なキャリアパスを提供できていないのかな?
自社の若手がすぐ辞めてしまうのは「やる気がないなら」と思いがちですが、決してそうではありません。
実は、多くの企業が若手社員の早期離職に直面しており、その背景には複数の要因が存在します。
なぜなら若手社員の退職理由は単純なものではなく、人間関係やキャリアパスの不明確さ、社内のコミュニケーション不足など様々な要素が絡み合っているからです。
また、若手社員が辞める前には特定の前兆があり、これを見逃してしまうと離職に繋がります。
筆者は「株式会社Pro-D-use」という経営コンサルティング会社で、「若手社員の早期離職防止策」の成功も失敗も見てきました。
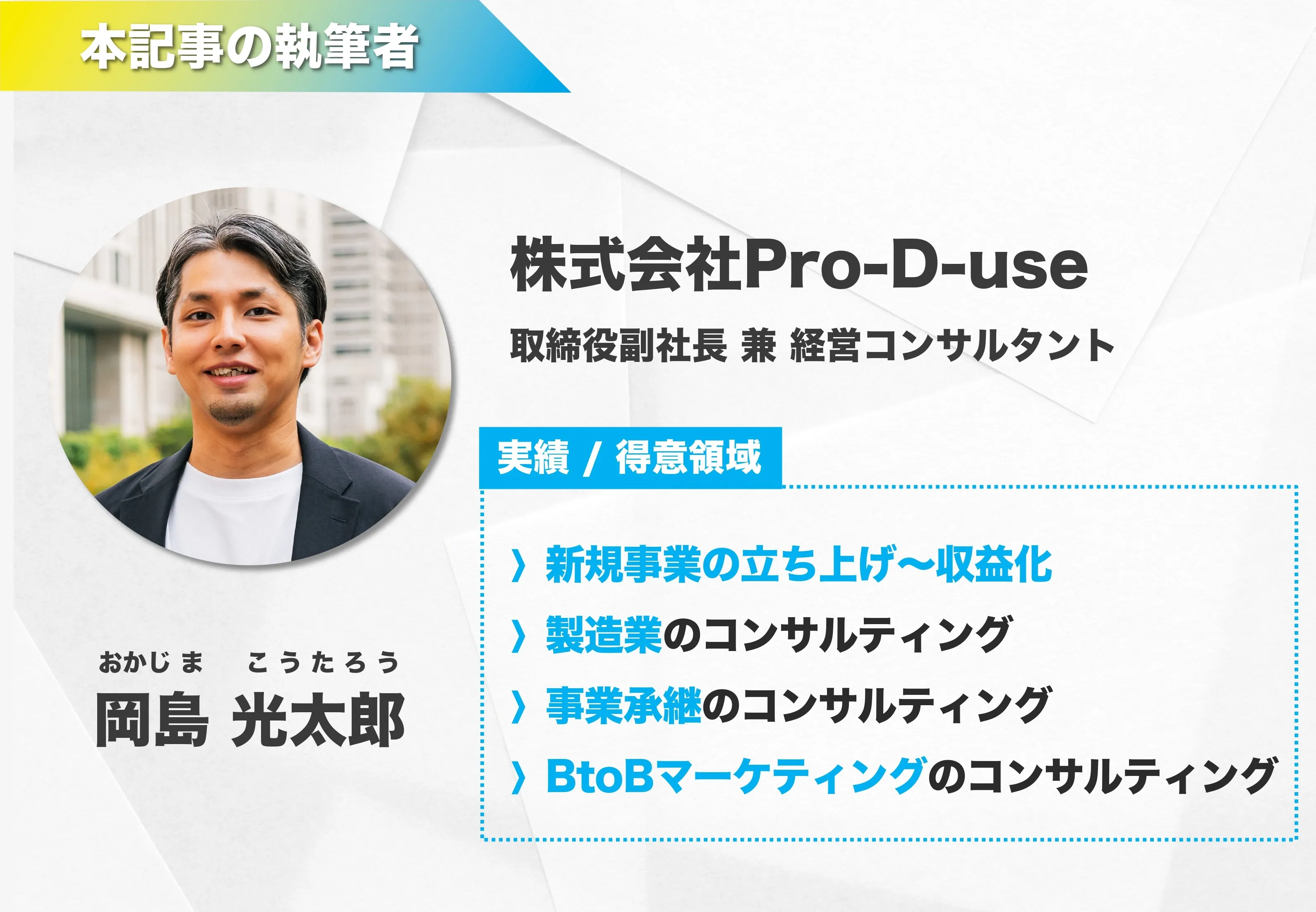
本記事では、辞めて欲しくない若手社員が辞めてしまう原因と、その防止策について詳しく解説します。
人事や経営者が押さえておくべきポイントは以下。
- 給与体系の公平性と競争力を保ち、良好な人間関係を築くための社内コミュニケーションを促進する
- 職場のマンネリ化を防ぐための多様な業務や、キャリアビジョンの共有を行う
- 業務量のバランスを適切に管理する
この記事を読めば、こんな事が実現できます。
- 優秀な社員が辞める原因を理解し、対策を行うことができる
- 適切な人員配置や人事評価システムを見直すことができる
- 企業文化と組織の柔軟性を高めることで、組織全体の成長に繋げられる
今回の記事を参考に、優秀な社員を維持し、組織の繁栄につなげる方法について理解を深めてみてください。
また当社では「エース社員がやる気がない理由と改善策」についても解説していますので、詳しく知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
あわせて読みたい
エース社員のやる気がないのはなぜ?効果的な改善策と退職を防ぐための方法
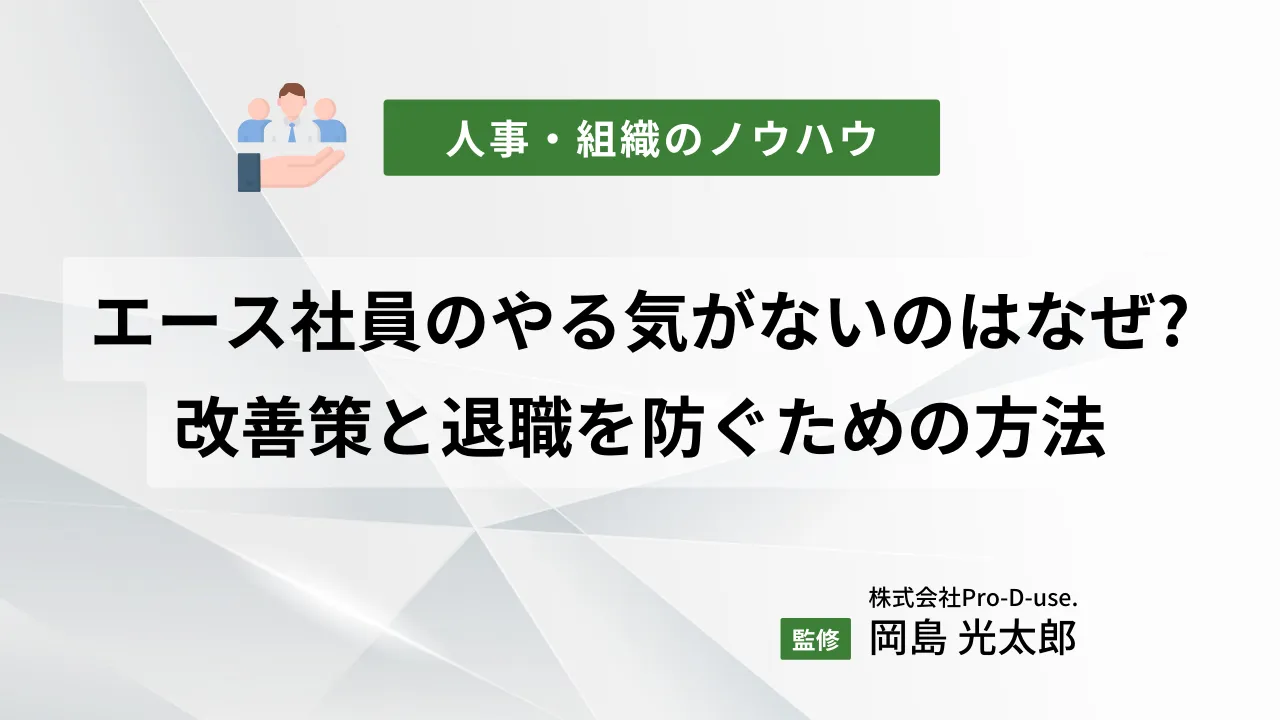
以前と比べると、エース社員として期待している人のやる気がないと悩んではいませんか? 実は、エース社員は自社での成長の機会に見切りをつけてしまっているかもしれません。なぜなら、エース社員は本質的に能力が高く、活躍できるスキルを持っているので、…
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
目次
なぜ若手社員は会社を辞めるのか?
出生率の減少とともに労働人口の不足を背景に人材の採用と定着は重要な経営課題の1つとなっています。
特に企業の大小にかかわらず、優秀な若手社員ほど定着しづらい傾向にあり、悩みを抱えている企業は少なくありません。
会社を辞めることや転職が珍しくはない現代において、若手社員の離職理由にはどんなものがあるのでしょうか。
若手社員が辞める理由
2017年に内閣府が行った「子供・若者の意識に関する調査」(29歳までの男女10,000名対象)によると、離職理由には次のようなものが挙げられました。
- 仕事が自分に合わなかった
- 人間関係が良くなかった
- 労働条件が良くなかった
この調査から若手社員に対する離職対策のアプローチには以下のような取り組みが考えられます。
- ハード面・・・賃金、福利厚生、就業条件など
- ソフト面・・・成長実感、やりがい、有能感など
辞める理由は「全部ウソ」だと心得る
離職を申し出た若手社員に退職理由を確認した際に口から出た理由は「ほぼウソ」で本音ではないと心得ましょう。
実際当たり障りのない表面的な理由を伝える人がほとんどです。
本音を伝えられる職場環境であれば退職に発展する手前で改善が図れていますし、退職を決めている職場にわざわざ本音を伝える必要性も感じないからです。
そのような理由を本音だと信じていると根本的な改善ができません。
若手社員の主な退職理由は以下の通りです。
- 嫌いな上司・先輩・同僚がいる
- 上司のようになりたくない
- 優秀な先輩が辞めて不安になった
1.嫌いな上司・先輩・同僚がいる
直近の経済産業省のデータでも分かりますが離職理由のワースト1位は「人間関係」です。
職場での人間関係は日々の出来事の積み重ねによって作られているケースがほとんどで、会社がこの事実を把握のは難しいのが現状です。
仕事に対して「やりがい」や「面白味」を感じていたとしても、人間関係の悩みはモチベーションやパフォーマンスに大きな影響を与えます。
ハラスメント対策や窓口が設置されていたとしても、「上司と合いません」「同僚または先輩が嫌いです」とは言いにくいものです。
職場に相談できる仲間や理解者や味方になってくれる存在がいるかどうかも大きなポイントになります。
2.上司のようになりたくない
優秀な若手社員は、スキルアップやキャリアアップなど成長意欲が高いという特徴があります。
そのような若手社員にとって「自分が将来どうなれるか」は、仕事をする上で大きな関心事の1つです。
管理職が大変そうであったり、目指したいと思えるポジションが見えないと将来への展望が感じられません。
管理職の職域や職務の定義、管理職が仕事を評価される制度設計など、希望の持てる将来性が提示できるかどうかは重要なポイントの1つです。
3.優秀な先輩が辞めて不安になった
転職が珍しいことではなく、どこの企業も人材不足でキャリア採用が盛んであるため、優秀な中堅社員にとって、転職はキャリアアップや収入アップにつながる見込みがあります。
若手社員にとって身近な存在であった中堅社員が辞めることは、不安を与えるインパクトの大きい出来事です。
理由としては次のようなことが考えられます。
- 優秀な先輩が転職することで会社の将来性に不安を感じる
- 理解者や相談相手であった先輩が辞めることで職場環境に不安を感じる
若手の離職は「やる気がない」のではない
一般的に中堅社員やベテラン社員と比較すると若手社員の方が離職率が高い傾向にあります。
若手社員は忍耐力ややる気がないから離職するのかというと、一概にはそうとは言えません。
会社を辞めることや転職は非常にエネルギーを使うからです。
そのエネルギーを使ってまで離職するということは、そこではないどこかに対して「意欲がある」と言えるでしょう。
意欲が高さが「辞めやすさ」につながっている
「チャレンジしてみたい」、「やりたいことがたくさんある」といったやる気が会社の仕事以外に向いていることも離職の理由となります。
意欲が高いからこそ、挑戦するならやり直しがきく若いうちに行動したいというケースです。
行動力のある意欲の高い若手社員に会社にとどまってもらうには、「活躍の場」を用意するなど工夫が必要です。
個性的な人材を採用しても定着しない
日本経済団体連合会が会員企業に実施した調査によると企業が大卒者に期待する能力の上位に「創造力」があがっています。
しかし、創造力のある個性的な人材を採用しても、職場環境になじめずに定着しないことが多いようです。
違和感の共有ができることが離職対策になる
職場環境の違和感が共有でき、解決や改善に対するフットワークが軽いと、社員同士の関係性が良くなる傾向があります。
つまり、仕事をするうえで気になることを話し合える、仕事や職場の課題について意見が言いやすい環境や関係性ということです。
若手社員がみせる離職の前兆
退職を考え始めた若手社員に現れやすい特徴的な言動について解説します。
次のような言動が見えはじめたら注意が必要です。
愚痴や不平・不満が増えた
職場や仕事に対して「やる気」や「熱意」がなくなり嫌気がさしてきていると愚痴や不平・不満が現れはじめます。
良い点が見えなくなり、無い点や悪い点にばかりフォーカスしている状態になっているからです。
そうなると周囲とも上手くいかなくなり、居心地も悪くなった結果、離職へと加速していくことになります。
会議やミーティングでの発言しなくなった
仕事に対して積極性がみられていた若手社員が会議やミーティングの場で発言をしなくなったら要注意です。
何らかの理由でモチベーションが低下していたり、仕事に対する将来性や希望が見いだせなくなっているのかもしれません。
メンタル不調の可能性もあるため慎重に見守ることも必要です。
同僚など社内での交流が希薄になった
これまでは同僚とプライベートでの交流があった若手社員が急に仕事以外では交流が希薄になった場合、退職を考えている可能性があります。
退職に向けて距離をおいているかもしれないので、注意が必要です。
若手社員の離職を防ぐ対策方法とは
若手社員の退職は必ずしも防げるものではありません。
しかし、できれば避けたい退職を未然に防ぐためにできる対策を4つご紹介します。
採用時点のミスマッチを改善する
若手社員の離職は、実は採用マッチングの時点で改善が図れる可能性があります。
会社側が良い面ばかりを見せない、社員に対しても都合の良い面ばかりを見ないことが重要です。
採用戦略の見直しが、若手社員の離職率を低下させることに繋がります。
相談しやすい環境や機会をつくる
困りごとが発生した時に相談が気軽にできる環境が整っているかどうかは大きな違いがあります。
他の社員の目を気にすることなく上司に相談できる機会、上司以外に相談できる仕組み、両方あるのが望ましいです。
ポイントは、社員が安心して相談ができる場を用意することです。
人間関係の改善を図る
仕事の悩みの多くは人間関係の占める割合が非常に大きいので、職場の人間関係を円滑にすることは離職防止に効果的です。
上司が人間的魅力を見せたり、部下に対して歩み寄る姿勢を見せたりすることも大切です。
しかし、同じ環境下での改善には限界があるため、配置転換などの対策も取れる環境や仕組みがあるとより良いでしょう。
部下の提案を受け入れる
部下の言い分や提案をそのまま受けれるということではなく、聞く耳があることが大切です。
人間関係や職場環境の改善についても、上司側からの一方的な提案だけでは十分とはいえません。
部下側からも提案しやすい雰囲気と検討する姿勢があると、部下の職場に対する安心感や信頼感へと繋げられるでしょう。
働きやすくても離職につながる場合もある
若手社員の離職というフレーズを耳にすると、長時間労働や過度な残業やパワハラがあるなどのブラック企業をイメージするかもしれません。
しかし、近頃ではコンプライアンスが見直されていることもあり、このような理由での離職は少なくなりました。
働きやすいホワイト企業であっても若手社員の離職は少なくないのが現状です。
「やさしく、ゆるい職場」が生み出す焦りと不安
職場環境も整っていて、風通しも良い職場であっても、離職とは無縁ではありません。
新入社員を対象におこなった調査によると、厳しい職場ではなく、やさしくゆるい職場であっても「不安だ」との回答が多い傾向にあります。
何が不安なのかというと「別の会社や環境、別の部署では通用しないかもしれない」と感じることのようです。
入社前に社会経験を積んでいる若手社員が多い
若手社員の多くが入社前の学生時代に「社会的な経験」を積んでいるケースが多いようです。
アルバイトやインターンといった経験だけでなく、個人での起業や法人設立、イベントの主催・運営など、さまざまな経験をしている若手社員が増えています。
そういった、社会的な活動の経験が乖離を生み、職場や仕事への向き合い方が違っていることも要因の一つとなっています。
多様性が求められる時代
現代はさまざま変化の激しい時代です。
入社時点で社会的な活動の経験が多い人もいれば少ない人もいる中で、優秀な若手社員に活躍してもらうためには、多様な若手が活躍できる職場環境を整える必要があります。
これまでとは異なる会社と若手社員の新しい関係性、多様性が求められる時代になっているといえるでしょう
若手社員の離職を防いで活気のある職場にしていきましょう
今回は、若手社員が会社を辞める理由や早期離職してしまう原因について知りたい方に向けて、辞める原因と、その防止策について重要なポイントを紹介しました。
若手社員が長期間働ける環境づくりのポイントについては、主に以下が挙げられます。
- 創造的な態度を持つ若手のニーズを満たす
- 早期退職の前兆に注意し、適切な対応を行う
- 退職理由の真実を理解する
今回の記事を参考に、若手社員の定着率向上を成功させてみてください。
若手社員の早期離職や定着率が低いことにお困りではありませんか? Pro-D-useなら手放しで経営がみるみる改善!
⇒Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
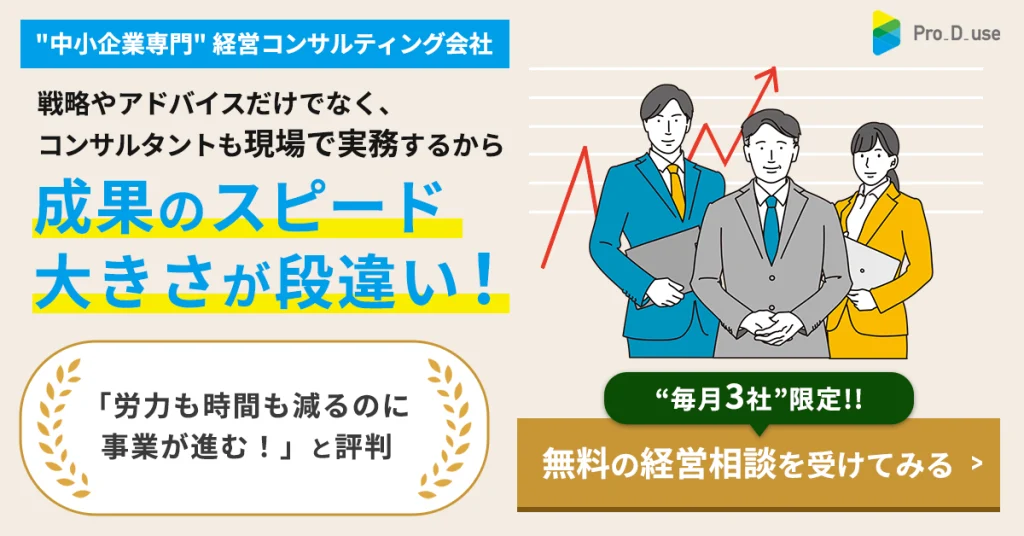
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)