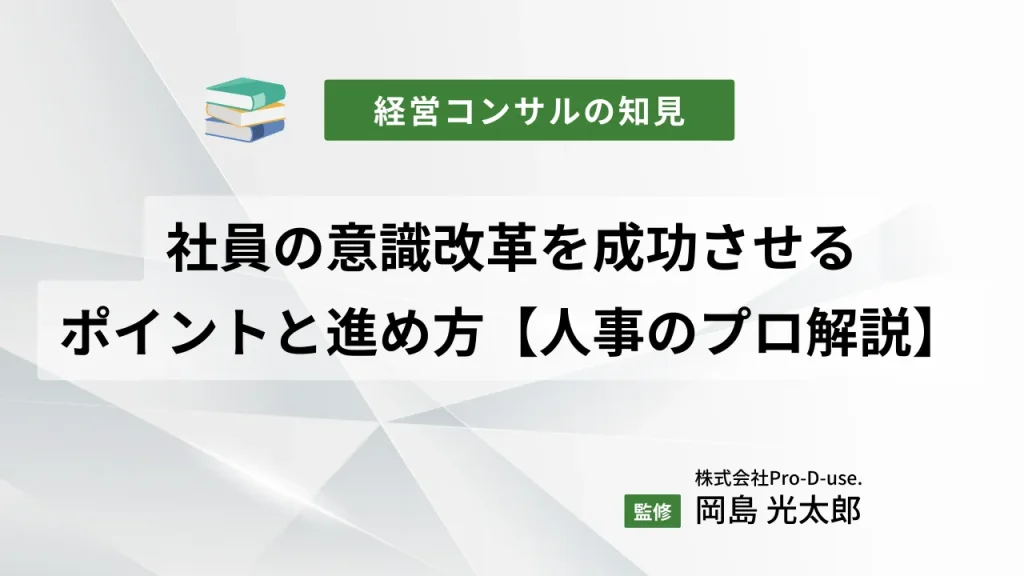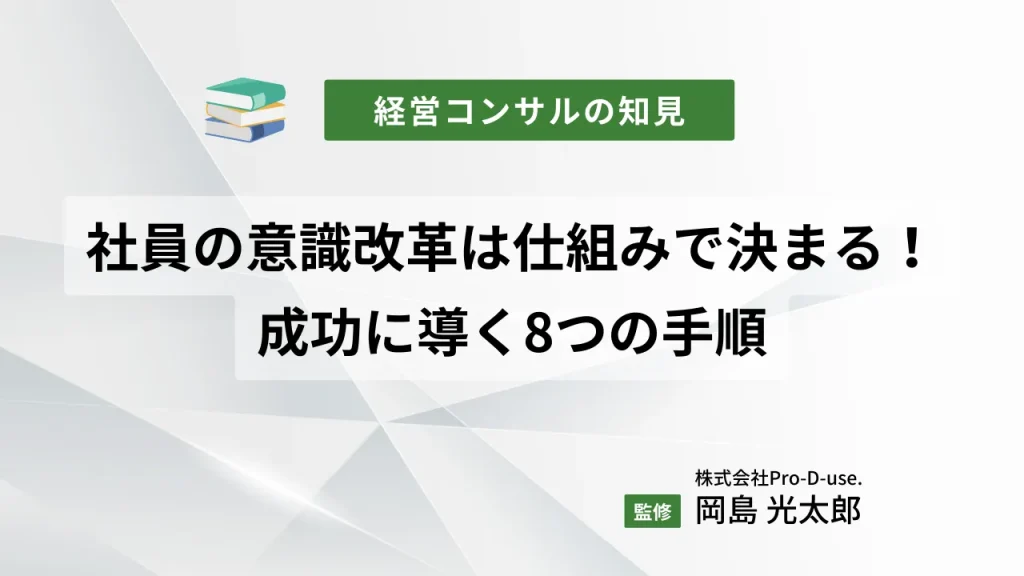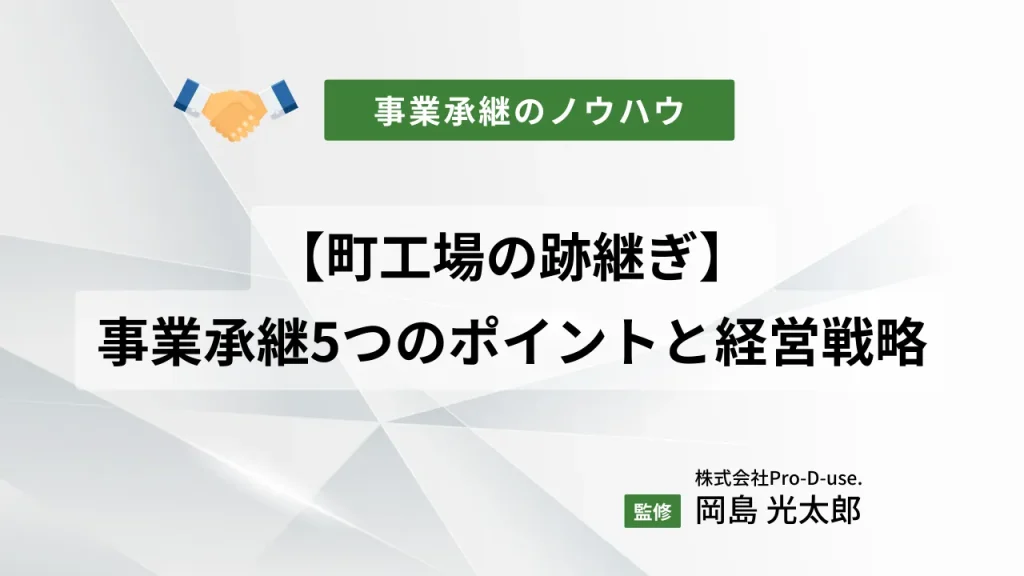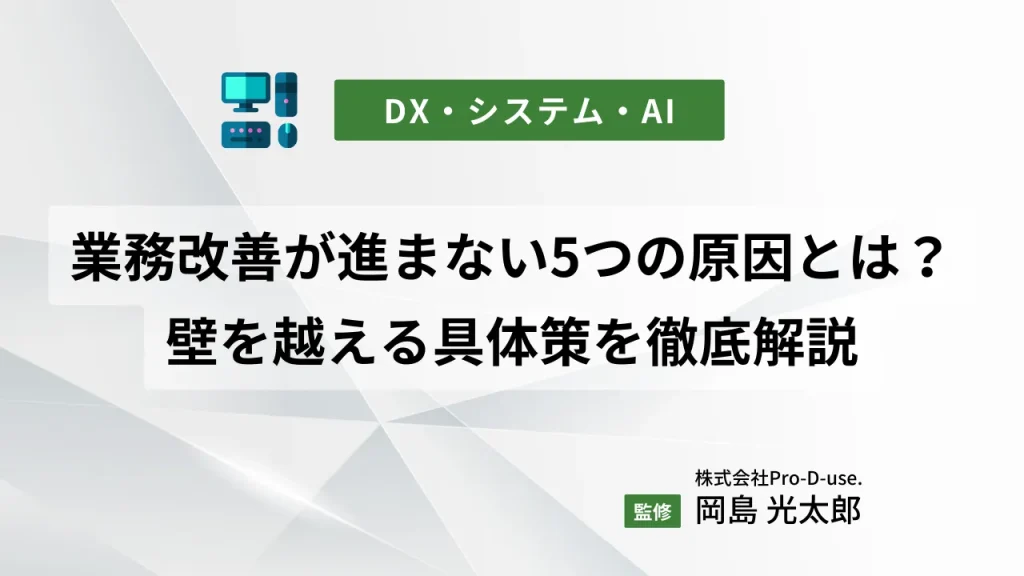「社長と従業員」の関係がすれ違う4つの理由と改善ステップ
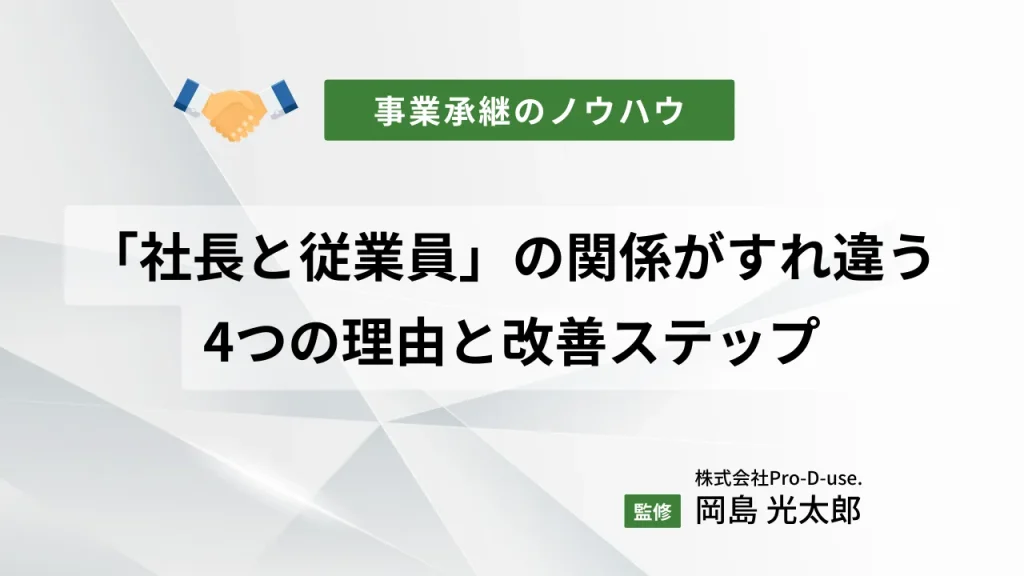
-
- 事業承継
- 経営ノウハウ
- 2025年9月2日
経営者の方であれば誰しも、以下のように社長と従業員との関係性にお悩みを感じる方も多いのではないでしょうか?
- 従業員が会社や私(経営者)を理解してくれない…
- 指示を待つだけで主体性に欠ける社員が多いと感じる…
- 社内の雰囲気がぎこちなくて一体感が感じられない…
社長と従業員の関係がすれ違ったままでいると、「目標の達成」や「人材の定着率」が低下し、企業成長の大きな阻害要因となりかねません。
社長と従業員がすれ違う原因は、以下の「4つの構造的な違い」によって引き起こされます。
▼すれ違いを起こす「4つの構造的な違い」
- 構造的な違い1. 社長と従業員の利益の違い
- 構造的な違い2. 社長と従業員の役割の違い
- 構造的な違い3. 社長と従業員の視点の違い
- 構造的な違い4. 社長と従業員の期待のギャップ
その上で、これからの時代の社長と従業員の理想の関係性は以下を目指すべきだと筆者は考えます。
▼これからの時代の「社長と従業員の理想像」
- ビジョンや目標を共有し、同じ方向を向く関係
- 意見や提案を自由に交わせる関係
- 互いの成長を支え合う関係
- 経営状況が透明で納得感を持てる関係
- 多様性を尊重し、柔軟に働ける関係
筆者は「(株)Pro-D-use」という組織再編に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの会社の「社長と従業員との関係性の修復」をご支援をしてきました。
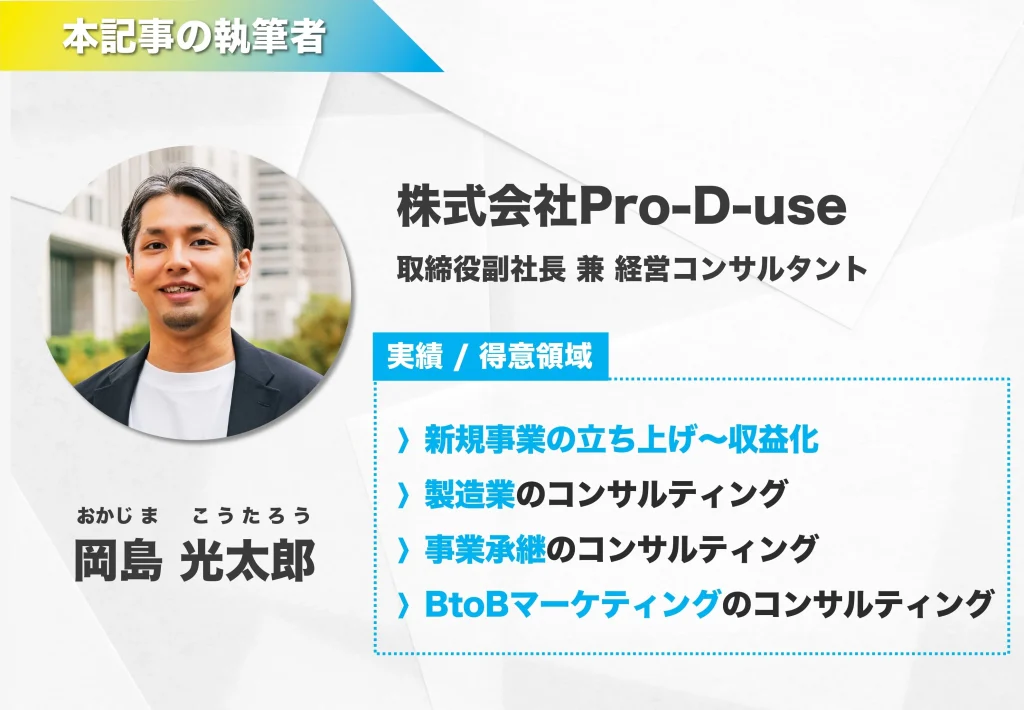
本記事では、そんな筆者の経験をもとに、「社長と従業員の関係が悪化する原因」と、「理想的な関係を築くためのステップ」を解説します。
記事を読めば従業員の主体性を引き出し、組織全体に一体感を生み出すヒントを得られます。社長と従業員の良好な関係性を築き、会社の持続的な成長につなげていきましょう。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
目次
社長と従業員の関係がすれ違う「4つの構造的な違い」
社長と従業員は立場や見ている景色の違いにより、関係がすれ違いやすい構造にあります。具体的な背景には、以下が挙げられます。
▼すれ違いを起こす「4つの構造的な違い」
- 構造的な違い1. 社長と従業員の利益の違い
- 構造的な違い2. 社長と従業員の役割の違い
- 構造的な違い3. 社長と従業員の視点の違い
- 構造的な違い4. 社長と従業員の期待のギャップ
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
構造的な違い1. 社長と従業員の利益の違い
社長と従業員では、会社から得たい「利益」の捉え方が根本的に異なります。社長は会社の長期的な成長と利益を重視する立場です。事業のリスクをすべて背負う立場であるため、成功によって得られる会社の利益を「自分ごと」として捉えることが自然です。
一方で、従業員は給与や職場環境など生活の安定を第一に考える傾向があります。会社の利益が待遇に反映されなければ、利益そのものへの関心は下がりやすくなります。
社長は数年先の成長を重視し、従業員は目の前の業務や待遇に関心を寄せるなど、両者では目指す利益が異なることが実情です。
構造的な違い2. 社長と従業員の役割の違い
社長と従業員はそれぞれの役割が異なります。社長は事業全体の方向性を定めて会社の将来を築く役割を担い、従業員は与えられた業務を遂行する役割を担います。
社長と従業員の具体的な役割の違いは、以下のとおりです。
▼社長と従業員「役割の違い」
| 役割の側面 | 社長の役割 | 従業員の役割 |
|---|---|---|
| 意思決定と業務遂行 | 会社の進むべき道を最終的に決定する | 社長の決定にもとづいて業務を実行する |
| 責任の範囲 | 会社の存続に関わるすべての責任を負う | 担当業務に対する部分的な責任を負う |
| ビジョン策定と実現 | 会社の未来像を描く | 未来像を実現するために自分の持ち場で貢献する |
| リスクと安定 | 会社の将来のために資金調達などのリスクを取る | 安定した環境で仕事に集中できる |
| 仕組みづくりと運用 | 組織や働くための仕組みを設計する | 与えられた仕組みの中で、自分の能力を発揮する |
構造的な違い3. 社長と従業員の視点の違い
社長と従業員では物事を見る範囲や時間軸が異なります。それぞれの視点に差が生まれる背景には、責任の重さや持っている情報量の違いがあります。
社長は会社の未来に責任を持つ立場として、的確な意思決定を行う力が不可欠です。市場の動きや会社のバランスを俯瞰しながら、社長は必要に応じてリスクを取ることも求められます。
一方、従業員は自分に任された業務に集中する立場です。目の前の業務や所属部署に意識が向きやすく、従業員の関心は「今日・今週・今月」といった短期的な目標達成に置かれます。従業員は変化やリスクよりも、安定した環境を優先する傾向が強く見られます。
構造的な違い4. 社長と従業員の期待のギャップ
社長と従業員の間には、お互いに対する「期待」に大きなギャップが存在します。社長と従業員の期待の違いは、以下のとおりです。
▼社長と従業員の「期待のギャップ」
| 社長の期待 | 従業員の期待 |
|---|---|
| 会社を自分ごとに捉えて行動してほしい | 生活の安定を優先したい |
| 自主的に動いてほしい | 明確な指示がほしい |
| 長期的な成長を目指してほしい | 目先の評価や給与を重視したい |
| 組織の成長のために厳しい意見も受け入れてほしい | 承認や共感がほしい |
何を優先するかという価値観の違いが、社長と従業員の間に見えない溝を生んでしまいます。
社長と従業員の関係が悪化する理由
社長と従業員の関係が悪化する主な原因は、価値観やコミュニケーションのズレです。互いの意図や期待がすれ違うと、不信感が生まれてしまいます。社長は「もっと主体的に動いてほしい」と思っていても、従業員は「指示が曖昧で動けない」と感じているケースがあります。
特に「業務改革」や「事業承継」など、これまでのやり方を変える局面では、従業員の不安が高まりやすいものです。社長がビジョンや方向性を十分に説明せずに改革を進めてしまうと、反発や不満が生じて従業員との関係の悪化につながります。
社長と従業員のすれ違いを防ぐためには、社長自身の考えを丁寧に伝える努力と、従業員の声に耳を傾ける姿勢が欠かせません。信頼関係は日々の対話と相互理解の積み重ねによって築かれます。社長が主体的にコミュニケーション改善に取り組むことが、組織全体のパフォーマンス向上にも直結します。
あわせて読みたい
社長が嫌われる「5つの原因」と、好かれる社長になる方法を解説
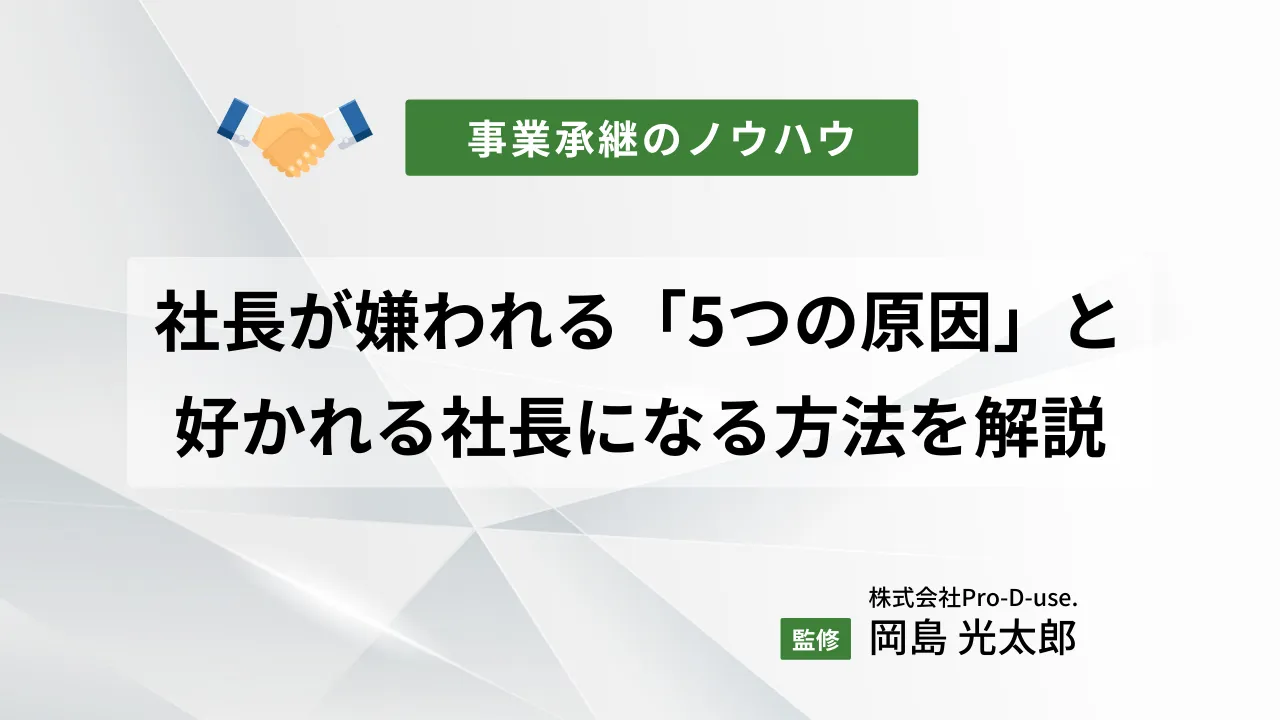
社長が組織を率いる中で、以下のように「社員に嫌われている」と感じたことはありませんか? 社員との間に目に見えない壁を感じる 指示を出しても社員が期待通りに動いてくれない 会社のためを思って下した判断が、かえって反感を招いてしまう 社員との心…
社長と従業員の理想的な関係
会社の持続的な成長には、社長と従業員の良好な関係が欠かせません。時代や働く人々の価値観の変化により、従来の関係性の見直しが求められていることも事実です。これまでの社長と従業員の関係を振り返ったうえで、現代の企業が目指すべき理想的な関係について解説します。
本章では、「これまでの時代」「これからの時代」に分けて社長と従業の関係について解説していきます。
これまでの時代の、社長と従業員の関係
かつて多くの会社では、社長が絶対的な権限を持つトップダウン型の関係性が一般的でした。トップダウン型の関係性の背景には終身雇用や年功序列が前提となり、長く勤めることが当たり前だった時代の働き方があります。従業員にとっては安定した雇用と引き換えに、社長の指示に従うことが当然とされていました。
しかし、トップダウン型の関係では従業員の自主性や創造性が育たず、組織の柔軟性と成長力を損なう恐れがあります。
これからの時代の、社長と従業員の理想的な関係
これからの時代に求められる理想的な関係とは、社長と従業員が共に会社の未来を作る関係です。従業員一人ひとりが能力を発揮し、自律的に動ける組織であれば、変化の激しい現代を柔軟に乗り越えられます。社長と従業員が目指すべき関係性は以下のとおりです。
▼これからの時代の「社長と従業員の理想像」
- ビジョンや目標を共有し、同じ方向を向く関係
- 意見や提案を自由に交わせる関係
- 互いの成長を支え合う関係
- 経営状況が透明で納得感を持てる関係
- 多様性を尊重し、柔軟に働ける関係
社長と従業員がお互いを尊重し、支え合うパートナーシップを築くことが会社の持続的な成長につながります。
社長と従業員との関係性を理想の状態にするには、社長と従業員という当事者同士で解決するのは非常に難しいものです。
「自社で解決するのは難しい」と感じる方は、弊社 株式会社Pro-D-useの無料の経営相談をご活用ください。組織再編や、従業員マネジメントに強いコンサルタントが、初回3回までは無料で経営相談を実施しております。まずは以下のボタンから無料の経営相談にお申し込みください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
社長と従業員の理想的な関係を作る【3ステップ】
社長と従業員の関係を構築するためには、社長が主体的かつ計画的に行動することが重要です。従業員との信頼関係が確立されると、会社の雰囲気が向上して組織の成長が促進されます。
社長と従業員の理想的な関係を作るステップは、以下3ステップです。
▼理想的な関係をつくる3ステップ
- ステップ1. 明確なビジョンと目標を共有する
- ステップ2. オープンなコミュニケーションを促進する
- ステップ3. フィードバックと評価制度を構築する
それぞれ、詳しく解説していきます。
ステップ1. 明確なビジョンと目標を共有する
社長と従業員が同じ方向を向いて進むためには、会社のビジョンと目標を明確に示し、全員で共有することが欠かせません。会社の方向性や目指すべき姿がわからなければ、従業員は自分の仕事に意味を見出しにくくなります。明確なビジョンがあれば従業員は仕事の意義を実感し、意欲と一体感が高まります。
ビジョンと目標を共有するためには、社長自身の言葉で会社の目指す未来像を繰り返し伝えることが重要です。会社の大きな目標を部署や個人の具体的な目標にまで落とし込み、日々の業務とのつながりを理解してもらうことが求められます。
ステップ2. オープンなコミュニケーションを促進する
会社の風通しを良くして意見を言いやすい環境を作ることは、社長と従業員の信頼関係を築くために有効です。従業員が安心して自分の考えを話せる雰囲気がないと、現場で起きている問題や新しいアイデアが社長まで届かなくなります。
従業員の安心感につながるオープンなコミュニケーションを促進するためには、以下の取り組みが効果的です。
▼オープンコミュニケーションの取組み例
- 経営や業績に関する情報を積極的に開示する
- 匿名で意見を出せる目安箱や社内アンケートを設置する
- 失敗も含めた挑戦を評価する文化を作る
- 社長が定期的に現場を訪問し、直接対話する機会を持つ
社長が従業員一人ひとりの声に耳を傾け、反対意見や厳しい意見も大切な情報として受け止める姿勢も必要です。
ステップ3. フィードバックと評価制度を構築する
従業員の頑張りを正しく評価して成長を後押しする仕組みは、社長と従業員の信頼関係を築く土台となります。一部の従業員だけが評価されているように感じると不公平感が生まれ、社内に不満が広がる要因にもなりかねません。公平かつ透明性のあるフィードバックと評価制度が、従業員のモチベーションを高める鍵となります。
従業員が安心して働ける評価制度を整えるためには、以下のポイントが重要です。
▼評価制度のポイント
- 評価の目的を明確にする
- 評価基準を具体化し、全員と共有する
- フィードバックを日常的に行う
- 自己評価や同僚の意見を取り入れる
- 評価結果と報酬・キャリアを結びつける
- 評価者への研修を実施する
- ポジティブなフィードバックを重視する
適切に評価する仕組みを整えることで従業員は安心して仕事に集中でき、会社への貢献意欲も高まります。
自社オリジナルの評価制度やコミュニケーション設計をするのはとても大変です。
「自社だけで考えるのは無理だ」と感じる方は、弊社 株式会社Pro-D-useの無料の経営相談をご活用ください。組織再編や、評価制度の設計に強いコンサルタントが、初回3回までは無料で経営相談を実施しております。まずは以下のボタンから無料の経営相談にお申し込みください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
社長が意識すべき!従業員とのコミュニケーション「3つの工夫」
社長と従業員の良好な関係を築くためには、意識的なコミュニケーションの積み重ねが欠かせません。社長自身が積極的に関わろうとする姿勢を示すことで、従業員の安心感や会社への信頼感が自然と高まります。社長がすぐに実践できるコミュニケーションの工夫は、以下のとおりです。
▼従業員とのコミュニケーション「3つの工夫」
- 工夫1. 定期的にミーティングを実施する
- 工夫2. 社内SNSやチャットツールを活用する
- 工夫3. 非公式な交流の機会を増やす
それぞれ詳しく解説していきます。
工夫1. 定期的にミーティングを実施する
従業員との対話を増やすためには、定期的なミーティングの機会を設けることが効果的です。社長が一方的に話すのではなく、従業員の意見に真摯に耳を傾けることで本音や現場のリアルなアイデアを引き出せます。ミーティングを実施する際は、発言の質や集中力の向上のために目的を明確にします。
従業員の考えを深く理解する手段として、1対1の面談やプロジェクト単位の少人数ミーティングを取り入れることも効果的です。社長と従業員の距離が縮まり、より率直な意見交換が生まれやすくなります。会議の内容を実行に移すことで、ミーティングが実際に役立つと実感してもらうことも可能です。
工夫2. 社内SNSやチャットツールを活用する
社内SNSやチャットツールは、時間や場所にとらわれずにコミュニケーションが取れる便利な手段です。ミーティングのように改まった場所を設けなくても、日常的に気軽に意見交換できる環境を整えられます。チャットは文章でのやり取りが中心であるため、対面では言いづらいことも伝えやすくなるメリットがあります。
社内SNSやチャットツールの具体的な活用方法は、以下のとおりです。
▼SNSやチャットの具体的な活用方法
- 理念やビジョンを社長の言葉で発信する
- 社長が従業員の声にすぐ応える
- 成功事例を全体で共有する
- 日々の進捗や気づきを手軽に報告できる仕組みを作る
- アンケートなどで意見を集めやすい環境を整える
ツールを上手に活用することで社長と従業員の距離が縮まり、風通しの良い組織づくりにつながります。
工夫3. 非公式な交流の機会を増やす
仕事以外の場で交流する機会を設けることは、従業員との信頼関係を深めるうえで効果的です。業務中には見えにくいお互いの人柄に触れることで親近感が生まれ、本音で話しやすい関係が築きやすくなります。仕事の緊張感から離れた場は、従業員がリラックスして社長と接する機会にもなります。
交流の具体的な取り組みは、以下のとおりです。
▼交流を促す取り組み例
- ランチ会・食事会の開催
- 季節ごとの社内イベントの実施
- 部活動やサークル活動への支援
- リラックスできる休憩スペースの整備
社長自身が交流の場に積極的に参加して楽しむ姿勢を見せることで、会社全体に安心感と一体感が広がっていきます。
従業員の声を生かすために社長ができる「3つの取組み」
従業員の声を経営に取り入れることは、会社の未来を築くうえで欠かせない視点です。現場で働くからこそ見える課題や、お客様に近い立場だからこそ生まれるアイデアには、会社を成長させるヒントが多くあります。
従業員の声を会社の力に変えていくために、社長ができることは以下のとおりです。
▼社長ができる「3つの取組み」
- 取組み1. 従業員アンケートを実施する
- 取組み2. 従業員の意見を反映させる仕組みを作る
- 取組み3. 従業員参加型のプロジェクトを推進する
それぞれについて、詳しく解説していきます。
取組み1. 従業員アンケートを実施する
社長が従業員の正直な声を聞くためには、従業員アンケートの実施が効果的です。日々の業務の中では従業員一人ひとりの本音を聞く機会は限られていますが、アンケート形式であれば意見を伝えやすくなります。
従業員アンケートを効果的に実施するポイントは、以下のとおりです。
▼従業員アンケートのポイント
- 目的を明確にする
- 匿名性を確保する
- 多角的な視点で質問を設計する
- 回答・集計の手間を最小限に抑える
- 透明性を持って結果を共有する
従業員アンケートを定期的に実施することで、組織の継続的な改善につなげることが可能です。
取組み2. 従業員の意見を反映させる仕組みを作る
従業員から集めた意見を会社の運営に生かすには、意見を反映させる仕組みを整えることが重要です。仕組みがあれば従業員は自分の声が社長に届くと実感でき、積極的に意見を出しやすくなります。
従業員の意見を反映させる仕組みには、具体的に以下の方法があります。
▼従業員の意見を反映させる仕組み例
- 匿名で意見を出せる提案箱を設置する
- 優れた提案にインセンティブを与える
- 意見を検討する会議を定期開催し、議事録を共有する
- 採用・不採用の理由を提案者にフィードバックする
- 部署や役職を越えて「改善委員会」を作る
社長が従業員の意見を大切にしている姿勢を示すことは、会社の活性化に欠かせません。
取組み3. 従業員参加型のプロジェクトを推進する
従業員の声を生かす取り組みとして、従業員が主体的に参加するプロジェクトを立ち上げる方法があります。課題解決や新たな価値の創出に自ら関わることで、従業員の貢献意欲が高まります。従業員主体のチームを組織したり、部署を横断したメンバーを公募したりする方法が効果的です。
従業員参加型のプロジェクトで成功体験を重ねることで、従業員は「自分の行動が会社に影響を与えている」と実感できるようになります。
» 内閣府「社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集」(外部サイト)
社長と従業員の関係は会社の成長に直結!
社長と従業員の関係にすれ違いが生まれる背景には、利益の捉え方や役割の違いなどがあります。しかし、日々のコミュニケーションを重ねることで、お互いの信頼関係を築くことが可能です。
従業員との信頼関係が生まれれば、「生産性の向上」や「人材の定着率アップ」といったプラスの効果が期待できるでしょう。
社長と従業員の関係性は、目に見えない「会社の資産」です。日々のコミュニケーションを大切にしながら、共に会社の未来を作っていきましょう。
一方で、社長と従業員との関係性を理想の状態にするには、社長と従業員という当事者同士で解決するのは非常に難しいものです。
「自社で解決するのは難しい」と感じる方は、弊社 株式会社Pro-D-useの無料の経営相談をご活用ください。組織再編や、従業員マネジメントに強いコンサルタントが、初回3回までは無料で経営相談を実施しております。まずは以下のボタンから無料の経営相談にお申し込みください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)