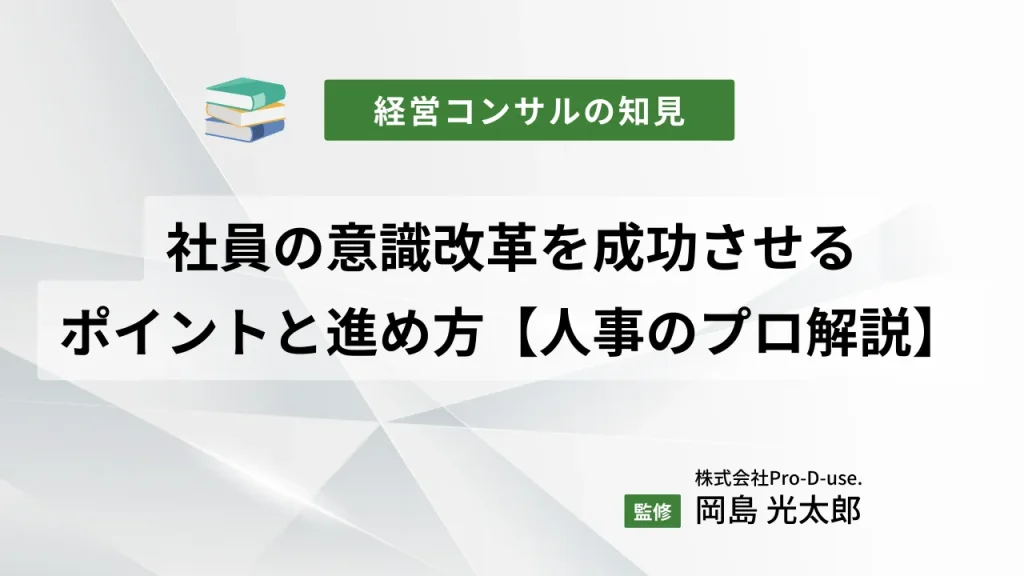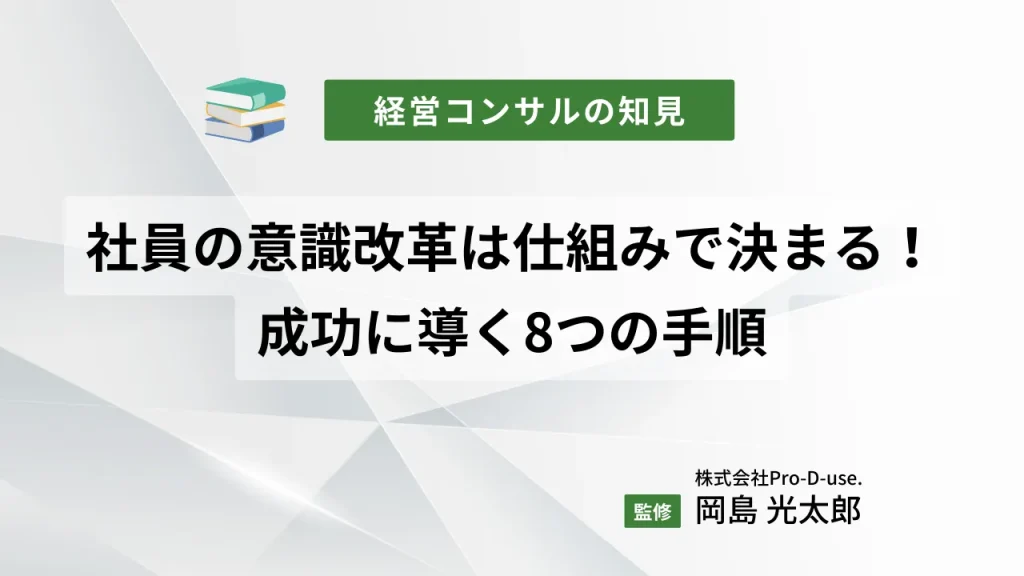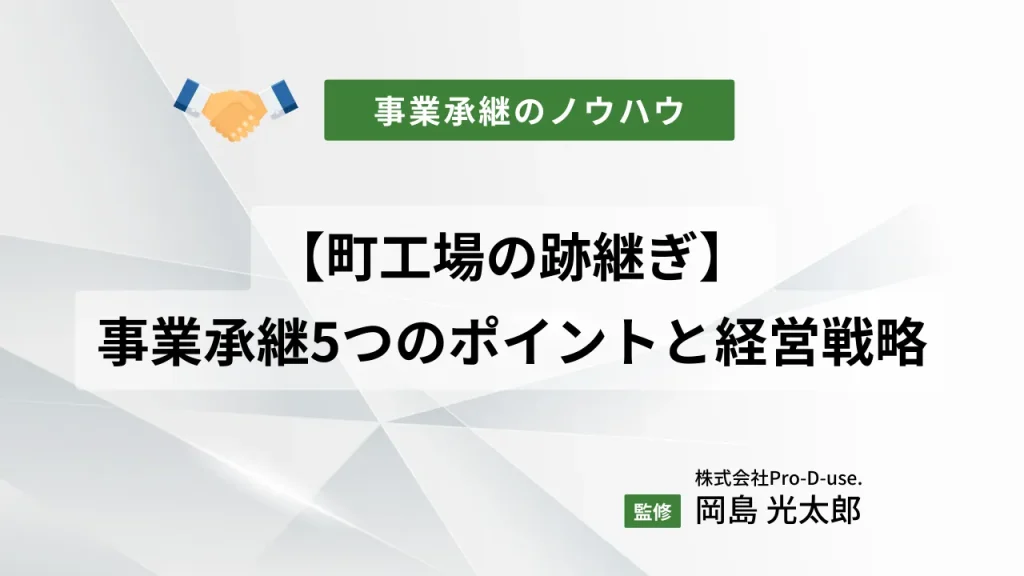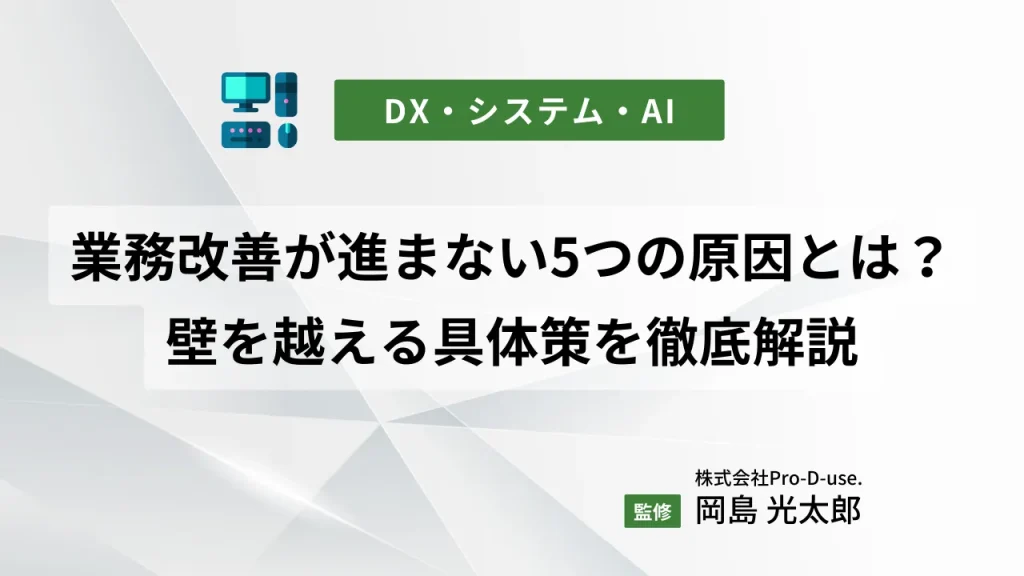社長が嫌われる「5つの原因」と、好かれる社長になる方法を解説
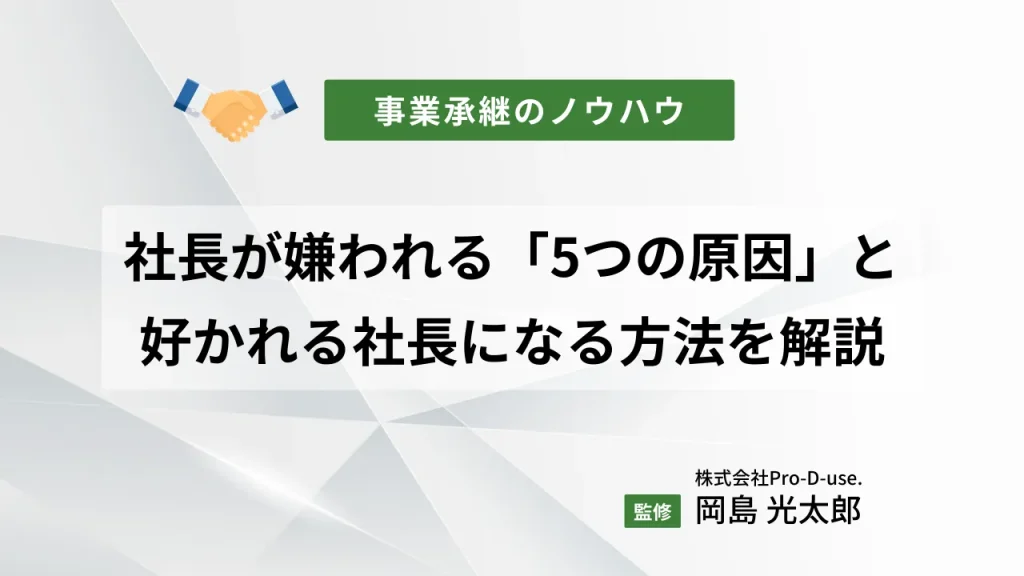
-
- 事業承継
- 経営ノウハウ
- 2025年9月2日
社長が組織を率いる中で、以下のように「社員に嫌われている」と感じたことはありませんか?
- 社員との間に目に見えない壁を感じる
- 指示を出しても社員が期待通りに動いてくれない
- 会社のためを思って下した判断が、かえって反感を招いてしまう
社員との心理的な溝を放置すれば、業務の停滞や優秀な人材の離脱にもつながりかねません。
結論、社長が嫌われる原因は以下の5つに集約されます。
▼社長が嫌われる「5つの原因」
- ワンマン経営をしている
- 社員との会話・軋轢を避けようとする
- 明確な判断を示さない
- ネガティブな態度をとる
- 社員の立場を理解しない
その上で、少しでも従業員との関係性を良好に保つために、社長は以下の取り組みをすべきだと筆者は考えます。
▼社長が嫌われないための取組み例
- 取組み例1. 口だけでなく一生懸命な姿を背中で見せる
- 取組み例2. 定期的なミーティングを実施する
- 取組み例3. 社員が働きやすい環境を整備する
- 取組み例4. 決断の過程を社員にも共有する
筆者は「(株)Pro-D-use」という組織再編に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くの会社の「社長と従業員との関係性の修復」をご支援をしてきました。
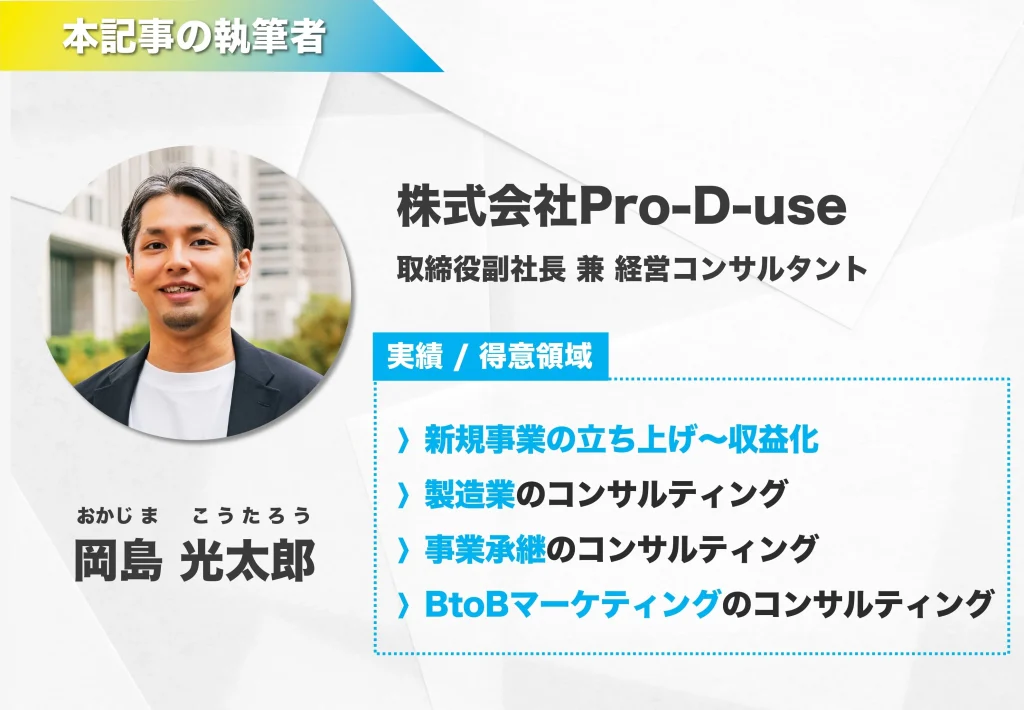
本記事では、そんな筆者の経験をもとに、「社長が社員に嫌われる原因」と、「好かれる社長になる具体的な方法」を解説します。
本記事を読めば社員との関係性を改善し、信頼関係を築くためのヒントが得られます。社員と真摯に向き合いながら、組織全体のパフォーマンスを高めていきましょう。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
目次
社長が嫌われる「5つの原因」
社員から嫌われる社長には共通した特徴があります。社員が「社長についていきたい」と思えない行動を無意識にとってしまうと、信頼関係が崩れる原因になります。社長が嫌われてしまう主な原因は以下のとおりです。
▼社長が嫌われる「5つの原因」
- ワンマン経営をしている
- 社員との会話・軋轢を避けようとする
- 明確な判断を示さない
- ネガティブな態度をとる
- 社員の立場を理解しない
それぞれについて、詳しく解説していきます。
ワンマン経営をしている
ワンマン経営は社長が社員から嫌われる典型的な要因です。社長の判断がすべてで社員の意見が無視され続けると、社員は「自分は尊重されていない」と感じ、やる気を失ってしまいます。
社長の以下の行動はワンマン経営と受け取られやすく、社員の不満を招きます。
▼ワンマン経営と思われてしまう行動
- 社員の意見を聞き入れない
- 一方的に指示を出す
- 裁量を与えない
- 頻繁に方針を変える
ただし、ワンマン経営そのものを一概に否定すべきではありません。中小企業においては意思決定の迅速さや経営者としてのカリスマ性が、組織を前進させる大きな推進力となる場面もあります。
社員との会話・軋轢を避けようとする
社員との会話や意見のすり合わせを避けていると、社長の考えや会社のビジョンが社員に正しく伝わりません。会社の方向性が曖昧になり、社員の行動や判断にも迷いが生じやすくなります。社長は現場の実態を正確に把握できず、最適な経営判断を下すことも難しくなってしまいます。
社長が社員との会話を避け続ければ社員の自主性や意欲が低下し、結果として会社の成長を妨げる要因となりかねません。
明確な判断を示さない
明確な判断を示さない社長は社員からの信頼を損ないやすく、敬遠される存在となる恐れがあります。社長の決断が遅れると社員は会社の方向性がわからなくなり、業務の停滞を招いてしまうためです。
社長の以下の行動は、社員の不信感を招きやすい典型例です。
▼社員の不信感を招きやすい行動例
- 決断を先延ばしにする
- 方針を明示しない
- 結論を避ける
- 発言に一貫性がない
社長の頭の中で方針や意図が整理されていたとしても、社員に正確に伝わっていなければ認識のズレが生じます。
ネガティブな態度をとる
社長のネガティブな態度は社員の意欲を削ぎ、職場全体の雰囲気を悪化させる要因となります。常に不機嫌な態度や否定的な発言を繰り返していれば、社員は安心して意見を述べられず、組織の活力が失われてしまいます。
社員のモチベーションが低下する社長のネガティブな態度は、以下のとおりです。
▼嫌われるネガティブな態度例
- 愚痴をこぼす
- 責任を押しつける
- 提案や報告を否定する
- 失敗ばかりを指摘する
- 不機嫌な態度をとる
社員の士気は経営の土台であり、会社の持続的な発展には欠かせません。
社員の立場を理解しない
社員の立場や状況を考慮せず、自身の価値観や考え方を一方的に押し付ける社長は、社員からの信頼を損ないやすくなります。経営者と社員とでは、物事を見る視点や情報量、責任の重さが大きく異なるためです。社長の視点を基準に物事を判断すると、社員との間に認識のズレが生じてしまいます。
現実を無視した理想論や精神論の押し付け、社員の私生活を軽視する姿勢は、社員の不満を高める大きな要因となります。不公平な評価や責任を社員に転嫁するような対応も信頼関係を損なうリスクが高く、十分な注意が必要です。
社長が嫌われてしまった「2つの事例」
社長が社員から嫌われる行動には典型的なパターンがあります。社員から嫌われる行動を続けていると社員のモチベーションが低下し、会社の生産性にも悪影響を及ぼします。
筆者のクライアントで実際に起きた、社長が嫌われてしまった具体的な事例は以下のとおりです。
- 事例1. 部門間の連携を強要して現場の意見を無視する
- 事例2. 達成が困難な無理難題を提案する
それぞれについて、詳しく解説します。
事例1. 部門間の連携を強要して現場の意見を無視する
筆者のこれまでの経験上、部門間の連携を一方的に指示し、現場の声を顧みない社長の姿勢は社員からの強い反発を招くことが多いと感じています。実態を理解しないまま発せられる指示は「負担の押し付け」と捉えられやすいためです。組織の改善を目的とした指示であっても、進め方を誤れば社内の対立を深めてしまいます。
社員から反発が生じる背景には、部門間連携の目的や将来像が現場に十分に共有されていないことが挙げられます。意義が不明確なまま連携を求められれば、現場としては「業務が増えるだけ」といった懸念を抱くのは自然な反応です。社員からの意見や懸念を一方的に否定してしまうと、信頼関係は大きく損なわれます。
事例2. 達成が困難な無理難題を提案する
現場の状況を踏まえず達成が現実的でない目標を一方的に押し付ける社長の姿勢は、社員からの嫌われる大きな要因となります。十分な計画や支援がない指示では具体的な行動がわからず、社員は困惑するためです。社員は「どうせ無理だ」と感じ、目標に対する納得感や主体性が低下してしまいます。
実際に、筆者のクライアントの社員の方々は、以下のような指示や指示の仕方に不満を募らせていました。
▼実際に不満が出ていた指示の例
- 人員や予算を無視して売上倍増を命じる
- 実情を無視し、他社の成功例をそのまま模倣させる
- 準備不足のまま大規模なシステム変更を強行する
- 課題提起に対し反論を認めず精神論で押し切る
実現性を欠く社長の指示は社員の混乱や反発を招き、会社の推進力を損なう恐れがあります。
社長が社員から嫌われない取組み方法
組織の信頼関係はトップの姿勢次第で大きく左右されます。嫌われない社長になるためには、社員を尊重する姿勢が欠かせません。
社長が社員から嫌われないための具体的な取り組みは以下のとおりです。
▼社長が嫌われないための取組み例
- 取組み例1. 口だけでなく一生懸命な姿を背中で見せる
- 取組み例2. 定期的なミーティングを実施する
- 取組み例3. 社員が働きやすい環境を整備する
- 取組み例4. 決断の過程を社員にも共有する
それぞれについて、詳しく解説していきます。
取組み例1. 口だけでなく、一生懸命な姿を背中で見せる
社員からの信頼を得るためには、単に言葉で指示を出すだけでなく、社長自身が行動で示す姿勢が不可欠です。社長が会社のために取り組む姿を見せることで誠意が社員に伝わり、共感と信頼を得ることにつながります。
日々の業務においては、社長の以下の行動が効果的です。
- 早出や清掃を率先して行う
- 現場で社員と共に業務を担う
- クレーム対応に自ら出向く
- 課題に対して具体的な打開策を講じる
- 一度交わした約束を必ず守る
社長の言動は組織の文化を方向づけ、社員の価値観や行動に強く影響します。
取組み例2. 定期的なミーティングを実施する
社員との信頼関係を築くうえで、定期的なミーティングの実施は欠かせません。社長と社員が直接コミュニケーションを取る機会を設けることで、組織全体の風通しが良くなり、健全な関係性が育まれます。
ミーティングは社長のビジョンや方針を共有する場であると同時に、現場の課題や意見を吸い上げる貴重な機会です。対話を通じて自分の声が経営に反映されていると感じることで、社員の貢献意欲は自然と高まります。
1on1ミーティングでは個々の悩みやキャリアに耳を傾け、チームミーティングでは現場の課題や改善策を共有します。全体会議ではビジョンや経営状況をオープンに伝えることで、組織の方向性を明確にすることが可能です。ミーティングは社長が一方的に話すのではなく、社員が安心して意見を言える環境が求められます。
取組み例3. 社員が働きやすい環境を整備する
社長が社員に嫌われない方法の一つに、社員が働きやすい環境を整えることがあります。職場環境に不満があると、社長への不信感へとつながりやすくなるためです。安心して働ける環境があれば社員は前向きに仕事へ取り組み、社長への信頼も自然と高まります。
社員が働きやすい環境を整えるためには、以下の取り組みが有効です。
- 柔軟な働き方の導入
- 透明性の高い人事評価制度
- ワークライフバランスの確保
- 職場への設備投資
- スキルアップ支援制度の充実
- 福利厚生の整備
環境が整備されている職場では、社員は「自分は大切にされている」と感じやすくなり、仕事への意欲が高まります。働きやすい環境づくりは社員との信頼関係を築き、社長への信頼を深めるうえでも欠かせません。
取組み例4. 決断の過程を社員にも共有する
社長の決断は結果だけでなく、背景や理由も併せて伝えることが重要です。決定事項を一方的に伝えるだけでは、社員は「またトップダウンだ」と不信感を抱く恐れがあります。判断に至った理由を明確に伝えることで、社員は社長の決断に対して納得しやすくなります。
社長が以下の情報を意識的に共有すると、社員の理解を深めることが可能です。
- 検討した他の選択肢
- 目指す未来像や期待する効果
- 想定されるリスクや懸念点
意見交換や質問ができる場を設定することも、社員との信頼関係の構築につながります。社長の誠実な意思決定の共有が、組織の一体感を高める鍵となります。
「嫌われる社長」から「好かれる社長」に変わる4つの方法
社長の姿勢や行動は会社の雰囲気に影響します。社員から好かれるためには、社長自身の意識と行動を変えることが重要です。
社長が好かれるための具体な方法は、以下のとおりです。
▼社長が好かれるための方法
- 方法1. 社長としての姿勢を見直す
- 方法2. オープンなフィードバック環境を作る
- 方法3. 社長のビジョンを社員に共有する
- 方法4. 研修を通じて社員の成長を促す
それぞれについて、詳しく解説していきます。
方法1. 社長としての姿勢を見直す
社員から好かれる社長になるためには、日々の態度や考え方を見直すことが不可欠です。社長の言動は、社員のやる気や職場全体の雰囲気に直接的な影響を与えます。社長が日ごろから意識すべき行動は、以下のとおりです。
- 物事を多角的に捉え、先入観にとらわれない
- 社員の立場に立って気持ちや状況を理解する
- 成果だけでなく努力や過程も認める
- 役職や年齢に関係なく公平に接する
- 感情に流されず、筋道を立てて判断する
- 小さな成果にも感謝や称賛を伝える
基本的な姿勢を日々実践するだけでも、社員からの信頼や評価は大きく変わります。
方法2. オープンなフィードバック環境を作る
社員が安心して意見を伝えられる環境を作ることは、信頼される社長に欠かせない姿勢です。社員が「自分の声が組織の成長につながっている」と実感できれば、主体性や会社への愛着も高まります。風通しの良い職場は、問題の早期発見やアイデアの活性化にもつながります。
社長が実践したい具体的な取り組みは、以下のとおりです。
- 匿名の意見箱やアンケートを設置する
- 意見を真剣に受け止め感謝を伝える
- 意見の反映例を全員に共有する
- 自身の失敗談や苦手なことを率直に話す
社員が安心して声を上げられる仕組みを整えることで、社長との信頼関係はより深まります。
方法3. 社長のビジョンを社員に共有する
社長が会社のビジョンを社員に共有することは、組織の一体感を高めるうえで欠かせません。会社の目指す方向が見えなければ、社員は日々の業務に意味を見出しにくくなるためです。ビジョンを明確に示すことで社員一人ひとりが仕事の意義を理解し、共通の目標に向かって協力し合えるようになります。
社長が会社のビジョンを社員に伝える際には、抽象的な表現ではなく具体的な言葉で示すことが重要です。ビジョンを日常業務にどう結びつけるかを明確にし、社長自らが実践することで社員の理解と行動につながりやすくなります。
社長が未来に向けたビジョンを示し続けることで、社員は安心して挑戦でき、組織全体の結束も強まります。
方法4. 研修を通じて社員の成長を促す
社員が自身の成長を実感できる機会を作ることは、社長への信頼を高める有効な手段です。学びを通じてスキルやキャリアを磨ける場があることで、社員は「会社が自分の将来を支えてくれている」と感じやすくなります。
効果的な取り組み例は以下のとおりです。
- 個々のキャリア目標に沿った研修プログラムを設ける
- 資格取得や外部セミナー参加を金銭的にサポートする
- 役職や経験年数ごとに必要な知識を学べる研修を実施する
- 社長自らが将来像を語り、学びの方向性を示す
- 研修内容を業務に結びつけ、成果を共有する場を設ける
研修制度を充実させることで、社員は「成長できる職場」で働いている実感を持ち、組織全体の活力と信頼関係の強化につながります。
» 厚生労働省「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」(外部サイト)
» 厚生労働省「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」(外部サイト)
» 経済産業省「中小企業のためのダイバーシティ経営」(外部サイト)
社長が果たすべき「3つの役割」
社長には会社の未来のために決断を下し、結果に責任を持つ強い覚悟が不可欠です。覚悟を行動で示すために、社長には以下の役割が求められます。
▼社長が果たすべき「役割」
- 役割1. 社長は嫌われる勇気を持つ
- 役割2. 社長自らが向上心を常に忘れない
- 役割3. 地域や社会に貢献する
それぞれについて、詳しく解説していきます。
役割1. 社長は嫌われる勇気を持つ
社長に求められることは、嫌われることを恐れずに決断する勇気です。組織の再建には人員の見直しやルールの変更など、社員に負担がかかる決断が必要になることもあるためです。すべての人に好かれようとする姿勢は中途半端な判断を招き、結果的に経営の停滞につながります。
社長の役割は組織を正しい方向に導き、社員の生活を守ることです。社員からの反発を恐れず、会社の未来を最優先に考える強い意志が求められます。
役割2. 社長自らが向上心を常に忘れない
社長が向上心を持って学び続ける姿勢は、会社の成長に欠かせません。挑戦する姿勢を社員に示すことで、会社に前向きな空気が生まれます。
社長には具体的に以下の行動が求められます。
▼社長が「向上心を示す行動例」
- 業界の最新トレンドや技術を継続的に学ぶ
- 過去の成功に固執せず、変化に応じて柔軟に対応する
- 異業種の経営者との交流やセミナーで外部の視点を吸収する
社長が変化を恐れず挑む姿を見せることで、社内にチャレンジする空気が広がります。
役割3. 地域や社会に貢献する
社長は利益の追求だけでなく、地域や社会への貢献も欠かせません。地域に役立つ取り組みは会社の信頼を高め、事業の安定にもつながります。
社長は具体的に以下の形で地域や社会に貢献できます。
▼地域・社会貢献の例
- 安定した雇用の創出
- 地元企業との取引を通じた経済の活性化
- 地域イベントや活動への参加・協賛
- 納税を通じた公共サービスの支援
- 地元学生へのインターン・職業体験の提供
地域に根ざした存在となることで、会社への信頼と評価が高まります。
「嫌われる社長」と「好かれる社長」には明確な違いがある!
社員から好かれる社長と嫌われる社長には、日々の言動や姿勢に明確な違いがあります。嫌われる社長に共通することは、一方的な指示や曖昧な判断、社員を軽視する態度です。
一方、好かれる社長は社員との対話を大切にし、決断の背景を丁寧に説明します。社員の成長を支援し、自ら率先して行動する姿勢と最終的な責任を負う覚悟を持っています。明確なビジョンを掲げ、社員とともに成長しようとする姿勢こそが信頼されるリーダーの条件です。
社員に好かれる社長になるためには、自らの姿勢を見直し、社員が話しやすい環境を整えることが大切です。社員との信頼関係を育みながら、会社を成長させていきましょう。
» 社長と従業員の理想的な関係を築くステップを徹底解説!
なお、社長と従業員との関係を理想の状態にするには、社長と従業員という当事者同士で解決するのは非常に難しいものです。
「自社で解決するのは難しい」と感じる方は、弊社 株式会社Pro-D-useの無料の経営相談をご活用ください。組織再編や、従業員マネジメントに強いコンサルタントが、初回3回までは無料で経営相談を実施しております。まずは以下のボタンから無料の経営相談にお申し込みください。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)