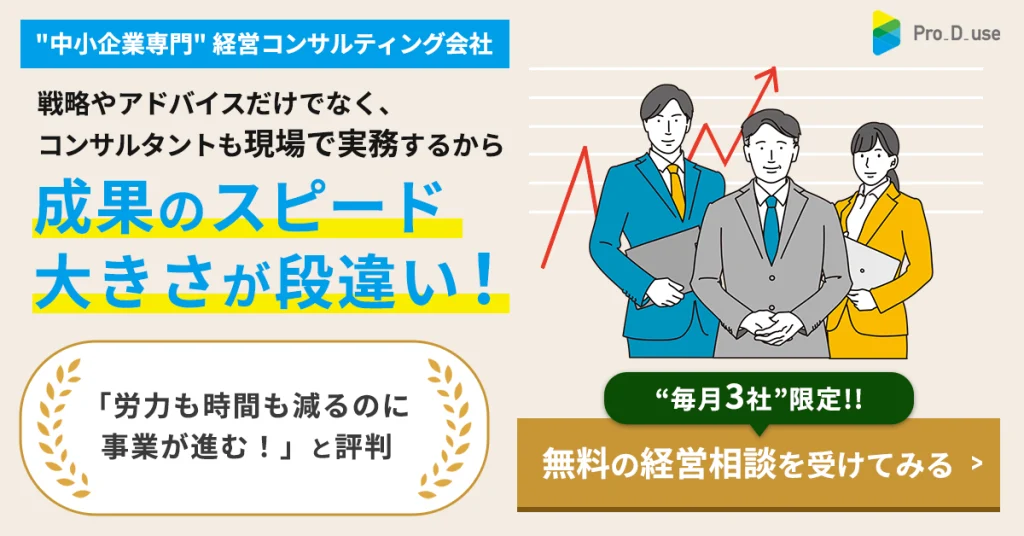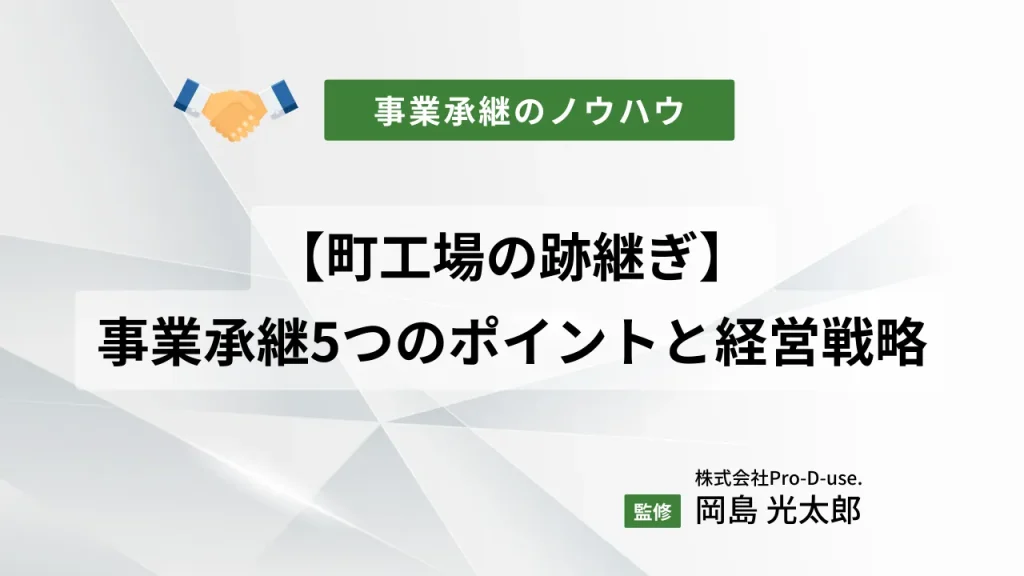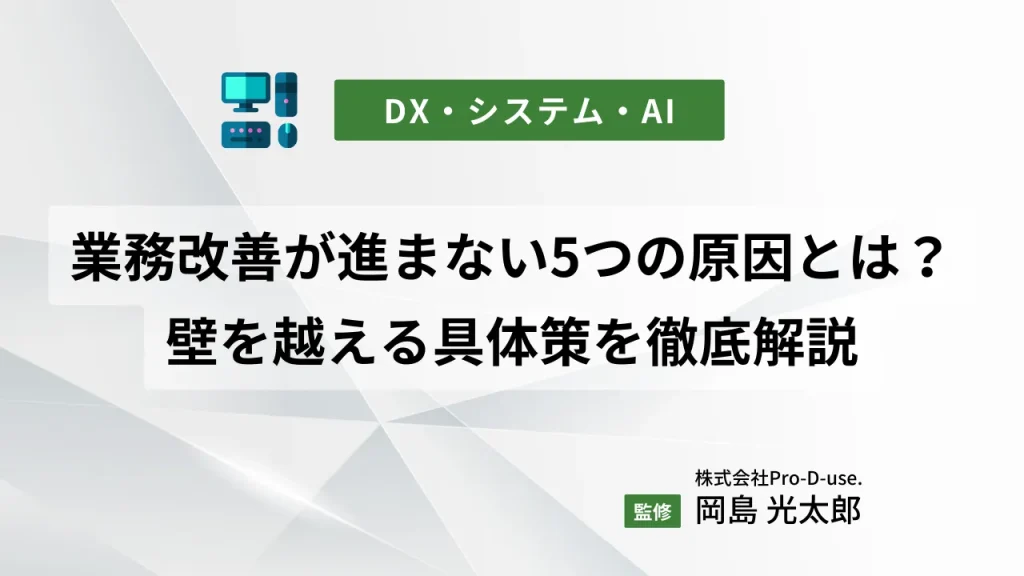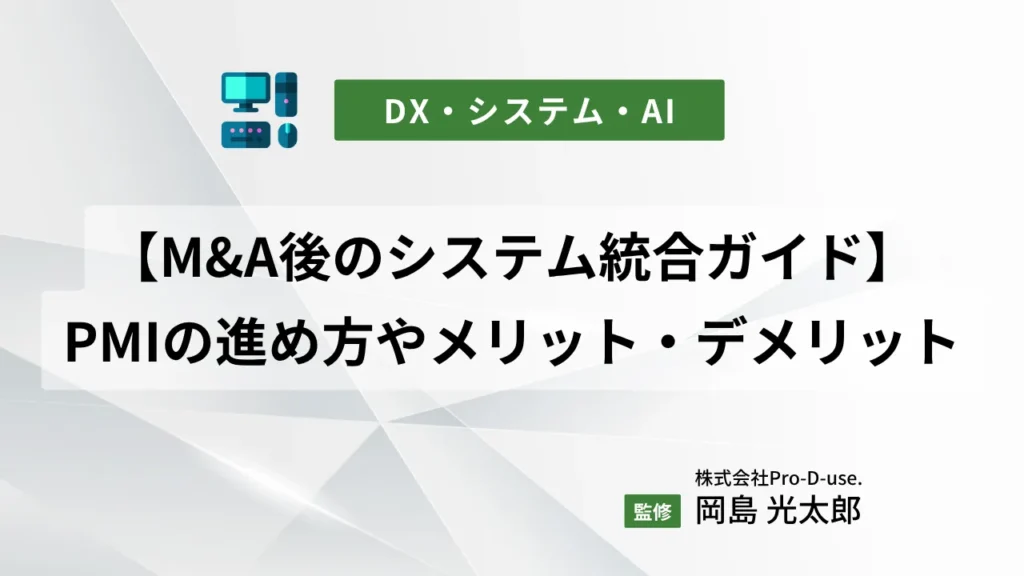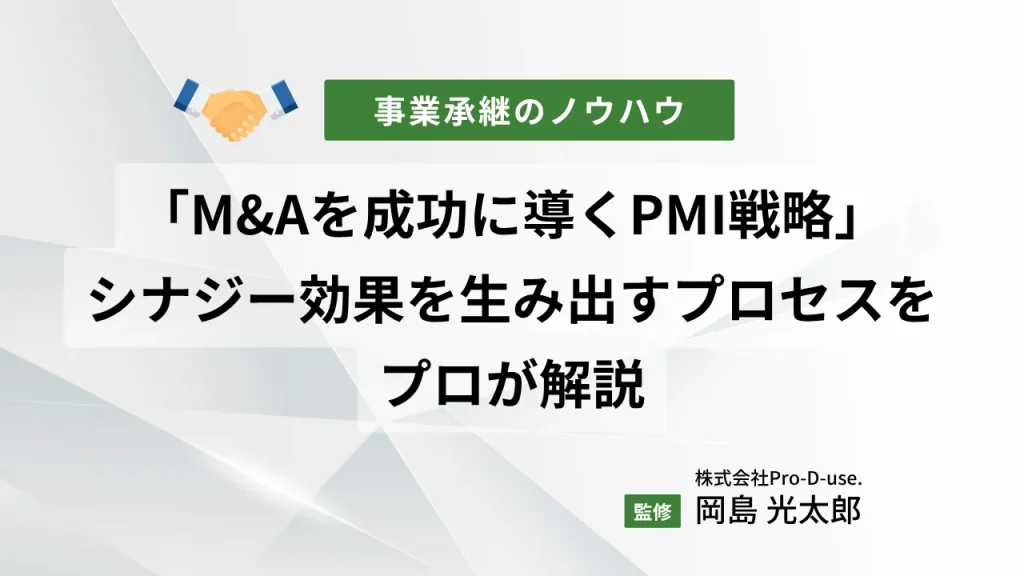中堅社員が「会社を辞める5つの理由」と「6つの退職防止策」
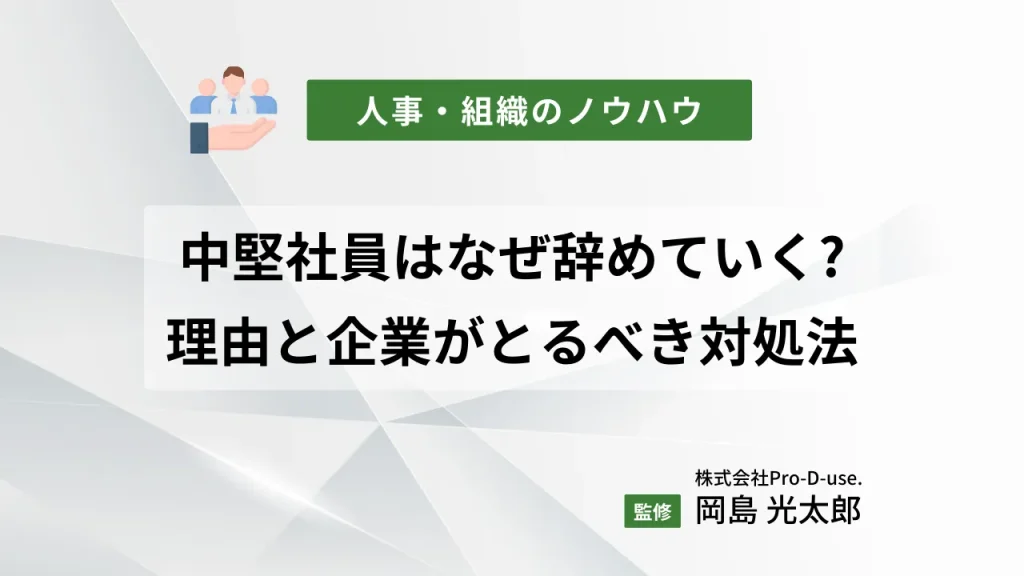
-
- 経営ノウハウ
- 2024年9月25日
中堅社員とは一般的に役職がない入社3年目以降の社員で、年齢的には20代後半〜30代を指します。
中堅社員は現場での中心人物となる人材であり、新人や若手の育成にも欠かせません。管理職と現場の調整をして、円滑に業務を進められるため中堅社員の企業への影響力や貢献度は大きく、会社にとってなくてはならない存在です。
仕事のできる優秀な中堅社員が辞めてしまうことに、絶望して途方に暮れている経営者は以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
「丁寧に育ててきたはずの中堅社員が辞めてしまうのは、なぜ?」
「給料は他社より良いはずなのに、なぜ退職してしまうのか…。」
「いきなり中堅社員が辞めると業務が回らないため、困るっている」
中堅社員は長く勤めてくれる方が多いため、「安定して貢献してくれる」思われがちですが、実は中堅社員ほど、会社組織の雰囲気に敏感で、表に出さないストレスが溜まっているものです。
筆者は「株式会社Pro-D-use」という経営コンサルティング会社で、これまでたくさんの「中堅社員」のマネジメントに携わってきました。
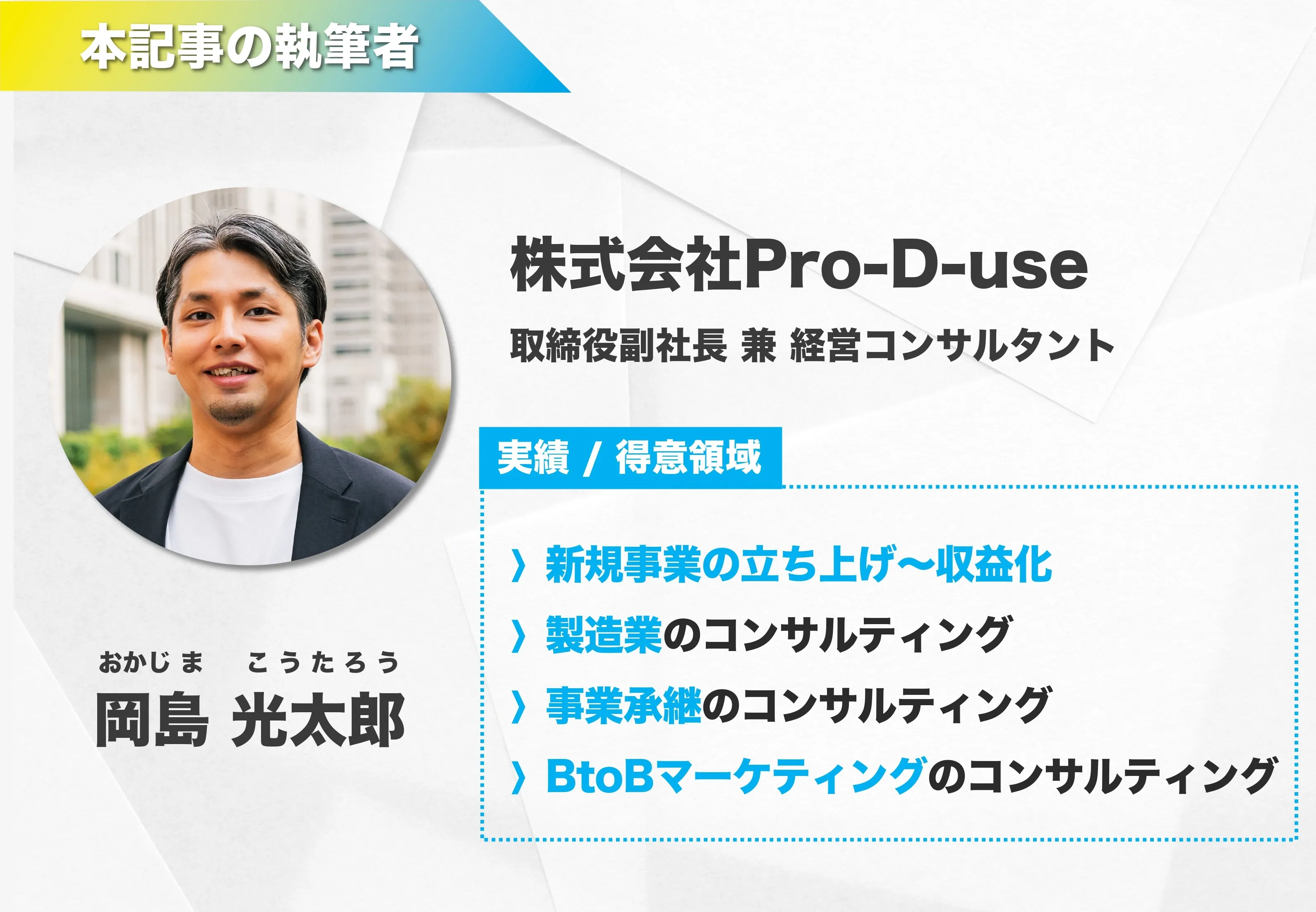
本記事では、中堅社員が退職を考える経緯や阻止するための対策といった、重要なポイントについて解説します。
中堅社員が辞めないためにできる企業としての注意点は以下。
◆中堅社員が辞めないための注意点
- 社員にとっての「働きやすさ」をはき違えない
- 中堅社員が求めているものを明確にし、環境作りをする
- 中堅社員の存在は企業にとって重要であると再確認する
この記事を読めば、こんな事が実現できます。
- 中堅社員の退職が防げるようになり、後輩社員の育成にもつながる
- 企業としての体制を見直し、柔軟なシステムが構築できる
- 社員全体の意識向上のポイントを熟知し、業績に反映させる
今回の記事を参考に、中堅社員の退職について理解を深めてみてください。
また当社では「エース社員のやる気がないのはなぜ?効果的な改善策と退職を防ぐための方法」についても解説していますので、詳しく知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
あわせて読みたい
エース社員のやる気がないのはなぜ?効果的な改善策と退職を防ぐための方法
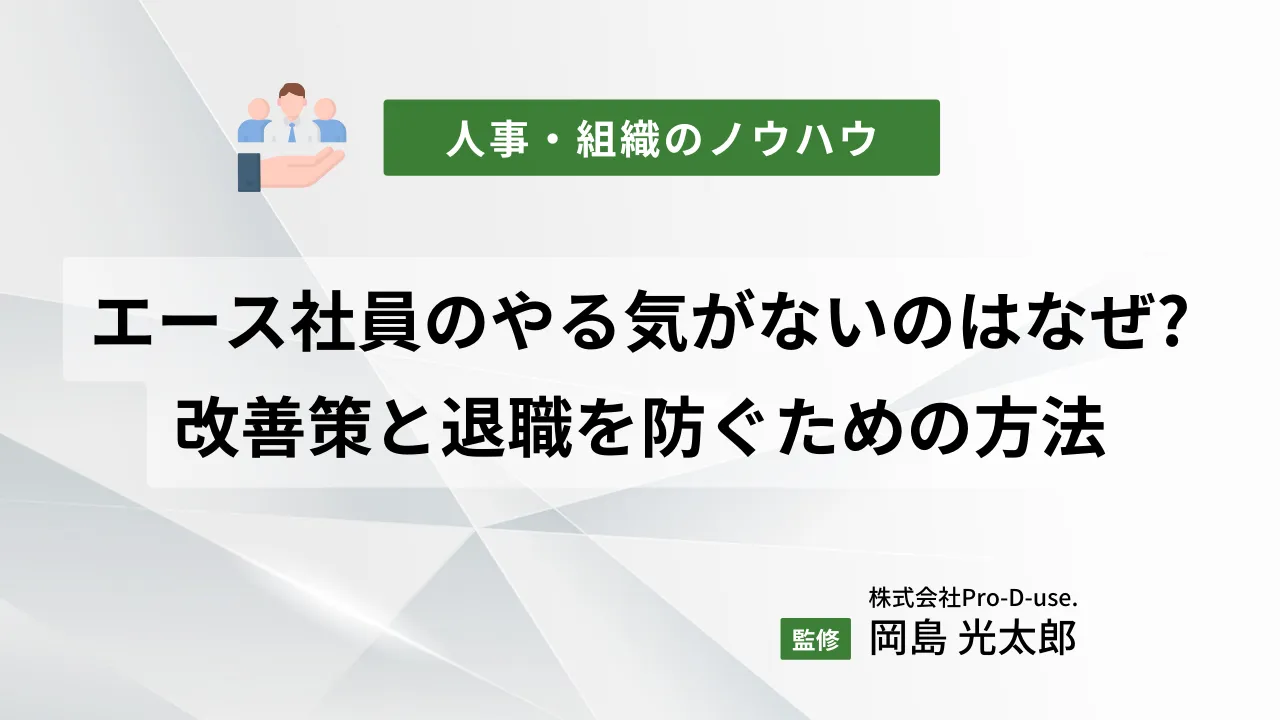
以前と比べると、エース社員として期待している人のやる気がないと悩んではいませんか? 実は、エース社員は自社での成長の機会に見切りをつけてしまっているかもしれません。なぜなら、エース社員は本質的に能力が高く、活躍できるスキルを持っているので、…
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/
目次
せっかく育ててきた中堅社員が、入社3年で退職してしまった事例
「せっかく育ってきた中堅社員が、入社3年で辞めてしまった…」これは、弊社のクライアントのとあるIT企業の人事担当者がこぼした言葉です。
その社員は中途採用で入社して3年が経過。業務にも十分に慣れ、チームの中心として活躍していました。しかし、ある時期から徐々に仕事への意欲が低下し、やがては退職意思を申し出てきました。
◆中堅社員が不満に思っていたこと
「今の職場ではこれ以上成長が見込めない」
「将来のキャリアが描けない」
中堅社員は、以上の理由で退職を申し出ました。
さらに驚くべきことに、その後数カ月のうちに、他の中堅クラスの社員2名も退職を決意。理由を聞くと「評価が曖昧で、努力が報われる実感がない」「社内の空気が重い」といった声が上がりました。このように、明確なキャリアパスが示されないことや、評価制度への不満、職場環境の不安定さが、中堅・中途社員の早期退職につながる事例は少なくありません。
中堅社員が辞めていく5つの理由
本来であれば社内の中心にいるはずの中堅社員が辞めていくのには、このような理由が考えられます。
◆中堅社員が辞めていく5つの理由
- 仕事に慣れてやりがいを感じない
- 自分のキャリアに不安を抱えている
- ライフスタイルが変化した
- 評価や待遇に不満を感じている
- 人間関係が良好ではない
それでは、5つの理由を1つずつ解説してまいります。
理由1. 仕事に慣れてやりがいを感じない
若手の頃とは違い、中堅になると業務に慣れており、こなすスピードも早くなっています。上司にとっては仕事が振りやすい存在となりますので、中堅社員はルーティーンワークをこなす日が増えていきます。
すると仕事内容に新鮮味がなくなり、こなすだけの業務が大半を占めるようになります。自身での成長も感じられず、仕事にやりがいを感じられなくなってしまいます。
理由2. 自分のキャリアに不安を抱えている
若手の頃は社内で研修を受ける機会がありますが、中堅社員になると教育が受け終わった立場になるケースも多いです。中堅社員は自身の成長が停滞しているように感じ、将来のキャリアに不安を抱えるようになっていきます。
また会社の将来性に不安を感じた中堅社員も、自分の将来と重ね合わせて退職を考えるようになります。優秀な人材ほどシビアに将来を考えていきますので、中堅社員にもステップアップの機会を設けるように対策をしてくべきです。
理由3. ライフスタイルが変化した
中堅社員とは20代後半~30代なので、結婚や出産などライフスタイルが変化していく時期でもあります。独身時代は仕事中心の生活をしていたとしても、家族やプライベートの時間を充実させたいと考えるようになっていきます。
希望をしても、残業が常習化していて聞き入れてもらえない状態だと、柔軟に働ける企業へ転職したいと考えても無理はありません。管理職もこれらの考え方を理解し、ワークライフバランスへの意識を持つようにしましょう。
理由4. 評価や待遇に不満を感じている
中堅社員は同期入社社員との格差を感じている場合もあります。
「自分だけ正当に評価されていない」「相応しい報酬が受け取れていない」と感じていると、退職を考えるキッカケとなります。自己評価との開きがあると、公正な評価をされていないと不満が溜まってしまいます。
正当な評価と共に、仕事内容に見合った報酬が設定されているかも重要です。
理由5. 人間関係が良好ではない
中堅社員に限らず、人間関係の良し悪しは退職の大きな理由のひとつです。仕事の内容や評価に不満がなかったとしても、人間関係が悪いと仕事を続けていくのは難しくなるでしょう。
中堅社員は上司や若手社員との双方と接する機会が多く、人間関係のストレスを抱えやすい環境にいます。周囲への気遣いができる人が意外とストレスを溜めているというケースもありますので、社内の人間関係を良好に保てているかを見直してみましょう。
中堅社員が辞めていくと出る4つの影響
働きざかりの中堅社員が突然辞めてしまうと、社内にはこのような影響がでると考えられます。
◆中堅社員が辞めてしまうと社内に出る4つの影響
- 社内の雰囲気が悪くなる
- 業務に支障がでる
- 退職が連鎖する
- 新規雇用・社員育成にコストがかかる
影響1. 社内の雰囲気が悪くなる
中堅社員は管理職と若手社員の橋渡し的な存在であり、社内の雰囲気を保っていてくれている存在だと言っても過言ではありません。その中堅社員がいなくなると、その他の社員の不満が溜まり、雰囲気が悪くなってしまいます。
コミュニケーションがうまく行かなくなり、上下間の雰囲気が悪くなると会社の業績にも影響を及ぼしかねません。
社内の雰囲気が悪くなると残された社員は働きにくさを感じ、会社に不満を募らせるようになっていく可能性もあります。
影響2. 業務に支障がでる
中堅社員が辞めると、単純に残された社員への負担が増えます。多くの業務を辞めた中堅社員に頼り切っていた部署では、負担する業務の難易度も高くなるでしょう。
辞めた中堅社員の業務を負担に感じて、不満を溜める社員も出てきたり、全体的に業務が円滑に回らなくなるという問題も発生します。
経験を積んでいる中堅社員が辞めてしまうと、一時的に生産性の低下が懸念されます。
影響3. 退職が連鎖する
仕事を辞めるか否かの判断は、個人の自由です。しかし中堅社員が1人退職した事実を「たった1人が辞めただけ」と楽観視していると、退職の連鎖が起きてしまうかもしれません。
優秀な中堅社員が辞めると、「あの人が辞めるなら私も辞めよう」「あの人が辞めるなら将来性のない会社なのかも」と考える社員も出てきます。中堅社員が辞めるのには会社に原因があると捉え、退職の連鎖が起きないように早めに対策をしていきましょう。
影響4. 新規雇用・社員育成にコストがかかる
中堅社員が辞めた分、新規雇用や社員育成をしていく必要があります。経験を積んだ中堅社員のように自走できる社員に育てるためには、時間もお金もかかってしまいます。
辞めた中堅社員の穴埋めは、簡単ではありません。教育コストがかかるだけでなく、教育担当者の分の利益も失われますので、中堅社員の退職は会社としてリスクとなります。
中堅社員を辞めさせないための6つの対策
中堅社員が辞めてしまうと多くのリスクがありますので、「辞めたい」と思わないような職場作りをしていく必要があります。
中堅社員を辞めさせないために、これらの対策に取り組んでみましょう。
◆中堅社員を辞めさせないための6つの対策
- 中堅社員の業務内容を見直す
- 人事評価制度を見直す
- 人員配置をライフスタイルに合わせる
- キャリアプランを明確にする
- キャリアアップのため選択型研修を活用する
- コミュニケーションを活発化させる
対策1. 中堅社員の業務内容を見直す
中堅社員は知識や経験、スキルがありますので、つい業務が集中してしまいます。
しかし自身はキャリアアップを求めており、成長の機会を望んでいますので、誰でもできるような業務ではなく、やりがいのある業務を振っていきましょう。新しい仕事や責任のあるポジションを任せてみると、仕事にやりがいを感じられます。中堅社員の持つ能力を発揮できる機会を与えられれば、会社にとってもプラスになるはずです。
例えば、以下のような対策があるので、参考にしてみてください。
◆中堅社員の業務見直しの具体的対策
- 業務棚卸しを実施し、「誰でもできる業務」と「中堅社員が担うべき業務」を明確に分ける
- 定型業務は若手や外部パートナーへ移管し、中堅社員にはプロジェクト型業務を割り当てる
- 中堅社員向けの「社内メンター」「育成担当」など、責任ある役割を正式に任命する
- 他部署との合同プロジェクトへの参加機会を提供し、視野とスキルの幅を広げる
- 「中堅社員の挑戦枠」として、社内公募制度や新規提案制度を設ける
対策2. 人事評価制度を見直す
仕事をする以上はやりがいも重要ですが、報酬に関する条件も無視できません。業務への取り組みや貢献を明確に評価できる制度は、整っているでしょうか。
昇給や昇格といった目に見える形で表し、自己評価と会社からの評価のズレがないようにしておきましょう。適切な評価制度があれば社員のモチベーションにもつながり、顧客満足度や会社の業績にも良い影響を及ぼすでしょう。
例えば、以下のような対策があるので、参考にしてみてください。
◆人事評価制度の見直しの具体的対策
- 評価基準を明文化し、全社員に共有する
- 半期または四半期ごとのフィードバック面談を必須化し、評価内容を口頭で説明する
- 自己評価シートを導入し、上司との認識のズレを事前に洗い出す
- 「昇給・昇格の条件(例:○○スキル取得、○件以上の案件担当)」を具体的に提示する
- 評価制度に対する社員アンケートを年1回実施し、継続的な見直しに反映する
対策3. 人員配置をライフスタイルに合わせる
中堅社員のライフスタイルの変化を無視せずに、人員配置に反映してみましょう。
女性は年齢によって大きな変化がでるのは当然ですし、昨今では男性にも同様の配慮が必要です。「残業ができない」「業務時間が限られる」「リモート業務を望んでいる」という希望を的確に考慮し、人員配置に反映させます。
本人が「辞めたくない」という意志を持っているのであれば、なおさら急いでこの制度を整えなければいけません。このような柔軟な体制が整えば、若手社員にとっても長く働きたい会社だという認識となります。将来的な中堅社員の離職防止にもつながっていくでしょう。
例えば、以下のような対策があるので、参考にしてみてください。
◆人事配置の柔軟化への具体的対策
- 定期的なライフスタイルに関するヒアリング(育児・介護・通勤事情など)を実施する
- 希望勤務スタイル(時短勤務、リモート、フレックスなど)を選択できる制度を整備する
- 異動や配置換えの際は、本人の意思を確認する面談を必須とする
- 勤務地・業務内容に関する社内公募制度を導入し、自主的なキャリア選択を支援する
- 子育て・介護中社員向けの短時間正社員制度や限定業務制度を導入する
- 一時的な業務量調整(繁忙期のサポートチーム配備など)で無理のない働き方を支援する
対策4. キャリアプランを明確にする
評価制度や人間関係に満足していたとしても、自身のキャリアプランに不安があると退職の理由のひとつになります。一方的に示すのではなく、ミーティングをして中堅社員自身の意見を聞いた上で、キャリアプランを話合っていきましょう。
「今感じている不安」「今後取り組んでいきたい内容」「身に着けたいスキル」などを理解し、
この会社で仕事を続ける理由が見出せると退職の防止になります。
例えば、以下のような対策があるので、参考にしてみてください。
◆キャリアプランの明確化のための具体的対策
- 半期に1度、上司とキャリアプランについて話し合う個別面談(キャリア面談)を実施する
- 「今感じている不安」「今後やりたい業務」「身につけたいスキル」などのヒアリング項目を事前に用意する
- 各職種・等級に応じたスキルマップを社内に提示し、成長ステップの見える化を図る
- 3〜5年後の目標とその実現に必要なスキル・経験を一緒に言語化し、プランとして共有する
- 社内のロールモデル社員を紹介し、具体的なキャリア像をイメージしやすくする
- キャリア希望に沿った研修や外部セミナー参加を支援する制度を導入する
対策5. キャリアアップのため選択型研修を活用する
中堅社員のキャリアアップのため、選択型研修を取り入れていきましょう。選択型研修は、自身のキャリアアップに沿った研修が受けられます。
「新人だから新人研修」「管理職には管理職研修」という枠組みを取っ払い、社員それぞれが自分の意志で選択しスキルを身に着けていきます。自身で受講内容を選択するため、キャリアについて深く考えるキッカケにもなりますし、社員の自主性を重んじる研修スタイルなので、会社としてもメリットになると考えられます。
例えば、以下のような対策があるので、参考にしてみてください。
◆キャリアアップの選択型研修活用のための具体例
- 管理職志望者向け、専門職志望者向け、マネジメント未経験者向けなど、多様なコースを用意する
- 「研修受講申請制度」を整備し、社員が自らの意志で研修に応募できる仕組みを設ける
- 研修選択の前後で上司と面談を行い、目的や期待効果をすり合わせる
- 外部研修プログラムの受講費補助制度を導入し、社外の知見も柔軟に取り入れられる環境を整える
対策6. コミュニケーションを活発化させる
良い人間関係を築くには、活発なコミュニケーションが欠かせません。
定期的な話合いや1on1ミーティングができれば望ましいですが、まずはちょっとした挨拶からでも雰囲気作りができます。信頼関係ができていると安心した環境での業務ができますので、チームで力を発揮できるようになります。ちょっとした質問や相談もしやすくなるので、大きなトラブルの芽を早めに摘めるというメリットもあります。
社内イベントを計画してもいいですし、雰囲気に合わせてコミュニケーションの活発化を促していきましょう。
例えば、以下のような対策があるので、参考にしてみてください。
◆コミュニケーションを活発化させるのための具体例
- 上司と部下の定期的な1on1ミーティングを月1回以上実施する制度を設ける
- 雑談・軽い相談ができる「オンライン雑談タイム」やチャットツールの雑談チャンネルを活用する
- 担当業務に関係ない「社内勉強会」「ランチ会」などを定期開催して交流の場をつくる
- 新人・中堅社員同士の交流促進のため、世代をまたいだペアランチやシャドーイング制度を設ける
- イベントは強制ではなく任意参加とし、負担なく楽しく交流できる雰囲気を醸成する
中堅社員が辞めて困った時の3つの対処法
中堅社員が辞めないよう事前に対策できればいいですが、それでも退職をしてしまう場合もあるでしょう。
中堅社員が抜けると大きな負担になりますので、応急処置としてこのような対処法があります。
◆中堅社員が辞めて困った時にできる3つの対処法
- フリーランスを頼る
- 副業人材を頼る
- 派遣社員を雇う
フリーランスや副業人材はスキルがありますので、新しい社員を育てる時間がない時に活躍してくれるでしょう。
社員を雇うよりも低コストで、週10~30時間程度雇いたい時に向いています。
専門的な業務を求めないのであれば、派遣社員を雇うのも方法のひとつです。
大量採用もできるので、とにかく業務を回したいという時に活用するといいでしょう。
中堅社員が辞めない離職率が低い業界とは
職業の種類によって、離職率が異なります。
厚生労働省の令和5年雇用動向調査結果の概況によると、離職率の低い業界ランキングと離職率はこのようになっています。
◆「中堅社員が辞めない」離職率の低い業界とは?
| 順位 | 業種 | 離職率 |
|---|---|---|
| 1位 | 複合サービス事業 | 6.8% |
| 2位 | 製造業 | 8.7% |
| 3位 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 9.3% |
| 4位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9.4% |
| 5位 | 教育・学習支援業 | 9.5% |
| 6位 | 建設業 | 10.3% |
| 7位 | 金融業・保険業 | 10.6% |
| 8位 | 情報通信業 | 12.4% |
| 9位 | 不動産業・物品賃貸業 | 13.4% |
人の生活に欠かせないインフラや、業績が安定している業種が離職率が低い傾向にあります。
長く働ける環境が整っている、給与水準が高いといった条件が合うと、離職率が低くなるとわかります。
離職率が低い会社のデメリット
中堅社員の離職は最低限に抑えていきたいですが、離職率が低すぎる企業にはデメリットも出てきます。
◆離職率が低い会社のデメリット
- 企業内で少子高齢化が起こる
- ポストが空かないので昇進できない
- 組織としてマンネリ化する
離職率が低くてもこのようなデメリットがありますので、「離職率を下げる」というよりも、
働きやすい職場作りを目標に風通しのよい雰囲気を目指していきましょう。
辞めていくのは中堅社員だけでなく、若手社員も!
辞めていくのは中堅社員だけではありません。若手社員も退職するケースは増えています。特に「Z世代」と呼ばれる1990年代後半〜2000年代生まれの世代では、入社後3年以内に退職するケースが目立っています。その理由として、以下のような傾向が見えてきます。
◆Z世代の若手社員の退職理由
- 1位:キャリア・個人成長(31.7%)
- 2位:仕事へのやりがい(20.2%)
- 3位:人間関係・社風(20.0%)
- 4位:ワーク・ライフ・バランス(18.5%)
- 5位:給与・待遇面(5.6%)
- 6位:安定性(4.0%)
そりゃ辞めるわ…「3年以内に退職したZ世代」の退職理由ランキング…ワースト2位は「やりがい」、では1位は?
https://diamond.jp/articles/-/360287
最も多かったのは「キャリア・個人成長」で約3割を占めています。Z世代は自身の成長に対する意識が非常に高く、会社の中でスキルアップやキャリアの展望が感じられないと、比較的早い段階で転職を選択する傾向があります。
また、2位の「仕事へのやりがい」や3位の「人間関係・社風」も、彼らが“心理的な満足”を重要視していることを示しています。Z世代は単に待遇や安定性ではなく、「自分が納得して働ける環境か」を重視しているのです。
この傾向から見えてくるのは「給与を上げれば辞めない」といった古い常識ではZ世代には通用しないという現実です。企業側には、彼らが成長を実感できる環境づくり、仕事の意義や期待をきちんと伝えるマネジメント、そしてフラットで風通しのよい組織文化の構築が求められます。そのためこの記事で紹介した中堅社員を辞めさせないための対策を実施して、中堅・若手全ての社員に対して対策する必要があるのです。
中堅社員の求めているものを明確に
中堅社員は、自身のキャリアアップや仕事へのやりがいを考えると、退職し新しい職場の方が活躍できるのではないかと考えます。
同じ職場で数年働いていれば外の景色を見てみたいと考えるのは、ある意味健全な傾向なのかもしれません。
しかし手塩にかけて教育してきた中堅社員が辞めていくのは、会社にとって損失になります。
「今の会社で何ができるのか」「中堅社員の求めているものは何なのか」を、見直してみましょう。
新しい制度への改革は、将来的に働きやすい環境を作るための第一歩となります。
経営コンサルタント選びは「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社に貢献するコンサルタントを選ぶなら、多角的な視点で選定しましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「はじめての経営コンサルタント」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」に経営相談をしてみませんか?詳しくは以下のサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useのコンサルの詳細を見る >>
\【伴走型の経営コンサル】探してるなら/