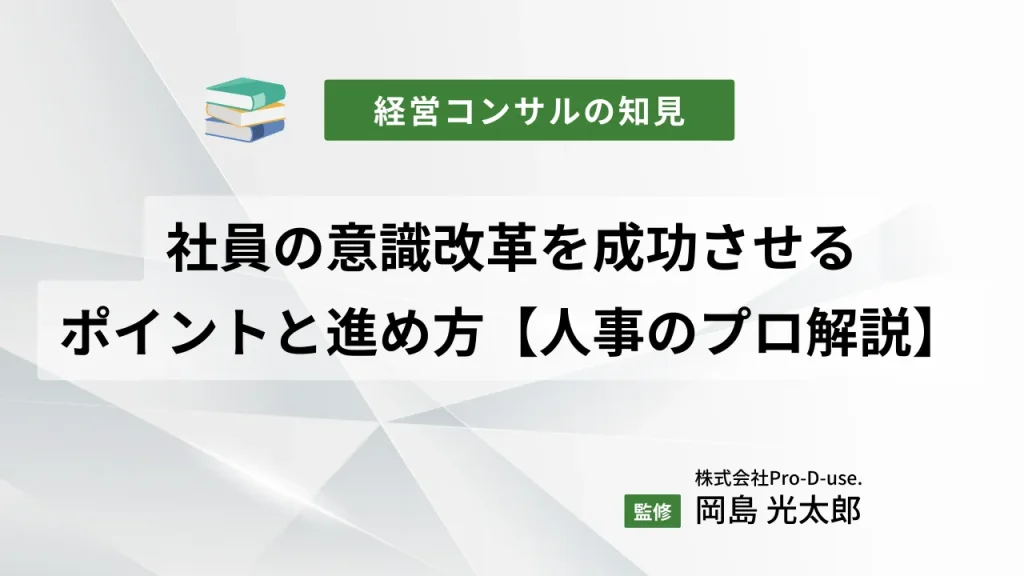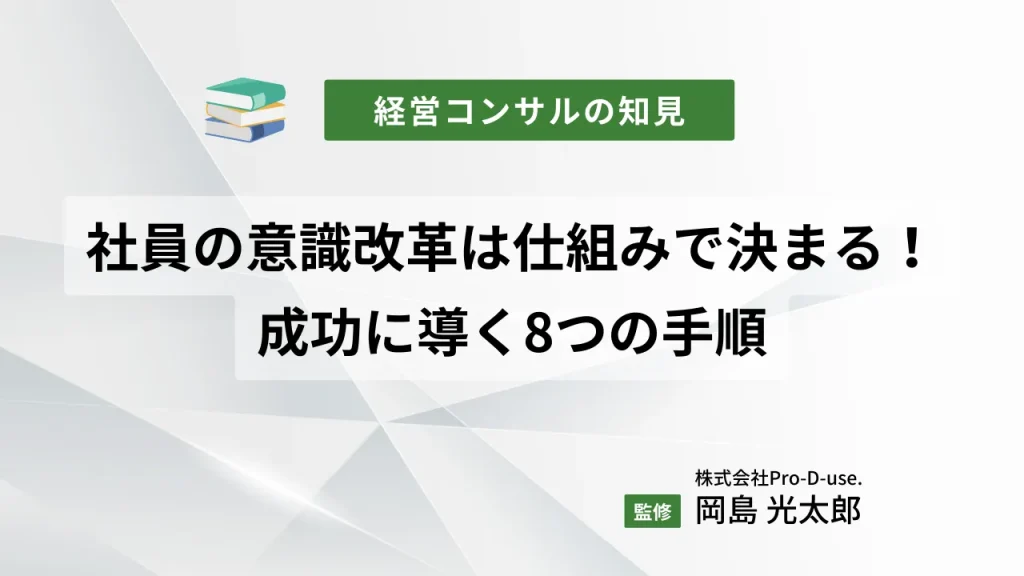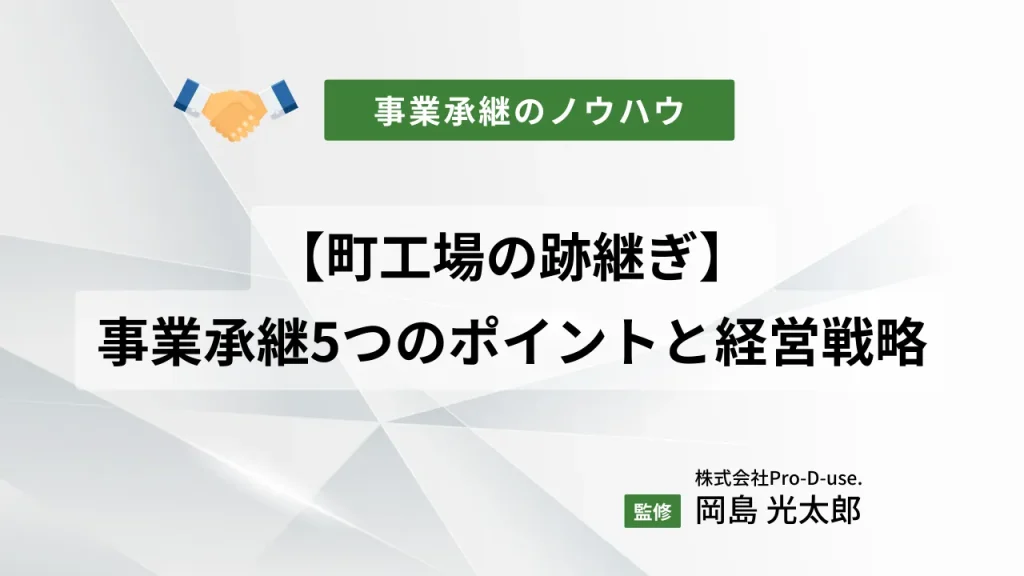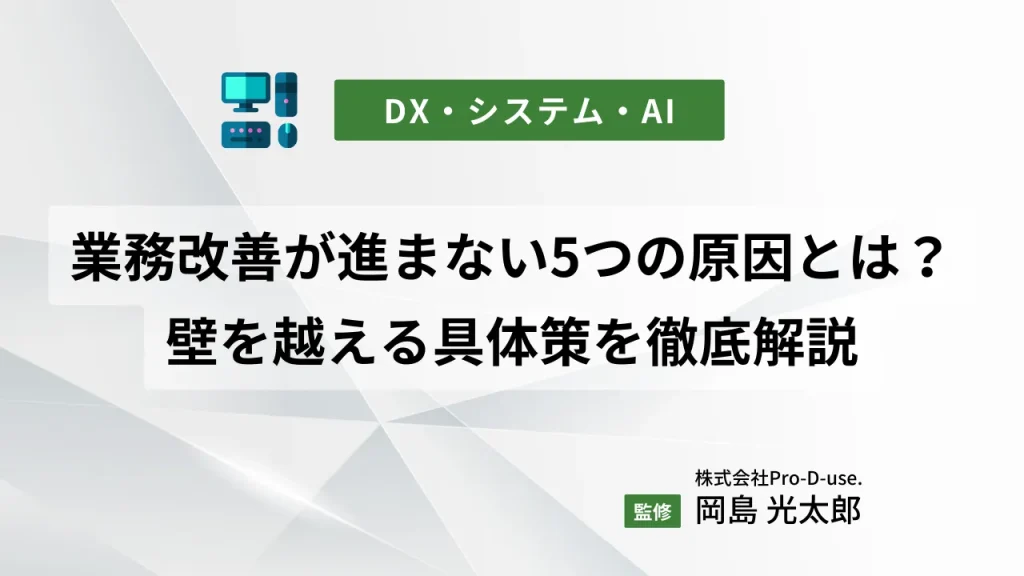\ 事業がグンっと前に進む /
\ サービス内容が知りたい方 /
M&A後のシステム統合の完全ガイド!PMIの進め方をプロ解説
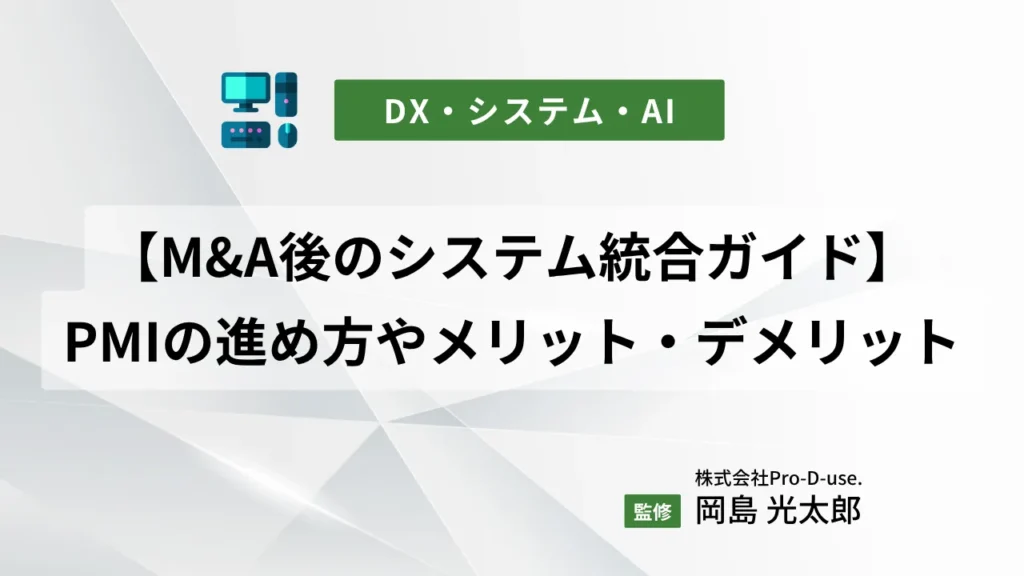
-
- 事業承継
- 経営ノウハウ
- 2025年11月15日
M&Aを実施した企業の経営者の方は、システム統合についてこんな悩みをお持ちではないでしょうか?
- M&Aを実施したが、期待したシナジー効果が得られていない
- 買収先と自社で異なるシステムを使っており、業務が非効率だ
- M&A後のシステム統合の進め方や注意点がわからず、プロジェクトが停滞している
こうした悩みが絡み合うことで、M&A後のシステム統合が後回しになりがちです。その結果、M&A後の業務の効率が悪くなり、生産性が落ちてしまうリスクがあります。
このような状況を避けるには、以下の手順で着実にM&A後のシステム統合を進めることが大切です。
▼【M&A後のPMI】システム統合の進め方【5ステップ】
- 現状分析をして統合課題を明確化する
- 要件を定義して統合の方向性を定める
- システムを選定して最適な統合基盤を決める
- システムを設計してデータ・機能の整合性を取る
- 実装・移行作業を行い安定稼働を確立する
これらを実行することで、M&A時のシステム統合に伴うリスクを最小限に抑えられます。
筆者は「(株)Pro-D-use」という事業承継に強いコンサルティング会社を経営しており、これまで多くの事業承継を支援してきました。
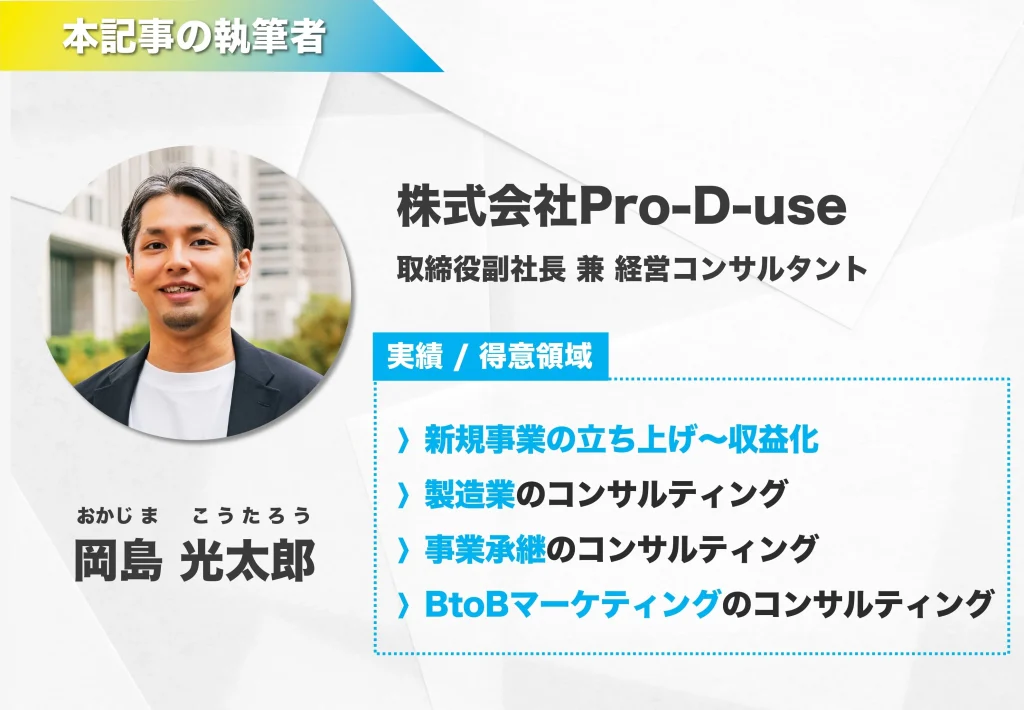
本記事ではM&Aにおけるシステム統合の重要性から、具体的な進め方、メリット・デメリット、成功のポイントまでを網羅的に解説します。
▼この記事で解説すること
- M&Aにおけるシステム統合の重要性
- システム統合の具体的な進め方
- システム統合のメリット・デメリット
- システム統合を成功させるポイント
「M&A後のシステム統合をどのように進めれば良いかわからない」とお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
DXコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。DXは経営戦略からシステム構築・運用まで複雑になるため、” 現場まで入り込んでコンサルする “会社に依頼すべきです。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、「経営者と現場の間に入り、DXを伴走推進する」コンサルが強みのコンサルティング会社です。これまで多くの中小〜中堅企業のDX推進のご支援で実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、DXの無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。
「(株)Pro-D-useのコンサルサービス」詳細を見る >>
\「現場に入り込む」伴走型DXコンサル/
目次
システム統合の失敗事例「みずほ銀行」
M&A後のシステム統合の典型的な失敗例として、みずほ銀行のケースは日本でもよく知られています。
2002年に旧第一勧業銀行、旧富士銀行、旧日本興業銀行の3行が統合して誕生したみずほ銀行では、各行が独自に運用していた勘定系システムを一本化する統合作業が極めて困難を極めました。
当初、統合方針やシステム構成が十分に固まらないまま開業初日を迎えた結果、ATMの停止や公共料金の二重引き落とし、口座振替の遅延といった大規模なシステム障害が発生し、数十万件にも及ぶ未処理が生じました。
その後も複数回にわたりシステム障害が続き、統合完了までに実に十数年以上の期間を要するなど、統合後の業務運営に長期的な影響を与えています。
みずほ銀行の事例が示すように、統合方法やデータ移行計画、現場の運用調整が不十分なままシステム統合を進めると、M&A後の業務に長期間にわたって深刻な支障をきたすリスクが高まります。
このように、会社統合やM&A後のシステム統合は、単なる技術的な作業ではなく、業務プロセスや現場運用を含めた全体設計を前提に慎重に進めるべき重要なPMI施策だと言えます。
参考記事:みずほ銀行の失敗に学ぶ
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/040400287/040400001/
M&A後のシステム統合で期待できる「6つの効果」
M&Aの成功において、両社のシステムを1つにまとめる「システム統合」は極めて重要な要素です。M&A後のシステムがバラバラでは期待する相乗効果が生まれにくいからです。
システム統合によりM&A後の業務の無駄をなくすことで、会社全体の力を最大限に引き出せます。M&A時のシステム統合には以下の効果が期待できます。
▼M&Aのシステム統合で期待できる「6つの効果」
- 効果1. シナジー効果の最大化
- 効果2. 生産性向上
- 効果3. 経営データの一元管理
- 効果4. ITコスト削減
- 効果5. ガバナンス強化
- 効果6. 組織文化の融合
これらの効果を確実に得るためには、単なる「システムの統一」ではなく、業務と組織まで含めた統合設計が欠かせません。
【M&A後のPMI】システム統合の進め方【5ステップ】
M&A後のPMIにおけるシステム統合は、以下の流れで進めることが一般的です。
▼【M&A後のPMI】システム統合の進め方【5ステップ】
- ステップ1. 現状分析をして統合課題を明確化する
- ステップ2. 要件を定義して統合の方向性を定める
- ステップ3. システムを選定して最適な統合基盤を決める
- ステップ4. システムを設計してデータ・機能の整合性を取る
- ステップ5. 実装・移行作業を行い安定稼働を確立する
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
ステップ1. 現状分析をして統合課題を明確化する
M&A時のシステム統合を成功させるには、まず両社の現状を正確に把握し、課題を「見える化」することが大切です。それぞれの会社が現在使っているシステムや仕事の進め方を調べることで、統合するうえでの問題点が見えてきます。
M&A時にシステム統合をする際には以下の点を一つひとつ調査し、統合における課題を洗い出します。
▼分析すべき「7つの分析項目」
- 分析項目1. システムの種類・機能・コスト
- 分析項目2. IT設備の構成・運用状況
- 分析項目3. データの種類・保管場所・連携
- 分析項目4. 業務フローと属人化業務
- 分析項目5. 管理体制と技術レベル
- 分析項目6. 重複・不足機能
- 分析項目7. セキュリティ・データ管理ルール
システムや仕事の進め方を整理・分析することで、M&A後の統合に向けた具体的な課題が明確になります。
ステップ2. 要件を定義して統合の方向性を定める
現状分析で明らかになった課題をもとに、統合後の会社の理想の姿を具体的に描き、システム統合の全体的な方向性を決定します。最初にM&A時のシステム統合のゴールを明確に設定すると、プロジェクトの関係者全員が同じ目標に向かって進むことが可能です。
以下の項目を一つひとつ決めていくことで、M&A時のシステム統合の全体像がはっきりと見えてきます。
▼定義すべき「6つの要件」
- 要件1. 統合の基本方針
- 要件2. 業務ルールの統一
- 要件3. 必要な機能の洗い出し
- 要件4. 機能以外の条件設定
- 要件5. 予算とスケジュールの策定
- 要件6. 優先順位の決定
システム統合の目的や細かい条件の定義によって、システム選びを迷わず進められます。
ステップ3. システムを選定して最適な統合基盤を決める
M&A時の統合の方向性が定まったらシステムを選定する段階に移ります。両社のシステムをどちらかに統合するのか、あるいは新しいシステムを導入するのかを基本方針に沿って決定します。
M&A時のシステムを選定する際は、以下の手順で進めることが一般的です。
▼M&A時にシステムを選定する5つの手順
- 手順1. システム選定基準を明確にする
- 手順2. システム候補をリストアップする
- 手順3. システムの比較検討を重ねる
- 手順4. システムの操作性を確認する
- 手順5. システムの費用対効果を検証する
システム選定の手順を意識すると機能やコストに加え、現場の使いやすさと将来性も踏まえて総合的に判断できます。複数の候補を客観的な基準で慎重に比較検討することは、M&A時のシステム統合を成功させるための重要な要素の一つです。
ステップ4. システムを設計してデータ・機能の整合性を取る
統合するシステムが決まったら、次は新しいシステムの設計図を描く段階です。M&A後に両社のデータや業務の進め方がうまくかみ合うように、設計作業でシステムを細かく調整します。
M&A後のデータや機能の整合性を取るために、主に以下のシステム設計を進めます。
▼M&A時のシステム設計の具体的な5つの内容
- 内容1. 機能・画面・業務フローの設計
- 内容2. データ管理ルールの統一
- 内容3. データ移行手順の設計
- 内容4. 機能の過不足調整
- 内容5. 他システムとの連携設計
一つひとつの業務やデータについて丁寧にシステムの設計図を作ることで、M&A後の開発やデータ移行がスムーズに進みます。
ステップ5. 実装・移行作業を行い安定稼働を確立する
M&A時のシステムの設計図が完成したら、実際のシステム構築とデータ移行に進みます。システム構築とデータ移行の段階では計画通りに作業を進め、トラブルなく新しいシステムを安定稼働させることが最も重要です。
綿密な計画と準備を怠ると、システム移行中に予期せぬトラブルが発生し、業務に大きな支障をきたす恐れがあります。大切なデータを守り、M&A後に従業員が安心して新システムを使えるようにするため、実装・移行作業には安全性を重視した手順が求められます。
M&A後の安定したシステム稼働を実現するためには、以下の作業を段階的に進めることが不可欠です。
▼安全性を重視した実装・移行作業の手順
- 手順1. 移行計画とスケジュールを策定する
- 手順2. データを整理する
- 手順3. テスト環境での移行リハーサルをする
- 手順4. 従業員向けのトレーニングを実施する
- 手順5. バックアップを取得する
- 手順6. 復旧手順の整備・検証を行う
- 手順7. 稼働後の監視・サポート体制を構築する
準備を万全に行うことで、M&A時のシステム統合に伴うリスクを最小限に抑えられます。
» 中小企業庁「PMIを実施する」(外部サイト)
» IPA「重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド Ver.1.0」(外部サイト)
DXコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。DXは経営戦略からシステム構築・運用まで複雑になるため、” 現場まで入り込んでコンサルする “会社に依頼すべきです。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、「経営者と現場の間に入り、DXを伴走推進する」コンサルが強みのコンサルティング会社です。これまで多くの中小〜中堅企業のDX推進のご支援で実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、DXの無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。
「(株)Pro-D-useのコンサルサービス」詳細を見る >>
\「現場に入り込む」伴走型DXコンサル/
M&Aに伴うシステム統合「3つのメリット」
M&A後のシステム統合は企業に以下のメリットをもたらします。
▼M&Aに伴うシステム統合の3つのメリット
- メリット1. 部門間の情報共有が容易になる
- メリット2. 情報管理コストと業務負荷を圧縮できる
- メリット3. 戦略立案までのスピードが向上する可能性がある
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
メリット1. 部門間の情報共有が容易になる
M&A時のシステム統合の大きなメリットは部門間の情報共有が簡単になることです。M&A時にシステムを統合すると以下の効果が期待できます。
▼M&A時のシステム統合により得られる情報共有に関する効果
- リアルタイムでの状況把握
- 各部門のデータがリアルタイムで連携され、データの二重入力や部門間の確認作業がなくなります。
- 業務効率化
- 部門の壁を越えたスムーズな情報共有により、迅速な意思決定や業務効率の向上が実現できます。
- 属人化の解消
- 情報が特定の担当者に依存する「属人化」を解消し、円滑な事業承継を後押しします。
システム統合により全部門の従業員が同じデータにアクセスできるようになることで、認識のズレを軽減する効果が期待できます。
メリット2. 情報管理コストと業務負荷を圧縮できる
M&A時のシステム統合は情報管理にかかる費用や従業員の業務負荷を大きく減らす効果があります。統合前に別々に管理していたシステムや業務の流れが一つにまとまるため、会社全体の無駄をなくせるからです。
M&A時のシステム統合によって、以下のコストや手間を圧縮できます。
▼システム統合で削減可能なコスト・手間
- コスト削減可能1. 各社で契約していたシステムのライセンス料やサーバー代
- コスト削減可能2. システム管理を担当する従業員の作業時間と人件費
- コスト削減可能3. システム間のデータ転記や二重入力といった手作業
- コスト削減可能4. 手作業による入力ミスや、データの確認・修正にかかる手間
システム統合は従業員の負担を軽くして、会社全体の生産性を高めるうえでも役立ちます。
メリット3. 戦略立案までのスピードが向上する可能性がある
M&A後にシステム統合が成功すれば、経営戦略を立てるまでの時間を短縮できる可能性があります。システムが統合されることで、統合前には別々に管理されていたデータが一元化され、情報へのアクセスが容易になるためです。
M&A時のシステム統合により、以下の効果が期待できます。
▼システム統合で得られる経営判断の効果
- 効果1. データの一元管理が可能になる
- 効果2. 集計・分析が自動化できる
- 効果3. 新たな販売戦略の発見につながる
システムを統合すると全部門が同じデータを見られるため、会議における意思疎通が円滑になり、迅速な意思決定につながる可能性があります。データにもとづいた意思決定の基盤が整うことから、M&A時のシステム統合は経営スピードの向上に寄与することが期待されます。
DXコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。DXは経営戦略からシステム構築・運用まで複雑になるため、” 現場まで入り込んでコンサルする “会社に依頼すべきです。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、「経営者と現場の間に入り、DXを伴走推進する」コンサルが強みのコンサルティング会社です。これまで多くの中小〜中堅企業のDX推進のご支援で実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、DXの無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。
「(株)Pro-D-useのコンサルサービス」詳細を見る >>
\「現場に入り込む」伴走型DXコンサル/
M&Aに伴うシステム統合「3つのデメリット」
M&A時のシステム統合には以下のデメリットが存在します。
▼M&Aに伴うシステム統合の3つのデメリット
- デメリット1.移行作業に時間・費用がかかる
- デメリット2.移行時のデータ欠損リスクがある
- デメリット3.障害や動作不良が発生する可能性がある
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
デメリット1.移行作業に時間・費用がかかる
M&Aに伴うシステム統合のデメリットとして、移行作業に多くの時間と費用がかかる点が挙げられます。統合前に別々に運用されてきた2つの会社のシステムを一つにまとめる作業は困難です。
M&A後のシステム統合の過程で発生する時間や費用は以下のとおりです。
▼M&A時のシステム統合の過程で発生する時間や費用
| フェーズ | 主な作業内容 | 発生する費用 (目安) |
|---|---|---|
| 現状分析 | 調査・ヒアリングの工数、ドキュメント整備の時間、必要に応じた外部アセスメント費用がかかります。 | 50万〜300万円 |
| 設計・開発 | 要件定義~基本/詳細設計の人件費、追加開発・カスタマイズ費、結合/総合テストの工数が発生します。 | 300万〜3,000万円 |
| データ移行 | クレンジング・名寄せ作業の工数、移行ツールやスクリプト作成費、夜間・休日移行の割増人件費が必要です。 | 100万〜1,000万円 |
| 機器・ソフトウェア導入 | ライセンス/サブスク費、クラウド利用料(初期+月額)、環境構築・設定の初期費用、冗長化/セキュリティ対策の追加費が発生します。 | 初期費用:50万〜200万円 月額費用:数千円〜数十万円 |
| 外部委託 | PMO/移行支援/コンサルのフィー、ベンダー工数単価×稼働時間、契約・管理の間接コストがかかります。 | 月額30万〜300万円 |
| 従業員研修 | 研修実施費・教材作成費、トレーニング時間中の生産性低下(機会損失)、スーパーユーザー育成の追加工数が考えられます。 | 月額15万〜100万円 |
| 新旧システム維持 | 並行稼働期間の二重ライセンスや保守費、運用・問い合わせ対応の追加工数、突合チェックの確認時間が発生します。 | 月額10万〜100万円 |
M&A時のシステム統合は大規模なプロジェクトになるため、事前に計画を立てなければ想定以上の時間とコストがかかる可能性があります。
デメリット2.移行時のデータ欠損リスクがある
M&A時のシステム統合を進める際には、蓄積された企業データが失われるリスクがあります。古いシステムと新しいシステムでは、データの形式や管理方法が異なる場合がほとんどだからです。システム移行作業中の人的なミスやツールの設定不備が原因で、データが壊れたり消えたりする可能性もあります。
会社の根幹に関わる以下のデータが失われると、事業の継続に深刻な支障をきたす恐れがあります。
▼会社の根幹に関わるデータ
- データ1. 顧客情報・取引履歴
- データ2. 会計・財務データ
- データ3. 商品・在庫管理データ
一度失われたデータを完全に元通りに復旧することは困難です。データの欠損は会社の信用を大きく損なったり、貴重なビジネスチャンスを逃したりする原因にもなります。
このような事態になっても復旧できるように、あらかじめバックアップデータを取得し、移行前後でデータの整合性を確認する体制を整えておくことが不可欠です。
特にM&A時のシステム統合では、単純なバックアップ取得だけでなく、復元テストや突合チェックまで含めた移行計画を事前に設計しておく必要があります。
デメリット3.障害や動作不良が発生する可能性がある
M&A時のシステム統合のプロセスを慎重に進めなければ、障害や動作不良が発生する可能性があります。それぞれ独立して作られたシステム同士を無理に連携させようとすると、互換性の問題や想定外のトラブルが起こりやすくなるからです。
M&A時のシステム統合では以下の問題が発生する危険性があります。
▼システム統合に伴う障害や動作不良の例
- 例1. 既存システム同士の相性が悪く、連携時にエラーが出る
- 例2. テスト不足により、本稼働後に重大な不具合が見つかる
- 例3. サーバーへの負荷増大により、動作が遅くなったり停止したりする
- 例4. 従業員の操作ミスがトラブルやデータ破損の原因となる
- 例5. 業務フローの見落しで、一部業務が滞る
M&A後のシステム統合に伴う障害や動作不良は業務に深刻な影響を与える恐れがあります。入念なテストと計画的な移行が、安定したシステム稼働の鍵を握ります。
M&A時のシステム統合を成功させる「4つのポイント」
M&A時のシステム統合は以下のポイントを押さえることで成功しやすくなります。
▼M&A時のシステム統合を成功させる「4つのポイント」
- ポイント1. 統合の目的を明確にする
- 情報の一元化や意思決定の迅速化など、M&A時のシステム統合によって実現したい成果を具体的に定めましょう。M&A時のシステム統合の目的が曖昧なままでは、現場の混乱や投資の無駄につながります。
- ポイント2. 現行システムの棚卸しを行い、重複や非効率な部分を洗い出す
- 現場の業務フローを理解したうえで進めることで、使いやすく定着しやすいシステム統合が可能になります。
- ポイント3. 統合の優先順位を定め、段階的に進める
- 段階的なM&A時のシステム統合によりリスクを抑えつつ、運用を確認しながら移行することでトラブルを最小限にできます。統合の優先順位は、M&Aの目的、期待されるシナジー効果、統合の難易度、業務への影響度などを総合的に考慮して決定します。
- ポイント4. M&AやPMIに詳しい専門家の支援を受ける
- 外部の知見を取り入れることで、経営と現場の両面から最適なシステム統合を進められます。
システム統合は将来のビジョンを明確にし、現場スタッフの協力を得ながら計画的に進める複雑なプロジェクトです。M&A時のシステム統合では技術面だけでなく、組織や人材に関する課題にも配慮した慎重なアプローチが必要です。
» M&Aを成功に導くPMI戦略を解説!
DXコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。DXは経営戦略からシステム構築・運用まで複雑になるため、” 現場まで入り込んでコンサルする “会社に依頼すべきです。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、「経営者と現場の間に入り、DXを伴走推進する」コンサルが強みのコンサルティング会社です。これまで多くの中小〜中堅企業のDX推進のご支援で実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、DXの無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。
「(株)Pro-D-useのコンサルサービス」詳細を見る >>
\「現場に入り込む」伴走型DXコンサル/
M&A後のシステム統合で、よくある質問(Q&A)
最後に、M&A後のシステム統合の現場で、筆者がよく受ける質問と回答を共有します。ぜひ、ご参考ください。
Q1. システム統合は、M&A後の成功にとってなぜそれほど重要なのでしょうか?
システム統合は、M&Aのコストの大部分を占める要素であり、その成否を左右する重要な要因の一つです。
▼M&A後のシステム統合のインパクト
- シナジー効果の実現
ITシステムの統合は、M&Aの目的達成、当初計画された相乗効果の実現を目指す上で不可欠です。 - 業務効率化・コスト削減
システムを一元管理することで、重複するシステムの運用コストを削減し、部門をまたいだ情報共有や業務連携をスムーズにし、業務効率の向上を狙えます。 - 迅速な意思決定
顧客データや基幹業務データなどが一括管理され、経営層がリアルタイムなデータでより迅速かつ的確な意思決定が可能になります。
逆に、統合が遅延・失敗すると、業務の混乱、コストの増加、従業員のモチベーション低下、顧客満足度の低下といった深刻な悪影響を及ぼし、M&Aの価値を大きく損なう可能性があります
Q2. システム統合が「失敗する原因」と「悪影響」を教えてください。
システム統合は「M&Aの最大の難所」です。失敗の要因は技術的な問題だけでなく、経営層のコミットメントや人材課題に起因することも多いです。
主な失敗要因と陥りやすいパターンには以下のものがあります。
▼システム統合の失敗原因と悪影響
- 事前準備の不足(ITデューデリジェンス不足)
M&A前にITのPMIへの準備が不十分であったり、デューデリジェンスでIT資産の評価が甘かったりした結果、買収後に想定外の多額なシステム更新費用や、古いシステム、システムに関するドキュメントの欠落といった潜在的リスク(技術的負債)が発覚することが多々あります。 - 経営層のリーダーシップと方針の欠如
経営陣がシステム統合の重要性を十分に理解しておらず、統合後の明確な統合方針を決定しないまま、現場に丸投げしてしまう。 - データ移行とシステム統合のプロセス過小評価
異なるシステム間でデータを移行・統合する際、データの形式が異なったり、データ量が多かったりする場合の移行工数や複雑さを過小評価してしまい、結果、プロジェクトの長期化を招きます。 - 関係者間の連携不足と抵抗
IT部門だけで統合を進め、業務プロセスや現場のニーズを軽視した結果、従業員が新しいシステムや業務フローへの変更に抵抗し、生産性低下や離職につながります。 - キーマンの流出
買収された企業のシステムを熟知したIT人材や運用担当者が離職してしまい、属人化したシステムが動かせなくなり、業務継続が困難になる。
こうした失敗要因は事前に想定できるものも多いため、早い段階でリスクを洗い出し、対策を組み込んだ統合計画を立てることが重要です。
Q3. ERP、会計、人事システム統合で特に注意すべき点は何ですか?
ERPや会計、人事システムは企業の基幹システムのため、そのシステム統合はかなり困難です。また、失敗した際の経営への影響も相当に大きく、ミスができない領域だと筆者は考えます。
その上で、各システムそれぞれで注意しなければいけない点が異なりますので、以下からそれぞれ説明します。
▼ERPの統合
ERPは経営・業務全体に深く関わるため、単なるシステム変更ではなく「業務そのものを変革」する一大プロジェクトになります。そのため、経営トップの強力なコミットメントが不可欠であり、全社的な業務標準化とデータ一元管理を通して、データドリブン経営を目指す必要があります。
重要な統合であるため、「数ヶ月で解決できるでしょ」と軽く見ずに、数年単位で改革・改善を進めていく覚悟で取り組むべきです。
▼会計・人事システム統合
決算や給与計算など、1日も止められない重要な機能を担っています。この統合が遅れると業務効率が下がるだけでなく、情報入力の重複により迅速な経営判断が難しくなります。そのため、迅速な統一と早期のITガバナンス整備が求められます。
特に人事制度(報酬、評価など)は企業文化と密接に関連するため、システム統合と同時に人事制度の段階的な統一を慎重に進める必要があります。
Q4. システム統合の具体的な手法パターンは、どのようなものがありますか?
システム統合の手法には、M&Aの目的や両社のシステム環境の複雑さによって、主に以下の3パターンから適切に選択しましょう。
| 統合方式 | 概要 | メリット | デメリット リスク |
|---|---|---|---|
| 方式1. 一方のシステムへの移行 | どちらか一方(主に買い手側)のシステムに統一する。 | 短期間での統合が可能であり、システム維持コストも抑えられる。 | 廃止側の優れた業務プロセスやデータを失うリスクがある。 |
| 方式2. 新規システムの導入 | 両社のシステムを廃止し、新しいシステムをゼロから構築・導入する。 | M&A後に最適な経営戦略に合致したシステムを構築できる。 ※クラウドベースのシステム導入が推奨 | 多大な費用と工数がかかり、データ移行の不具合リスクが高い。 |
| 方式3. 既存システム利用+データ連携 | 既存のシステムは残したまま、システム間でデータ連携のみを行う。 | 現行業務への影響が最も小さく、統合コストを抑えられる。 | システム構造が複雑化し、データ連携部分で不具合が発生する可能性がある。 |
どの方式が最適かは、統合スピード・コスト・現場への影響のバランスを見ながら判断することが大切です。
M&Aに伴うシステム統合をスムーズに行って、経営リソースを集約しよう
M&Aを成功させるためには安全性を重視したシステム統合が不可欠です。M&A時のシステム統合は単なるIT作業ではなく、会社全体の力を結集し経営リソースを最大活用する経営戦略そのものです。
システム統合によりM&A後の情報共有がスムーズになり、業務の無駄を削減して相乗効果を生み出せます。コスト削減と生産性向上によって、持続的な成長の基盤を築くことも可能です。
M&A時のシステム統合に専門的な知識が必要な場合は、専門家の活用も有効です。計画的なシステム統合でM&Aの効果を最大化し、企業の未来をより良いものにしていきましょう。
DXコンサルの検討は、「”なんとなく”で選ぶ」と必ず失敗します。DXは経営戦略からシステム構築・運用まで複雑になるため、” 現場まで入り込んでコンサルする “会社に依頼すべきです。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は、「経営者と現場の間に入り、DXを伴走推進する」コンサルが強みのコンサルティング会社です。これまで多くの中小〜中堅企業のDX推進のご支援で実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、DXの無料相談をしてみませんか?詳しくは▼下記ページ▼をご覧ください。
「(株)Pro-D-useのコンサルサービス」詳細を見る >>
\「現場に入り込む」伴走型DXコンサル/
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)