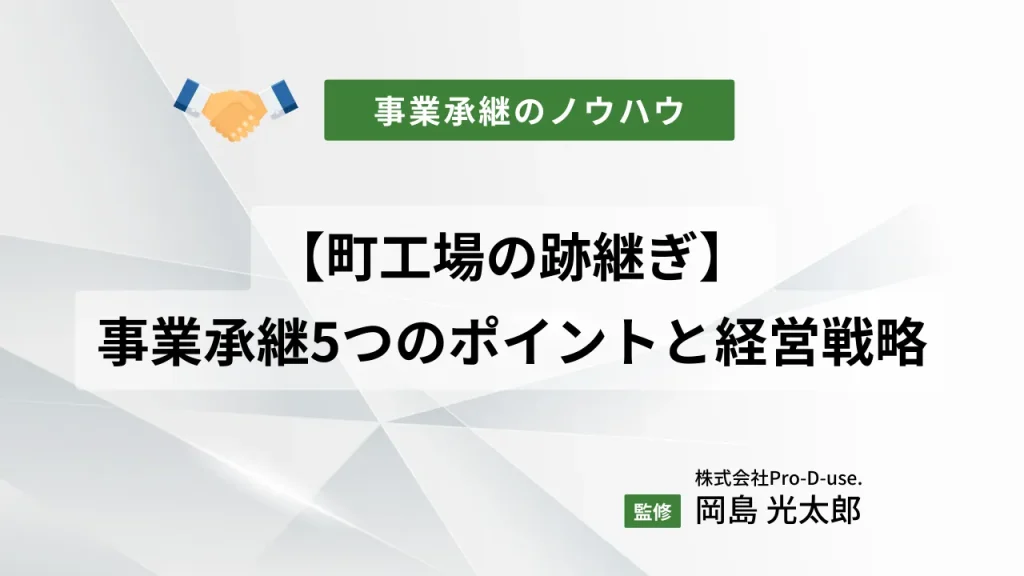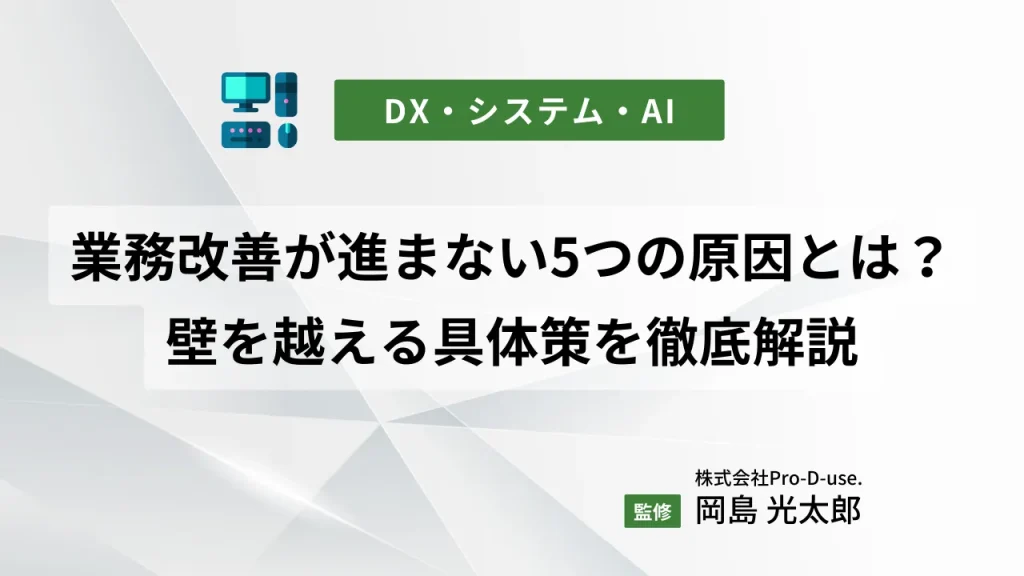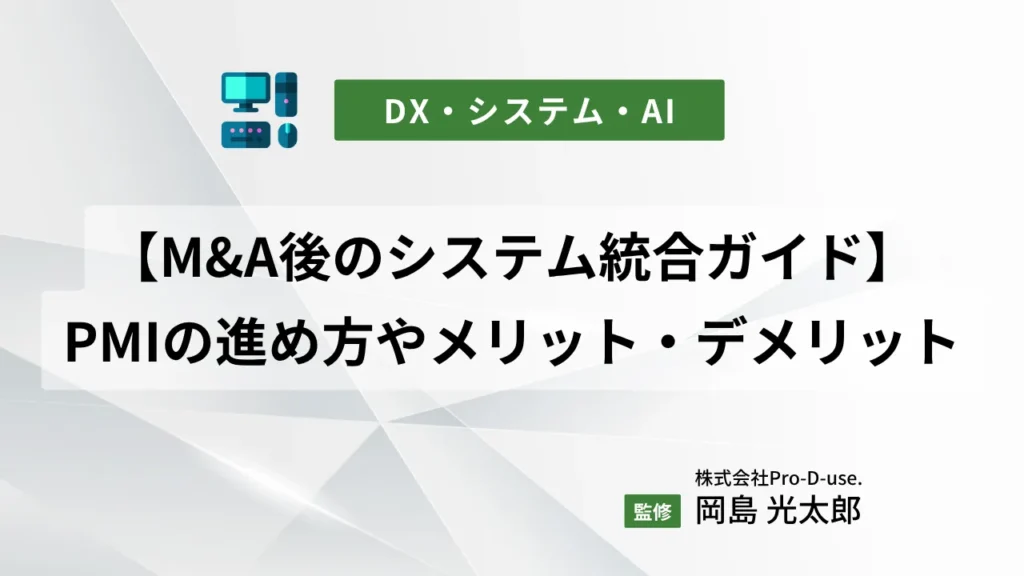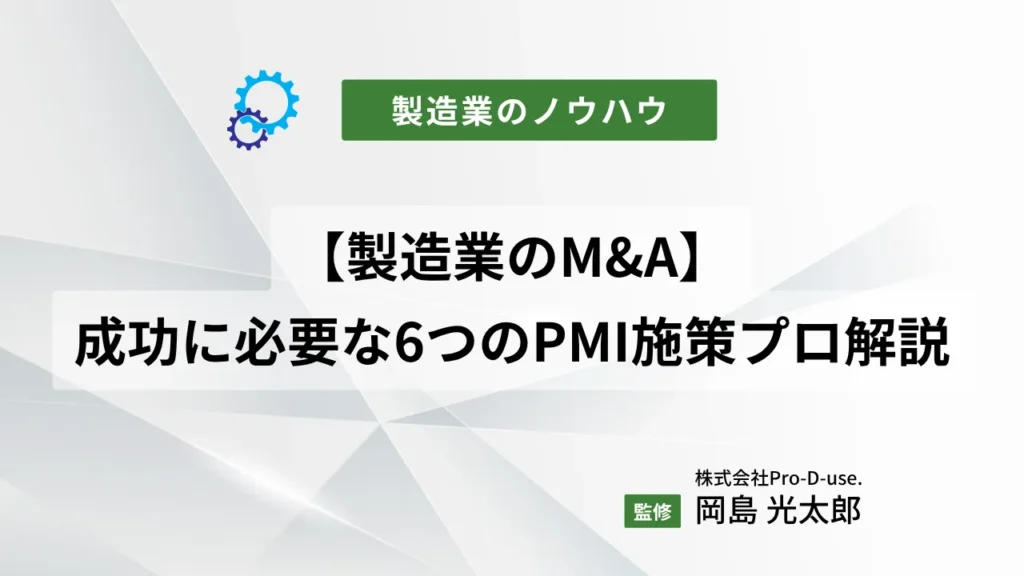「M&Aを成功に導くPMI戦略」シナジー効果を生み出すプロセスをプロが解説
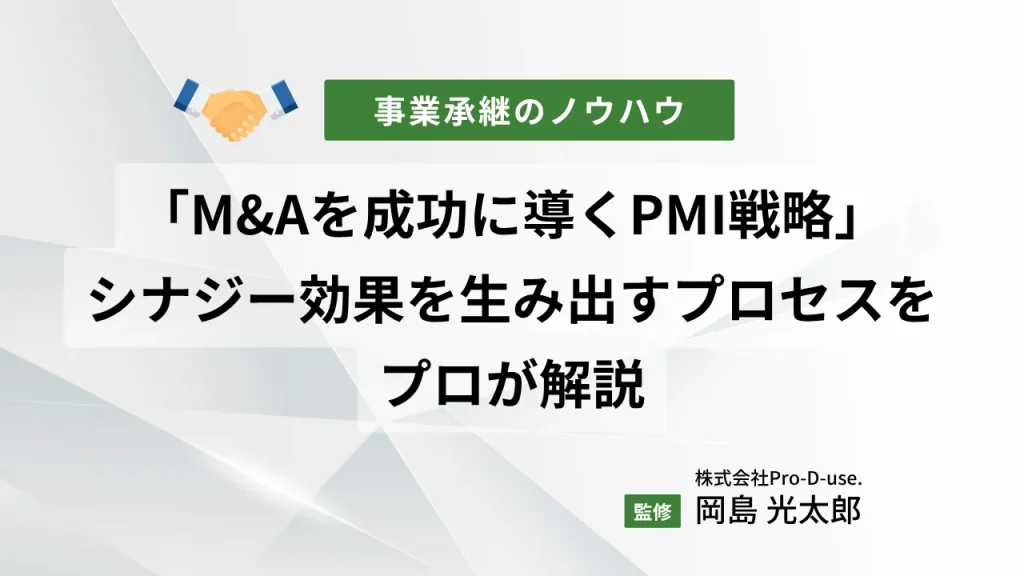
-
- 事業承継
- 経営ノウハウ
- 2025年10月21日
M&Aを考えている経営者の方はこんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
- 期待したシナジー効果が出ず、社員が疲弊している
- 文化の違う2つの組織のまとめ方がわからない
- M&Aは決まったが統合プロセスが定まっていない
こうした悩みがあると、M&Aによるシナジー効果を十分に得られなくなります。M&Aの成功は契約締結ではなく、統合後のプロセスである「PMI」が左右します。しかし、多くの企業では組織文化や人材の統合がうまく進まずに現場の混乱や離職を招くなど、PMIの推進につまずきがちです。
このような状況では、以下の「PMIが網羅すべき統合の5つ領域」を参考にPMIを整理していくことが大切です。
▼PMIで成功するために網羅すべき統合の5領域
- 領域1. 経営のPMI:ビジョン・戦略の再構築
- 領域2. 人と組織のPMI:文化とエンゲージメントの融合
- 領域3. 業務オペレーション・ITシステムのPMI
- 領域4. 財務・経理のPMI:経営基盤の整備
- 領域5. ステークホルダーのPMI:不安解消と信頼関係の維持
これらを実行することでM&A後のPMIが円滑に進み、期待以上のシナジー効果を生み出す道筋が見えるようになります。
筆者は「株式会社Pro-D-use」という事業承継やPMI支援に強い経営コンサルティング会社を経営しており、これまで多くのPMI支援を行ってきました。
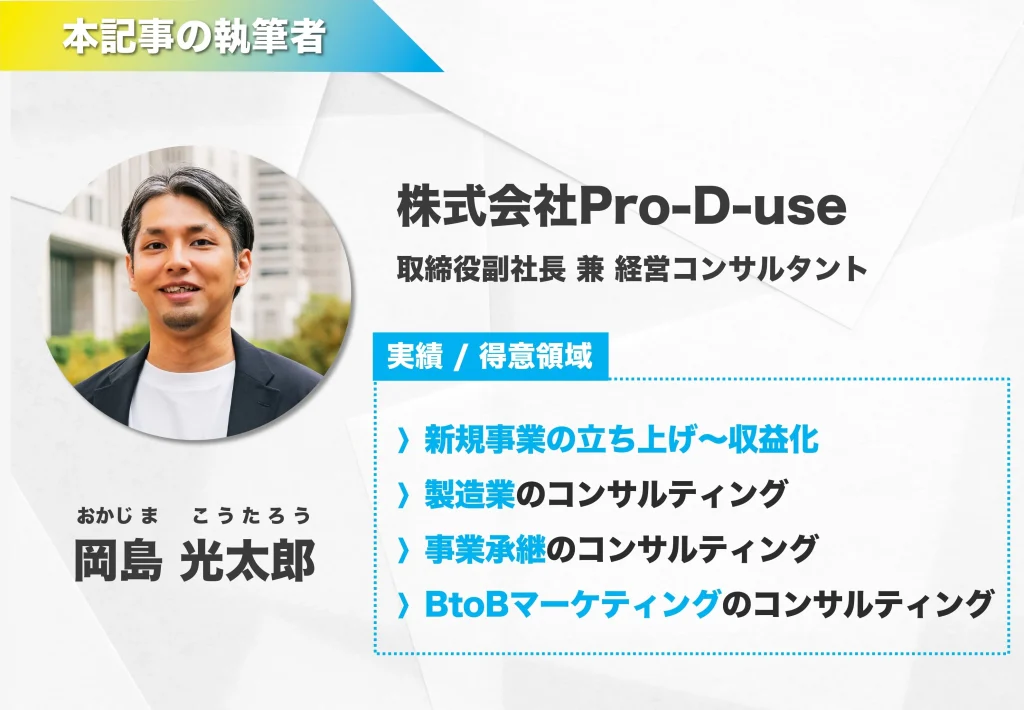
本記事ではM&A後のPMIで得られるシナジー効果や成功に不可欠な統合領域、PMIの具体的な進め方を解説します。
▼この記事で解説すること
- 従来型PMIが陥るワナ:「シナジー未達」と「組織の段階的崩壊」
- M&AのPMIで得られるシナジー効果
- 【領域別】PMIで成功するために網羅すべき統合の5領域
- M&A後のPMIの具体的な進め方
M&A後のPMIに不安がある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>
\“現場で一緒に”事業承継を進めます/
目次
従来型PMIが陥るワナ:「シナジー未達」と「組織の段階的崩壊」
M&A後のPMIにおいて財務やシステムなどのハード面を優先すると、人や文化といったソフト面が置き去りにされます。PMIの偏りは社員の不安や不信感を生み、キーパーソンの離職や生産性の低下、顧客離れなどの負のサイクルに陥ります。
DeNAが2014年に買収したiemoやMERYの事例は組織の段階的崩壊の典型例です。DeNAは編集基準やガバナンスの統合が不十分なまま、外部ライター任せの属人的運営を続けました。属人的運営を続けた結果、医療情報サイト「WELQ」で信憑性のない記事が拡散され、全10サイトの閉鎖と謝罪会見にまで発展しています。
» 東洋経済オンライン「DeNA、「3時間謝罪」でも解明しない詳細経緯」(外部サイト)
東芝でも経営陣が掲げた過剰な利益目標が現場に過度な圧力をかけ、不正会計が常態化する事態に発展。監査機能やリスク管理が機能せず、東芝の企業文化が空洞化したことで社員の士気が下がり、組織全体の信頼が失われました。
» 東洋経済「東芝「不適切会計」とは、何だったのか」(外部サイト)
従来型PMIによる組織の構造的な崩壊は中小企業でも起こり得ます。属人性の高い経営体制ではキーパーソンが離職するだけでノウハウや取引関係が途絶え、事業の基盤が脆弱になるためです。
PMIの本質は単なる数字の統合ではなく、人と文化の融合にあります。経営層が理念を共有し、現場と信頼を築くことがM&Aを真に成功へ導く鍵です。
M&AのPMIで得られる「3つのシナジー効果」
M&A後のPMIは2つの企業の経営資源を統合し、単独では得られないシナジー効果を生み出す重要なプロセスです。M&Aが生み出すシナジー効果は以下のとおりです。
▼M&AのPMIで得られるシナジー効果
- 効果1. 売上拡大・コスト削減を実現する
- 効果2. 経営資源を有効活用する
- 効果3. 社員のモチベーションを向上させる
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
効果1. 売上拡大・コスト削減を実現する
M&Aによって両社の強みを生かし、重複業務や非効率な運用を見直すことでより収益性の高い経営体制を構築できます。ただし、売上の拡大とコスト削減を実現するにはそれぞれの目的に合った以下のようなPMI施策が必要です。
▼売上を拡大するPMI
- それぞれの既存顧客に対して商品・サービスを提案して顧客単価を上げる
- 両社の営業網や販売チャネルを共有して新規の市場や顧客層を開拓する
- 技術・ノウハウを融合して付加価値の高い新商品・新サービスを開発する
▼コストを削減するPMI
- 購買や調達を一本化し、スケールメリットによって仕入れコストを抑える
- 工場や倉庫などの拠点を統合・最適化して物流や生産効率を高める
- 経理・総務などの管理部門を統合して、重複作業や人件費を削減する
シナジー効果を最大化するためにはPMIを短期的な目線だけに終わらせず、中長期的な成長戦略と結びつけることが重要です。M&A後のPMIを戦略的に進めることで、経営統合にとどまらず企業の総合力を高められます。
» 中小企業庁「中小PMIガイドライン概要版」(外部サイト)
効果2. 経営資源を有効活用する
M&A後のPMIを効果的に進めることで両社の経営資源を再構築し、企業全体の競争力を高められます。M&A後のPMIで競争力を高められる理由は、両社の強みを合わせることで単独で実現できなかった価値を生み出せるためです。企業全体の経営資源を最大限に生かすための主なPMI施策は以下のとおりです。
▼経営資源を最大限に生かすPMI
| PMI | 期待できる効果 |
| 技術や特許を融合する | 新しい製品・サービスを創出して競争力を高める |
| 販売網と顧客情報を共有する | 既存顧客への提案範囲を拡大して売上を伸ばす |
| 人材を新規事業へ再配置する | 個々のスキルを生かして成長分野の推進力を高める |
| 遊休資産を活用・売却する | 資金効率とキャッシュフローを改善する |
PMIを通じて「人・モノ・金・情報」などの基盤資源を最適に統合・配置させることで、組織で持続的なシナジーを生み出せます。
» 中小企業庁「中小PMIガイドライン」(外部サイト)
効果3. 社員のモチベーションを向上させる
PMIが成功すると優秀な人材が定着し、企業全体の組織力が強化されます。PMIによって優秀な人材が定着するのは社員が企業の方向性や評価基準を理解でき、安心感と納得感が生まれやすくなることが理由です。社員が能力を発揮できる環境を整えるためには、以下のPMI施策が効果的です。
▼社員が安心して能力を発揮できる「5つのPMI施策」
- 施策1. ビジョンと体制を明確にする
- 施策2. 経営トップと社員の対話を促進する
- 施策3. 公正な人事制度を構築する
- 施策4. キャリアプランを提示する
- 施策5. 社員交流を活性化する
PMIによって社員は自分の役割や目標、評価を理解しやすくなり、経営トップとの信頼関係が深まります。人を中心としたPMIが社員のモチベーションを維持し、M&Aによるシナジー効果を引き出す原動力となります。
» 社長と従業員の理想的な関係を築くステップを徹底解説!
【領域別】PMIで成功するために網羅すべき統合の5領域
M&Aの後は2社の違いを解消しなければ組織が適切に機能せず、期待した効果を得にくくなります。以下の5つの領域をPMIを通じて統合することでシナジー効果を生み出しやすくなります。
▼PMIで成功するために網羅すべき統合の5領域
- 領域1. 経営のPMI:ビジョン・戦略の再構築
- 領域2. 人と組織のPMI:文化とエンゲージメントの融合
- 領域3. 業務オペレーション・ITシステムのPMI
- 領域4. 財務・経理のPMI:経営基盤の整備
- 領域5. ステークホルダーのPMI:不安解消と信頼関係の維持
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
領域1. 経営のPMI:ビジョン・戦略の再構築
PMIにおいては全員が共有できるビジョンを掲げ、新しい経営体制と仕組みを整えることが求められます。統合後にビジョンや価値観が一致していないと、現場に摩擦が生じて十分なシナジー効果が発揮されません。
PMIの初期段階では「何のために存在するのか」や「どのような価値を提供するのか」を明確に定義する必要があります。M&A後の両社の経営理念や事業特性、従業員の意見を踏まえた定義にもとづき、戦略と中期経営計画が再構築されるためです。
ビジョンと企業戦略の再構築を行う際は買収側が方針を押し付けず、被買収側の経営トップや現場の知見を反映させてください。
領域2. 人と組織のPMI:文化とエンゲージメントの融合
M&A後のPMIの成功は「人と文化の融合」が実現できるかが鍵です。企業から従業員の心が離れてしまえば真の統合は成立しません。
M&A後の組織を1つにまとめるためには、衝突を避けつつ異なる文化や価値観を融合させなければなりません。特に社内のキーパーソンを慰留し、彼らが新しい組織で力を発揮できるよう支援する必要があります。
経営トップはPMIの初期段階から継続的に社員とコミュニケーションを図り、変革への理解と協力を促しましょう。経営トップが新しい方向性を明確に示し率先して社員と対話を重ねることで、従業員の不安を和らげ前向きな意識へと変えられます。
領域3. 業務オペレーション・ITシステムのPMI
PMIの初期段階では業務プロセスの可視化と最適化を徹底してください。両社の業務オペレーションを明確にし、重複や非効率を洗い出して標準化を進めることで統合の基盤が整います。特に「購買・生産・物流・販売」などの主要オペレーションは、優先的に整理・統一する必要があります。
PMIの初期段階ではITシステムの統合と最適化も計画的に進めなければなりません。PMIの初期段階でのシステム統合が遅いとデータの不整合や情報共有の遅延が発生し、経営判断の精度低下につながります。M&A後の混乱を防ぐために、以下のPMIを実施しましょう。
▼M&A後の混乱を防ぐためのPMI施策
- IT資産の棚卸しと統合計画の策定
- M&A後の企業同士が既存システムやデータベースを把握し、統合方針とスケジュールを明確化する。
- 情報の一元管理による意思決定の迅速化
- データを統合し、M&Aをする全社が同じ情報をもとに判断できる体制を築く。
業務とシステムを両輪で最適化することで統合後の企業は初めて1つの組織として機能し、シナジーを最大限に引き出せます。
領域4. 財務・経理のPMI:経営基盤の整備
PMIの初期段階で取り組むべきは会計ルールの統一と決算の早期化です。決算スピードを高めることでグループ全体の財務状況を迅速に把握でき、経営トップが適切なタイミングで意思決定を下せます。
会計処理の不整合を防ぐためには、連結決算体制も構築してグループ全体の財務情報を一元管理する仕組みを整えましょう。以下の財務・経理のPMIを最適化しておくことで、会社の経営基盤が強固になります。
▼最適化しておくべき財務・経理のPMI
- 会計システムの統一
- 内部統制の整備
- 共通KPIの設定
- 税務リスクの把握と管理
財務・経理のPMIをM&A後すぐに最適化することで、企業は安定した財務基盤をもとに持続的な成長へと進めます。
領域5. ステークホルダーのPMI:不安解消と信頼関係の維持
M&Aは多くの関係者に不安や疑念を生じさせるものであり、コミュニケーションを怠ると士気の低下に発展します。情報共有と継続的な対話を通じて統合の目的や今後の方針、雇用への影響を伝えることで従業員の不安を和らげられます。
M&A後は社外の取引先や金融機関に対する説明も欠かせません。取引先には新旧の経営者が直接訪問し、M&A後の事業継続や品質維持の見通しを示すことで安心感を与えられます。金融機関にはM&A後の新たな財務方針を共有し、グループ全体への信頼を高めましょう。
» 中小企業庁「事業継承ガイドライン第3版」(外部サイト)
M&A後のPMIの具体的な進め方【4ステップ】
M&Aの目的は契約ではなく統合によるシナジー創出です。場当たり的なPMIでは現場が混乱し、期待した成果を得られません。M&A後にシナジー効果を生み出すには、明確な方針にもとづいて一貫したプロセスを進めることが重要です。
以下にシナジー効果を最大化するためのPMIの具体的な進め方を、4ステップに分けてご紹介します。
▼M&Aのシナジー効果を生み出すための具体的なPMIの進め方
- ステップ1. 現状分析と統合方針を決める
- ステップ2. 100日プランを作成する
- ステップ3. 統合作業を着実に実行する
- ステップ4. 効果測定と改善を繰り返す
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
ステップ1. 現状分析と統合方針を決める
M&Aを行う2社の現状を理解しないままPMIを進めると、文化や制度の違いから対立や混乱が生じる恐れがあります。PMIを進める際は両社の特徴を以下の観点から多角的に分析し、共通点と相違点を明確にしましょう。
▼共通点と相違点を明確にするために分析すべきポイント
- 経営の理念とビジョン
- 事業内容
- 財務状況
- 組織構造
- 人事制度
- 企業文化
- 価値観
- 業務オペレーション
- ITシステム
「吸収合併」または「対等統合」などのM&Aの法的な枠組みを明確にし、会社のPMIの方向性を全社員で共有しましょう。
ステップ2. 100日プランを作成する
M&A後の100日プランを策定しておくことで「誰が・いつまでに・何をするのか」が明確になり、組織を同じ方向に動かせます。100日プランに盛り込むべき要素は以下の6つです。
▼100日プランに盛り込むべき6つの要素
- 領域ごとの目標設定
- 優先課題の特定
- 責任の明確化
- 関係者への説明計画
- 進捗確認の仕組みづくり
- 統合初日の準備
PMIを計画する段階で実現性の高い目標と責任体制を整えることで、統合後の安定と成長を早期に実現できます。
ステップ3. 統合作業を着実に実行する
PMIを成功させるには計画を現場任せにせず、進捗を可視化しながらタスクを進めましょう。M&A後のPMIを実行していく過程で想定外の問題や調整の遅れが発生することもあります。想定外のトラブルに備えるためには経営トップと現場がともに課題を把握し、柔軟に対応する仕組みを整えることが重要です。
進捗を管理しながら現場との信頼関係を築くことでPMIの実行力が高まり、統合の成果を着実に積み上げられます。
ステップ4. 効果測定と改善を繰り返す
PMIの初期段階で立てた計画どおりに進むとは限らないため、実績とのズレを把握して原因の特定と修正を重ねましょう。ズレを放置するとPMIによるシナジー効果が出ないだけでなく、組織に混乱を招く恐れがあります。
効果測定と改善を行うにはPDCAサイクルを継続的に回し、常に最適な統合プロセスを維持する姿勢が必要です。PMIの効果測定と改善のための効果的な取り組みは以下のとおりです。
▼PMIの効果測定と改善のための効果的な取り組み
- 取組み1. 目標達成度の確認
- 取組み2. 従業員の状況把握
- 取組み3. 差異分析と原因究明
- 取組み4. 実行プロセスの見直し
継続的に効果測定と改善を実施することでPMIの精度は除々に高まり、M&Aで想定したシナジーを最大化できます。
M&AのPMI開始前に準備すべき「3つのこと」
M&Aの成功はPMI開始前の準備段階で決まります。PMIを開始する前に以下のことを準備しておきましょう。
▼M&AのPMI開始前に準備すべき3つのこと
- 準備すべきこと1. PMIを始めるタイミングを見極める
- 準備すべきこと2. 統合推進チームを立ち上げる
- 準備すべきこと3. 達成すべき目標を明確化する
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
準備すべきこと1. PMIを始めるタイミングを見極める
PMIの準備はM&Aの交渉段階から始めることが理想です。M&A成立後にPMIの準備を始めると初動が遅れて体制づくりが後手に回り、従業員が不安や混乱を感じる原因になります。最悪の場合、人材流出や取引先との関係悪化につながります。
相手企業の調査と並行してPMIの準備を進めることで、統合後に必要な情報の事前整理が可能です。相手企業の調査で明確になった課題やリスクはPMI計画に直接反映させましょう。財務や人事、システムなどの課題を把握しておくとPMIをスムーズに実行できます。
準備すべきこと2. 統合推進チームを立ち上げる
M&Aは多くの部門が関わるため、特定の部署だけで対応すると抜け漏れや意思疎通の遅れが発生する恐れがあります。スムーズに統合を進めるにはM&AとPMIを推進する専門チームの立ち上げが必須です。統合推進チームを組織する際は、以下の項目を整えてM&A後の企業体制を構築しましょう。
▼統合推進チームを組織する際に満たすべき「6つの基準」
- 基準1. リーダーの選出
- 基準2. 各部門からの担当者選出
- 基準3. 役割とゴールの明確化
- 基準4. 意思決定権限の付与
- 基準5. 情報共有と会議ルールの設定
- 基準6. 外部専門家の活用
統合推進チームが中心となって部門間の調整や課題解決を主導することで、統合プロセスを効率的に進められます。
» PMI支援とは?重要性と失敗しない3ステップを解説!
準備すべきこと3. 達成すべき目標を明確化する
M&Aを成功に導くには統合後に「何を・いつまでに・どの程度達成するのか」を明確に定めることが不可欠です。ゴールが曖昧なままでは部門間の認識にズレが生じ、期待したPMIによるシナジー効果を得られません。M&A後に社員全員が同じ方向を向いて動くためにも、以下のような実現可能な目標を共有しましょう。
▼明確にすべき6つの目標
- 目標1. 売上シナジー
- 目標2. コストシナジー
- 目標3. 経営理念・ビジョン
- 目標4. 人材面の指標
- 目標5. 業務・システム統合計画
- 目標6. 財務目標
会社の目標を数値とスケジュールで定義しておくことで、組織全体が共通の成果イメージを持って行動できます。
M&AのPMIを成功させる「4つのポイント」
M&A後のPMIを成功させるには計画的な統合だけでなく、以下の4つの工夫が必要です。
▼M&AのPMIを成功させる4つのポイント
- ポイント1. 経営トップがリーダーシップを発揮する
- ポイント2. 自律性を尊重しつつ放任しない「ガバナンスのバランス」
- ポイント3. スピーディーに意思決定する
- ポイント4. バランスシート(B/S)の効率化を組み込んだ「攻めのPMI」
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
ポイント1. 経営トップがリーダーシップを発揮する
統合の過程では組織体制や業務プロセスが大きく変わるため、社員の間に不安や混乱が生じやすくなります。企業文化や価値観の違いから部門間の摩擦が起こることもあります。
M&A後に会社の進む方向を明確に示し、組織全体を1つにまとめるためには経営トップがリーダーシップを発揮しなければなりません。経営トップが統合の目的や将来像を自らの言葉で発信することで社員の不安を払拭し、組織全体の信頼が高まります。
ポイント2. 自律性を尊重しつつ放任しない「ガバナンスのバランス」
M&A後に買収先の文化や強みを無理に変えれば、優秀な人材の離職や士気の低下を招く恐れがあります。一方で、体制構築を任せきりにすれば業績管理や意思決定の遅れにつながります。
ガバナンスのバランスを保つためには統合初期から「見える化」と「規律の共有」を進めましょう。売上やコスト、KPIなどの経営データを把握すると迅速な意思決定や課題の早期発見ができ、健全な経営の維持につながります。
現場には一定の裁量を与えつつ、グループとしての経営方針とルールを統一しましょう。経営トップやPMIチームが定期的に状況を共有し、課題を把握することで現場との信頼関係を築けます。
ポイント3. スピーディーに意思決定する
意思決定が遅れると統合作業が停滞するだけでなく、社員の間に不安や憶測が広がって士気の低下を招きます。
M&A後のPMIが失敗する最大の要因は「決めないこと」です。完璧な計画の完成を待つよりも、素早く判断して実行しながらPMIを修正していく姿勢を持つ必要があります。
財務データや人事情報などの経営情報を共有できるシステムを導入しておくと、経営トップが情報を同時に確認可能です。経営トップが共通の情報をもとに議論できることで、認識のズレを防ぎつつ意思決定を迅速に行えます。
ポイント4. バランスシート(B/S)の効率化を組み込んだ「攻めのPMI」
企業が保有する資産や負債の中には活用されていない設備や過剰な在庫など、眠った資金が存在します。PMIの一環として非効率な資産を整理し、財務基盤を強化することで新たな成長投資の原資を生み出せます。
創出した資金は成長事業への設備投資や研究開発、新規M&Aへの再投資などに活用しましょう。総資産利益率(ROA)など、資産の効率性を測る指標を設定して全社で共有することもPMIの推進に効果的です。
バランスシートを最適化して資産を眠らせない構造をPMIで作ることが、M&Aを企業成長の戦略に転換する鍵となります。
M&AのPMIに関するよくある質問
M&AとPMIに関してよく寄せられる質問に対して解説します。
▼M&AのPMIに関するよくある質問
- Q1. 中小企業のM&Aでも内製化できる?
- Q2. M&A後の統合完了までどれくらいかかる?
- Q3. M&A専門家への相談タイミングはいつ?
それでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
Q1. 中小企業のM&Aでも内製化できる?
中小企業でもPMIを内製化することは可能です。ただし、すべてを自社で完結させようとすると、専門知識や人材リソースの不足によってM&A後の計画が滞るリスクが高まります。社内対応と専門家支援を組み合わせた以下のような「ハイブリッド型」で進めましょう。
▼専門家に任せるべき領域と社内で内製化しやすい領域
| 区分 | 専門家に任せるべき領域 | 社内で内製化しやすい領域 |
|---|---|---|
| 財務・会計 | 連結決算 資金繰り 税務処理 会計基準の統一 | 売上・経費データの共有 予算管理の運用 |
| 法務・契約 | 契約書の再締結 許認可手続き コンプライアンス体制の確認 | 契約書類の整理 社内ルールの共有 |
| 人事・労務 | 就業規則の統一 人事制度・給与体系の再設計 | 組織図の見直し 社内コミュニケーションの促進 |
| IT・システム | 基幹システムやデータベースの統合 | 社内ツールの整備 情報共有ルールの設定 |
| 経営・文化 | PMI戦略の策定 シナジー効果の数値化 | 経営理念の共有 社員向け説明会の実施 |
自社でできる範囲と外部に任せる範囲を見極め、必要な場面で専門家の力を借りることがPMIを円滑に進める鍵です。
Q2. M&A後の統合完了までどれくらいかかる?
企業規模や事業内容、組織文化の違いなどによって変動しますが、M&A後の統合が完了するまでには1〜3年程度かかります。
業務プロセスやITシステムなどの仕組みの統合は短期間で進められますが、社員の意識や企業文化の融合には長い時間が必要です。むしろ、価値観の共有や信頼関係の構築などの「目に見えない統合」こそがPMIの初期段階から継続的に取り組むべき課題です。PMIを長期的な企業成長を見据えたマラソンだと捉えて計画を進めましょう。
Q3. M&A専門家への相談タイミングはいつ?
M&Aを検討し始めた段階で専門家に相談すると、M&A後のPMIを見据えた戦略設計や体制づくりを早期に進められます。以下のような場面でM&A専門家への相談が効果的です。
▼M&A専門家への相談が必要な場面
- 自社の企業価値を正確に知りたいとき
- 買収・売却の相手候補を探し始めたとき
- 交渉や手続きの進め方に不安を感じたとき
- PMIを見据えて事前準備をしたいとき
M&A専門家への早期相談は不安を整理し、M&A後のPMIを成功させるための土台を築く第一歩となります。
中小企業こそM&AのPMI成功が明るい未来を切り拓く
中小企業におけるPMIは後継者不足や経営資源の限界を乗り越え、企業の未来を再構築するための取り組みです。PMIを通じて両社の強みを融合することで経営の効率化や新規事業の創出、市場拡大などのシナジー効果を生み出せます。
M&A後のPMIにおいては人と文化の統合こそが成功の鍵です。経営者と従業員が共通のビジョンを持ち、変化を前向きに受け入れることで組織全体の一体感と成長意欲が高められます。
その上で、以下の「PMIが網羅すべき統合の5つ領域」を参考に、PMIを進めていくことを心がけましょう。
▼PMIで成功するために網羅すべき統合の5領域
- 領域1. 経営のPMI:ビジョン・戦略の再構築
- 領域2. 人と組織のPMI:文化とエンゲージメントの融合
- 領域3. 業務オペレーション・ITシステムのPMI
- 領域4. 財務・経理のPMI:経営基盤の整備
- 領域5. ステークホルダーのPMI:不安解消と信頼関係の維持
ぜひ、混乱の少ないPMIを達成できるよう、本記事を参考にしていただけると幸いです。
事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に現場型の強いコンサルタントを選びましょう。
(株)Pro-D-use(プロディーユース)は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
そんな(株)Pro-D-use(プロディーユース)に、事業承継について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「事業承継コンサルサービス」詳細を見る >>
\“現場で一緒に”事業承継を進めます/
コラム著者プロフィール

岡島 光太郎
取締役副社長 兼 経営コンサルタント(Co-founder)
事業の「急所」を突き、収益構造を再構築する。
実務と経営を知り尽くした、現場主義の戦略家。
経営における課題は、決して単一の要素では生じません。
営業、マーケティング、財務、システム…。すべてが複雑に絡み合う中で、ボトルネックを的確に見極め、最短距離で解決へ導くこと。それが私の使命です。
私はリクルート等の大手企業における組織マネジメントと、急成長ベンチャーの創業期という「カオス」の両極を最前線で経験しきました。机上の空論ではなく、血の通った実務経験に裏打ちされたコンサルティングで貴社の事業成長を力強くご支援します。
■専門性と実績:収益最大化へのアプローチ
私の強みは、部分最適ではなく「全体最適」の視点にあります。株式会社リクルートでは営業・企画の両面で責任者を務め、MVPほか多数の受賞歴が証明する通り「売る力」を極めました。その後、データXやアソビューといった有力企業の創業・拡大期において、組織作りから新規事業の収益化、マーケティング、事業企画までを牽引。
これら現場叩き上げの知見をベースに、現在は以下の領域をワンストップで支援しています。
▼専門・得意領域
|収益エンジンの構築|
新規事業の0→1立ち上げから、Webマーケを連動させた「勝てる組織」の仕組み化。
|DX/業務基盤の刷新|
業務プロセスを可視化し、SaaSやITシステム導入による生産性の抜本的向上。
|財務・資金調達戦略|
事業計画と連動した融資獲得、キャッシュフロー経営の強化。
■仕事の流儀
「コンサルタントが入ってレポートを出して終わり」という関わり方はいたしません。経営者様の隣で、時には現場の最前線で、貴社の社員以上に貴社の利益にコミットします。
戦略を描くだけでなく、現場が自走できる状態になるまで徹底的に伴走いたします。
■資格・認定
中小企業庁認定:中小企業デジタル化応援隊事業認定IT専門家 / I00087391
経済産業省認定:情報処理支援機関 / 第39号‐24060007(21)