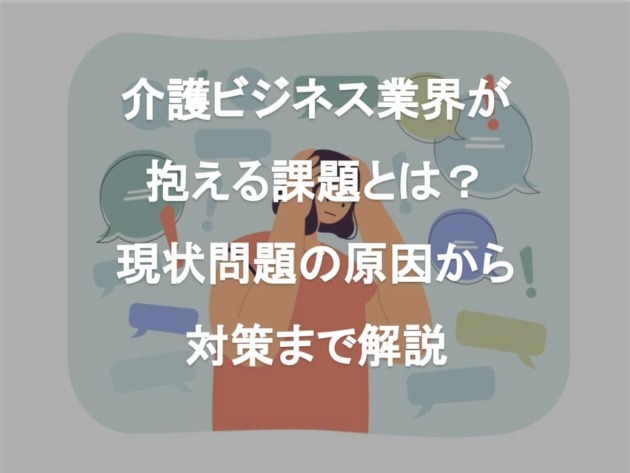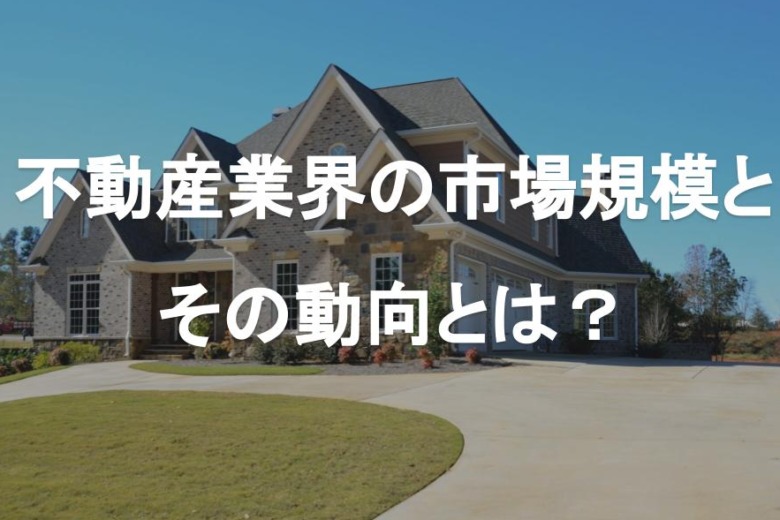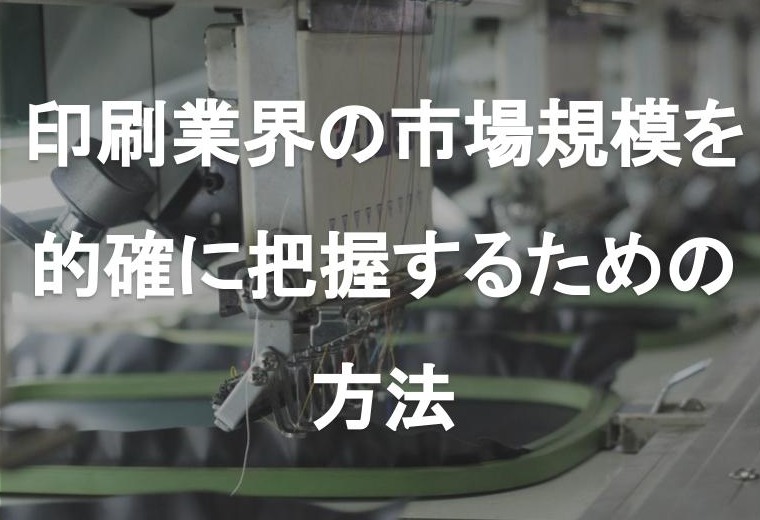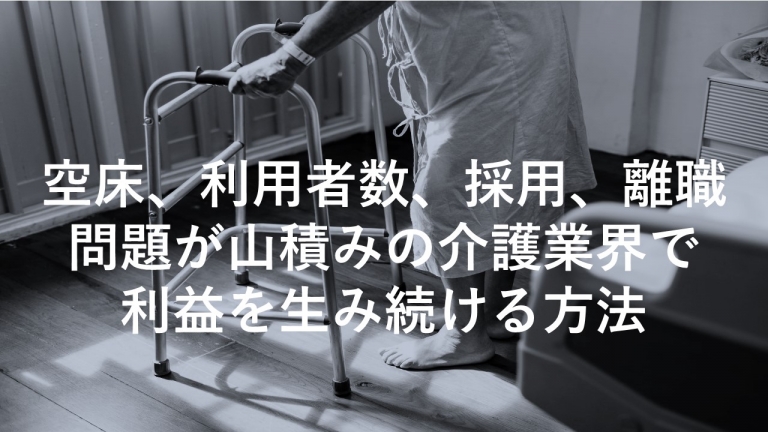新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。うまくいく新規事業には考え方や組織に一定のパターンがあり、それを知らずして新規事業を立ち上げても上手いかないケースがほとんどです。
「Pro-D-use」は伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談に乗り「売上10.38倍」「営業利益大赤字→23%の黒字化」など、数多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use」に新規事業の立ち上げ・実行について相談してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る

介護ビジネスの市場規模や今後の展開について知りたい。

介護ビジネスに参入しようと考えている。介護ビジネスには新たに参入する余地はあるのか?
介護ビジネスに参入を考えている方にとって、このような疑問を持っていう方は多いのではないでしょうか。
実は、介護ビジネスの市場規模は、2025年には2010年の約2倍にあたる予想がされているほど注目を集めています。
大きな要因としては、日本の高齢者人数増加による介護ニーズの増大です。
そこで、本記事では、介護ビジネスにおける重要な3点について詳しく解説していきます。
- 介護ビジネスの市場規模
- 介護ビジネスのメリット、デメリット
- 介護ビジネスのマーケティング方法
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 介護業界の現在の全体像から将来までを把握できるため、介護業界のリサーチにかける時間が短縮されます。
- 介護ビジネスで起きている動きが把握でき、今後のビジネスチャンスの手助けになります。
それでは早速、読み進めていきましょう。
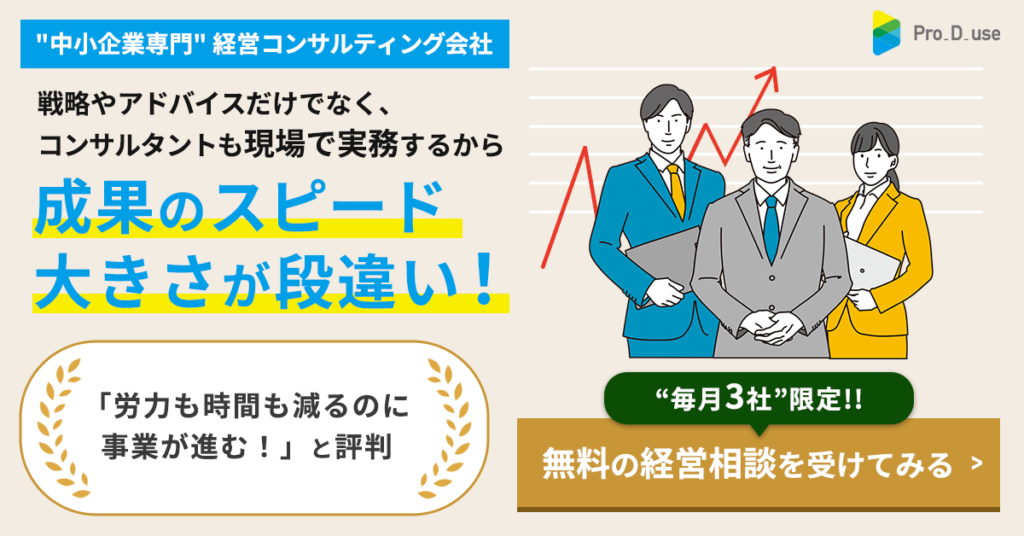
▼目次
2025年には市場規模が今の2倍|介護人材不足の現状
日本の高齢者人口は年々増加しており、65歳以上の高齢者の割合を表す高齢化率は2025年に30%を超えると予想されています。
また2025年には団塊の世代が75歳以上となり、全人口の20%弱にあたる約2,200万人が後期高齢者という超高齢化社会がやってくるのです。
これは「2025年問題」ともいわれ超高齢化社会に対応したさまざまな対応が求められています。
介護ビジネスの市場規模も年々拡大して右肩上がりの成長が確実視され、2025年の介護サービスの市場規模は2010年の約2倍にあたる15.2兆円と予想されています。
そのため拡大する介護サービスニーズに応えるため新規参入や既存業者の業務拡大による対応が求められているのです。
しかし成長が確実だからといって新規参入すれば成功が約束されるわけではありません。
介護業界の人手不足は現在深刻なものになっており、厚生労働省によると全職種の平均有効求人倍率が1.46倍なのに対し、介護職は3.95倍、訪問介護職は13.1倍と非常に高い数字になっています。
介護ビジネスに新規参入し安定経営をするためには介護ビジネスならではの特性をしっかりと把握することが重要です。
また高齢者だからといって必ず介護サービスを必要とするわけではありません。
介護ビジネスだけに限らず、高齢者向けの生活産業の市場規模も2025年には51.1兆円と2007年の40.3兆円に比較して27%増加すると予想されています。
宅配や家事代行など高齢者のニーズに対応した生活支援サービスを提供することも大きなビジネスチャンスといえるでしょう。
介護ビジネス業界が抱えている3つの問題点
介護ビジネスの特性を把握するためには、現在、介護ビジネス業界が抱えている問題点を知っておくと良いでしょう。
この項目では、介護ビジネス業界の中でも特に知っておくべき3つの問題点を紹介します。
- 制度改正の度に大きな影響を受ける
- 人材の確保が困難
- 他事業所との差別化が困難
それぞれ解説するので、ぜひ参考にしてください。
制度改正の度に大きな影響を受ける
介護保険制度は3年ごとに改定されますが、介護ビジネスには介護保険が大きく関係します。
制度上の影響を受けざるを得ず、施設への入所基準や提供できるサービスが変わるなど従来のやり方が通用しなくなる可能性もあるのです。
また、日本の社会保障費は増大傾向にあります。保険料収入だけでまかなうことは難しく、半分近くは公費で補っているのが現状です。
そのため、介護報酬についても見直される可能性があり、現状大きく利益が出ているサービスが提供できていても、改定により報酬が減額されるかもしれません。
介護ビジネス業界では、その流れを敏感にキャッチしてどのような制度改正が行われるのかを予想することが重要です。
人材の確保が困難
人材の確保も介護ビジネスにとっては大きな問題です。
年々利用希望者が増える介護ビジネス業界ですが、介護希望者を多く集めることができても職員が不足していては、介護サービスを提供することはできません。
介護業界には、3Kともいわれる、きつい・汚い・給料が安い、というイメージがあり、就職希望者が増えないのが現状です。また賃金が安いことなどによって、介護業界の離職率は高い傾向にあります。人材の採用と合わせて育成についても重要な課題です。
近年では、働き方改革や介護職の給料の増加など、働く環境は改善されつつありますが、年々増える介護利用者の需要を満たすためには、さらなる改善が必要といえます。
他事業所との差別化が困難
介護ビジネスにおけるサービスの内容や料金については、制度上画一化されています。そのため、他事業所より質の高いサービスを提供していても、その違いが見えにくいという問題があります。
そのため、他事業所との差別化が他の業界に比べて難しいです。今後参入する企業が増え競争が激化することも予想される中で、他事業所との違いをターゲットにどう認知してもらうかというマーケティングも重要になってくるでしょう。
また、介護ビジネスは前述の通り、制度改正に影響を受けやすく、人材の確保も難しい業種です。経営が安定しない中で、さまざまな工夫を凝らさなければならない点も、差別化を困難なものにしています。
介護業界の問題に対する3つの課題解決策
介護ビジネス業界はさまざまな問題を抱えています。業界に参入するためには、これらの問題を解決していかなければいけません。
そこでこの項目では、介護業界が抱える問題に対する3つの課題解決策を紹介します。
- 幅広い介護人材の確保
- 待遇、労働環境の改善
- ICTやロボットを活用した業務効率の改善
それぞれ詳しく説明するので、ぜひ参考にしてください。
幅広い介護人材の確保
介護を希望する高齢者は年々増加することが予想されます。そのため、介護人材を確保することは介護ビジネスでは必要不可欠です。
現在、国も介護人材の待遇改善などを行い、人材確保の支援を行っていますが、さらにより多くの介護人材の雇用が必要な状態です。
そのためには、未経験者や外国人、育児中の方など多様な人材に目を向けると良いでしょう。事業者間で人材を奪い合うのではなく、広い人材マーケットからの参入を狙うことで、人材の確保が困難という問題を解決できます。
未経験者や外国人でも働けるよう、しっかり育成できる職場環境を作ることが大切です。
待遇、労働環境の改善
待遇や労働環境の改善は、人材の確保や定着に役立ちます。近年は国の施策により介護職の給料は上がりましたが、まだまだ待遇や労働環境が良いとはいえません。3Kといわれる労働環境のイメージから脱却できるような、良質な労働環境を整えましょう。
厚生労働省が発行した、介護労働者の労働条件の確保・改善のポイントによると、就労時間や休日の設定、ストレスチェックなどを行うことが大切です。
また、36協定を締結し労働保険の手続きも行ってください。他にも、介護従事者の資格取得の支援やキャリアパスの構築を行うなどによって、労働環境は大きく改善します。
ICTやロボットを活用した業務効率の改善
人材不足対策には、ICTやロボットの活用も有効です。紙媒体で利用者の管理や勤怠の管理を行っている場合には、システムの導入によって大幅な工数短縮ができるでしょう。介護記録にICTを活用すれば、円滑な情報共有が可能となり、より良いサービスの提供が可能です。
このように、ICTを活用することで従業員の負担が大幅に軽減でき、3Kのイメージ払拭による就職希望者の増加や、定着率の向上が期待できます。
また、近年は介護ロボットも実用化されています。「移乗介助」「移動支援」「排泄支援」「入浴支援」といった、負担の大きな部分がロボットにより軽減されるため、業務効率改善のために、ぜひ導入を検討してみてください。
なお、中小企業のICT改善についは下記のような専門会社へご相談するのが有効です。業務効率化をお考えの方は1度、アクセスしてみてください。
介護ビジネスのメリット
介護ビジネスには介護保険が関連してくるため一般的なビジネスとは違ったメリットとデメリットがあります。
それでは介護ビジネスにはどんなメリットがあるのかを考えてみましょう。
まず資金回収のリスクが少ないことが挙げられます。介護保険は10%が自己負担、90%が保険でまかなわれています。
つまり介護報酬の90%が国保から支払われますので安定的に収入を確保でき、貸し倒れのリスクは限りなく低いビジネスであるといえるでしょう。
通所介護や訪問介護なども含めいったん顧客を獲得すれば他の業者に流れる可能性は低く、他のサービス業と比べても高いリピート率を見込むことができます。
また介護報酬額については厚生労働省で決められているので、一般的なサービスのように価格競争に巻き込まれるリスクがないこともメリットといえるでしょう。
無理な値下げをして利益を圧迫されるようなこともないので安定経営につながるのです。
介護事業者向けの助成金もあり小規模でも参入しやすいというメリットもあります。
在庫を抱える必要もないので資金を回しやすいビジネスであるといえるでしょう。
今後メインの顧客となる団塊の世代は高度成長期を経験して大量消費の先頭に立ってきました。
そのため今までの高齢者とは違った価値観を持っており、介護サービスに対するニーズも多様化することが予想されます。
そのニーズに応えるために介護保険外のサービスなどを合わせて提供すれば利益率を高めることにもつながるでしょう。
しかし、介護サービスのニーズを正確に捉えることや活用することはノウハウがなければ難しいです。需要と異なることをしてしまい「結局赤字に終わってしまった」となる可能性もあるでしょう。
Pro-D-useは経営コンサルタントのプロが市場を調査し、正確な経営コンサルティングが可能です。
介護ビジネスのサポートもPro-D-useにぜひご相談ください。
「課題は分かったものの、うまくできる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る
介護業界のマーケティング
介護ビジネスは制度上サービスメニューや料金が画一的なため他事業所と差別化しにくい傾向があります。
そのため似たような事業所が多く存在する中で自社を選択してもらうためには、マーケティング戦略が重要になるのです。
介護ビジネスは地域密着性が高いため、まずその地域の特性を把握することが重要です。どのようなサービスについてのニーズが高いのか、既存の業者は利用者に満足度の高いサービスを提供できているのかを調査、検討することが大切になります。
そのうえで自社ならでの優位点をピックアップし、他事業所とは違ったポジショニングを行うのが重要です。
他事業所との違いがあいまいであったり、ポジショニングが似ていたりしたのでは差別化につなげることは難しいでしょう。
例えば「○○の点は優れている」「○○は他事業所にはない」のように他事業所よりも優れている点やオリジナル性の高い点に注目すると効果的なポジショニングを行うことが可能です。
ポジショニングによって訴求すべきポイントが明確になったら、それをターゲットに効率よく伝えるプロモーションが必要になります。
商圏の大きさや事業の規模にもよりますがチラシやパンフレット、フリーペーパー、Webなどあらゆる媒体を活用して情報発信することが必要です。
他事業所との違いを明確に伝えることができれば大きな差別化につながるでしょう。
多様化する介護サービス
介護サービスの提供を受ける顧客の中心が団塊の世代になっていくのに伴い、介護サービスの内容も多様化することが予想されます。
団塊の世代は、それまでの高齢者とは違ってそれぞれのライフスタイルを重視する傾向があります。
そのため介護サービスについても多様化するニーズへの対応が求められるでしょう。
介護を必要としない高齢者も年々増加するのに伴い介護予防サービスへのニーズも高まります。
介護予防訪問看護や介護予防訪問入浴介護など「要介護にならない」「要介護の度合いを重くしない」ためのサービスを充実させることも重要になるでしょう。
また高齢者に求められるサービスは介護関連だけではありません。
食事や掃除などの家事、庭の手入れなどの代行、食料品や弁当の宅配など高齢者の生活を支援するサービスへのニーズも高まることが予想されます。
介護サービスと連携してこのような介護保険外のサービスを提供することで、より多くの顧客を獲得することにもつながるのです。
介護ビジネスは訪問系、通所系であっても地域密着型のビジネスです。
地域のニーズをしっかりと探り、どのように制度改定されるかを予想しながら、他の事業所にはない質の高いサービスを提供することが重要になります。
戦略的に他の事業所と差別化できるポジショニングを行い、介護ビジネスの成功へとつなげていきましょう。
「株式会社Pro-d-use」では、経営コンサルティングのプロが新規事業の調査から企画・立ち上げ・推進、収益化までを実際に現場に入って一緒に事業を進めます。
介護業界への参入も含めて、非常に煩雑で難しい新規事業の企画・立ち上げ、推進や収益化でお困りの際は、ぜひ一度、私たち株式会社Pro-d-useにご相談ください。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。うまくいく新規事業には考え方や組織に一定のパターンがあり、それを知らずして新規事業を立ち上げても上手いかないケースがほとんどです。
「Pro-D-use」は伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談に乗り「売上10.38倍」「営業利益大赤字→23%の黒字化」など、数多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use」に新規事業の立ち上げ・実行について相談してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る
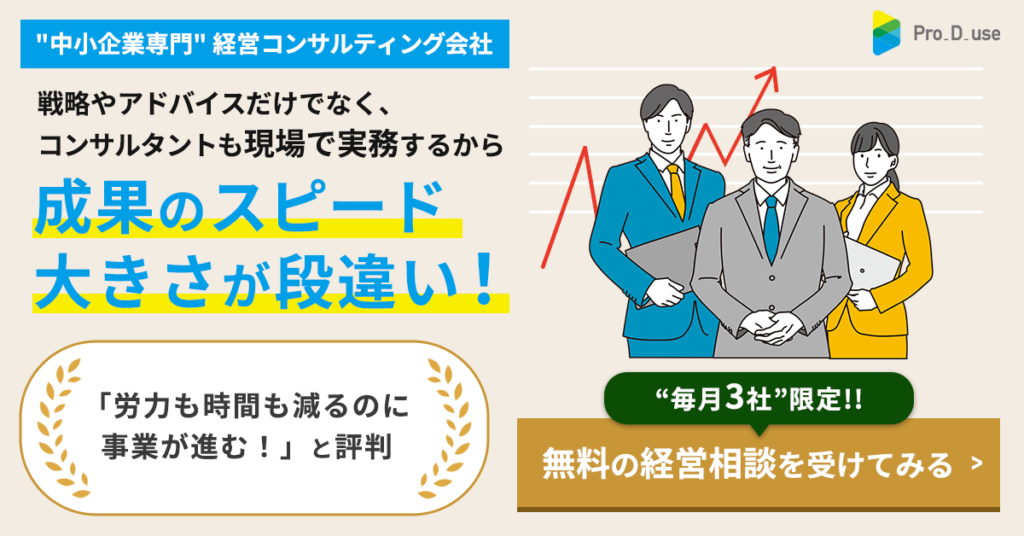
<参考>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-1.pdf
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/pdf/1039_03_03.pdf
http://www.r-lease-cc.jp/weekly/kaigoshijyou-sannyu/
https://books.google.co.jp/books?isbn=4798136239
https://www.projectdesign.jp/201310/nursing/000853.php
コンサルティング参考>> ICTの力で生産性向上を実現|株式会社Ardent(アーデント)