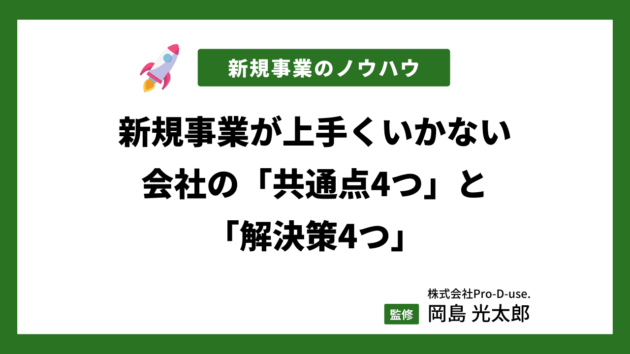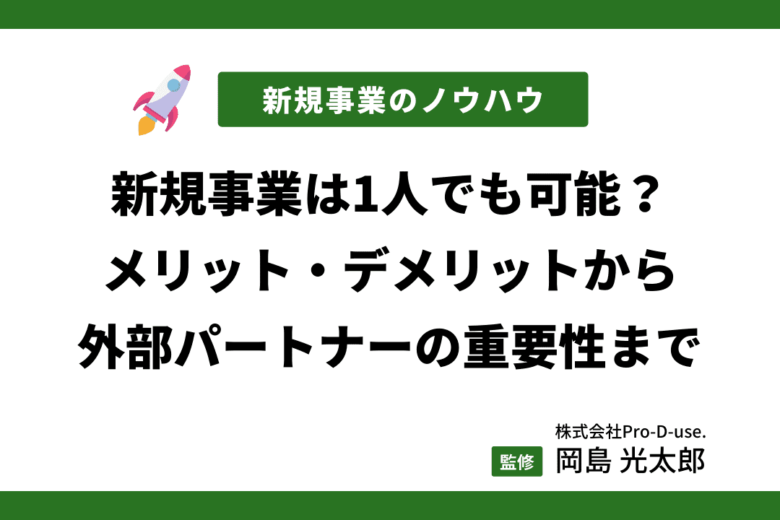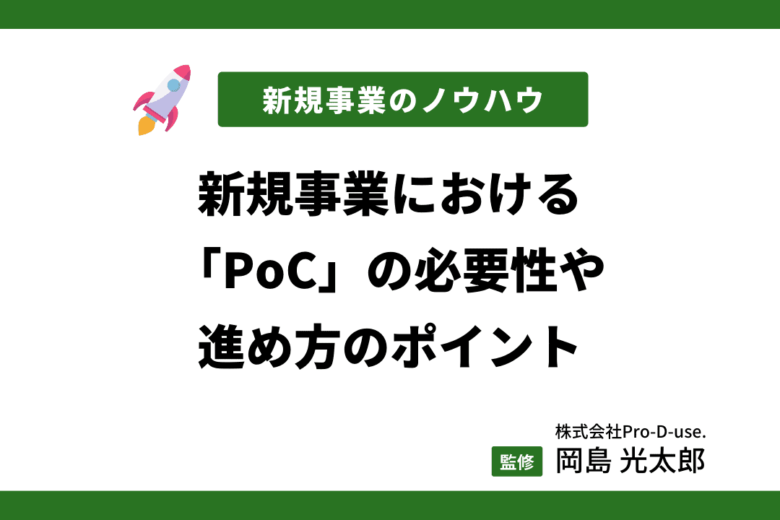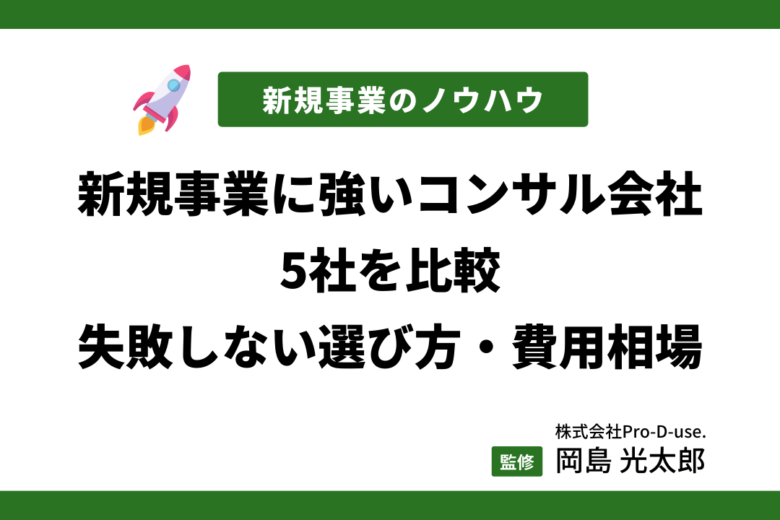新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業サービスはコチラ >>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /

新規事業において、失敗する可能性があり注意しなければならないポイントを事前に知りたい。

新規事業において、スピード感が重要なのは理解しているがスピード感が出ない。どのようにしたら、スピードをもって事業を進められるのだろうか。
新規事業に携わっていると、このような悩みや疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
もちろん、新規事業がうまくいかない理由は会社によってさまざまですが、実は共通して陥りがちなポイントがあります。そういったポイントを放置したままにすると、新規事業は当然うまくいきませんので、何らかの対処をしなければなりません。
新規事業がうまくいくためには、下記の2つのポイントが重要です。
- 新規事業を進められる環境が整っている。
- 事業を取り巻く環境に適応する。
本記事では、新規事業がうまくいかない会社の共通点とそれらに対する解決策4つをご紹介します。
この記事を読めば、こんなことが実現できます。
- 新規事業を進めて行く前に、あらかじめうまくいかない要因を把握しておくことで、スピード感をもって事業に取り組むことができます。
- 新規事業がうまくいっていない理由が明らかになるため、「何が原因でうまくいっていないのか」と悩む余計な時間が無くなります。
それでは早速、読み進めていきましょう。
▼目次
新規事業がうまくいかない会社に共通する4つのこと

会社によって新規事業がうまくいかない理由はさまざまですが、新規事業がうまくいかない会社には以下4つのような共通点が多く見られます。
- アイデア自体がなかなか見つからない
- 調査や分析に時間をかけすぎる
- 当初の計画を修正せずにそのまま進めようとする
- 社内で事業化を承認してもらえない
それぞれ、詳しく解説していきます。
1. アイデア自体がなかなか見つからない
本来新規事業の立ち上げは、何か実現したいアイデアがベースにあってそれをもとにして進めていくのが基本です。
ただ会社によってはアイデアベースではなく、「新しい風を会社に吹き込みたい」とか「競合他社に置いていかれるわけにはいかない」といったような、会社の決定ベースで新規事業が立ち上げられることもあります。
このような場合は、新規事業の核となるべきアイデアが見つかっていないゼロからのスタートになることも多いので、アイデアを見つけるところから始めなければなりません。
しかし、アイデアを見つけるということは0を1にするということであり、これが1を10にしたり10を100にしたりすることよりどれだけ難しいかは、経験者であればお分かりでしょう。
うまくいきそうなアイデアや会社の既存事業にフィットしそうなアイデアがなかなか見つからないと、新規事業計画はそのまま頓挫してしまう可能性が高いです。
2. 調査や分析に時間をかけすぎる
新規事業を進めるにあたってどのような顧客層をターゲットとして設定するか、市場規模はどのくらいありそうか、ライバルとなり得る商品の強み・弱みはどのような点かなどを調査・分析するのは、非常に重要です。
ただ、調査や分析に時間をかけすぎて、半ば目的化してしまうのはよくない傾向です。
データを調査・分析することで自社にとって都合のいい結果が出て、そのままスムーズに新規事業を進められるのが理想的ではありますが、期待している通りの結果が出ることなどほぼありません。
だからと言ってまた期待通りの結果が出るまで調査や分析を続けてしまうと、貴重な時間を無駄使いすることになります。
その間に他社から新商品が出たり世間の流行が変わったりで、後手後手に回ってしまう可能性もあるでしょう。
ある程度のところでゴーサインを出せるかどうかも、新規事業の立ち上げでは非常に重要なポイントです。
あわせて読みたい
新規事業の成功率がグッと上がる!「ニーズ調査」7つの手法をプロが解説
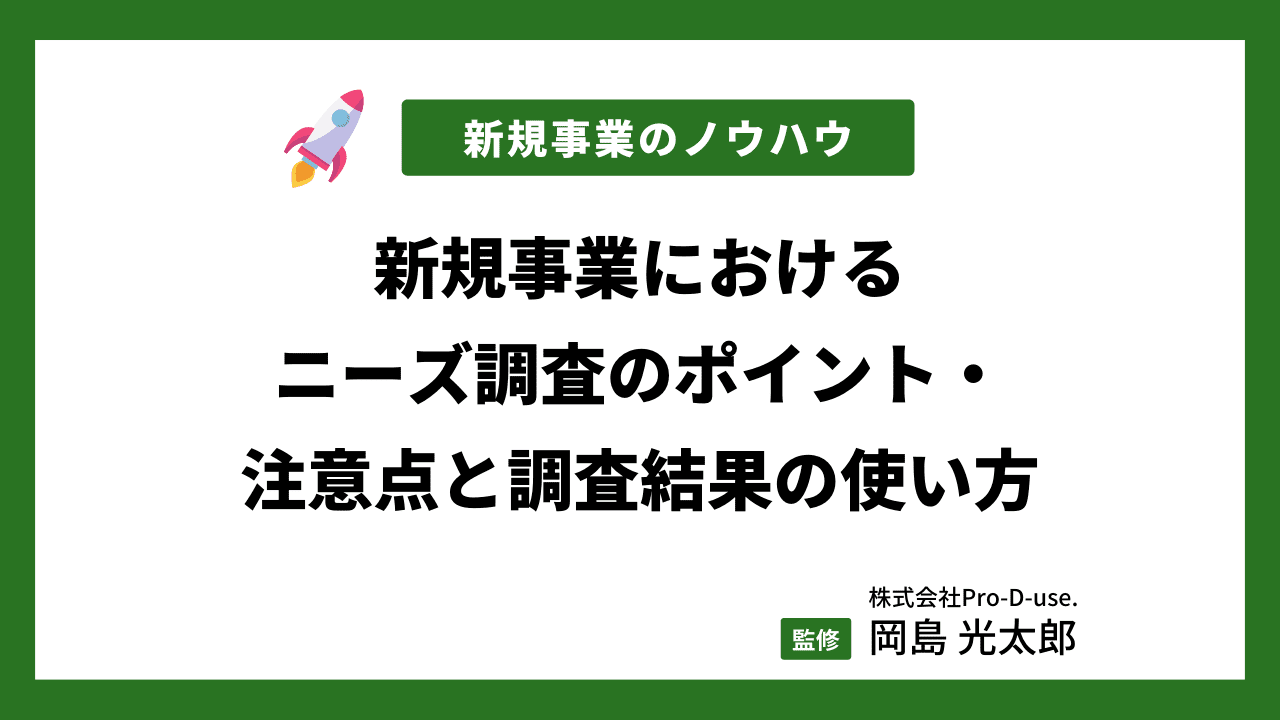
これから新規事業の調査をする新規事業責任者の方なら、以下のことに悩んでいるのではないでしょうか? 「新規事業のサービス・商品のニーズがあるか知りたいが、どう調査すればいいかわからない…。」「ニーズ調査で、押さえるべきポイントを知りたい。」…
3. 当初の計画を修正せずにそのまま進めようとする
新規事業を立ち上げる際に、しっかりとした骨子や計画を組むことは非常に重要ですが、それに固執しすぎるのはあまりよくありません。
先ほど少し触れたように、新規事業を取り巻く環境は刻一刻と変わっていくので、それに応じて柔軟に対応したりリスケをしたりしなければならないからです。
新規事業に賭ける想いが強すぎると、最初に打ち立てた理想をどうしても捨てきることができずに、多少無理な状況でも当初の計画のまま突き進もうとするきらいがあります。
まったくアイデアがない状態での新規事業立ち上げはそれはそれで骨が折れますが、アイデアに対する思い入れが強すぎる状態での新規事業立ち上げには、思わぬところに落とし穴が潜んでいるものです。
4. 社内で事業化を承認してもらえない
新規事業立ち上げとはいっても、事業領域が社内ですでに行っている事業とまったくかぶらないようなことはほとんどなく、既存事業と何らかの形で競合するケースも少なくありません。
そうなると既存事業で上がっている利益を守るために、新規事業を実際に事業化するための承認がもらえないこともあります。
場合によっては新規事業にゴーサインを出してもらうために、関係者への根回しが必要になるようなこともあるのですが、そのような点を疎かにしてしまうと承認の壁に阻まれて、事業化寸前で頓挫してしまうことも考えられます。
「課題は分かったものの、うまく対処できる自信がない」
「自社の状況に当てはめると、どう考えれば良いんだろう…?」
そんなときは、私たち「Pro-D-use」に相談してみませんか?Pro-D-useは伴走型の新規事業開発・収益化支援を得意とするコンサルティング会社です。詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
Pro-D-useの新規事業支援サービスの詳細を知る
4つの要因に対する4つの解決策

新規事業がうまくいかない場合は、上述した4つの要因のいずれか(もしくはすべて)に苦しめられている可能性が高いので、それぞれの要因に対して確実な対処をしなければなりません。
それぞれの対策としては下記の4点です。
- 社会の「不」を見つけてアイデアを出す
- 最初から完璧は目指さない
- 優先順位や最低ラインを決める
- 事業化によるメリットを整理する
こちらもそれぞれ、詳しく解説していきます。
1. 社会の「不」を見つけてアイデアを出す
よいアイデアを見つけるためには、社会にはどのような「不」があるかを探し出すことが重要です。
その「不」が明らかなものであったり自社との関りが薄いようなものだったりすると事業化は難しいですが、「不」が潜在的なものでかつ自社の事業と関係しているようなものであれば、新規事業の種になりえます。
「不」には例えば、
- 不満
- 不安
- 不便
- 不快
のようなものがありますので、日ごろから生活の中でさまざまなところにアンテナを張って、ささいな違和感やちょっとした発見を見逃さないようにすることで、社会が抱える「不」を探しやすくなるでしょう。
2. 最初から完璧は目指さない
また調査や分析に時間をかけすぎないようにするには、ようにしなければなりません。
どの程度のデータが出ればOKか、マネタイズが可能そうかというラインをあらかじめ決めておいて、そのラインを超せそうだということが分かったら調査・分析を切り上げて次のフェーズに進んでしまいましょう。
計画の修正のために適宜調査や分析を行う必要はありますが、それは専門のチームを組むなどして事業を推進する傍らで行っても、十分対処できます。
3. 優先順位や最低ラインを決める
当初の計画にこだわりすぎないようにするためには、計画なり骨子なりの中で譲れないものは何かを考えて優先順位を付けるようにしましょう。
外部環境の変化などで計画に手を加えることを余儀なくされても、変更になる部分が優先順位が比較的低めの部分なのであれば、甘んじて受け入れることで柔軟な対応が可能になります。
枝や葉っぱの部分を多少付け替えることになっても、幹の部分さえ事業立ち上げ時のまましっかりとしていれば、新規事業への情熱も冷めることなく前に進んでいけるでしょう。
4. 事業化によるメリットを整理する
社内で事業化を承認してもらうためには、新規事業を立ち上げるメリットをアピールしなければならないことはもちろんですが、既存事業にどのような影響が出る可能性があるかについても同時に説明する必要があります。
既存事業に悪い影響が出ない、もしくは既存事業に多少影響が出る可能性があるものの、新規事業を始めることによるメリットがそれを上回るようであれば、事業化の承認はしてもらいやすいでしょう。
先ほども少し触れたとおり、関係するであろう事業部の責任者などにはあらかじめ話を通しておく、といったような社内政治を行う必要もあります。
新規事業立ち上げのためには、そういった裏の部分での努力も必要になることが多々あるということを肝に銘じておきましょう。
新規事業立ち上げ時は経営コンサルティング会社に相談しよう!

新規事業を立ち上げる際にはいろいろな障壁がありますが、そういった障壁を自力で越えていくのは並大抵のことではありません。
そのため、経験が豊富なプロにサポートを依頼することで新規事業をスムーズに立ち上げられる可能性が高くなります。
これまでに新規事業立ち上げを数多くサポートしている経営コンサルティング会社であれば経験値も豊富ですし、社内で事業化を認めてもらうための材料のひとつとしても使えます。
経営コンサルティング会社の利用は、新規事業立ち上げという目的のための手段のひとつなので、効果的に活用することで新規事業を上手に推進させていきましょう。
新規事業は「なんとなく」で進めると、必ず失敗します。上手くいく新規事業には一定のパターンがあり、それを知らずに新規事業を始めてはいけません。
「Pro-D-use(プロディーユース)」は、“伴走型の新規事業支援” を得意とするコンサルティング会社です。これまで200件以上の新規事業の相談を受け「売上10.38倍」「営業利益大赤字→営利23%の黒字化」など、多くの実績をあげてきました。
そんな「Pro-D-use(プロディーユース)」に【新規事業の無料相談】してみませんか?詳しくは新規事業支援サービスページをご覧ください。
\\ プロに相談して楽になる! //
新規事業サービスはコチラ >>>
\ 新規事業の悩みがスッと軽くなる!! /