事業承継を考える多くの経営者は、「事業承継の失敗は避けたい」とお考えのことと思います。また事業承継に際して、「業績課題」や「コミュニケーション課題」でも悩んでいるのではないのでしょうか。
「事業承継は失敗できない。過去の失敗事例を参考にしたい…」
「事業承継で社内の混乱を避けるため、どんな準備が必要?」
「事業承継後の業績不振を避けるにはどうすればいい?」
実は、「事業承継」は事前の計画と準備なしだと、ほぼ100%多くの問題に直面してしまうことになります。仮に最初は上手くいったとしても、後々表面化するようなこともあります。
現場で支援している筆者が感じる、事業承継のよくある失敗事例は下記5つです。
◆ 事業承継でよくある5つの失敗事例
- 後継者が見つからない
- 準備不足が原因で社内混乱
- 親族トラブル
- 事業承継後の業績不振
- 相談しないまま事業承継を進めてしまう
「財政状況・業績の安定化」や「後継者との意思疎通」、「組織の安定化」、また、「節税対策」に至るまで、事業承継を失敗させないためには、早期に準備を開始し、しっかりと計画を立てる必要があります。
筆者は「株式会社Pro-D-use」という経営コンサルティング会社で、これまでたくさんの「事業承継」の成功も失敗も見てきました。
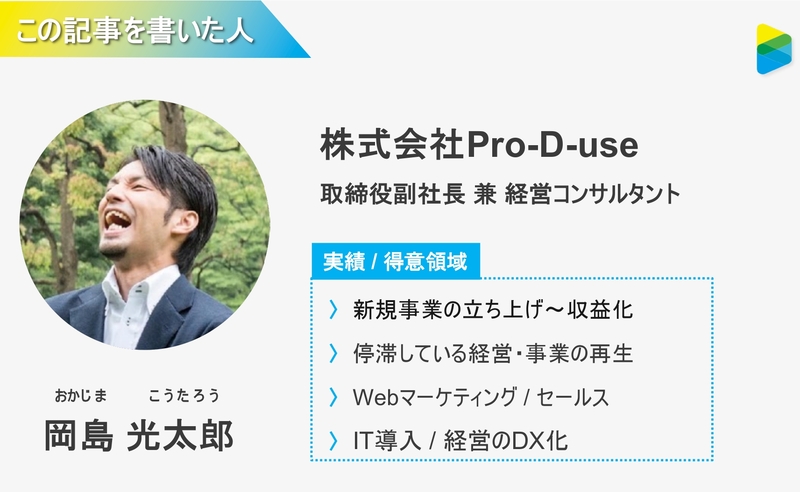
本記事では、事業承継の際に生じる様々な失敗事例と、それらを防ぐためのポイントについて詳しく解説します。
事業承継が失敗する主な理由は以下。
- 準備不足による社内混乱
- 親族間や派閥間のトラブル
- 財政状況の悪化
- 事業承継計画の不備
本記事を読で実現できること
- 事業承継失敗のリスクが減る
- 今後の事業計画において、リスクを未然に回避できる
事業承継を成功させるためには、現在の経営者と後継者が共に意思を疎通し、企業文化や理念を継承しながらも新しい風を取り入れる柔軟性が必要です。
ぜひこの記事を参考に、事業承継における理解を深め、計画的な準備と実行に役立ててください。
\ スムーズな事業承継をするなら!! /
事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に強いコンサルタントを選びましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>
\ “現場で一緒に” 事業承継を進めるなら!! /
事業承継の5つの失敗事例
まずは、事業承継でよくある失敗事例のパターン、以下5つを紹介します。
◆ 事業承継5つの失敗事例
- 失敗事例1. 後継者が見つからない
- 失敗事例2. 準備不足が原因で社内混乱
- 失敗事例3. 親族トラブル
- 失敗事例4. 事業承継後の業績不振
- 失敗事例5. 相談しないまま事業承継を進めてしまう
それぞれの失敗事例について解説していきます。
失敗事例1. 後継者が見つからない
事業承継をしなければいけない状況で、後継者が見つからないという失敗事例は多くみられます。事業継承をしなければいけない状況で、「後継者が見つからない」という失敗事例は多くみられます。以下の事例をご覧ください。
◆ 後継者不在の事例
後継者となり得る人材は親族と考えていましたが、後継者になる意思はありません。従業員や役員など、多くの人材を探しましたが、後継者となりうる人材は見つかりません。それでも諦めずに探し続けていましたが、結果的には廃業を選ぶことになりました。
後継者不在問題は、度々ニュースでもとりあげられており、特に中小企業においては以下のニュースのように社会問題となっております。
このような事態にならないためにも、専門家に頼る方法もあるので、早めに人材を見つけておくことが重要です。
失敗事例2. 準備不足が原因で社内混乱
事業承継は、綿密な計画と入念な準備がなければ成功することはできません。「事業継承」は綿密な計画と入念な準備がなければ成功することはできません。以下の事例をご覧ください。
◆ 社内混乱を引き起こす準備不足の事例
ある日突然、体調を崩してしまい、後継者として息子に経営を引き継ぎました。しかし、事業承継の進め方や、ノウハウを伝える準備をしていませんでした。その結果、社内が混乱してしまいました。経営不振によって、多くの従業員が退職する結果になりました。
事業承継では、経営者一人でおこなえないので、事前に事業承継をどのように進めるべきか決めておく必要があります。実際に、引き継ぎが上手くできていないと、手探り状態で経営を進めてしまうので、業績が悪化してしまう原因となります。
このように、経営者自身が健康に自信があっても、いつ何が起こるのかわからないので、事前に準備をしておきましょう。
失敗事例3. 親族トラブル
事業承継が失敗してしまうケースとして、親族トラブルも多くみられます。事業継承が失敗事例には「親族トラブル」も多くみられます。以下の事例をご覧ください。
◆ 親族トラブルが発生した事例
事業承継後は、経営者として長男が会社の経営をおこないました。次男は他の企業へ勤めているので、株式の一部を次男に相続しました。しかし、会社の業績は悪化してしまう事態になりました。そのような状況にもかかわらず、次男は配当を要求していました。結果的には業績改善へ活用できず、会社を畳むことにしました。
こうした相続後の親族トラブルは多くあるので、親族が絡んでいる事業承継では、慎重に決めることが大切です。
失敗事例4. 事業承継後の業績不振
業績不振による事業承継の失敗はもっとも多いケースです。筆者のクライアントでも、業績が悪かった(「赤字」「債務超過」「リスケ」など)ため、承継予定であった娘さんから「NO」を突きつけられて承継を断念したケースもありました。
その他、事業不振による事業承継の失敗は、以下の事例をご覧ください。
◆ 事業承継後に業績不振になった事例
周囲からの信頼が厚い経営者の引退が決定しました。事業承継はスムーズにおこなわれて、後継者が新たに経営をおこなうことに何の問題もなくスタートしました。後継者は、経営の仕方が悪かったのか、会社の業績を悪化させてしまったのです。経営を立て直すのは難しく、従業員の多くが退職してしまう事態となりました。
このようなケースは、事業承継後のアドバイスやサポートなどを怠ったことが原因といえます。事業承継後でも経営が安定するまでに、しっかりと引き継ぎをおこなうようにしましょう。
失敗事例5. 相談しないまま事業承継を進めてしまう
経営層や従業員などに相談せずに事業承継を進めてしまうケースも少なくありません。経営層や従業員などに相談せずに事業承継を進めてしまうケースも少なくありません、以下の事例をご覧ください。
◆ 自分一人で事業承継を進めたため、従業員が離反した事例
自分一人で事業承継について調べ上げ、会社売却の手続きはスムーズに進めることができたかに見えましたが、ここで予想外の出来事が起きてしまいます。他の誰にも会社売却の相談をしていなかったので、大きな反感を買ってしまう事態となりました。次々に従業員は離職してしまい、廃業の選択を選びました。
このようなケースから、いかに事業承継に関して、やり切る自信があったとしても、事前に相談して納得を得ることが重要です。また、事業承継をするためには、専門家に依頼することによって、リスクを最小限に抑えて事業承継を進めることにもつながります。
事業承継の失敗は「4パターン」ある
事業承継の失敗について考えられるパターンについては、主に以下4パターンがあります。
◆ 事業承継の失敗4パターン
- パターン1. 廃業に追い込まれる
- パターン2. 業績悪化
- パターン3. 離職者の増加
- パターン4. 資金繰りが厳しくなる
それぞれの項目について解説していきます。
パターン1. 廃業に追い込まれる
事業承継の失敗によって、廃業に追い込まれてしまうリスクがあります。実際に、後継者の不在が理由で「廃業を選択する」経営者も少なくありません。
また、事業承継によってシナジー効果や業績の改善などが期待通りに進まずに、廃業を余儀なくされるケースも少なくありません。
例えば、筆者に事業承継の相談があったご年配のクライアントも、同業他社への会社売却によって事業承継を進めたのですが、「同業であるから経営基盤と顧客基盤が相互に使える」と期待した事業シナジーが叶わず、結局、その会社の事業も従業員も、整理・解雇をされてしまいました。
パターン2. 業績悪化
事業承継が失敗してしまうことによって、業績が悪化してしまうリスクがあります。具体的に、事業承継後に業績が悪化してしまう要因については以下4つのパターンがあります。
- 従業員に不満が蓄積しモチベーションが低下した
- 後継者の選定や育成が不十分
- 経営に必要な素質やスキルが備わっていなかった
- 他の株主が新経営者に反発して対立してしまった
上記のように、事業承継による業績悪化は、準備不足が主な原因といえるでしょう。また、本業の経営が疎かになってしまい、業績が傾いてしまったというケースも少なくありません。
パターン3. 離職者の増加
事業承継前後では、従業員が自社から離れてしまう可能性が高くなるので、従業員のフォローが重要です。
実際に、事業承継後に新たな経営者に変更になったことによって従業員が不満を持って大量に離職してしまうケースもあります。
しかし、若い新経営者に交代することで、企業の成長率がアップしたというデータもあるので、事業承継のやり方次第では、業績を向上させることにもつながります。
パターン4. 資金繰りが厳しくなる
事業承継に失敗してしまうと、資金繰りが厳しくなる危険性があります。主な原因として、事業承継後の業績改善や既存事業の成長が見込めないことが挙げられます。
また、金融機関から融資を受ける際には、経営者の人格や信用性を重要な判断材料としており、現経営者の存在によって信頼を得ていた場合には、事業承継は悪影響となります。
そのため、現経営者は後継者に対して、金融機関との関係性も引き継ぐことが必要です。
3つの事業承継の種類
事業承継の種類を把握しておくことで、事業承継の成功率を高めることにもつながります。
事業承継の種類については、以下の3つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
◆ 3つの事業承継のメリット・デメリット
| 方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 種類1. 親族内事業承継 | ・会社の文化や価値観を継承しやすい ・従業員の信頼を得やすい | ・後継者が適任でない場合がある ・親族間での対立が起きる可能性 |
| 種類2. 親族外事業承継 | ・外部から新しい視点やノウハウを導入できる ・専門的なスキルを持つ後継者を選べる | ・適切な後継者の選定が難しい ・従業員の反発がある |
| 種類3. M&Aによる事業承継 | ・買収資金を資金調達が可能 ・経営資源を拡大できる | ・企業文化の融合が難しい ・買収後の統合が複雑 |
それぞれの事業承継の種類について解説していきます。
種類1. 親族内事業承継
親族内事業承継とは、経営者の親族や子供に既存事業を引き継ぐ方法です。主に、小規模企業が中心におこなっている承継の方法で、基本的には親から子への事業承継が多い傾向です。
親族内で事業承継をおこなうには、親族に対して経営者としての教育が必要になりますが、周囲からの後継者の受け入れがスムーズになるメリットがあります。
また、早期から事業承継することが決まっているのであれば、経営者に傍で実務経験を積むことで、経営者に求められるスキルや経験を養うことも可能です。
しかし、親族内に限定してしまうと、後継者に相応しい人材が見つからない可能性があり、事業承継が難航してしまうデメリットもあります。
種類2. 親族外事業承継
親族外事業承継とは、、親族以外の人材に事業を引き継ぐ方法です。基本的には、社内の役員や従業員を対象にしていますが、外部からの後継者を対象にするケースも少なくありません。
メリットについては、後継者候補を選択する幅が広がるので、適格者を選抜しやすくなります。社内の役員や従業員に経営を引き継ぐ際には、長年一緒に働いているので経営者に対しての理解度が高く、経営者の意向を引き継ぎやすいのもメリットといえるでしょう。
一方で、個人保証の引継ぎが難航しやすかったり、社内分裂が起きてしまうリスクも考えられます。さらに、親族外事業承継だと債権者の金融機関から承認を得られにくいデメリットもあります。
種類3. M&Aによる事業承継
M&Aによる事業承継とは、親族や従業員以外の第三者の買い手に経営権を譲渡して、自社の経営を引き継ぐ方法です。有償譲渡となるので、会社や事業の価値に応じた売却益を獲得することができます。
買い手企業による事業拡大や投資拡大、他事業とのシナジー効果などを期待することができます。
デメリットは、買い手企業との交渉が成立するまでに時間がかかってしまったり、買収後に雇用・労働条件の変更によって従業員の離職が起きてしまうケースも少なくありません。
また、探索範囲が飛躍的に広がってしまうので、M&Aの相手を探す難易度が高く、自社に最適なM&A先の選定をおこなえないリスクも考えられます。
事業承継の失敗を防ぐ5つのポイント
事業承継を失敗させないためのポイントは、以下5つです。
◆ 事業承継後の失敗を防ぐ5つのポイント
- ポイント1. できるだけ早く事業承継の準備を進める
- ポイント2. 事業承継計画表を作成する
- ポイント3. 財政状況を安定させておく
- ポイント4. 節税対策をしておく
- ポイント5. 後継者にしっかりと意思を確認する
それぞれのポイントについて解説していきます。
ポイント1. できるだけ早く事業承継の準備を進める
事業承継には、会社の状況や後継者の有無によって多少異なりますが、5年〜10年の準備期間が必要とされているので、できるだけ早く事業承継の準備を進めるようにしましょう。
現経営者が65歳で引退を考えているのであれば、55歳になった時点で事業承継の準備を始めることをおすすめします。
事業承継で重要なポイントになるのが、事業承継による焦りによって冷静な判断ができずに、間違った選択をしないことです。また、後継者の選定は事業承継で特に大切になるので、余裕を持って取り組むようにしましょう。
さらに、会社の経営が疎かになってしまうリスクも防ぐことにもつながります。
ポイント2. 事業承継計画表を作成する
事業承継計画表とは、事業承継後の目標やそのためのアクションについて示した計画表です。計画表を作成して後継者や従業員と共有しておくことによって、事業承継をスムーズにおこなうことにもつながります。
また、想定外のタイミングで後継者が会社を引き継ぐ状態になっても、事業承継計画表があれば社内の混乱を避けることが可能です。
事業承継計画を作成する際には、経営者だけではなくて後継者と一緒に作り上げていくことで、その過程で会社に必要な心構えができます。
ポイント3. 財政状況を安定させておく
事業承継では、会社の資産や負債なども引き継ぐことになるので、後継者が事業承継後に順調に経営をするためにも、財政状況を安定させておきましょう。
実際に、事業承継後に多くの負債があることが発覚して、最終的に廃業に追い込まれてしまうケースも少なくありません。そのため、事業承継後でも事業を円滑に進められるよう、現経営者は会社の財政状況をコントロールして、なるべくベストな状態で引き継ぐことが重要です。
ポイント4. 節税対策をしておく
事業承継では、節税対策をしないと、納税によって多額の資金を支払ってしまう事態になるので注意が必要です。贈与税や相続税が必要になるケースが多く、対策を怠ってしまうと、事業承継がうまくいかないことも多いのです。
節税対策には、主に以下2つがあります。
- 相続時精算課税制度
- 不動産購入による自社株の評価額引き下げ
上記以外にも、会社の状況によって節税対策があるので、事業承継をする前には確認をしておきましょうまた、事業承継を親族でおこなう場合には、相続税対策も必要になります。
ポイント5. 後継者にしっかりと意思を確認する
事業承継では、後継者にしっかりと意思を確認することがもっとも重要になります。
後継者は事業を持続させるのはもちろん、さらに発展させることが求められるので、中途半端な決意では務めることは難しいです。そのため、経営者としてどのような志を持っているのか、本人の意思を確認しましょう。
外部のコンサルに事業承継の相談する
事業承継問題については、外部アドバイザーとしてコンサルの力を借りることもができます。特に、専門家の視点から現状を客観的に分析し、最適な解決策を提案してもらうことができるため、自社だけで解決策を模索するよりも効率的です。
事業承継に強いコンサルタントは、事業承継に関する法的、税務的な知識を持っており、具体的なプランニングから実行支援までをサポートします。例えば、以下のような支援を受けることができます。
- 承継プランの策定
- 後継者の社内プレゼンス向上
- ビジョンや経営戦略の策定
- 組織改善・コミュニケーション支援
弊社、(株)Pro-D-use(プロディーユース)では事業承継の現場型の支援を行っており、事業承継に強いコンサルタントが多数存在します。コンサルタントが現場に入り込み、業績の向上させるだけでなく、後継者が社内で動きやすくなるために社内調整や組織改善も実行します。
初回の相談は無料ですので、ぜひ一度、ご相談ください。
\ スムーズな事業承継をするなら!! /
事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に強いコンサルタントを選びましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>
\ “現場で一緒に” 事業承継を進めるなら!! /
失敗事例を参考にし、事業承継を成功させよう!
今回は、事業承継の失敗事例や事業承継を失敗させないためのポイントを紹介しました。事業承継を失敗させないためには以下5つのポイントがあります。
◆ 事業承継を失敗させない5つのポイント
- できるだけ早く事業承継の準備を進める
- 事業承継計画表を作成する
- 財政状況を安定させておく
- 節税対策をしておく
- 後継者にしっかりと意思を確認する
また、事業承継の失敗事例を把握しておくことで、事業承継が失敗してしまうリスクを減らしたり、スムーズにおこなうことにもつながります。今回の記事を参考に、事業承継を成功させてください。
失敗を避けて事業承継を成功させませんか? (株)Pro-D-useなら、手放しで事業承継がドンドン改善します!
⇒Pro-D-useの無料経営相談を受けてみる
\ スムーズな事業承継をするなら!! /
事業承継は「なんとなく」で進めると必ず失敗します。あなたの会社には、頼りになる事業承継に強いコンサルタントを選びましょう。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」は「伴走・現場型で利益を押し上げる」コンサルティング支援が特徴の経営コンサルティング会社です。これまでたくさんの経営相談で「2代目・3代目の経営者支援」「コンサルタントの乗り換え」「事業拡大 / 事業再生」で数多くの実績をあげてきました。
「(株)Pro-D-use(プロディーユース)」にあなたの会社について相談してみませんか?詳しくは経営コンサルティングサービスページをご覧ください。
(株)Pro-D-useの「経営コンサルティングサービス」詳細を見る >>
\ “現場で一緒に” 事業承継を進めるなら!! /
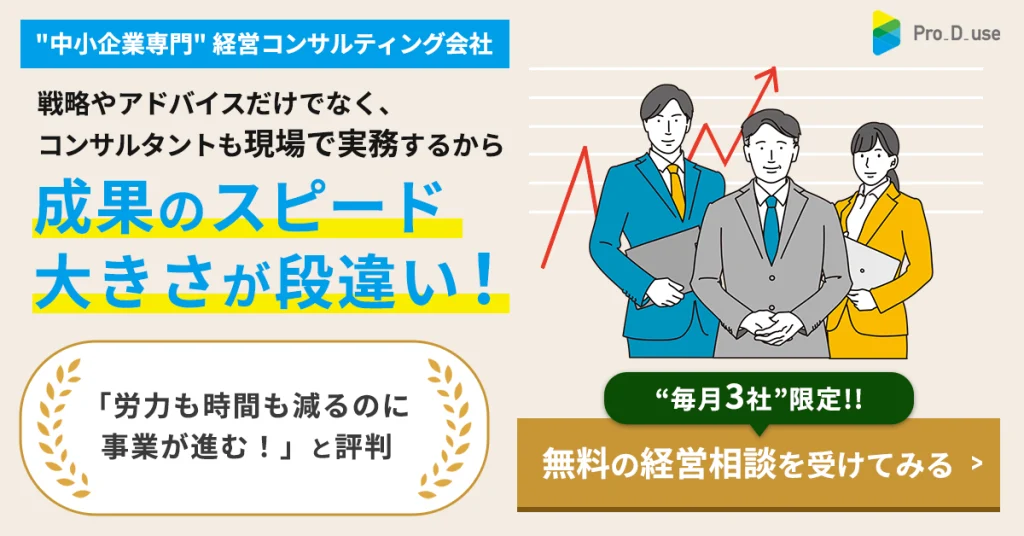
なお、事業継承については下記の記事もぜひご参考ください。
参考>> 事業継承についてはこちらも参考にしてみてください。
参考>> 信頼安心のM&AならレバレジーズM&Aアドバイザリー





